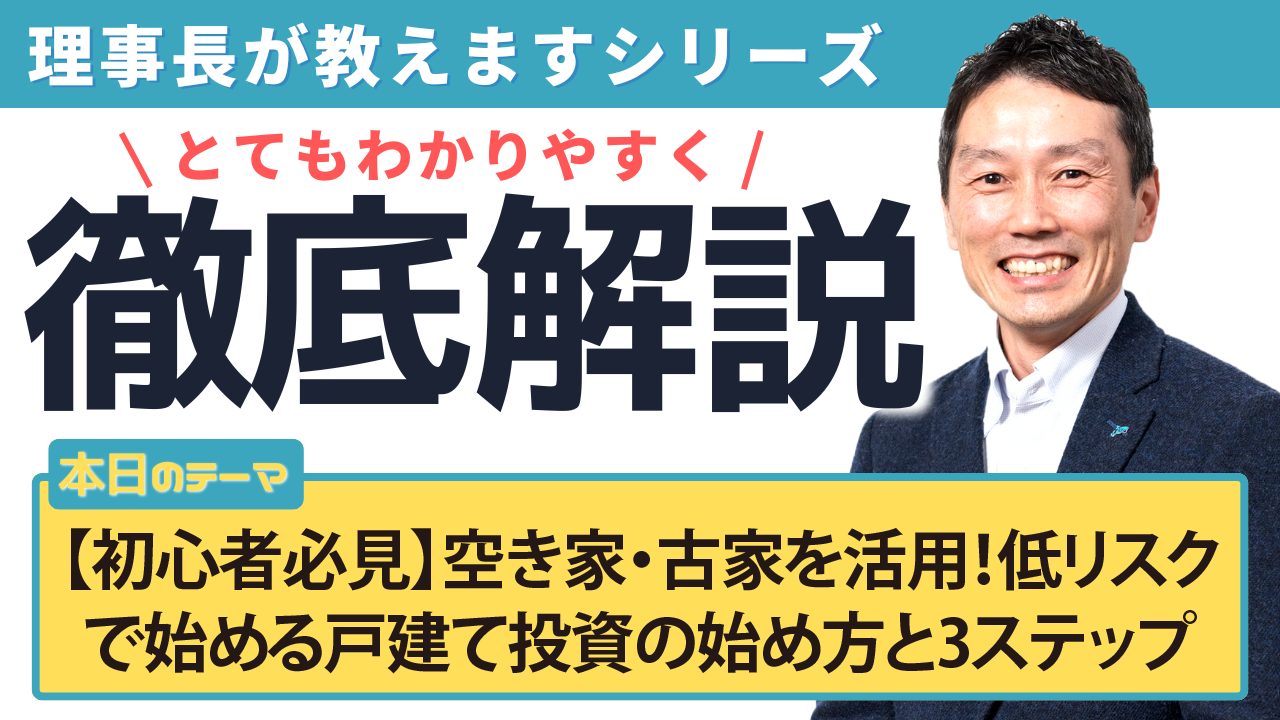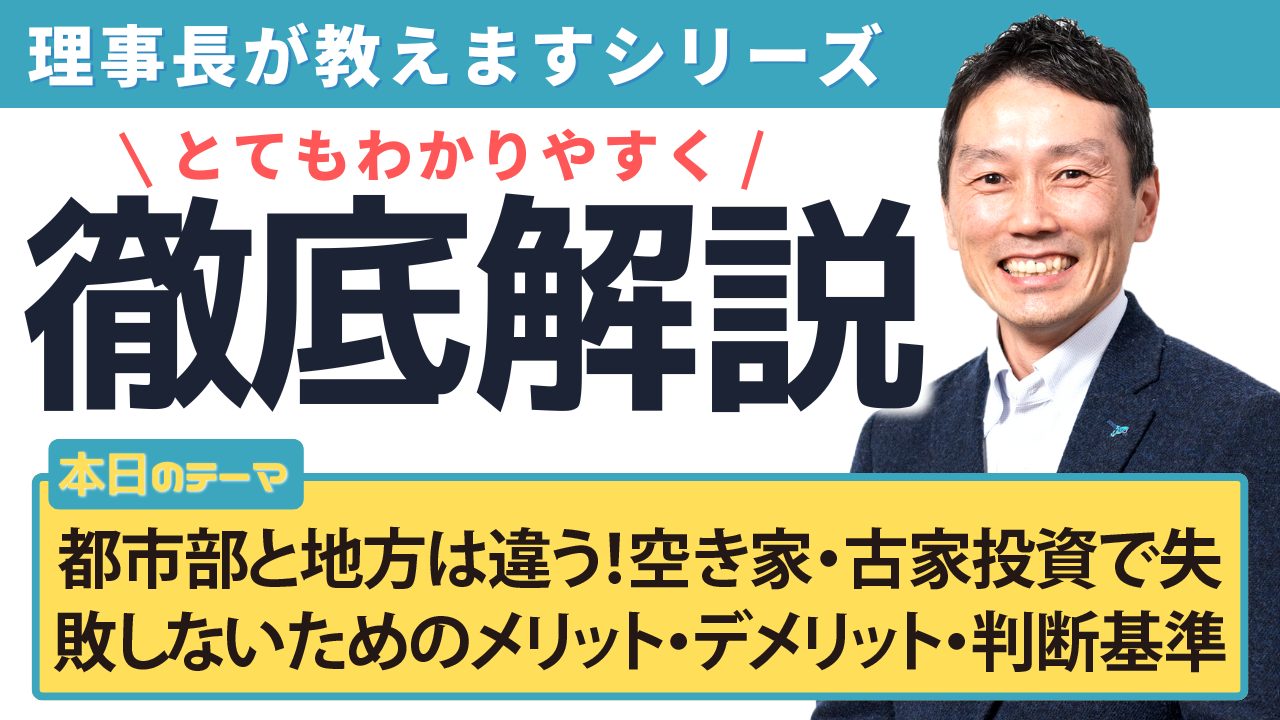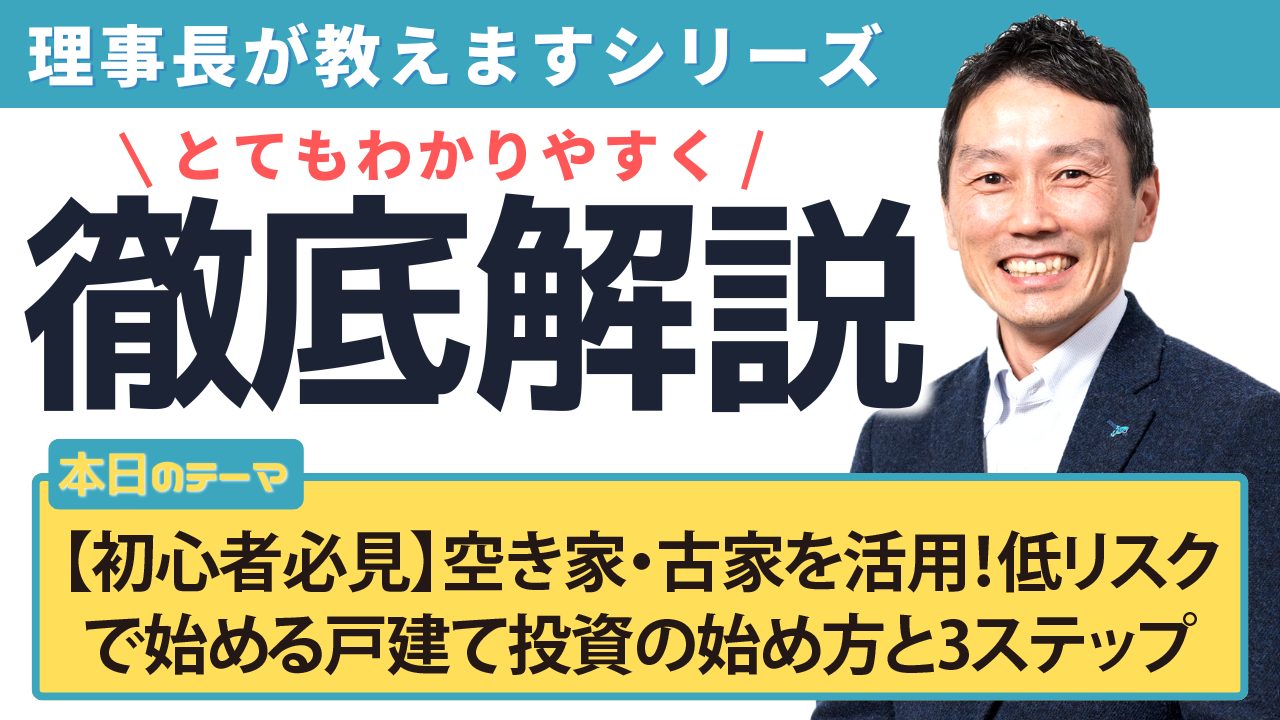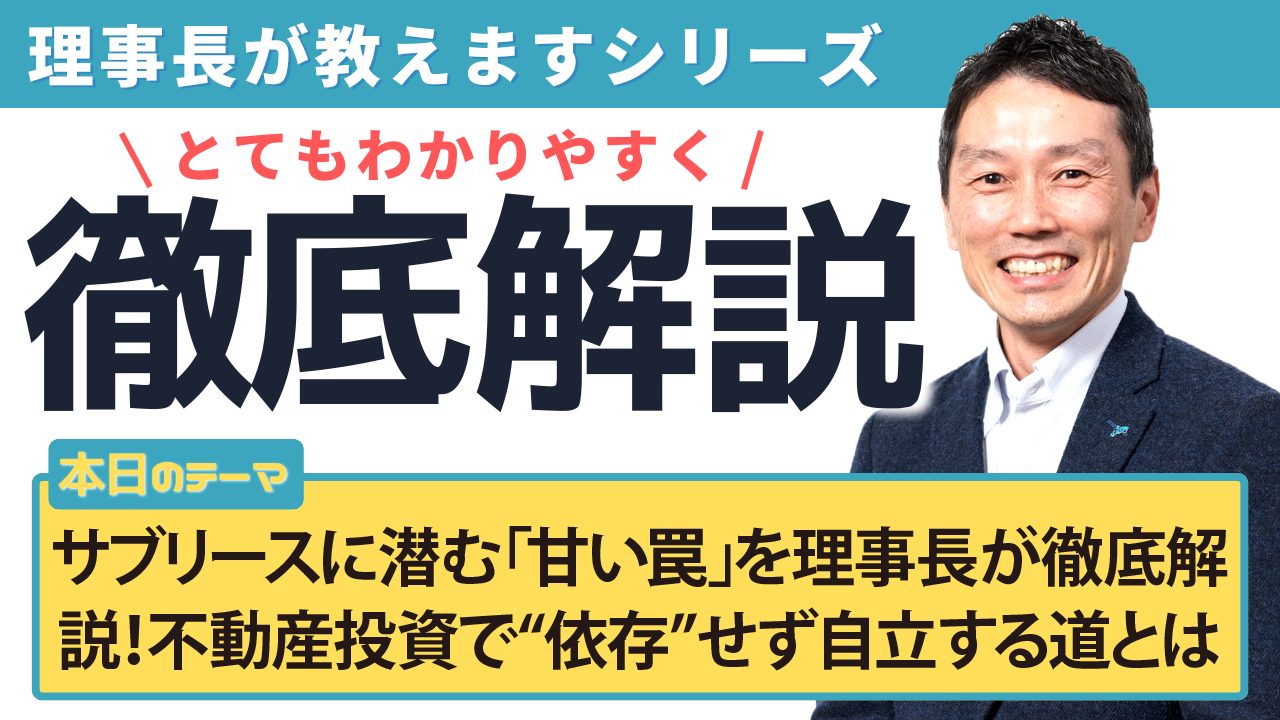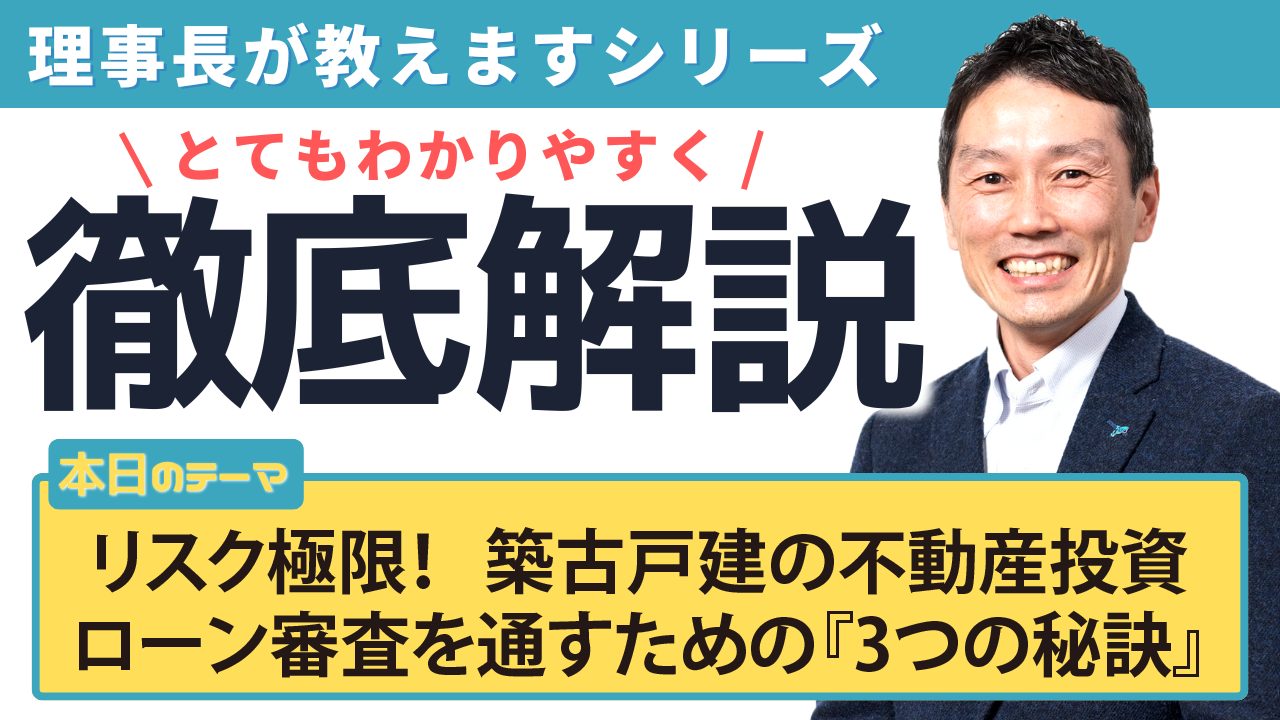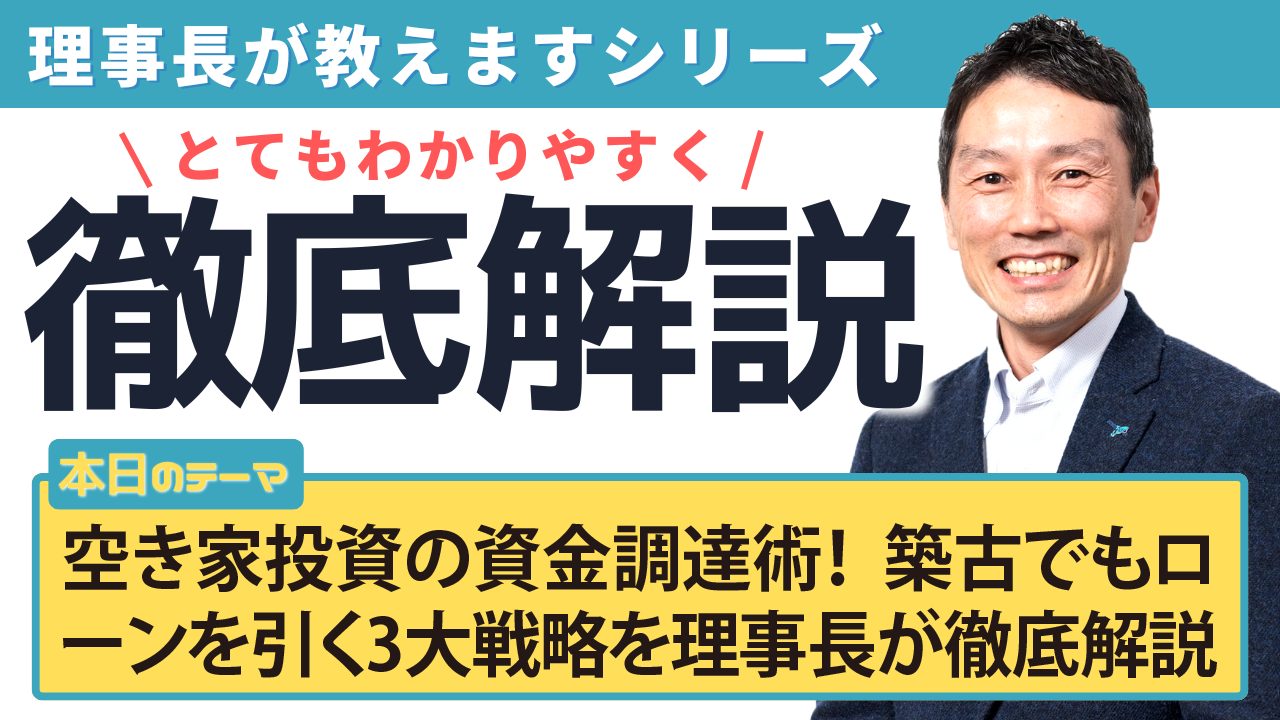
(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
もし、あなたが「老後2000万円問題」や「会社の給与以外に収入源が欲しい」と感じ、空き家・古家投資に興味を持たれたのなら、それは賢明な判断です 。私たち全古協の会員は、累計2,467棟以上の再生実績から、空き家・古家がリスクを極限まで抑えた高利回りな投資であることを証明してきました 。
しかし、一歩踏み出すのを躊躇してしまう、最大の壁があります。それが「資金調達(ローン)」の壁です。
「築40年、50年のボロ家なんて銀行が相手にしてくれないだろう…」
「低金利の融資を引いてレバレッジを利かせたいが、どうすればいい?」
ご安心ください。私たち協議会が指導し、多くの会員が実践しているのは、「築古」というハンデを乗り越え、金融機関を味方につけるための戦略です。机上の空論ではなく、2,467棟以上の実績から導き出した再現性の高い3大資金調達戦略があります。
この記事を最後まで読めば、あなたは漠然とした資金の不安から解放され、融資担当者を納得させる「大家業のプロ」としての道筋が見えるはずです。
目次
1. なぜ「築古空き家」の融資は難しいのか?【初心者が陥る3つの壁】
まず、なぜ築古の空き家投資で融資が難しいと言われるのか、その本質を理解しましょう。これは、金融機関が本能的に嫌う「リスク」に直結しているからです 。
1-1: 銀行が避ける「法定耐用年数」と「木造22年の壁」
銀行が融資の可否を判断する際、不動産の担保価値を重視します。この担保価値を測る基準の1つが法定耐用年数です 。
日本の税法上、木造住宅の耐用年数は22年と定められています。築22年を超えると、銀行は建物の価値がゼロに近づくと見なし、融資の対象外とするのが一般的です 。
旧耐震基準の壁: 1981年6月1日以前に建築確認を受けた建物は旧耐震基準であり、大規模な地震への懸念から、金融機関はさらに融資に消極的になります 。
空き家・古家投資の対象となる物件は、多くが築40年〜50年の木造住宅です。つまり、ほとんどの物件がこの「耐用年数」の壁にぶつかってしまうため、通常のアパート・マンション投資(アパマン投資)とは異なる資金調達戦略が必要となるのです 。
1-2: 「担保評価」が出にくい地方物件の現実と課題
都市部の不動産には投資資金が集まるため、需要と供給に関係なく価格が上がることがありますが、地方物件はもともと流動性が低く、価格の変動が緩やかです 。
融資の観点から見ると、地方物件は担保評価が低く出やすいという現実があります 。しかし、これは裏を返せば、土地の広さがあるため値下がりしにくいというメリットにもつながります 。
路線価が基準: 地方では路線価(国税庁が決めた土地の価格)以下で購入できる物件が多くあります 。これは、その物件の資産価値がこれ以上落ちないことを意味し、むしろ投資対象としては価値が高いと言えるのです 。
金融機関が不安視するのは、「万が一の際の売却可能性と価格」です。これを覆すためには、単なる建物の古さではなく、物件の収益性(利回り)を根拠として提示する必要があります。
1-3: 「再建築不可」や「借地」など特殊物件のリスク評価
築古物件には、再建築不可や借地といった特殊な物件も含まれます 。
再建築不可: 現在の建築基準法で建物を建て直せない物件を指します 。
借地: 別の人が土地を持っていて建物だけを買う物件です 。
これらの特殊物件は資産価値が低く、不動産業者も避ける傾向があります 。融資も当然、非常に困難になります。しかし、空き家・古家投資の考え方は、「リスク分、安く買う」ことです 。特殊物件は、その分利回りを12%高く設定してリスクを収益で補う戦略が有効です 。
全古協の会員の中には、借地権物件で25%の利回りを叩き出した事例もあります 。ただし、これらの物件は現金で購入し、短期で回収を目指すのが基本です。
2. 【大熊流】築古空き家投資を成功に導く「資金調達3大戦略」
担保価値の低い築古物件で融資を勝ち取るには、金融機関が評価する「担保」ではなく、「事業性」と「あなたの信用(属性)」を武器にする必要があります。
私たち協議会が推奨する、リスクを抑えながら資金調達を実現する「3大戦略」を解説します。
2-1: 戦略1:リスクを極限まで抑える「現金一括購入」の基本
空き家・古家投資は、少額(400万円程度)から始められる投資です 。まず、1軒目を現金で買って大家業をスタートさせるのが、最もリスクを抑えた鉄則です 。
大家業の「実績」づくり: 融資を受けるには、金融機関に「この人は安定して賃料収入を得られる大家だ」と認めてもらう実績が必要です。1棟目を現金で買い、入居付けに成功し、確定申告まで行うことで、初めて金融機関に対し信用を示すことができます 。
買付交渉の「スピード」: 安い物件、いわゆる「お宝物件」はスピード勝負です 。現金での買付は融資特約(融資が通らなければ契約解除となる特約)の心配がないため、売主や不動産業者にとって非常に有利に映り、競合に勝てる大きな武器となります 。
相続物件はリフォーム費用のみ: もし、あなたが相続物件を所有しているなら、物件購入費が不要となり、リフォーム費用のみの少額投資で大家業を始められるという最大のチャンスです 。
2-2: 戦略2:低金利を活かす「リフォームローン」で初期投資を圧縮
現金で物件を購入した後、あるいは自己資金がリフォーム費用に届かない場合に活用したいのがリフォームローンです。
これは、物件価格とリフォーム費用を切り離して考える戦略です。築古物件自体への融資は難しくても、「リフォーム(改修工事)」という事業性の高い用途には融資が出やすくなります 。
空き家活用ローン: 地銀数行が空き家活用ローンという商品を取り扱っており、物件取得費は出ないものの、リフォーム費用として500万円まで融資可能な場合があります 。返済期間10年、金利2.0%前後と比較的低金利です 。
手出しリスクの低減: 例えば、200万円の物件を現金で購入し、300万円のリフォーム費用を融資で賄うことで、手元に資金を残しながら物件を取得できます 。
担保評価の向上: リフォーム後の物件は当然、担保としての価値が向上します。金融機関も担保価値向上に繋がる融資には前向きになる傾向があります。
2-3: 戦略3:公的融資を活用する「日本政策金融公庫」の切り札
サラリーマン大家や、中小企業の経営者にとって、最も頼りになるのが日本政策金融公庫(公庫)です 。
公庫は国の政策として融資を行う機関であり、民間金融機関の融資対象から外れる築古物件や、新規事業(大家業)に対しても門戸が開かれています 。
融資の条件: 公庫の「普通貸付」は、不動産貸付業として利用でき、限度額は4,800万円です 。金利は1.9% 〜2.1%$程度の低金利で、無担保で借りられるケースもあります 。
公庫融資成功事例: 全古協が紹介したプランナー会員の中には、返済期間11年、固定金利、無担保で融資を得られた事例があります 。
融資のコツは「紹介」と「事業計画」: 公庫融資を受ける最大のコツは、「知らない人には貸さない」という基本原則から、誰かの紹介で行くこと、そして融資担当者を納得させる明確な事業計画書を用意することです 。
3. 融資担当者を納得させる「大家業のプロ」戦略
金融機関は「担保」ではなく「事業の成功可能性」を見ています。築古物件の再生をプロの事業として見せることで、融資のハードルは劇的に下がります。
3-1: 「家賃からの逆算」を徹底し、購入価格の根拠を示す
不動産投資における購入価格の決定は、売主の希望価格や売値から入るべきではありません 。
大熊流の投資判断は、まず「家賃からの逆算」を徹底します 。
この計算式に基づき、あなたの提示する買付額には明確な収益性の根拠が生まれます 。このロジックこそが、融資担当者を納得させる最も強力な武器となります。
利回り基準(目安):
関西: (10〜15坪)
関東・名古屋: (15〜25坪)
特殊物件(借地・再建築不可): リスク分を補うため、1%2%高く設定する 。
3-2: 実績が信頼を生む!融資交渉を有利にする知識と経験
「空き家投資をいくら勉強しても、物件を1つ購入するほうがはるかに勉強になる」とは言いますが 、融資の世界では知識武装と経験が求められます。
知識30%、経験70%の法則: 知識だけで経験が少ないうちに買ってしまうと、あとで苦労します 。まずはオンライン講座のようなもので体系的な知識を身につけ、その後物件見学ツアーで物件を「見て、感じて、体験」し、経験値を積み上げることが大切です 。
物件見学ツアーの価値: 半日で4〜5軒の物件を、再生士や先輩大家と一緒に見て回ることで、家賃の相場観やリフォームの価格、買付希望価格の目安が分かるようになります 。この目利き力こそが、融資交渉の説得力を高めます。
3-3: 「古家再生士」との連携で実現する「工事費の透明性」
融資担当者が築古物件で最も恐れるのは、「見えない工事費」です。床下の腐食、シロアリ被害、配管の老朽化など、予想外の出費が収益を圧迫するリスクです 。
古家再生士の役割: 私たち全古協が認定する古家再生士は、賃貸不動産の知識と差別化リフォームの技術を併せ持つ専門家です 。彼らは物件調査時にわずか10〜15分で工事費の概算を算出できます 。
融資への信頼性: 再生士と同行し、即座に正確な工事費を提示できることは、「この事業はプロの目で精査されている」という安心感を金融機関に与えます 。リフォーム予算は平均200万円を目安とし、これを超えると収益物件として成り立たないという判断基準を持っています 。
4. 地方こそ資金調達を有利にする「宝の山」である
都市部では利回りが落ちてきている今 、地方の空き家・古家に目を向けることは、資金調達の観点からも大きなメリットがあります。
4-1: 都市部との比較!土地値の低下率と家賃の下げ止まり
地方は都市部と比べて、土地の価格(土地値)が急激に落ちるのに対し、家賃の落ち方は緩やかです 。
土地値と家賃のギャップ: 郊外に行くほど、土地値は3分の1や5分の1になることがありますが、家賃は半分になることはなく、2〜3割減にとどまります 。
収益性の確保: この「土地値の急激な下落」と「家賃の下げ止まり」のギャップこそが、地方物件で高い利回り(15%超)を確保できる最大の理由であり、低リスクな投資の根拠となります 。
4-2: 利回り15%超を叩き出す「お宝物件」の探し方
地方物件の確定利回りは、関東首都圏の平均13.0%に対し、北陸地方は13.9%と上回っています 。
高利回り事例: 岐阜県大垣市周辺では、平均確定利回りという実績が出ています 。
広さと活用: 地方物件は土地が広く、駐車場(地方では必須)を複数台確保しやすいという強みがあります 。また、建物が広いため、法人需要(社宅・外国人研修用など)の借り上げも見込めます 。
高利回りは、すなわち短い期間で投資総額を回収できることを意味し、金融機関にとってリスクが低いと判断される大きな材料となります。
4-3: 「4方よしモデル」が金融機関の評価を高める時代
空き家・古家再生投資は、単なる投資活動ではなく、社会課題の解決に貢献する事業です 。
金融機関は、SDGsや地域社会への貢献といった視点を重視し始めています。私たち全古協の「4方よしモデル」は、この時代の要請に応えるものです 。
大家(投資家)よし: 低額で高利回り、安定収益 。
入居者よし: 低家賃で広くて住みやすい住居を提供 。
工務店(古家再生士)よし: 安定した仕事と正当な利益 。
地域よし: 空き家を減らし、地域活性化に貢献 。
この社会貢献性の高さが、あなたの事業の信用をさらに高めることになるのです 。
5. 【失敗事例に学ぶ】資金調達でつまずかないための心得
成功者が語らない「失敗談」こそ、あなたの投資を成功に導く最大の教訓です。
5-1: 「きれいな物件」にこだわりすぎて利回りを落とすな
初心者は、ついきれいな物件を選びたくなりますが、これは致命的なミスにつながります。
ボランティア物件の危険性: 多くの人は、入居者のためだと思ってリフォーム費用をかけすぎてしまい、まったく利回りが出ない「ボランティア物件」にしてしまいます 。
入居者の目線: 賃貸物件を探す人は、あなたの考える生活レベル(家賃月10万円のクオリティ)を求めていません 。求めているのは「自分の収入に見合った家賃」です 。
リフォームの原則: 「家賃に見合う質のリフォーム工事でOK」なのです 。無理に和室を洋室にしたり、高額な設備を入れたりするのは、あなたの感覚が良すぎるだけです 。工務店に言われるままにリフォームすると、予算倒れになります 。
5-2: DIYはコストより「時間とリスク」の損失が大きい
「リフォーム費用を節約したい」とDIY(セルフリフォーム)に手を出す人がいますが、これは初心者の資金調達・事業継続を危うくします。
時間とチャンスロス: DIYによる仕上がりの悪さや、慣れない作業による工期の遅延は、その間の家賃収入(1日円も生まない)を失うチャンスロスに直結します 。
入居後のクレーム: 素人のDIYによる水漏れや不具合は入居後のクレームとなり、結局、プロの業者に割増料金を払って修理させることになります 。最悪の場合、入居者が退去してしまうリスクもあります 。
結論: 質を維持できないDIYは止め、プロに任せてスピーディーに入居付けし、家賃を稼ぐほうが賢明です 。
5-3: 融資交渉前に「物件の売却・賃貸判断」を早く行うことの重要性
資金調達の計画を狂わせるのが、決断の遅れです。
放置の代償: 相続物件を「売却か賃貸か」迷い、1年間何もせず放置した結果、賃貸収入(1年分の家賃)が減っただけでなく、建物の傷みがひどくなり多額の修繕費用が必要になるという二重の損失を被った会員がいました 。
決断の早さが資産を救う: 融資が必要な場合も、物件の「売却」か「賃貸化」の判断を早く行うことが、資産の劣化を防ぎ、事業計画の具体性を増します 。判断を先延ばしにすることは、「損失の増大」に他なりません。
まとめ:あなたの投資は「借金」ではなく「投資」である
空き家・古家投資の資金調達は、確かに築古の壁にぶつかります。しかし、その壁は「知識」と「戦略」で乗り越えられます。
築古で融資を引くための要点
【知識武装】: 築古の融資が難しい理由を理解し、「家賃からの逆算」で物件の収益性を証明する 。
【3大戦略の活用】:
現金一括: 1棟目は現金で実績と信用を積み、交渉を有利にする。
リフォームローン: 低金利な公庫や地銀の空き家活用ローンで初期投資を圧縮する。
日本政策金融公庫: 「大家業の実績」を武器に、公的な融資を勝ち取る。
【プロの証明】: 古家再生士と連携し、リフォーム費用を正確に算出して事業計画の具体性と透明性を高める。
私たち全古協の活動は、単なる「金儲け」ではなく、「誰もが経済的自立を享受できる」社会を実現することを目指しています 。借金に依存せず、リスクを極限まで抑えたこの投資法こそ、あなたの将来を豊かにするツール(武器)です 。
このノウハウを体系的に学び、実践で使える「大家業のプロ」となるためのステップが、私たち協議会が提供する古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座です。知識を学び、物件見学ツアーで経験を積み、同じ志を持つ仲間と共に、あなたの人生を変える一歩を踏み出してください。
あなたの行動が、日本の空き家問題解決の扉を開きます。
POST: 2025.11.21