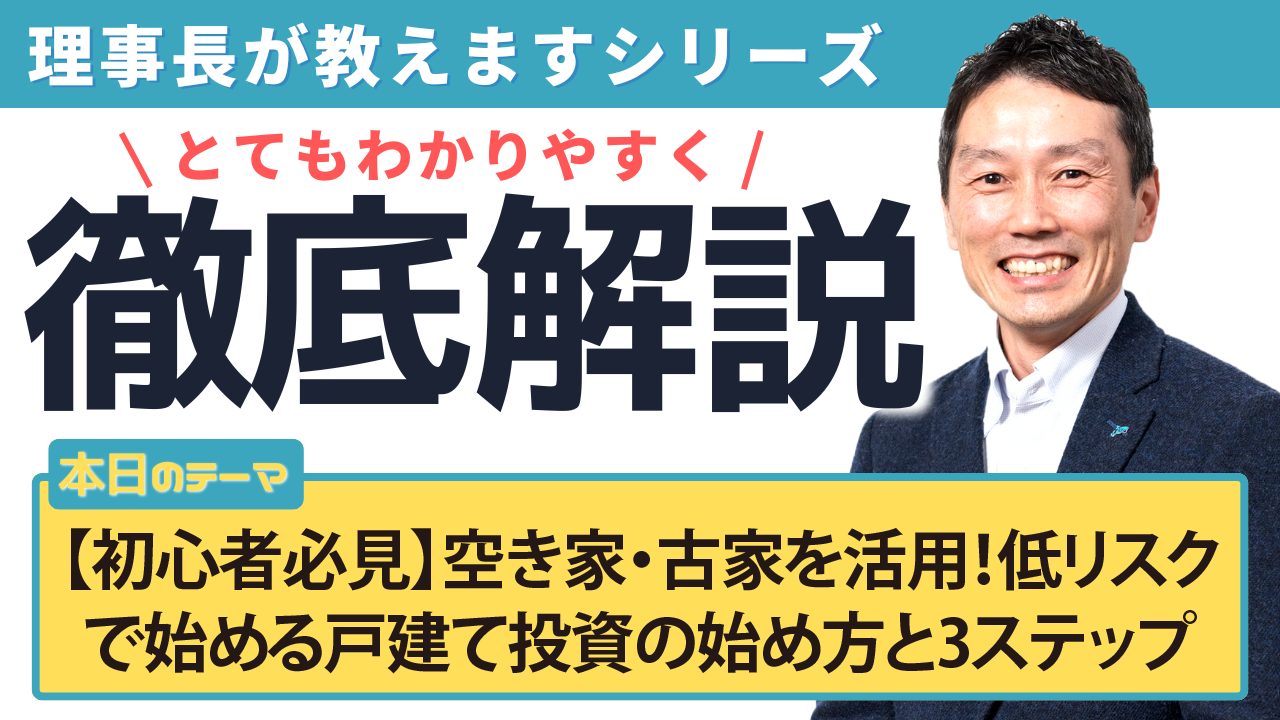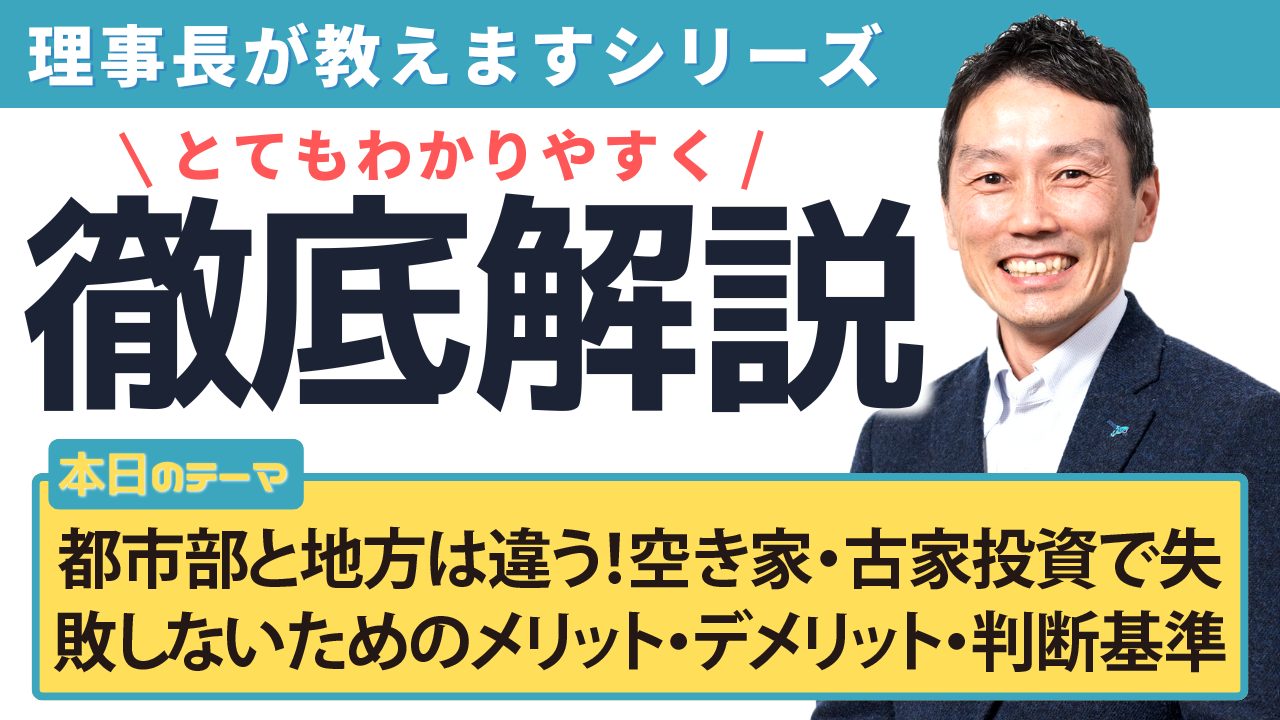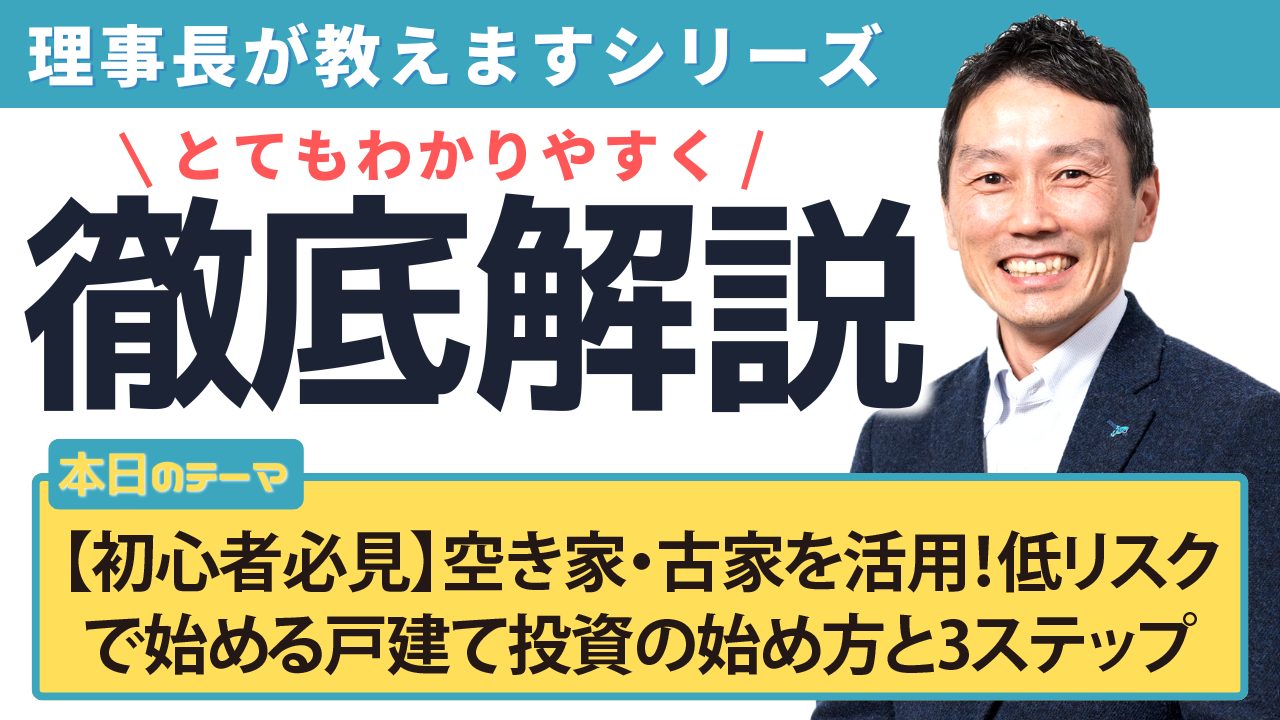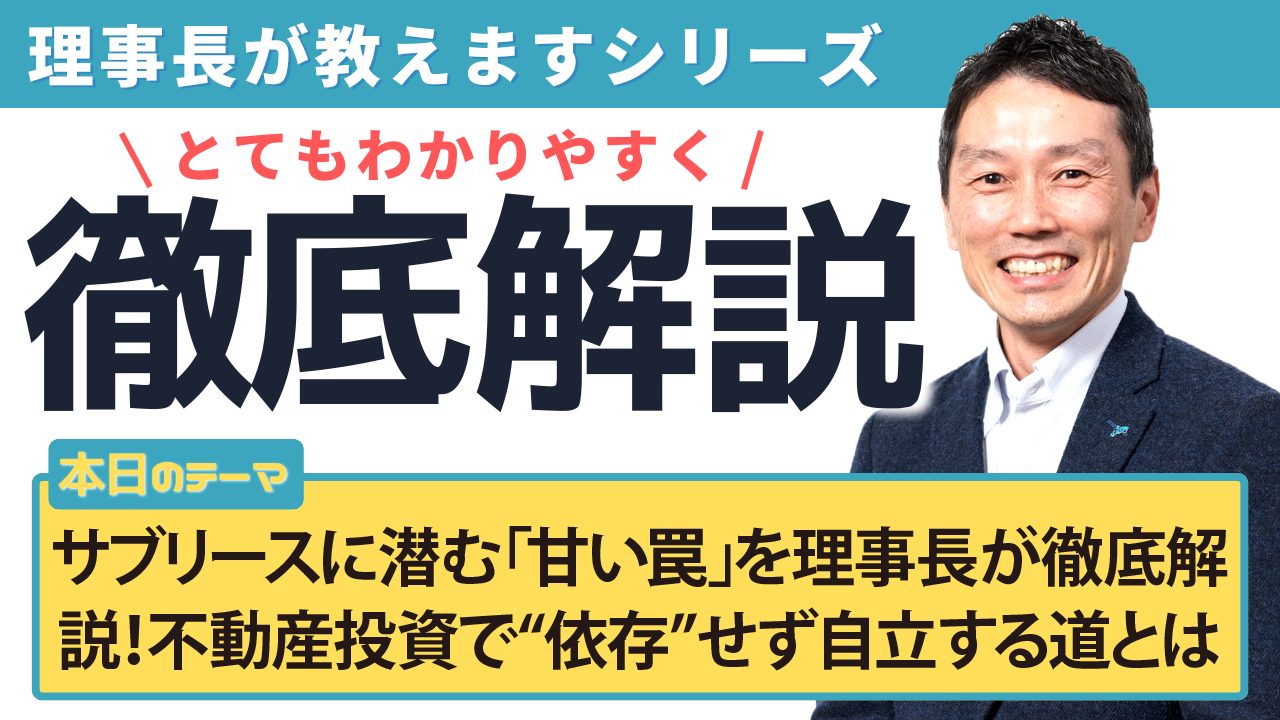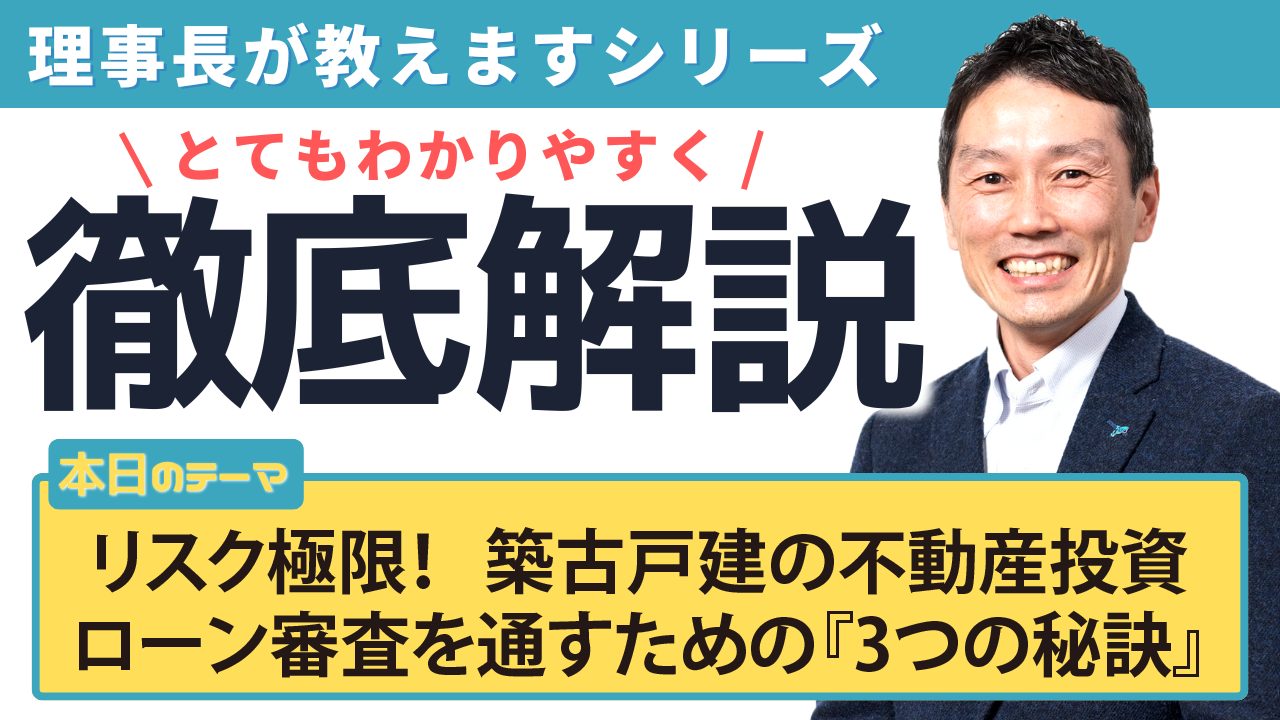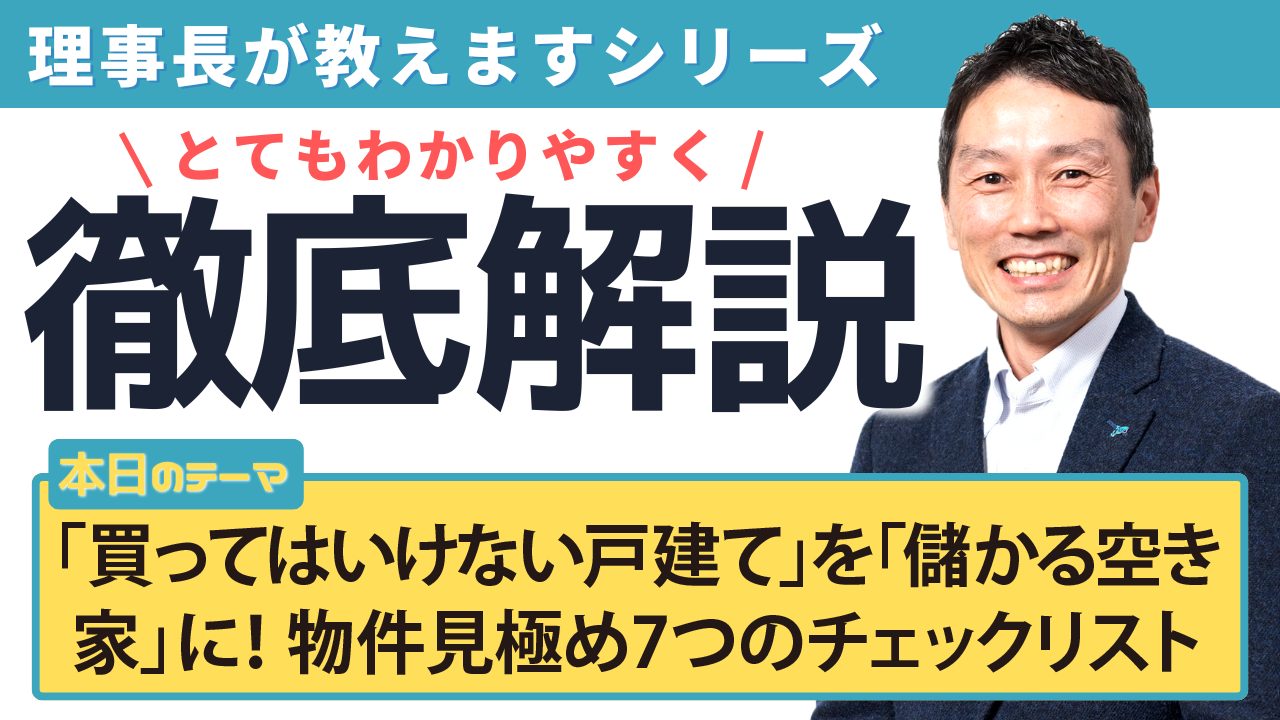
(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
もしあなたが「不動産投資に興味はあるけど、ボロボロの戸建てを買って失敗するのが怖い」「何千万円もするマンション投資より、低予算で安定的に儲けたい」と考えているなら、まさにその不安こそが成功への第一歩だと断言します。
世の中には「買ってはいけない戸建て」という情報があふれています。しかし、私たち協議会は、そうした物件を「儲かる空き家」に再生することに特化し、これまでに累計2,467棟もの再生実績と、全国20,280名の会員ネットワークを構築してきました。
この実績は、単なる運や勘ではなく、リスクを極限まで排除する「正しい目利き力」に基づいています。
この記事では、私が長年の経験と数々の失敗から導き出した「買ってはいけない戸建て」を避け、高利回り物件に生まれ変わらせるための理事長直伝【リスク極限排除】物件見極め7つのチェックリストを包み隠さず公開します。
目次
1. 序章:なぜ「買ってはいけない戸建て」が生まれるのか?
1-1. 投資初心者が陥る「二極化の罠」
不動産投資の初心者が戸建て物件を探すとき、最も陥りやすいのが「二極化の罠」です。これは、物件を「高値掴み」するか、「安物買いの銭失い」になるかの二択です。
高値掴みの罠: 築浅で綺麗な物件は安心ですが、購入価格が高すぎて利回りが確保できません。結果的にキャッシュフローが得られず、投資としての魅力が薄れてしまいます。
安物買いの罠: 100万円台の超低価格物件に飛びつきがちですが、建物の劣化が深刻すぎて、リフォーム費用が青天井になり、結局は採算が合わなくなります。
私たち古家再生投資が狙うのは、この中間です。一見するとボロいけれど、致命的な欠陥がなく、低コストで再生できる「宝の山」です。この「宝の山」を見極めるための知識こそが、あなたに必要な目利き力なのです。
1-2. 仲介業者も教えてくれない「隠れたリスク」の正体
不動産業者は、物件の売買を成立させることで収益を得るのがビジネスですから、彼らが物件の「負」の部分を積極的に開示することは稀です。
特に空き家・古家には、資料だけでは決して分からない「隠れたリスク」が潜んでいます。
地中のリスク: 過去の地盤沈下履歴、埋設物(浄化槽など)、土壌汚染の可能性。
近隣とのリスク: 境界線問題、越境(隣地の木やブロック塀が敷地に入り込んでいる)、前所有者との近隣トラブル。
インフラのリスク: 上下水道の配管の老朽化、前面道路への下水道本管の引き込みがない(汲み取り式の問題)。
これらのリスクは、現地調査や行政調査でしか分かりません。だからこそ、私たちは「机上の空論ではなく」、実績と実践を重視し、現場主義を徹底するのです。
2. 理事長が断言!絶対に避けるべき【構造・法的リスク】ワースト3
私たち協議会では、どんなに安くても、どんなに利回りが良くても、「買ってはいけない戸建て」として排除する明確な基準を設けています。
これが、あなたがリスクを極限まで抑えるためのワースト3です。
2-1. 傾き、雨漏り…躯体欠陥でリフォーム費用が青天井になるケース
リフォーム費用は、空き家・古家投資の成否を分ける最も重要な要素です。しかし、建物の躯体(くたい)に関わる欠陥は、簡単に修繕費が予算をオーバーし、利益を吹き飛ばします。
基礎の致命的な傾き: 著しく建物が傾いている場合、床下の造作(ぞうさく)によるレベル調整だけでは済まず、基礎自体をジャッキアップする大掛かりな工事が必要になることがあります。この費用は数百万円に及び、投資として採算が合わなくなる可能性が高いです。
雨漏り放置による広範囲の腐食: 屋根やベランダからの雨漏りを長期間放置すると、柱や土台が腐食し、シロアリ被害と複合して建物の強度が失われます。床が大きく緩んでいる、一部が下がっている場合は、要注意です。
断熱材の損傷(雪国など): 北陸や東北など積雪の多い地域では、断熱性能が極端に低い物件や、断熱材に深刻な欠陥がある物件は、入居者にとって快適な住環境を提供できず、退去やクレームに直結します。
2-2. 再建築不可、接道義務違反…売却できない「負動産」化の恐怖
出口戦略を確保するためにも、法的なリスクは絶対に排除しなければなりません。
再建築不可物件: 現行の建築基準法を満たさず、建物を解体すると二度と新しく建てられない土地です。買主が極端に少なくなるため、売却が非常に困難になり、「負動産」となるリスクが高いです。利回りが高くても、融資のハードルが上がるため、避けるべきです。
接道義務違反: 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これを満たしていない物件は、増改築もできず、売却時に大きな障害となります。
2-3. 土砂災害警戒区域、地盤沈下履歴…立地・環境に潜む致命的な罠
私たちは、地域社会への貢献(地域よし)を掲げていますが、入居者の生命に関わるリスクは絶対に許容できません。
ハザードマップの確認: 土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域など、災害リスクの高いエリアの物件は、入居者への説明責任だけでなく、資産価値の維持という観点からも大きな問題です。
地盤・液状化のリスク: 過去の地盤調査データや、近隣での沈下履歴などを徹底的に調査する必要があります。
災害リスクの分散: 2024年元日に発生した能登半島地震では、私たちの再生物件でも壁の亀裂などの被害が出ました。この経験から、物件の購入エリアを分散させ、リスクヘッジを図ることの重要性を痛感しています。
3. 【記事の核心】大熊式「儲かる空き家」に変える物件見極め7つのチェックリスト
「買ってはいけない戸建て」を排除したら、いよいよ**「儲かる空き家」**を見つけ出す実践的なノウハウです。私たち協議会のノウハウは、すべてこの7つのチェックリストに集約されています。
3-1. 【チェック1】家賃逆算シート:購入価格を決める唯一の基準
「売主がいくらで売りたいか」ではなく、「いくらで買えば儲かるか」で判断します。これが投資の鉄則です。
私たちが実践する家賃逆算の計算式は以下の通りです。
(相場家賃 × 12ヶ月 ÷ 希望利回り)- リフォーム費用 = 購入額
相場家賃の徹底調査: まずはインターネット(HOME’Sなど)や、地元の賃貸業者へのヒアリングで、リフォーム後の想定家賃を正確に割り出します。相場より1,000円でも高く設定すると入居付けに影響します。
希望利回りの設定: 私たち協議会では、テラスや再建築不可などのリスクを考慮し、12〜15%を目安としています。
売主交渉の根拠: この計算で導き出された購入額を根拠に、売主へ指値(さしね)交渉を行います。「安く叩く」のではなく、「収益性に基づいた適正価格」を提示することが、長期的な信頼関係の秘訣です。
3-2. 【チェック2】水回り3点集中法:コストを予測しやすい損傷レベル
リフォームにおいて、最もコストが高くなるのが水回りです。だからこそ、ここを「やるところ」と「やらないところ」に集中させます。
トイレ: ほとんどの場合、ウォシュレット付きの洋式トイレに交換します。汲み取り式の場合は、地域の慣習と入居者ニーズを考慮し、思い切って水洗化するか、汲み取り式でも許容できる家賃設定にします。
キッチン: 使える状態であれば、扉だけ色を変える、清掃のみに留めるなど、極力安価に抑えます。新品のシステムキッチンは、投資物件には「やりすぎ」です。
浴室・洗面: 浴槽がステンレスであれば、磨いて再利用し、グラスファイバーであれば塗装で表面をきれいにします。洗面化粧台は、入居希望者が毎日使う場所なので、シャンプードレッサー付きの新品を設置することで、差別化を図ります。
3-3. 【チェック3】間取りの「魔改造」禁止:入居者ニーズに合わせたシンプル再生
戸建て投資の主なターゲット層はファミリー層です。彼らが求めるのは、広さと使い勝手です。
LDK化の検討: 古家は台所と居間が分かれていることが多いため、壁を取り除いてLDK化することで、現代のライフスタイルに合わせます。
和室の活用: 和室を無理に洋室化せず、和のテイストを活かしたモダンなデザイン(塗装やアクセントクロス)にすることで、安価に差別化を図ります。
洗濯機置き場の確保: 昔の戸建ては室外に洗濯機置き場があるケースが多いですが、入居者の利便性を考え、室内に設置場所を新設します。
3-4. 【チェック4】市場外流通ルート:競争のない掘り出し物を狙う戦略
高利回り物件は、不動産情報サイトに出回る前に決まることがほとんどです。
地元の小規模業者との関係構築: 大手不動産会社は少額の古家を扱いたがりません。そこで、地域に密着し、相続案件などの情報を抱える地元の小規模な不動産業者や、宅建業を兼業している工務店と信頼関係を築きます。
情報提供のWin-Win: 彼らに「あなたの理念(地域貢献)と実績」を伝え、「すぐに買い付けを入れられること」を証明することで、優先的に情報を得られるようになります。
3-5. 【チェック5】シロアリと腐食:床下点検でわかる致命傷の有無
「床が緩い」と感じたら、それはシロアリ被害か腐食のサインです。
瑕疵担保免責の理解: 古家再生では、売主の瑕疵担保責任(雨漏りやシロアリ被害など)が免責となっている場合が多いです。そのため、買主側がリスクを負います。
床下・天井裏の点検: 購入前に床をめくることはできませんが、再生士などの専門家を同行させ、基礎や土台の状態をチェックします。シロアリの可能性がある場合は、薬を散布する費用を考慮した上で購入額を交渉します。
3-6. 【チェック6】公道の幅と接道:売却時を意識した法的クリア基準
「買ってはいけない戸建て」の多くが、この法規上の問題で将来的に売却できなくなります。
接道義務の徹底確認: 再建築が可能な物件でも、将来的な売却のハードルを避けるため、接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接しているか)は重要です。
地方物件の優位性: 地方は土地が広く、駐車場を複数台確保しやすいため、都心部で多い再建築不可や建ぺい率オーバー物件を避けられる傾向があります。
3-7. 【チェック7】協議会ネットワーク:プロの目で最終判断を仰ぐ方法
最終的なリスク排除は、独断を避けることです。
古家再生士の同行: 私たちが認定した古家再生士は、賃貸不動産の知識と格安リフォームのスキルを兼ね備えた専門家です。彼らは「躯体の強度」や「家賃相場」を即座に判断し、「数字が合わない物件」には容赦なく「やめときましょう」とストップをかけます。
仲間との情報交換: 私たちの物件見学ツアーでは、同じ志を持つ仲間と情報交換ができます。多角的な視点からアドバイスをもらうことで、あなたの判断ミスを防ぐことができます。
4. 理事長の失敗談と成功事例:買ってはいけない戸建てを宝に変えた実話
4-1. 「見た目の安さ」に騙された最初の失敗と、そこから得た教訓
私自身も、空き家・古家投資を始めた当初は失敗を経験しました。
私が最初に買った物件の一つは、駅から遠く、山の上にある築50年の木造アパートでした。不動産業者にも「無理」と断言されるほどの、まさに「買ってはいけない物件」です。
教訓1: 労力を惜しまない: 当時、私はその物件の沿線にある100軒弱の賃貸業者に自ら訪問し、物件を売り込みました。その結果、「山の上にあるから嫌でも歩く」という理由で入居を決めた方もいました。
教訓2: 諦めない実践: 業者任せにするのではなく、自ら行動し、「戸建て賃貸は競争が少ない」という強みを信じて突き進んだ結果、3ヶ月で満室になりました。
失敗は恥ずかしいことじゃない。むしろ、失敗から学ぶことが最も価値があると、私は確信しています。
4-2. 再生実績2,467棟!失敗物件を利回り20%超に変えた会員事例
私たちの協議会には、一見すると「買ってはいけない」と思われる物件を、高収益物件に変えた事例が数多くあります。
借地権物件で利回り25%超: 通常、不動産業者が避ける借地権付きの物件を、会員の一人が購入。資産価値が低い分、安く購入できるため、「相場家賃からの逆算」を徹底し、利回り25%という驚異的な数字を叩き出しました。
駐車場なし物件を猫OKで満室: 地方では必須とされる駐車場がない物件を、猫が12匹いるご家族に貸し出した事例もあります。キャットウォークなどの差別化リフォームと、家賃1万円増額で、入居者の悩みを解決しつつ、安定収益を確保しました。
地方は宝の山です。土地が広く、物件価格が安いため、工事費に予算をかけやすく、都市部では難しい高利回り物件を実現できるのです。
5. 【社会貢献と収益の両立】古家再生投資に宿る「4方よしモデル」の使命
私たち全国古家再生推進協議会が最も大切にしているのは、この「4方よしモデル」です。単なる金儲けではなく、社会に貢献しながら収益を上げる、持続可能なビジネスだと確信しています。
5-1. 古家再生投資が実現する「貸主・借主・地域・自分」の幸せ
「4方よし」とは、以下のすべてが幸せになる仕組みです。
買主よし(投資家/大家): 低予算で投資を始め、利回り12〜15%以上の安定収益を得られる(あなたの成功)。
借主よし(入居者): 再生された戸建てに、手頃な家賃(相場より少し安い設定)で広くて良質な住環境を得られる(低所得者や子育て世帯の住宅問題解決)。
地域よし: 放置されていた空き家が解消され、治安改善、景観向上、地域活性化につながる(社会課題の解決)。
売主よし: 処分に困っていた古い物件が生まれ変わり、相続問題が解決する。
この「4方よし」の土台があるからこそ、私たちは不動産業界の常識にとらわれず、安心して投資を続け、拡大することができるのです。
5-2. 日本の空き家問題解決に貢献する協議会の取り組み
私たちは、空き家問題という社会課題に真正面から取り組んでいます。
再生実績2,467棟のインパクト: 2025年10月20日時点で、これだけの空き家を市場に戻し、日本社会に貢献しています。
災害時の貢献: 能登半島地震の際、私たちは被災地の再生士と連携し、被害を受けた再生物件の修繕を迅速に進めました。また、インスタントハウスの設置費用を寄付するなど、組織として地域社会を支える活動を行っています。
空き家・古家投資は、単なるビジネスではなく、持続可能な社会づくり(SDGs)に直結する、誇りを持てる事業なのです。
6. 「机上の空論」で終わらせないための実践ロードマップと羅針盤
6-1. チェックリストの精度を100%にする「知識」と「仲間」の重要性
「買ってはいけない戸建て」を避ける7つのチェックリストは強力ですが、知識だけでは何も始まりません。
知識30%:経験70%の法則: 不動産投資の成功は、知識よりも経験に大きく左右されます。
実践の場(物件見学ツアー): 私たちの物件見学ツアー(累計2,196回開催)では、リフォーム前、工事中、完成物件を一度に見ることで、「ボロ家がどう変わるか」を体感し、目利き力という経験値を積むことができます。
独断で物件を購入するのではなく、プロの知恵と仲間というネットワークを最大限に活用すること。これがリスク極限排除の唯一の方法です。
6-2. 古家再生投資プランナー®️という「羅針盤」が導く成功への最短ルート
「何を、どこまで、どう学ぶか分からない」という方のために、私たちは古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座(認定者数1,429人)を提供しています。
この講座は、不動産の「ふ」の字も知らなかった小さな町工場の経営者だった私が、誰でも再現できるように体系化したノウハウです。
体系的な知識: 物件の見方、家賃設定、リフォームコスト削減術、融資の活用法まで、大家業に必要な「人・モノ・カネ・情報」のすべてを学べます。
プロのネットワーク: 認定者になれば、古家再生士®️(工務店)や先輩大家のネットワークに入り、物件の紹介やリフォームの相談など、卒業後も継続的なサポートを受けることができます。
この資格は、あなたが不安を抱えながら投資の荒波をさまようのではなく、確かな羅針盤を持って成功へと進むための最短ルートとなるでしょう。
まとめ
「買ってはいけない戸建て」は、知識と経験の欠如が生み出す幻想にすぎません。正しいノウハウがあれば、それは「宝の山」に変わります。
私たちが実践するリスク極限排除の投資術は、以下の3点に集約されます。
致命的な欠陥(ワースト3)を徹底的に排除する。(躯体欠陥、再建築不可、災害リスク)
家賃逆算法に基づき、感情ではなく数字で「儲かる購入額」を決定する。
7つのチェックリストを羅針盤として用い、プロのネットワークで独断を避ける。
「大金は用意できない…」「何から始めればいいか分からない…」と迷っている時間は、賃料収入を失っているのと同じです。
「いつかやりたい」ではなく「今すぐ行動」を起こすことが、あなたの人生を変える転機となります。
まずは一歩を踏み出し、あなたの人生を変える挑戦を始めてみませんか。
POST: 2025.11.21