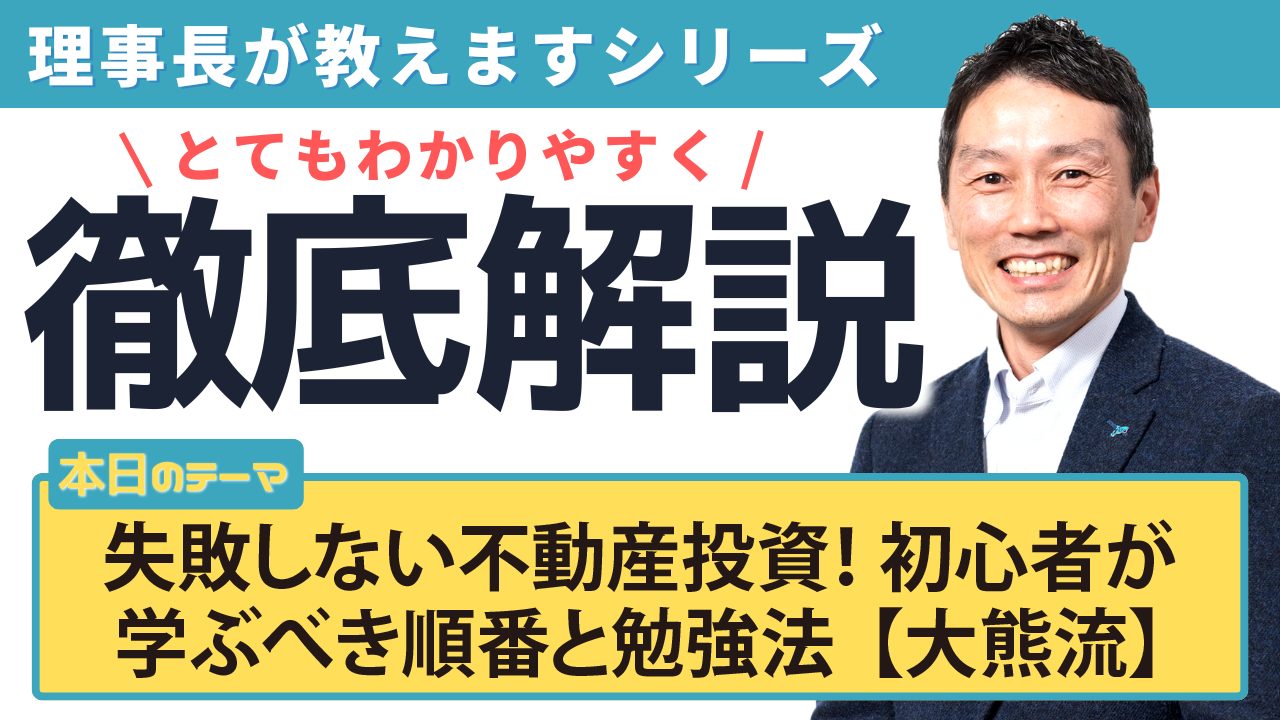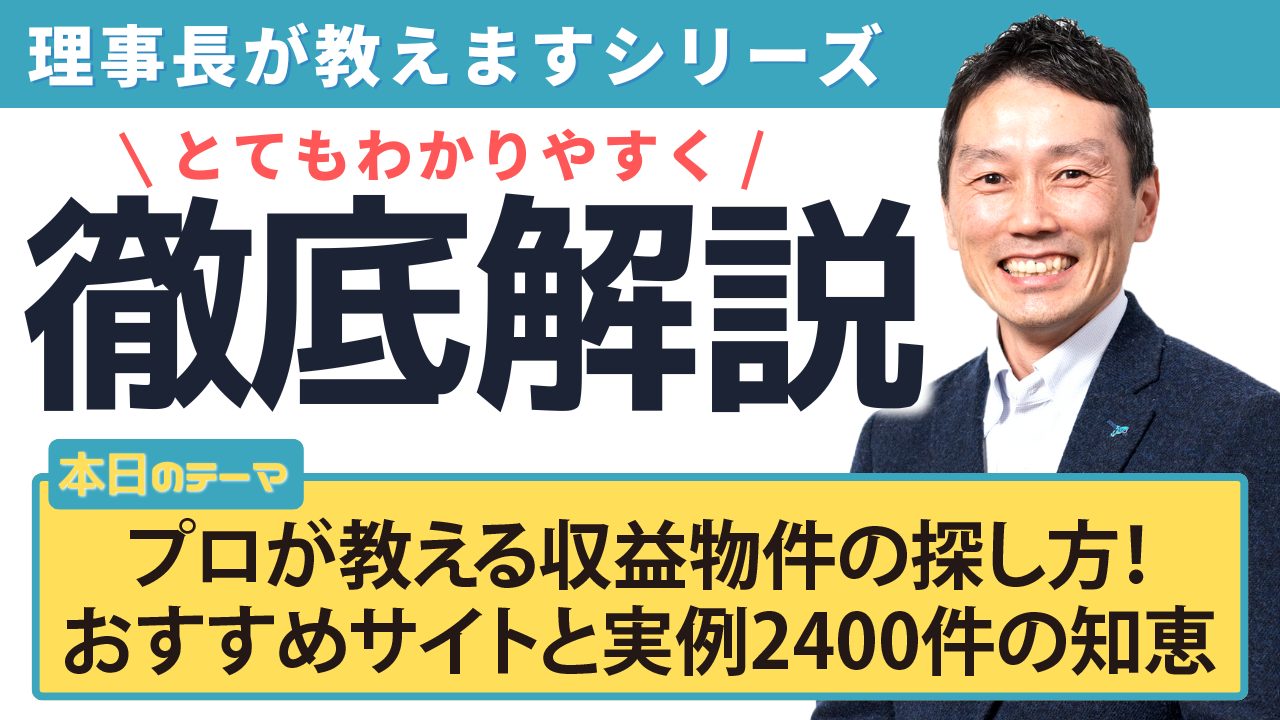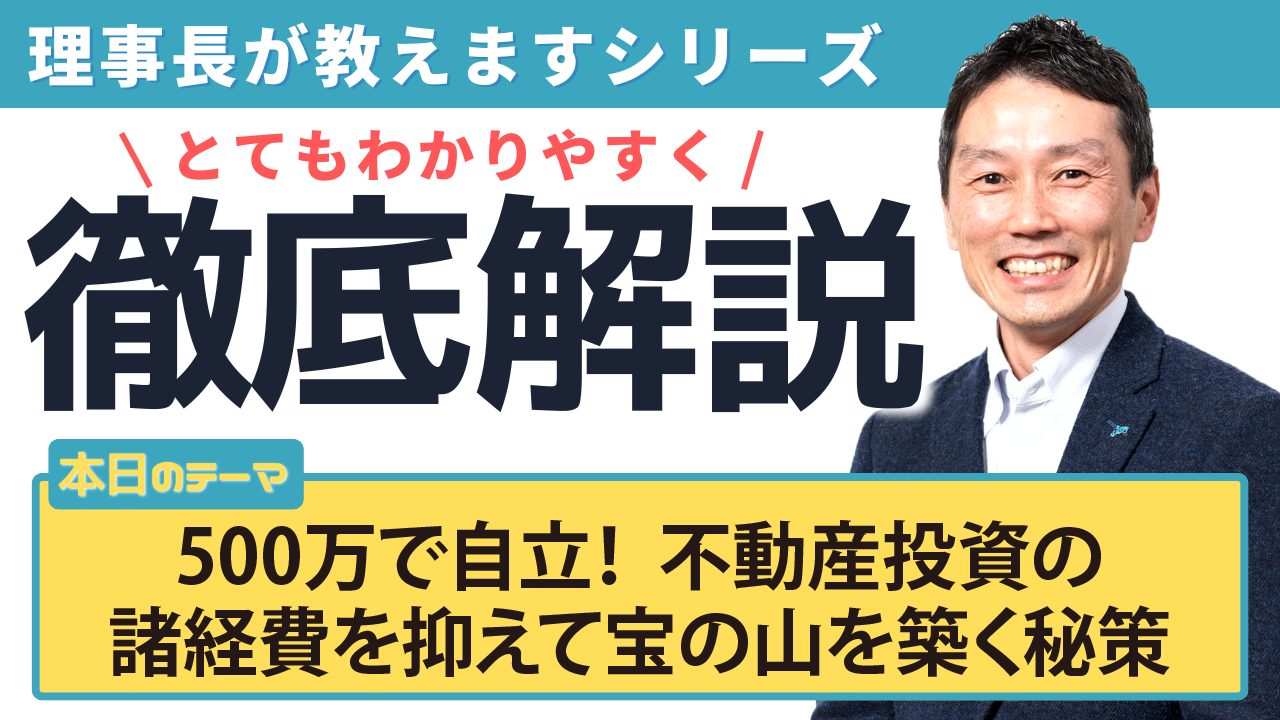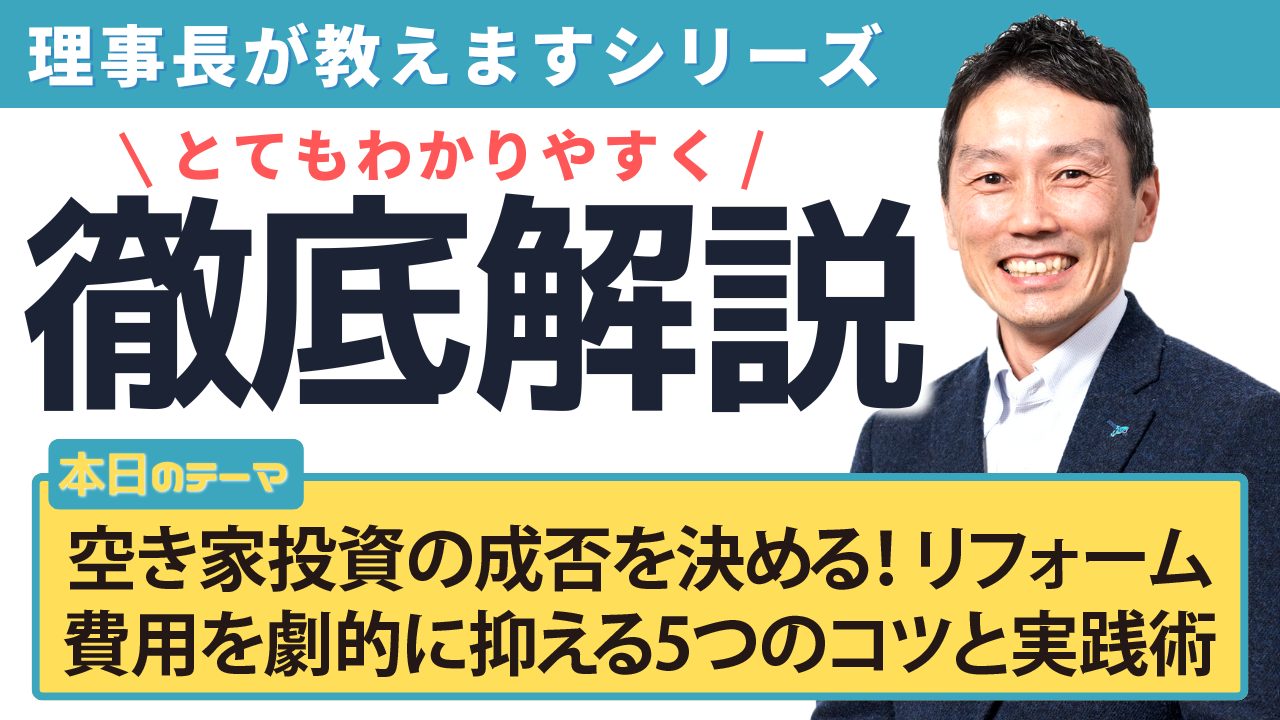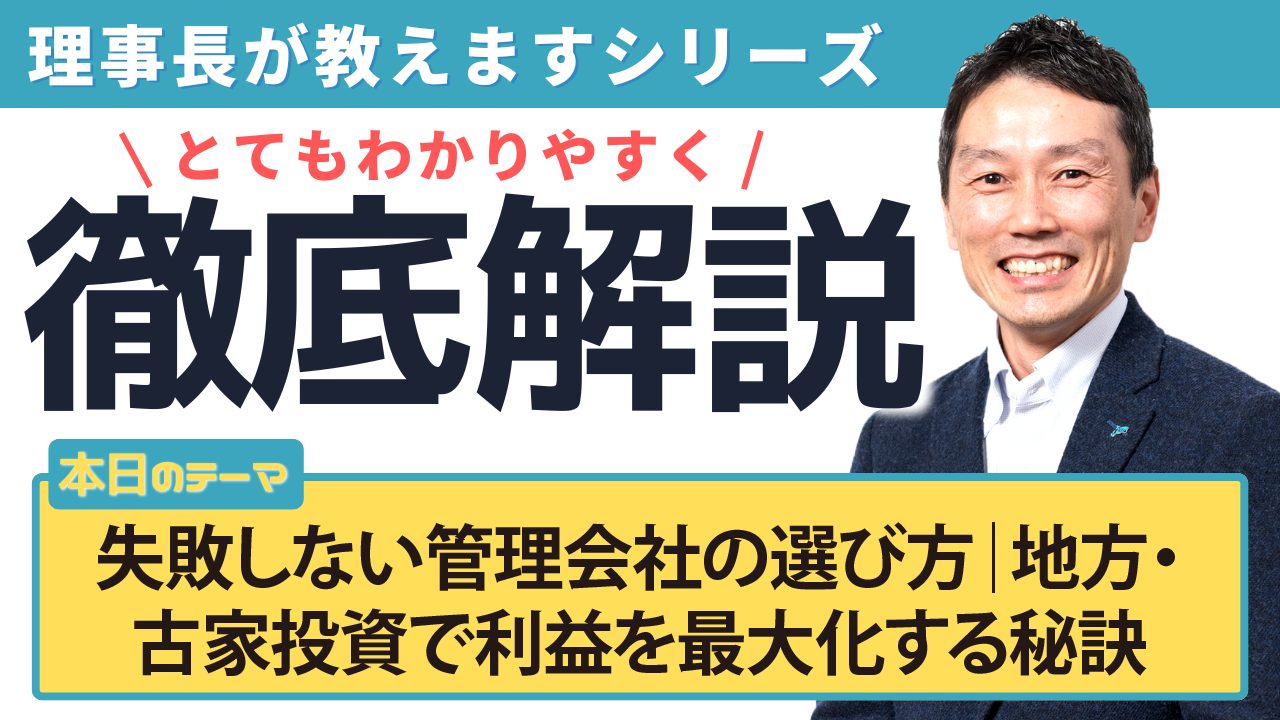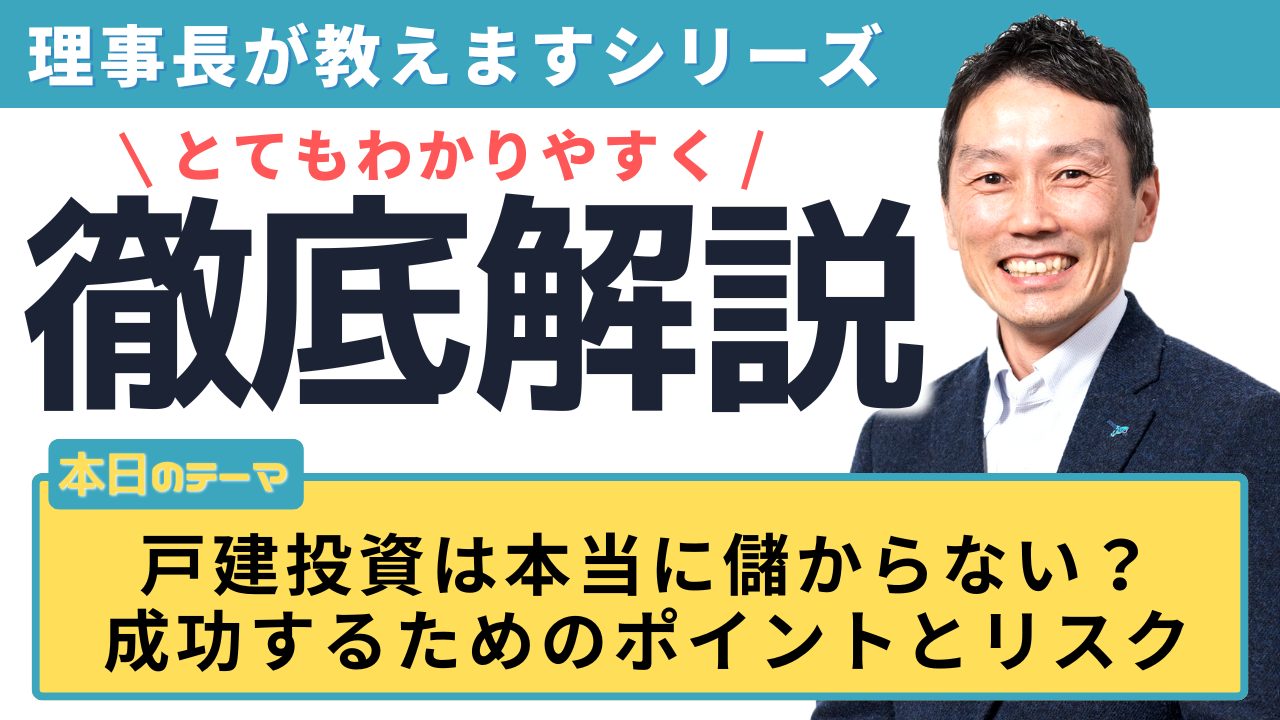
こんにちは。(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
「戸建て投資は儲からない」「リスクが高い割にリターンが少ない」といった声を耳にして、一歩を踏み出せずにいませんか?確かに、インターネットや書籍では戸建て投資の失敗談も多く語られており、不安に感じるのは当然のことです。しかし、本当に戸建て投資は儲からないのでしょうか。
結論から申し上げますと、**正しい知識と戦略さえあれば、戸建て投資は非常に有効な資産形成の手段となり得ます。** むしろ、他の不動産投資にはない独自の魅力と可能性を秘めているのです。
この記事では、「戸建て投資は儲からない」と言われる理由を徹底的に分析し、そのうえで、空室リスクや維持管理コストといった課題を乗り越え、成功を掴むための具体的なポイントを私の経験と数々の成功事例をもとに詳しく解説します。
この記事を最後までお読みいただければ、戸建て投資に対する漠然とした不安が解消され、あなたにとって戸建て投資が有望な選択肢であるかどうかの判断ができるようになるはずです。さあ、一緒に戸建て投資の真実を探求していきましょう。
目次
戸建て投資の基本理解
まずは、戸建て投資がどのようなものなのか、その基本的な概念と市場の現状を正しく理解することから始めましょう。基礎知識を固めることが、成功への第一歩です。
戸建て投資とは何か?基本的な定義を解説します
戸建て投資とは、その名の通り、一戸建ての住宅を購入し、賃貸物件として貸し出すことで家賃収入を得る不動産投資の手法です。アパートやマンション一棟を丸ごと所有する「一棟投資」や、マンションの一室を所有する「区分マンション投資」とは異なり、土地と建物を一つの単位として扱うのが特徴です。
この投資のメリットとデメリットを整理してみましょう。
【メリット】
●土地という資産が手に入る
マンション投資と違い、土地も所有することになるため、資産価値がゼロになりにくいです。建物が古くなっても、土地の価値は残ります。
●入居期間が長い傾向
戸建てに住むのは、主に子どもがいるファミリー世帯です。一度入居すると、子どもの学校などの関係で長く住んでくれる傾向があり、安定した家賃収入につながります。
●競合が少ない
賃貸市場ではアパートやマンションが供給過多になる一方、賃貸用の戸建ては数が少なく、希少性があります。
●多様な出口戦略
賃貸として貸し出すだけでなく、実需(自分で住む人)向けに売却したり、更地にして土地として売ったりと、状況に応じた出口戦略を描きやすいです。
【デメリット】
●空室リスクが高い
アパートやマンションと違い、入居者は一世帯のみです。退去されると、次の入居者が決まるまで家賃収入はゼロになります。
維持管理の手間と費用建物の修繕(外壁、屋根など)から庭の手入れまで、すべてオーナーの責任範囲となり、管理の手間と費用がかかります。
●流動性が低い
アパートやマンションに比べ、売却に時間がかかる場合があります。
具体例を挙げると、地方に存在する築古の空き家を考えられます。例えば、100万円という価格で売られているボロ戸建てを見つけたとします。この物件を300万円かけてリフォームし、月々7万円の家賃で貸し出すことができれば、年間84万円の収入になります。初期投資400万円は、約5年で回収できる計算です。もちろん、これは単純計算であり、実際には税金や修繕費がかかりますが、少ない自己資金からでも始められる資産形成の可能性があることを理解していただけるでしょう。
特に、築古の空き家を再生する投資は、社会問題の解決に貢献しながら資産を築くことができるうえ、非常にやりがいのある分野です。自分でDIYを施してコストを抑え、魅力的な住宅に生まれ変わらせることも可能です。こうした物件を一棟、二棟と持っていくことで、安定したキャッシュフローの基盤を建築していくことができるのです。
戸建て投資の市場動向、今後の予測は?
現在の**不動産投資**市場において、中古**戸建て**は非常に注目されている分野です。新築物件の価格が高騰を続ける中、**比較的**価格が**安定**している中古物件に目を向ける投資家が増えています。
【最近の市場トレンド】
総務省の「住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家は増加傾向にあり、中古住宅の流通市場を活性化させようという国の後押しもあります。特に、リモートワークの普及により、都心から少し離れた郊外や地方の戸建て住宅への需要が高まっている点は見逃せません。かつては**東京**のような大都市への集中が一般的でしたが、今はライフスタイルの多様化に伴い、住まいの選択肢も広がっています。
【地域ごとの価格変動】
価格の動向は地域によって大きく異なります。首都圏や関西圏などの都市部では、利便性の高いエリアの戸建て価格は依然として高い水準を維持しています。一方で、地方都市やその郊外では、手頃な価格の物件が多く存在します。
ここで重要なのが「地方と都市のギャップを**利用**する」という視点です。例えば、まず収益性の高い地方の物件で経験と資金を積み、その収益を元に資産価値が安定している都市部の物件を購入していく、という戦略です。これにより、収益性と資産性のバランスが取れたポートフォリオを組むことが可能になります。
【今後の予測】
2025年には、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、相続による空き家の発生がさらに加速すると予測されています。これは、投資家にとっては優良な中古物件を安く手に入れるチャンスが増えることを意味します。
ただし、物件を取得すれば固定資産税などの税金が毎年かかります。そのため、物件を検討する際は、表面的な価格だけでなく、将来にわたってかかるコストや賃貸需要を総合的に判断することが不可欠です。
私たち全国古家再生推進協議会のような専門機関のサイトやホームページでは、常に最新の市場情報や物件情報を提供しています。こうした情報を活用し、自分なりの市場観を養っていくことが、これからの不動産投資で成功するためには欠かせないでしょう。
戸建て投資が儲からないと言われる3つの理由とは?
「戸建て投資は儲からない」という声の背景には、いくつかの明確な理由が存在します。これらを事前に理解し、適切な対策を講じることができれば、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。
空室リスクが収入に与える深刻な影響とは?
戸建て投資における最大のリスクは、何と言っても「**空室**リスク」です。アパートやマンションのように複数の部屋があれば、一室が空室でも他の部屋の家賃でカバーできます。しかし、戸建て投資は入居者が一世帯のみ。退去が発生すれば、その瞬間から家賃**収入**はゼロになります。
【空室期間中の負担】
収入がゼロになる一方で、支出が止まるわけではありません。
・ 固定資産税・都市計画税
・火災保険料
・ローンの返済
・ 最低限の光熱費(通水など)
・管理会社への委託料(契約による)
これらの費用は、空室期間中も容赦なくかかり続けます。実際、経験の浅い大家さんの中には、この状況に耐えきれず、焦って不適切な条件で入居者を決めてしまい、後々のトラブルに繋がる事例も少なくありません。
【空室リスクを減らす対策】
この問題を乗り越えるための対策は、突き詰めれば「入居者に選ばれる物件にすること」に尽きます。
1.適正な家賃設定
周辺の家賃相場を徹底的に調査し、物件の価値に見合った、かつ競争力のある家賃を設定することが重要です。
2.ターゲットを明確にする
ファミリー層向けなのか、単身者・カップル向けなのか。ターゲットを絞り、その層に響く設備や間取りにリフォームすることが入居率を高める鍵です。
3. 募集活動の強化
複数の不動産会社に募集を依頼したり、魅力的な写真や紹介文を用意したりと、積極的に情報を発信する必要があります。
一度退去が発生すると、次の入居者が決まるまでの目安は1〜3ヶ月と言われていますが、物件やエリアによっては半年以上かかる可能性もあります。この期間の損失をあらかじめ計画に織り込んでおく冷静さが、安定した運営には不可欠です。
維持管理コストは予想以上に増加する?
「物件を安く買えたから成功だ」と考えるのは早計です。戸建て投資の経営において、見落とされがちなのが維持管理コストです。特に築年数が古い物件ほど、このコストは予想以上に増え、収益を圧迫する要因となります。
【老朽化による修繕費用の増加】
建物は時間とともに必ず劣化します。安定した賃貸経営を続けるには、計画的な修繕が欠かせません。
●外壁・屋根の塗装/修繕(10〜15年周期)
100万円以上の費用が発生することも珍しくありません。雨漏りなどが発生すると、内部の構造材まで傷み、さらに高額な修繕が必要になります。
●給湯器の交換(10〜15年周期)
15〜30万円程度かかります。
●水回りの設備(キッチン、浴室、トイレ)
パッキンの交換といった小さな修繕から、設備自体の交換まで、**トラブル**が**多い**箇所です。
●内装の修繕
入居者の退去時には、壁紙の張り替えや床の補修など、原状回復費用が**かかり**ます。
【予期しない費用の発生】
計画的な修繕に含めにくいのが、突発的なトラブルです。
・ 給排水管の詰まりや破損
・シロアリ被害
・ 台風や地震による損害
こうした予期せぬ出費に対応するためには、家賃収入の一部を修繕費として積み立てておくことが極めて重要です。私の周りの大家さんを見ていても、成功している方は例外なく、家賃収入の20〜30%程度を修繕・メンテナンス用に確保しています。家賃をすべて自分の生活費に使ってしまうと、いざという時に修繕ができず、物件の価値が下がり、入居者が見つからない…という負の流れに陥ってしまいます。
しっかりとした維持管理計画を立て、将来の支払いに備えること。これこそが、長期的に安定した運営を実現するための秘訣です。
地域の賃貸需要の変化に対応できていますか?
物件自体のコンディションが良くても、その物件が建っているエリアの賃貸需要が低下してしまっては、元も子もありません。特に、人口減少が続く日本では、地域の需要変化は非常に重要なリスク要因です。
【人口減少と経済状況の影響】
日本の多くの地方都市では、人口減少と高齢化が深刻な問題となっています。若者世代が都市部へ流出し、地域の主要産業が衰退すると、賃貸住宅への需要そのものが先細りしてしまいます。たとえ「ボロ家」を安く購入し、きれいにリフォームしたとしても、住みたい人がいなければ家賃収入は得られません。
例えば、ある企業の工場が撤退したことで、その周辺のアパートや戸建ての空室率が一気に上昇した、という話は決して珍しくありません。投資を検討している地域の人口動態や、基幹産業の動向といったマクロな環境を把握しておくことは、投資家としての必須スキルです。
【需要に応じた投資戦略】
では、どうすれば良いのでしょうか。重要なのは、需要の変化を予測し、それに合わせた戦略を立てることです。
●エリア選定の徹底
これから人口が増える、あるいは減りにくいエリアを選ぶことが基本です。都市計画や再開発の情報をチェックし、将来性のある地域を見極めましょう。例えば、同じ埼玉県内でも、都心へのアクセスが良く再開発が進むエリアと、そうでないエリアでは将来性が大きく異なります。
●ターゲット層の明確化
その地域ではどのような層(例:子育て世帯、単身者、外国人労働者)からの需要が高いのかを分析し、ターゲットに合わせた物件を提供することが重要です。庭付きの戸建ては、ペット可にすることで他物件との差別化を図れる部分もあります。
●変化への柔軟な対応
もし所有物件のエリアの需要が低下してきたら、損切りして早く売却することも一つの戦略です。一つの物件に固執せず、ポートフォリオ全体で利益を最大化するという事業的な視点が求められます。
物件の状態だけでなく、その物件を取り巻く環境の変化に常にアンテナを張っておくこと。これが、変化の激しい時代に賃貸経営を成功させるための鍵となるのです。
戸建て投資のメリットとデメリットを再確認しよう
「儲からない理由」を知ると不安になるかもしれませんが、戸建て投資にはそれを上回るほどの魅力的なメリットも存在します。ここで改めてメリットとデメリットを整理し、バランスの取れた視点を持ちましょう。
なぜ初期投資が少なく始めやすいのですか?
不動産投資と聞くと、数千万円単位の高額な資金が必要というイメージがあるかもしれません。しかし、戸建て投資、特に中古の戸建て投資は、他の不動産投資と比べて少ない資金で始められるのが最大のメリットです。
【手持ち資金が少なくても始めやすい】
その理由は、物件価格そのものが安いからです。都心部の新築マンションなら億単位も珍しくありませんが、地方や郊外に行けば、数百万円、場合によっては100万円台で購入できる築古の戸建てが数多く存在します。このような物件は、まさに初心者が初めての不動産投資に挑戦するうえで、心理的にも金銭的にもハードルが低いと言えるでしょう。
【ローンを利用しやすい】
少額の物件であれば、全額自己資金で購入することも不可能ではありません。しかし、より大きなリターンを狙うなら、ローン(融資)の活用が有効です。物件価格が低いため、金融機関からの借入額も少なくなり、審査のハードルも相対的に下がります。また、日本政策金融公庫など、中小零細企業や個人事業主向けの融資を積極的に行っている金融機関を利用するのも一つの方法です。
【物件選びでコストを抑えられる】
初期費用を抑えるためには、物件選びが重要です。例えば、あえてリフォームが必要な「ボロ家」を安く買い、自分でDIYをしたり、信頼できる工務店に依頼したりして再生させることで、トータルコストを大幅に抑えることが可能です。この「再生」のプロセスにこそ、古家再生投資の醍醐味があります。
このように、戸建て投資は資産形成の基礎を築きたいけれど手持ち資金が少ない、という方にとって、非常に魅力的な選択肢となり得るのです。
長期的な収益性に潜む不安要素とは?
一方で、手軽に始められるからといって、長期的な収益性が安泰とは限らないのがデメリットです。成功のためには、いくつかの不安要素を正しく認識しておく必要があります。
【市場の変動に影響されやすい】
不動産価格や家賃相場は、景気の動向、金利の変動、地域の人口増減など、様々な外部要因に影響を受けます。特に、一つの物件しか所有していない場合、そのエリアの賃貸需要が低下すれば、収益は直接的な打撃を受けます。期待していた利回りが、気づけば大幅に低下していた、という失敗も十分にあり得ます。
【維持管理コストがかかる】
前述の通り、戸建ては建物と土地を丸ごと管理するため、修繕費やメンテナンス費用が継続的に発生します。築年数が経過するほど、その費用は増加する傾向にあります。特に、購入時に物件の状態をしっかりと見極めないと、後から高額な修繕費が発生し、利益をほとんど食いつぶしてしまうリスクがあります。長く安定した収益を出すためには、このコストをいかに抑え、計画的に資金を確保するかが問われます。
【賃貸需要の変化を考慮する必要がある】
今は人気のあるエリアでも、10年後、20年後も同じとは限りません。周辺に新しいアパートやマンションが建ち、競争が激化するかもしれません。あるいは、地域の産業構造が変化し、人口が流出するかもしれません。長期的な視点で地域の将来性を見通し、場合によっては適切なタイミングで売却するという「出口戦略」を常に頭に入れておくことが重要です。
これらのデメリットは、裏を返せば、しっかりとした知識と計画があれば乗り越えられる課題でもあります。安易な期待はせず、リスクを直視し、それに対する備えを怠らないこと。それが、戸建て投資で失敗しないための鉄則です。
「儲からない」を覆す!戸建投資で成功する戦略
「儲からない」と言われるリスクを理解したうえで、それらを乗り越え、成功を掴むための具体的な戦略について解説します。鍵となるのは「物件選び」と「リフォーム・メンテナンス」です。
儲かる物件選びに欠かせないポイントとは?
戸建て投資の成否は、9割が「物件選び」で決まると言っても過言ではありません。どのような物件を購入するか。その最初の選択肢が、将来の収益を大きく左右します。以下に挙げるポイントを必ずチェックしましょう。
1. 立地の重要性を理解する
最も重要なのが立地です。いくら建物が立派でも、需要のない場所では意味がありません。
●交通の便
最寄り駅からの距離、主要駅へのアクセス時間は重要です。特にファミリー層をターゲットにする場合、車での移動がメインになることも多いため、幹線道路へのアクセスや駐車場の有無も考慮しましょう。
●周辺環境
スーパー、コンビニ、学校、病院、公園などの生活利便設備が整っているかは、入居者にとって大きなポイントです。実際に現地を歩き、自分の目で住環境をチェックすることが大切です。
●ハザードマップの確認
地震や水害などのリスクが少ないエリアかどうかも、長期的な資産価値を保つうえで必須の確認事項です。
2. 市場動向をリサーチする
そのエリアの賃貸市場を徹底的に調査します。
家賃相場
周辺の類似物件がいくらで貸し出されているかを調べ、購入しようとしている物件でどの程度の家賃が期待できるかを把握します。
空室率
そのエリアの空室率を調べ、賃貸需要が安定しているかを確認します。
競合物件の分析
周辺にどのような競合物件があるかを比較し、自分の物件が持つ強み(例:ペット可、庭付き、リノベーション済みなど)を明確にします。
3. 物件の状態を確認する
特に中古物件の場合、建物の状態を見極めることが、将来の予期せぬ出費を避けるために不可欠です。
●構造部分
基礎にひび割れはないか、建物に傾きはないか、雨漏りの形跡はないかなど、建物の骨格となる部分を重点的に確認します。
●設備の状態
給湯器やキッチン、浴室などの設備が、あと何年数くらい使えそうかを確認します。
●再建築不可物件に注意
接道義務を果たしていないなどの理由で、一度建物を解体すると新しい建物を建てられない「再建築不可」物件があります。こうした物件は価格が安いですが、担保価値が低くローンが付きにくい、出口戦略が限られるといったデメリットがあるため、初心者は避けたほうが賢明です。
これらのポイントを総合的に判断し、複数の物件を比較検討することが、成功への近道です。このプロセスにおいて、専門的な知識が必要となります。そこで役立つのが、私たち(一社)全国古家再生推進協議会が認定する「古家再生投資プランナー®」です。プランナーは、こうした物件の見極め方を体系的に学ぶため、より確かな目で優良物件を探すことが可能になります。
なぜリフォームとメンテナンスが重要なのでしょうか?
良い物件を安く手に入れたら、次のステップは「物件の価値を最大化する」ことです。そのための手段が、リフォームとメンテナンスです。これらを適切に行うことで、入居者からの需要を確保し、長期的に安定した収益を生み出すことができます。
【リフォーム計画を立てる】
リフォームは、ただ古くなった部分を新しくすれば良いというものではありません。
●ターゲットに合わせる
誰に住んでほしいのかを明確にし、そのターゲット層が好む内装や設備を導入します。例えば、若いカップル向けならデザイン性の高いキッチン、ファミリー向けなら収納の多さや安全性を考慮したリノベーションが有効です。
●費用対効果を考える
無限に予算をかけられるわけではありません。どこにお金をかければ入居者に最も響くのか、費用対効果を常に意識しましょう。水回り(キッチン、浴室、トイレ)は、費用がかかりますが、入居者の満足度に直結しやすい部分です。
●コストを抑える工夫
すべてを業者に任せるのではなく、自分でできる部分はDIYに挑戦する(セルフリノベーション)ことで、コストを大幅に削減できます。壁の塗装や床材の張り替えなど、少し手間はかかりますが、大きな節約につながります。
【定期的なメンテナンスを実施する】
一度リフォームして貸し出したら終わり、ではありません。建物の価値を維持し、大きなトラブルを未然に防ぐためには、定期的なメンテナンスが必須です。
●定期点検
外壁のひび割れ、屋根の状態、給排水管の異常など、定期的に物件の状態をチェックします。入居者がいる場合でも、許可を得て点検させてもらうことが重要です。
●小さな修繕への迅速な対応
入居者から「給湯器の調子が悪い」「雨樋が詰まった」といった連絡があった場合、迅速に対応することが、入居者満足度を高め、長期入居につながります。
リフォームや修繕には専門的な情報と知識が必要です。どこを、どのように、いくらで直すべきか。この判断を誤ると、無駄な費用がかさんでしまいます。
「古家再生投資プランナー®」の資格取得講座では、こうしたリフォームの勘所や、コストを抑えつつ効果的な修繕を行うためのノウハウを具体的に学びます。物件を再生し、価値を入れていくスキルは、戸建て投資で成功するための強力な武器となるのです。
あなたはどっち?戸建て投資に向いている人の特徴
戸建て投資は、誰にでも向いているわけではありません。成功するためには、ある種の適性が必要です。ここでは、戸建て投資に特に向いている人の特徴を2つのタイプに分けてご紹介します。
リスクを取れる投資家とはどんな人ですか?
不動産投資は、元本が保証された預金とは異なり、必ずリスクが伴います。このリスクを正しく理解し、許容し、コントロールできる人でなければ、成功は難しいでしょう。
【リスク管理の重要性を理解する】
「儲かるかもしれない」という期待だけでなく、「損をするかもしれない」という現実を直視できる冷静さが必要です。空室、家賃下落、予期せぬ修繕費の発生、金利上昇、災害など、考えられるリスクを事前にリストアップし、それぞれに対する対策を立てられる人が向いています。例えば、「自己資金は最低でも物件価格の2〜3割は用意しておく」「家賃収入の3割は修繕費として積み立てる」といった具体的なルールを自分で設け、それを守れる規律が求められます。
【多様な投資先を持つ】
一つの物件に全財産をかけるのは非常に危険です。最初の一棟が成功したら、二棟、三棟と物件を増やしていくことで、リスクは分散されます。ある物件が空室になっても、他の物件の家賃収入でカバーできるからです。また、地方の高利回り物件と、都市部の資産価値が安定した物件を組み合わせるなど、ポートフォリオ全体でリスクとリターンのバランスを持つ視点が重要です。
【市場の変動に柔軟に対応する】
不動産市場は常に変化しています。金利の動向、税制の変更、地域の再開発計画など、関連する情報を常に収集し、学ぶ姿勢が欠かせません。業者や管理会社任せにせず、自己の判断で戦略を修正していく柔軟性が必要です。時には、損失を最小限に抑えるために、損切り(売却)を決断する勇気も可能でなければなりません。
こうしたリスクを前向きに捉え、ゲームのように戦略を練ることを楽しめる人こそ、真の「リスクを取れる投資家」と言えるでしょう。
なぜ地域貢献を重視する人が成功しやすいのですか?
意外に思われるかもしれませんが、「儲けたい」という気持ちと同じくらい、「地域に貢献したい」という思いを持つ人が、結果的に戸建て投資で成功する傾向にあります。
【地域のニーズを把握する】
地域貢献を考える人は、自然と「この地域には何が足りないのか」「どんな人が住まいに困っているのか」という視点で物事を考えます。例えば、
・「このエリアはファミリー世帯が多いのに、ペットと暮らせる賃貸が少ない」→ペット可の戸建てを提供する。
・「外国人の技能実習生が増えているのに、受け入れ先が不足している」→シェアハウスとして再生する。
・「高齢の単身者が安心して暮らせる住まいがない」→バリアフリーにリフォームして貸し出す。
このように、地域のニーズを的確に捉えることで、競合が少なく、入居者に「ぜひ住みたい」と思うことができる、人気の高い物件を創り出すことができます。結果として、空室リスクが低減し、高く安定した利回りが実現できるのです。
【地域活性化に寄与する方法を考える】
放置された空き家を再生することは、それ自体が地域の景観や防犯面の改善につながる立派な地域貢献です。私の知人には、再生した古民家の一部をコミュニティスペースとして地域住民に開放し、信頼関係を築いている大家さんもいます。こうした活動は、すぐに直接的な収益には結びつかないかもしれませんが、地域での評判を高め、優良な入居者の紹介につながることも多くあります。
【地域とのつながりを大切にする】
そのため、投資というとドライなイメージがありますが、戸建て投資は非常にウェットな側面を持っています。地元の不動産会社、工務店、そしてご近所さんと良好な関係を築くことで、有益な情報を得られたり、困ったときに助けてもらえたりします。こうした「人のつながり」を大切にできる人は、長期的に見て安定した賃貸経営をやっていけるのです。
自分の資産形成と地域貢献を両立できる。これこそが、古家再生投資が持つ大きな魅力の一つであり、成功への理由でもあるのです。
失敗しないために!戸建て投資を始める前の準備
思い立ったらすぐ行動、という姿勢も大切ですが、無計画に飛び込むのは無謀です。成功確率を最大限に高めるために、始める前に必ず考慮すべき2つの重要な準備について解説します。
失敗しないための資金計画の立て方を解説します
「戸建て投資は儲からない」という人の多くは、この**資金**計画の甘さが原因です。どんぶり勘定ではなく、精緻な計画を立てることが、失敗を避けるための第一歩です。
【初期投資額を明確にする】
まず、物件を購入して賃貸に出すまでに、トータルでいくら必要なのかを正確に計算します。
・物件購入価格
当たり前ですが、これが基本となります。
・諸費用
意外と見落としがちなのがこの費用です。仲介手数料、登記費用、不動産取得税、印紙税、ローン手数料、火災保険料など、物件価格の7〜10%程度が目安となります。
・リフォーム費用
中古物件の場合、ほぼ必須です。どの程度のリフォームを実施するかで大きく変動しますが、あらかじめ複数の業者から見積もりを取り、現実的な金額を把握しておきましょう。
【維持費用を算出する】
次に、物件を所有し続けることで継続的に発生する費用を予測します。
・固定資産税・都市計画税
毎年必ずかかる税金です。市町村から送られてくる納税通知書で確認できます。
・管理委託料
管理会社に運営を依頼する場合、一般的に家賃の5%程度がかかります。
・修繕積立金
将来の大規模修繕に備え、家賃収入の10〜20%を毎月積み立てておくのが理想です。
・その他
町内会費や、空室時の光熱費なども考慮に入れておきましょう。
【収益予測を行う】
支出を把握したら、次はようやく収入の予測です。
・想定家賃収入
周辺の家賃相場から、現実的な家賃を設定し、年間の収入を計算します。
・空室損失
年間のうち1ヶ月分は空室になる、といったように、一定の空室期間を考慮して、実質的な収入を算出します。(例:家賃8万円なら、8万円×11ヶ月 = 88万円)
これらの計画を立てたうえで、融資を利用するのか、自己資金はいくら投入するのかを考えるのが正しい手順です。金融機関に相談する際も、こうした具体的な資金計画を提案できるかどうかで、担当者の心証は大きく変わります。2025年に向けた市場の変化も踏まえ、無理のない返済期間で計画を立てることが、安定した運用の鍵となります。
なぜ市場調査が成功の鍵を握るのでしょうか?
物件を探す前に、まず「どの市場で戦うか」を決める。これが、成功する投資家の共通点です。精度の高い市場調査こそが、あなたの投資の羅針盤となります。
【地域の需要を把握する】
「戸建て投資は儲かるか?」という問いの答えは、この地域の需要把握にかかっています。
・人口動態
総務省統計局のサイトなどで、市区町村別の人口増減や年齢構成を検索できます。人口が増加している、あるいは若年層の割合が高い地域は、将来的な賃貸需要が期待できます。
・交通インフラと開発計画
新しい駅や道路ができる計画、大型商業施設の建設計画などがあれば、そのエリアの魅力は高まります。自治体のホームページなどで情報を集めましょう。
・ターゲット層の特定
その地域に住んでいるのは、どのような人たちでしょうか?大学が近ければ学生、工場が多ければ単身の労働者、公園や学校が充実していればファミリー層、といった具合に、ターゲットを明確にすることで、どのような物件が求められているかが見えてきます。
【競合物件の分析を行う】
あなたの物件は、他の多くの賃貸物件と競争することになります。
・家賃相場の調査
SUUMOやHOME’Sといったポータルサイトを**活用**し、狙っているエリアの間取りや築年数ごとの家賃相場を徹底的に比べます。
・競合の強み・弱み
周辺の物件がどのような設備(例:無料インターネット、宅配ボックス)を導入しているか、ペット可か、などを分析し、自分の物件でどう差別化するかを考えます。
【トレンドを理解する】
不動産市場のトレンドは常に変化しています。リモートワークの普及による郊外需要の高まり、DIY可能な賃貸物件の人、古民家カフェの流行など、社会の動きに興味を持つことが、新しい投資チャンスの発見につながります。
これらの調査は、時間と手間がかかります。しかし、このプロセスを惜しむと、「儲からない物件」を掴んでしまう可能性が大きなります。もし自分一人での調査に不安があれば、信頼できる不動産会社に相談したり、私たちが開催するようなセミナーに参加したりして、専門的な知識と情報を得るのが賢明です。
大切なのは、他人の情報を鵜呑みにするのではなく、自分で調べ、考え、判断する力を養うことです。そのための第一歩として、「古家再生投資プランナー®」の資格を取得し、体系的な知識を身につけることは、非常に有効な方法と言えるでしょう。
最後に…
「戸建て投資は儲からない」というテーマでここまでお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。この記事を読んで、その言葉が、必ずしも真実ではないということをご理解いただけたのではないかと思います。
確かに、戸建て投資には空室リスクや修繕コストといった、無視できない課題が存在します。計画なしに飛び込めば、失敗する可能性は高いでしょう。しかし、それはどんな事業や投資でも同じことです。
重要なのは、リスクを正しく理解し、それに対する備えを徹底すること。そして、物件選び、資金計画、リフォーム、市場調査といった各ステップで、正しい知識に基づいた判断を下していくことです。
特に、私たちが推進する「古家再生投資」は、単なる資産形成の手段にとどまりません。社会問題化している空き家を再生させ、新たな価値を吹き込み、地域の活性化に貢献するという、大きな意義を持っています。自分の投資活動が、誰かの暮らしを支え、街を元気にする。これほどやりがいのある投資は、他にはなかなかないと私は確信しています。
「でも、何から始めていいかわからない…」
「自分一人で成功できるか不安だ…」
そう感じるのは、当然のことです。その第一歩を踏み出すために、私たちは「古家再生投資プランナー®」という資格制度をご用意しています。この講座では、私がこれまで培ってきたノウハウのすべてを注ぎ込み、物件の探し方からリフォーム、賃貸経営の基礎まで、成功に必要な知識を体系的に学ぶことができます。
資格を取得すれば、私たちが主催する物件見学ツアーに参加し、実際に優良な古家物件を購入するチャンスも得られます。あなたは一人ではありません。同じ志を持つ仲間たちと共に、投資家としての道を歩み始めることができるのです。
資産形成という視点から、あなたには投資家として目覚めてほしい。もし、あなたがこの記事を読んで少しでも心を動かされたのなら、ぜひ「古家再生投資プランナー®」への扉を叩いてみてください。あなたの挑戦を、心からお待ちしております。
POST: 2025.07.24