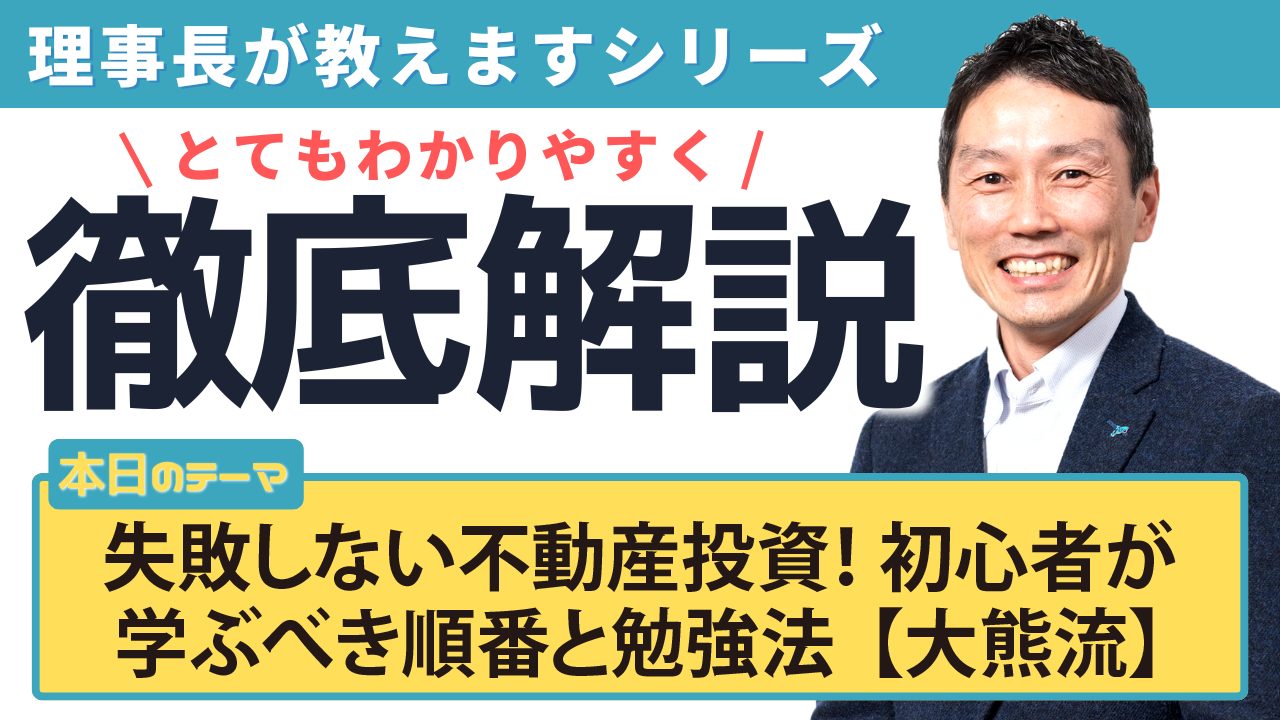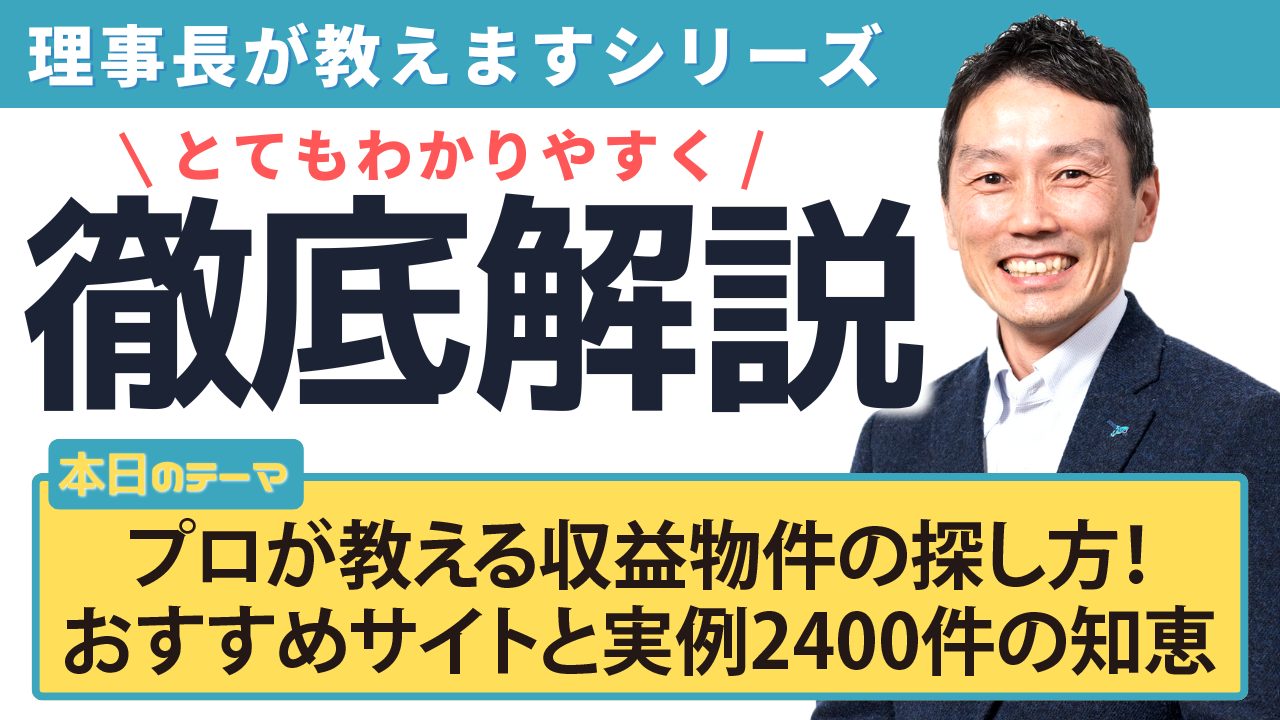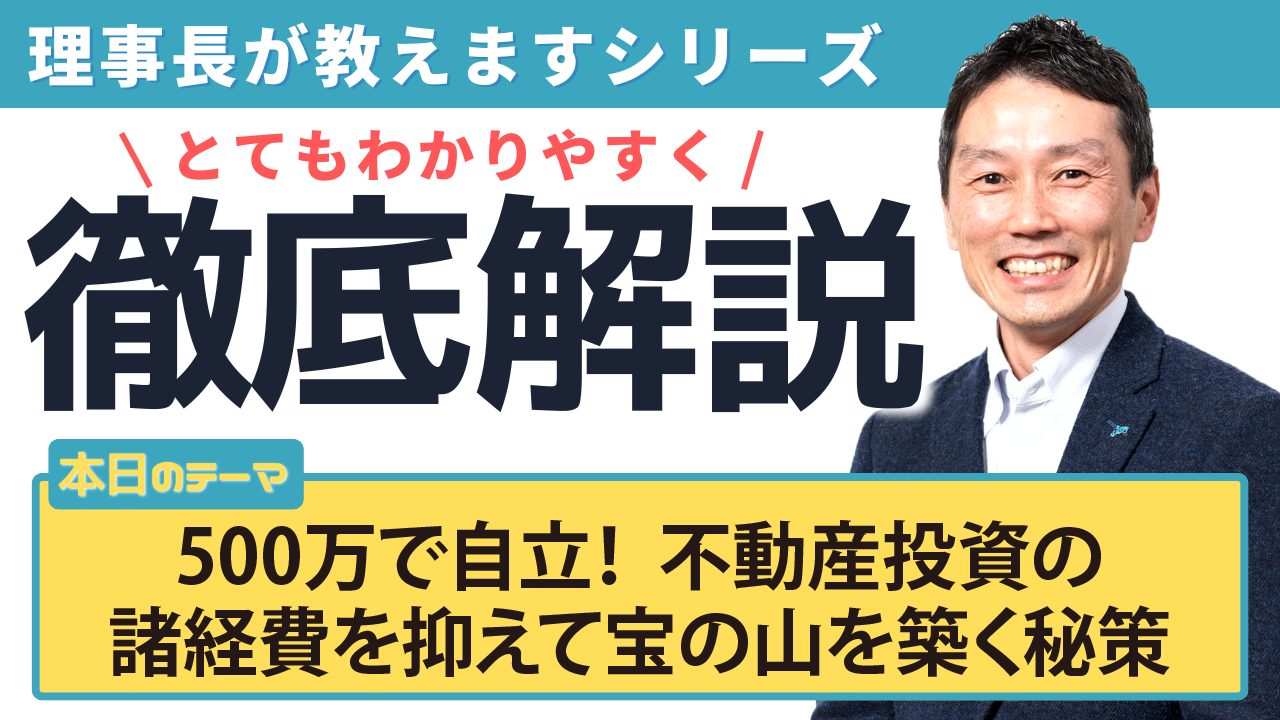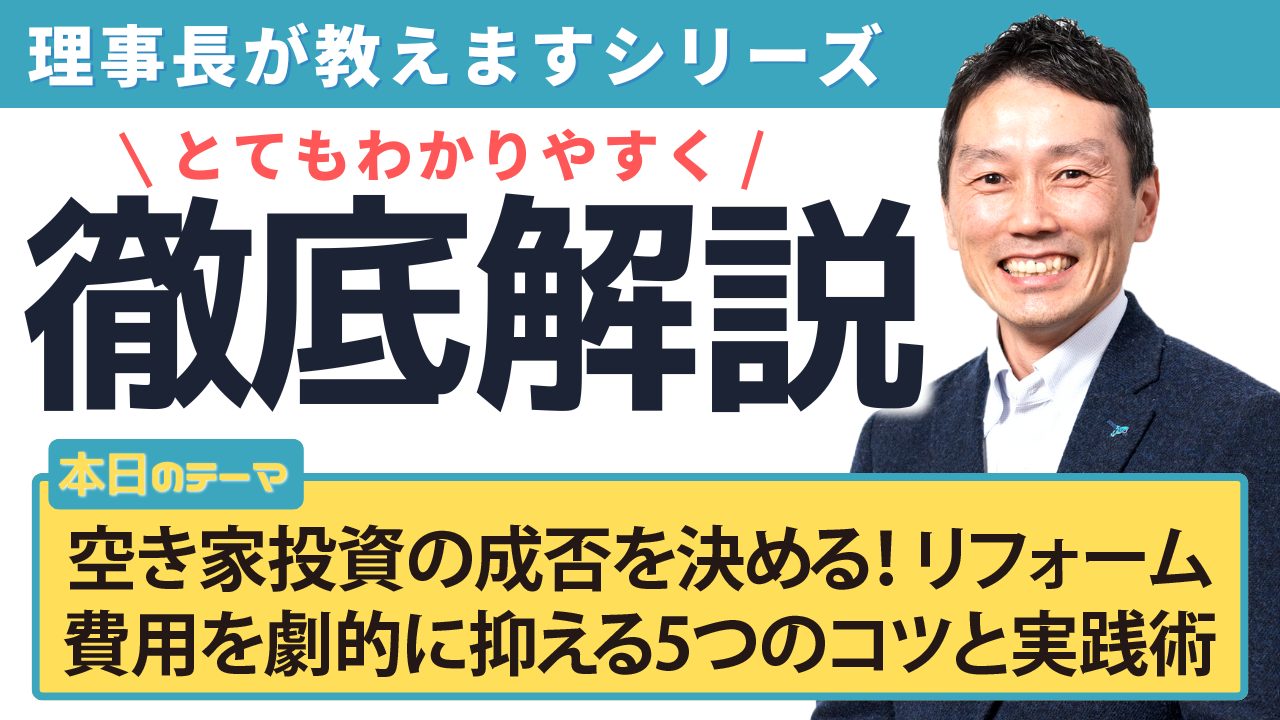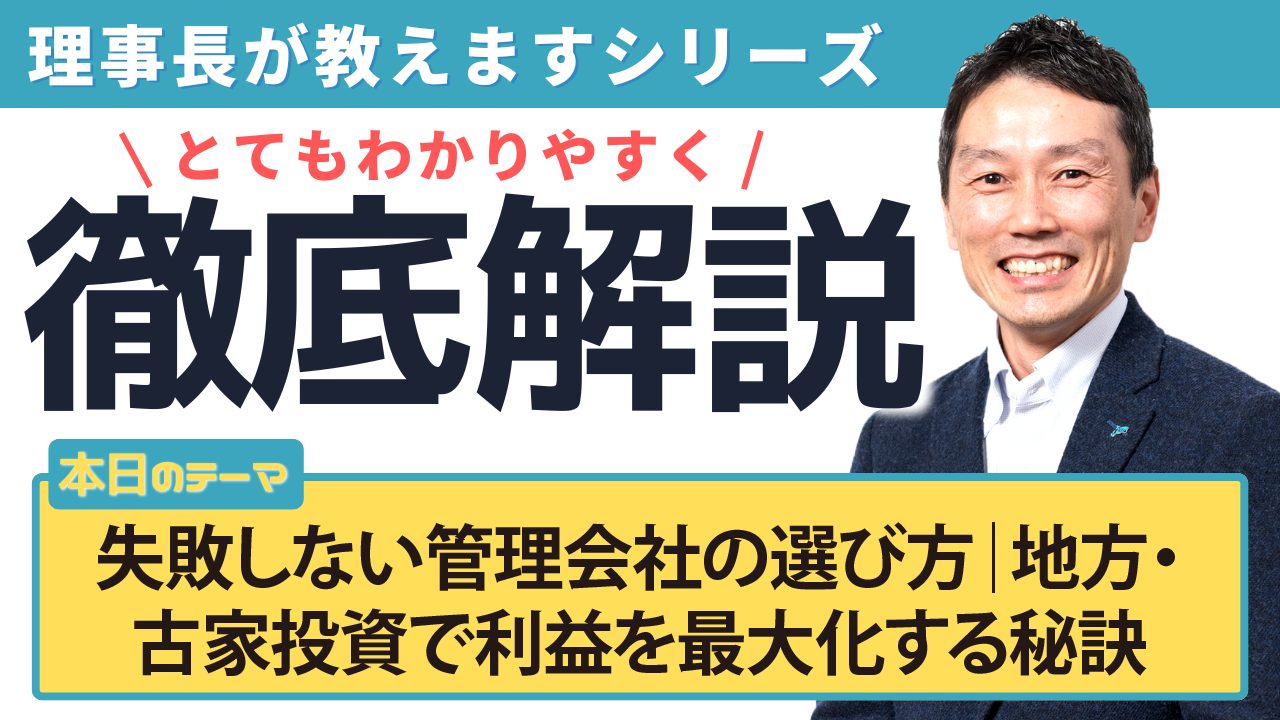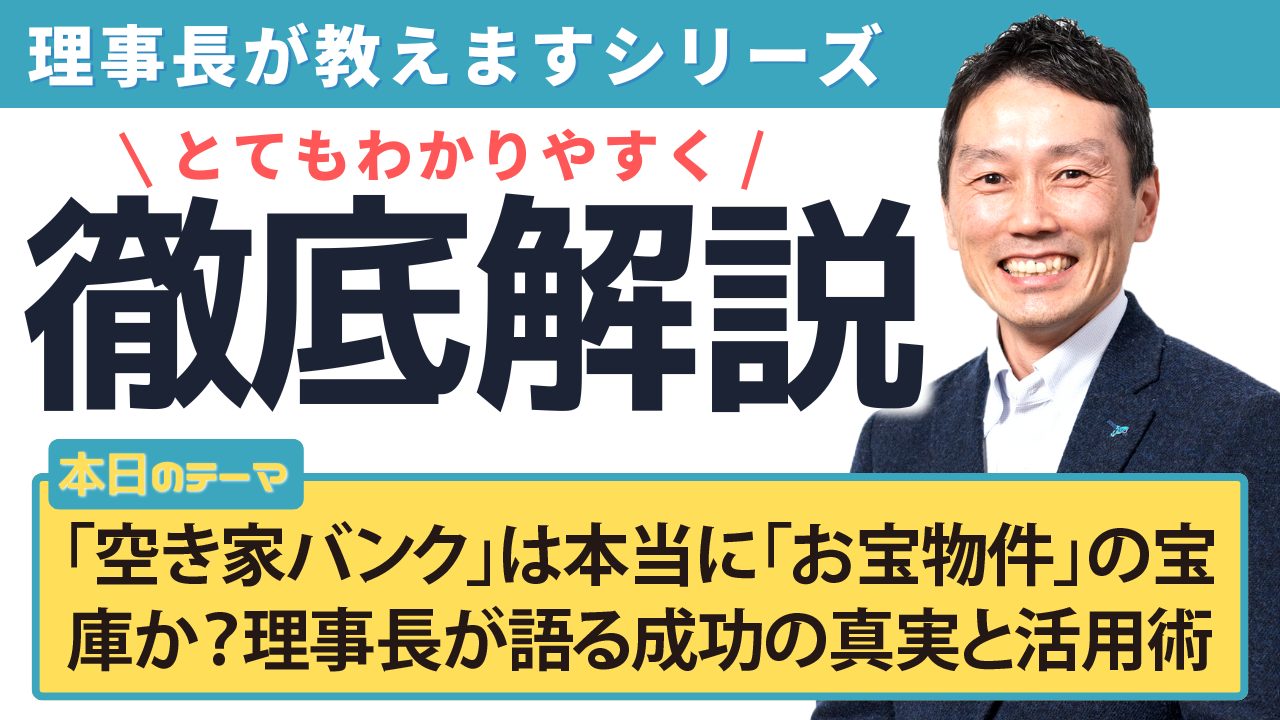
(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
近年、テレビやインターネットで「空き家バンク」が取り上げられる機会が増え、「一戸建てが数万円で手に入る」「リフォームすれば儲かるお宝物件の宝庫だ」といった華やかなイメージが先行しています。
しかし、私たち協議会が2013年から空き家・古家再生投資に取り組み、累計2,467棟以上の再生実績を積み重ねてきた中で見えてきた現実は、その華やかなイメージとは大きくかけ離れています。
実際、安さに惹かれて空き家バンクの物件に飛びつき、予想外の修繕費用や法的な問題で立ち往生する投資家を、私は数多く見てきました。これは、空き家バンクの「闇」の部分、つまり行政や不動産業界の構造的な課題を理解しないまま、「買える物件」と「儲かる物件」の違いを見誤っているからです。
この記事を最後まで読んでいただければ、空き家バンクの仕組みの裏側から、リスクを極限まで抑えて儲けるための「大熊流」活用術まで、その成功の真実がすべてわかります。私たち協議会が提唱する「リフォーム逆算思考」と「4方よしモデル」を基盤に、空き家バンクを真の「宝の山」に変えるノウハウをお伝えします。
さあ、机上の空論ではない、実践に基づいた空き家バンク投資の現実を見ていきましょう。
目次
空き家バンクとは何か?投資家が知るべき基本の「キ」
空き家バンクとは、地方自治体が主体となって運営する、空き家情報を提供する仕組みのことです。まずは、この行政サービスが生まれた背景と、通常の不動産市場との決定的な違いを理解することが、成功の第一歩となります。
空き家バンクの仕組みと行政が運営するメリット・デメリット
空き家バンクが生まれた最大の理由は、日本が抱える深刻な空き家問題の解決です。総務省の統計を見ても、空き家率は年々上昇し続け、放置された空き家は治安の悪化や景観の破壊といった社会問題を引き起こしています。
行政は、こうした空き家を減らし、定住促進や地域活性化に繋げたいという社会的使命を持って空き家バンクを運営しています。そのため、通常の不動産仲介業者が取り扱いにくい、築年数が古く、価格の低い物件でも情報が公開されます。
<行政運営のメリット>
物件価格が安い: 数十万円、場合によっては無償譲渡の物件もある。
補助金の活用: 自治体によっては、購入者やリフォーム費用に対する補助金制度がある。
社会貢献性: 物件の再生が地域活性化に直結する。
<投資家から見たデメリット>
瑕疵(かし)リスクが高い: 物件の状態が悪い、所有者が物件管理に無関心だったケースが多い。
情報の精度が低い: 行政が仲介を担うわけではないため、物件情報が古い、または詳細に欠ける場合がある。
売買に時間がかかる: 所有者(売主)が遠方に住んでいる、または売却に消極的な場合があり、交渉や手続きに時間を要する。
なぜ一般的な不動産情報には上がらないのか?(市場流通しない理由)
空き家バンクに登録される物件の多くが、なぜ大手不動産サイトや地元の仲介業者の店頭に並ばないのか。その背景には、不動産仲介業者側の「費用対効果」という現実的な問題があります。
不動産仲介業者の主な収入源は、売買が成立した際の仲介手数料です。仲介手数料は物件価格に応じて算出されるため、数百万円、数十万円といった安価な空き家物件では、仲介手数料もわずかなものになってしまいます。
例えば、物件価格が100万円の場合、仲介手数料の上限は(100万円×5%+4万円)の9万円(税別)程度です。このわずかな手数料で、現地調査、所有者との交渉、契約書類の作成、法務局での確認といった手間をかけることに、一般的な仲介業者は消極的になります。
結果として、手間がかかる割に儲けが少ない空き家バンク物件は、市場流通から外れ、行政のバンクで「買える人を待つ」という状態になってしまうのです。この構造を知っておくことは、空き家バンク物件に真剣に取り組む投資家にとって必須の知識です。
なぜ「お宝物件」だと勘違いされるのか?その裏側にある構造的現実
空き家バンクを「お宝物件」と呼ぶのは、「破格の安さ」だけに注目している証拠です。しかし、私たちの投資手法の肝は、著書『地方は宝の山! リスクを極限まで抑えて儲ける「空き家・古家」不動産投資』でも繰り返し述べている通り、リスクを極限まで抑えることです。
安さの裏側に潜む「構造的な現実」を見抜かなければ、その物件は一瞬にして「負の遺産」と化してしまいます。
登録物件に潜む「瑕疵(かし)リスク」と「リフォーム逆算思考の欠如」
空き家バンクの物件が安い理由のほとんどは、「瑕疵(欠陥・問題点)」があるからです。
構造的な瑕疵: 白蟻被害、深刻な雨漏り、基礎のクラック
環境的な瑕疵: 建て替え不可の再建築不可物件、隣地との境界線問題、心理的瑕疵
管理上の瑕疵: ゴミの放置、残置物の多さ、給排水管の老朽化
初心者が安さだけに飛びつき、物件を目の前にして「たしかに安いけど、これを直すのにいくらかかるんだろう?」と立ち止まってしまうのは、「リフォーム逆算思考」が欠けているからです。
私たちが提唱する「リフォーム逆算思考」とは、「いくらで貸したいか(家賃設定)」→「そのためにはどんなリフォームが必要か」→「そのリフォーム費用なら、物件価格はいくらまで出せるか」と、出口(利回り)から逆算して物件価格を決める考え方です。
この思考がないと、「物件価格50万円!安い!」と飛びついた結果、修繕費で500万円かかり、想定利回りを大きく下回る事態に陥ります。安さに騙されてはいけません。
行政の立場と不動産業者の立場のギャップが物件選定を難しくする
空き家バンクの物件選定が難しい構造的な原因は、行政と不動産業者の立場のギャップにあります。
行政の立場: 「空き家を減らす」ことが目的であり、「投資家を儲けさせる」ことではない。
不動産業者の立場: 「手間がかかる」「仲介手数料が少ない」ため、積極的に動かない。
このギャップの結果、空き家バンクに登録される物件は「市場で売れない」もの、つまり「売主が早く手放したいが、プロ(仲介業者)が積極的になれない」物件が多くなります。
投資家は、誰も積極的になれない物件に対し、自らの判断力と地元工務店との強力な連携という武器を持って立ち向かわなければなりません。著書『儲かる!空き家・古家不動産投資入門』でも述べている通り、この分野で成功するには、市場の論理ではなく、社会課題解決の意識と実践的なノウハウが必須なのです。
「買える」と「儲かる」は違う!成功のための3つの見極め方
空き家バンクで「買える」物件はたくさんあっても、「投資として儲かる」物件はほんの一握りです。私たち協議会の会員が実践し、2,467棟の再生実績に結びついた、成功のための具体的な見極め方を3点お伝えします。
見極め方①:価格と修繕費のバランスを見抜く「リフォーム概算力」
前述した「リフォーム逆算思考」を実践するためには、現地で「リフォーム概算力」を発揮できなければなりません。
例えば、築40年の木造物件を見たとき、あなたは瞬時に「これは水回りを全部入れ替えて、屋根の塗り替えと、内装のクロス張替えが必要だ。概算で300万円はかかるな」と判断できますか?
これができなければ、すべての交渉は机上の空論になります。
<概算力の習得ポイント>
概算力は、著書『不動産投資入門』で解説しているように、成功する大家業の基本です。この概算力があれば、「物件価格50万円+修繕費300万円=総費用350万円」で利回り何%になるかを即座に計算し、購入の是非を判断できます。
見極め方②:地方都市でも賃貸需要が確実にあるエリア選定
空き家バンクの物件は地方に集中していますが、「地方=賃貸需要ゼロ」ではありません。重要なのは、地方の中でも「人が住み続ける理由がある場所」を選ぶことです。
<需要が見込めるエリアの条件>
生活の利便性: スーパー、コンビニ、病院、役場などが徒歩圏内にある(車移動が必須でも、主要施設へのアクセスが10分以内)。
駅やバス停からの距離: 地方では車社会ですが、高齢者や学生は公共交通機関を頼ります。徒歩10分圏内であればなお良し。
地元の就労環境: 地域の主要な工場、企業、大学など、確実に賃貸需要を生み出す場所から車で15分圏内。
私たちが地方投資を「宝の山」と呼ぶのは、こうしたニッチな需要をしっかりと捉え、賃貸経営のプロではない一般の仲介業者が気づかない市場を見つけているからです。人が住まない場所を再生しても意味がありません。
見極め方③:現地調査で絶対にチェックすべき「隠れた瑕疵」
空き家バンクの物件では、通常の仲介物件では考えられないような「隠れた瑕疵」が潜んでいます。現地調査は投資判断の成否を分ける最重要ステップです。
<現地で徹底的にチェックすべき隠れた瑕疵>
屋根裏・天井: 雨漏りの染み、断熱材のズレ、動物のフン。
床下・基礎: 白蟻被害の有無、床下の湿気、カビの発生、基礎の深いクラック。
給排水管: 蛇口をひねり、水がスムーズに出るか、下水の臭いがないか、排水管の詰まりがないか。
電気設備: 分電盤の容量、漏電ブレーカーが作動するか。
これらは、私自身が過去に多くの失敗経験から学んだ、「リスクを極限まで抑える」ためのチェックポイントです。特に水回りや構造に関する瑕疵は、修繕費が数百万単位で跳ね上がる要因となるため、徹底的に確認してください。
リスクを極限まで抑える!大熊流「4方よし」の空き家バンク活用術
私たち全国古家再生推進協議会が、なぜこれほど短期間で2,467棟もの再生実績を積み上げ、会員20,280名という巨大コミュニティを構築できたのか。それは、単に儲けるノウハウだけでなく、社会貢献と収益を両立させる「4方よし」の哲学に基づいているからです。
大熊重之が提唱する「古家再生投資」の基本戦略(無借金・低リスクの考え方)
私の提唱する古家再生投資は、「無借金・低リスク」を徹底的に追求します。空き家バンクの物件は、物件価格が安いため、高額な銀行融資を必要としません。
<低リスク戦略の柱>
キャッシュ(自己資金)の範囲内: 物件価格+修繕費の総額を、無理のない自己資金の範囲内で賄う。
高利回り設定: 修繕費を抑える工夫と家賃設定の工夫で、利回り15%以上を目指す(著書**『儲かる!空き家・古家不動産投資入門』**でも高利回り事例を多数紹介)。
家賃収入の再投資: 得られた家賃収入を次の物件の頭金に充て、雪だるま式に資産を増やす。
リスクを極限まで抑えることで、空室期間や予期せぬ修繕が発生しても、事業全体が揺るがない強固なポートフォリオを構築できます。
成功の鍵は「地元工務店」との連携によるコストコントロール
空き家バンク投資で最もコストがかさむのは、物件価格ではなくリフォーム費用です。
通常の不動産投資家は、リフォーム会社や大手リフォームチェーンに依頼しますが、これでは中間マージンや広告費が上乗せされ、コストが膨らんでしまいます。私たちは、この問題を解決するために「地元工務店との直接連携」という戦略を徹底しています。
地元工務店のメリット: 大手のような中間マージンがなく、適正価格で施工が可能。地域に根ざしているため、物件の修繕や入居後のトラブル対応も迅速。
協議会の仕組み: 全国古家再生推進協議会では、全国の古家再生士という専門家が、地元工務店との橋渡し役となり、投資家と工務店が直接、対等な立場で仕事ができる環境を構築しています。
この独自ネットワークが、私たちの会員が圧倒的な低コストで再生を実現できる最大の秘訣であり、高利回り達成の土台となっています。
社会貢献と収益の両立を実現する「4方よしモデル」の浸透
空き家バンクを真に活用するということは、単に自分が儲けることではありません。それは、社会課題の解決に貢献し、地域全体を豊かにする活動です。これが私たちの提唱する「4方よしモデル」です。
空き家バンク物件を再生することは、この「世間よし」の部分に特に大きく貢献します。社会に貢献しているという確固たる理念が、投資を継続する上での大きなモチベーションとなり、結果として持続可能な収益に繋がるのです。
【実例紹介】空き家バンクを活用し再生実績2,467棟に至った成功事例
私たちの活動は、机上の理論ではなく、すべて具体的な実績に基づいています。累計2,467棟の再生実績と、全国20,280名の会員ネットワークの中から、空き家バンク物件を真の「お宝」に変えた成功事例と、失敗から学んだ教訓をご紹介します。
会員が実践した高利回り再生事例(地方都市・郊外での成功例)
地方の空き家バンクで見つけた物件を、リフォーム逆算思考と工務店連携によって、利回り20%超を達成した事例は枚挙にいとまがありません。
<地方都市・郊外での成功事例の共通点>
物件の取得費: 50万円~150万円(空き家バンク経由、または売主直接交渉)
リフォーム費: 250万円~400万円(工務店と直接連携で低コスト化)
総投資額: 300万円~550万円
家賃設定: 5万円~6万円(地域の相場を調査し、古家として高めの設定)
利回り: 18%~24%
例えば、ある会員は空き家バンクで「無償譲渡」の物件を取得しました。残置物撤去と水回り、内装の最低限のリフォームに350万円をかけ、家賃6万円で賃貸。総投資額350万円に対し、年間収入72万円で利回り20.5%を達成しました。この会員は、この成功体験を基に、現在では10棟以上の古家を所有しています。これが「誰でも再現できる」低リスク高リターンの古家再生投資です。
失敗事例から学ぶ!空き家バンクの物件でつまずく典型的な落とし穴
「失敗は成功のもと」です。失敗談を隠さず正直に伝えることが、読者の皆さんが同じ轍を踏まないための最も重要なノウハウだと考えます。
<空き家バンク物件での典型的な失敗事例>
残置物処理の甘さ:
事例: 「残置物込みで格安」という物件を購入。処理費用を軽視していたら、ゴミ処理業者への費用が100万円を超え、リフォーム予算を圧迫した。
教訓: 残置物は「ゴミ」ではなく「費用」と考えること。必ず事前に概算見積もりを取るか、売主に処分交渉を行う。
法的な問題(再建築不可):
事例: 再建築不可物件を深く考えず購入。リフォーム後に売却を検討したが、買い手が見つからず、出口戦略を失った。
教訓: 「不動産投資入門」でも強調していますが、将来的な売却も視野に入れるなら、再建築不可物件は極めて慎重に判断すべき。
こうした失敗は、すべて事前の知識不足と徹底した現地調査の怠りに起因します。机上の空論ではなく、実際の失敗から学び、リスクを回避する姿勢こそが、私たち実践者の鉄則です。
空き家バンクでつまずいたら。次のステップ「古家再生投資プランナー®️」という選択
空き家バンクという玉石混交の市場で成功するには、独学での知識や、インターネットで得られる断片的な情報だけでは限界があります。
独学と体系的な学びの決定的な差
空き家バンク投資は、一般的なアパートやマンション投資とは異なり、「瑕疵を見抜く力」「工務店と交渉する力」「地域の需要を掘り起こす力」といった、極めて実践的なノウハウが求められます。
独学: 情報が断片的で、何が正しくて何が間違っているかの判断が難しい。失敗したときに修正がきかない。
体系的な学び: 成功に必要な知識・ノウハウが、論理的かつ実践的なカリキュラムで提供される。失敗事例から学び、成功法則を再現できる。
私たち協議会では、古家再生投資で失敗する人を一人でも減らしたいという思いから、この体系的なノウハウを結集した「古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座」を開発・提供しています。全国で1,429人の認定プランナーが、このノウハウを実践し、成功を収めています。
私たち協議会が提供する実践的なノウハウと全国のサポート体制
この講座では、私の著書の内容はもちろん、それ以降に蓄積された2,467棟の再生データと、全国20,280名の会員ネットワークから得られた最新の知見が凝縮されています。
特に、空き家バンク物件で最大の難関である「リフォームコストの削減」と「リスクの見極め」については、以下のような具体的なサポートを提供しています。
リフォーム概算力の徹底指導: 物件を見て、その場で概算見積もりができるスキルを習得。
成功事例の共有: 実際に空き家バンク物件を再生した会員の最新事例や、失敗事例を分析。
地元工務店との連携サポート: 全国に広がるネットワークを活用し、低コストで信頼できる工務店を紹介・連携をサポート。
これは、単なる資格ビジネスではありません。これは、**「空き家問題の解決」という社会的な使命を共有し、「誰でも再現できる成功」**を追求するための実践的なコミュニティなのです。
まとめ・結論
(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
空き家バンクは、幻想を抱いて飛び込む人にとっては「負の遺産」となり得ますが、正しい知識と戦略、そして社会貢献の意識を持って活用する人にとっては、間違いなく「お宝物件の宝庫」となり得ます。
この記事で私が伝えたかった重要なポイントを3点にまとめます。
「買える」≠「儲かる」: 安さの裏には必ず理由(瑕疵・リスク)がある。行政や不動産業者の構造的な課題を理解した上で、冷静に見極めよ。
成功の鍵は「リフォーム逆算思考」と「概算力」: 出口(家賃)から逆算して、物件価格+修繕費のバランスを瞬時に見抜くスキルが必須である。
大熊流「4方よしモデル」を実践せよ: 低リスクの無借金投資を基本とし、地元工務店と連携してコストをコントロールし、社会貢献と収益の両立を目指すことで、持続可能な成功が手に入る。
私自身、小さな町工場経営からこの古家再生投資によって人生を大きく変えることができました。あなたも、「不動産投資は難しい」「自分には無理だ」という固定観念を捨て、一歩踏み出す行動を起こしてください。
私たち協議会は、この低リスクで再現性の高い古家再生投資という手法を通じて、あなたに安定した資産形成の道筋を提供するとともに、全国の空き家問題解決に共に取り組む仲間を求めています。
もしあなたが、
「リフォーム概算力を体系的に身につけたい」
「全国の信頼できる工務店ネットワークを活用したい」
「低リスクで利回り15%超を狙う具体的なノウハウを知りたい」
とお考えでしたら、ぜひ古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座への参加をご検討ください。机上の空論ではない、2,467棟の再生実績と20,280名の仲間の知恵が、あなたの挑戦を強力にサポートします。
共に日本の空き家問題を解決し、豊かな未来を築いていきましょう。
POST: 2025.10.27