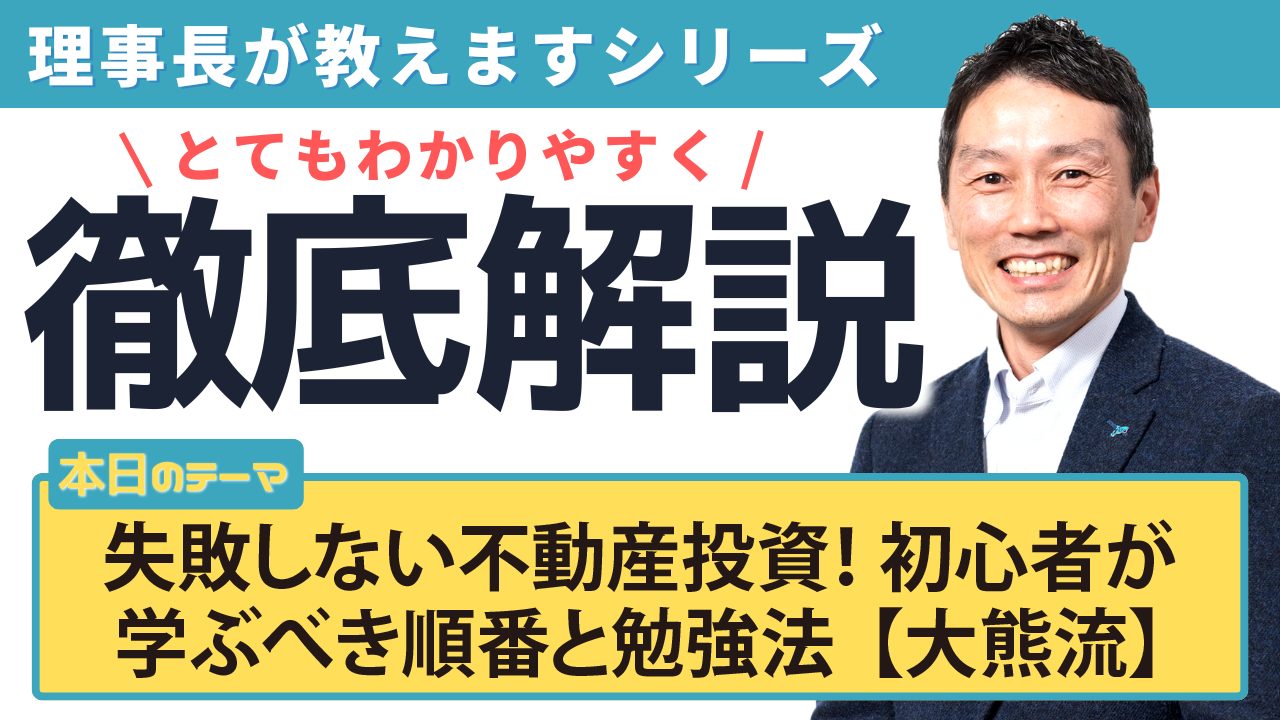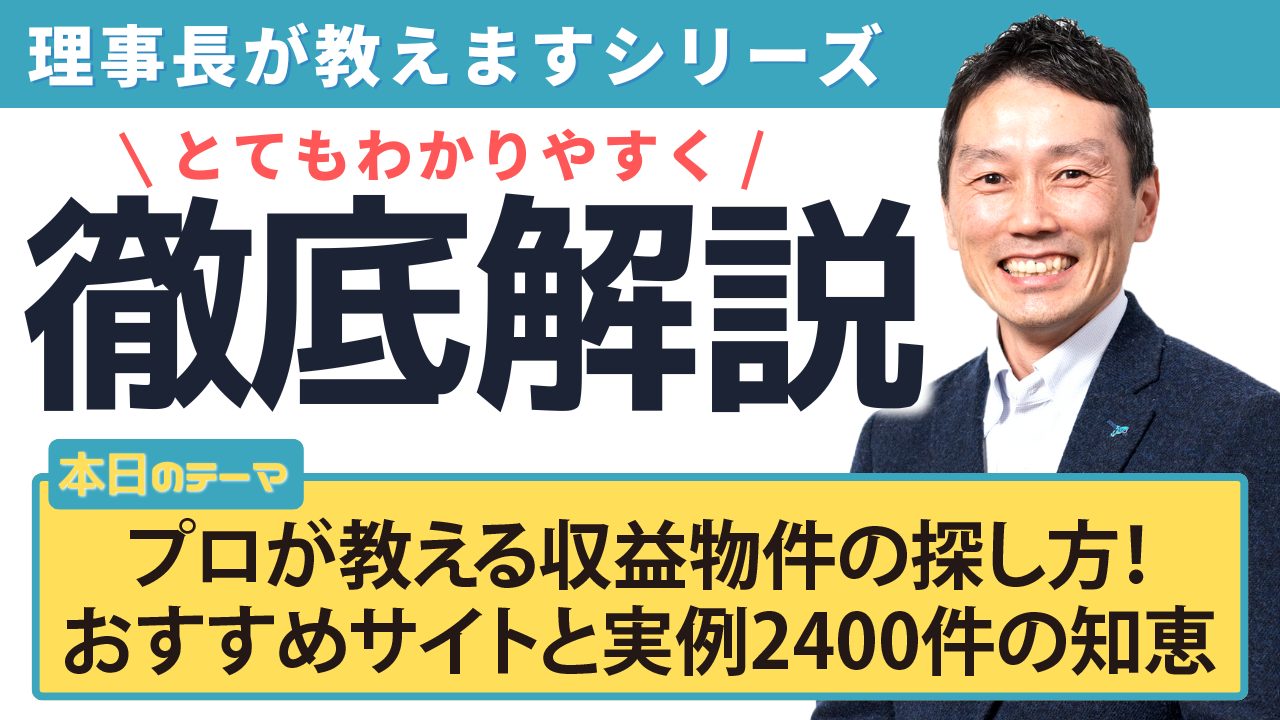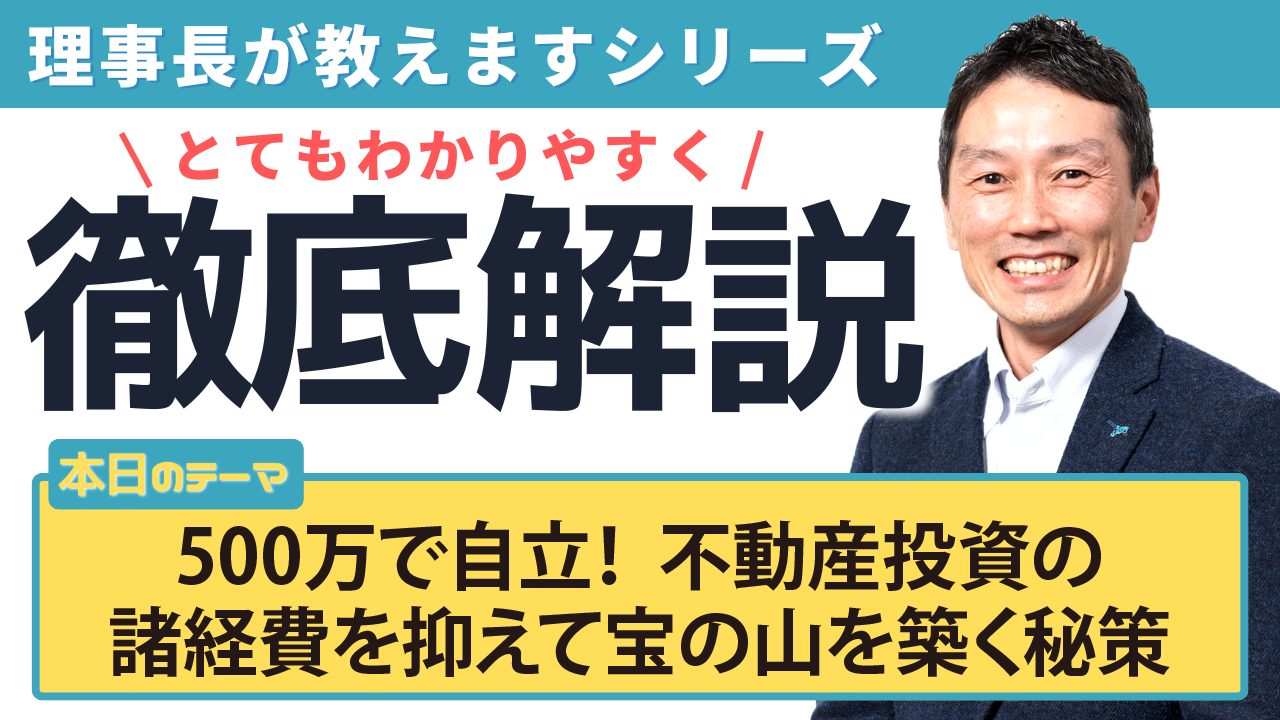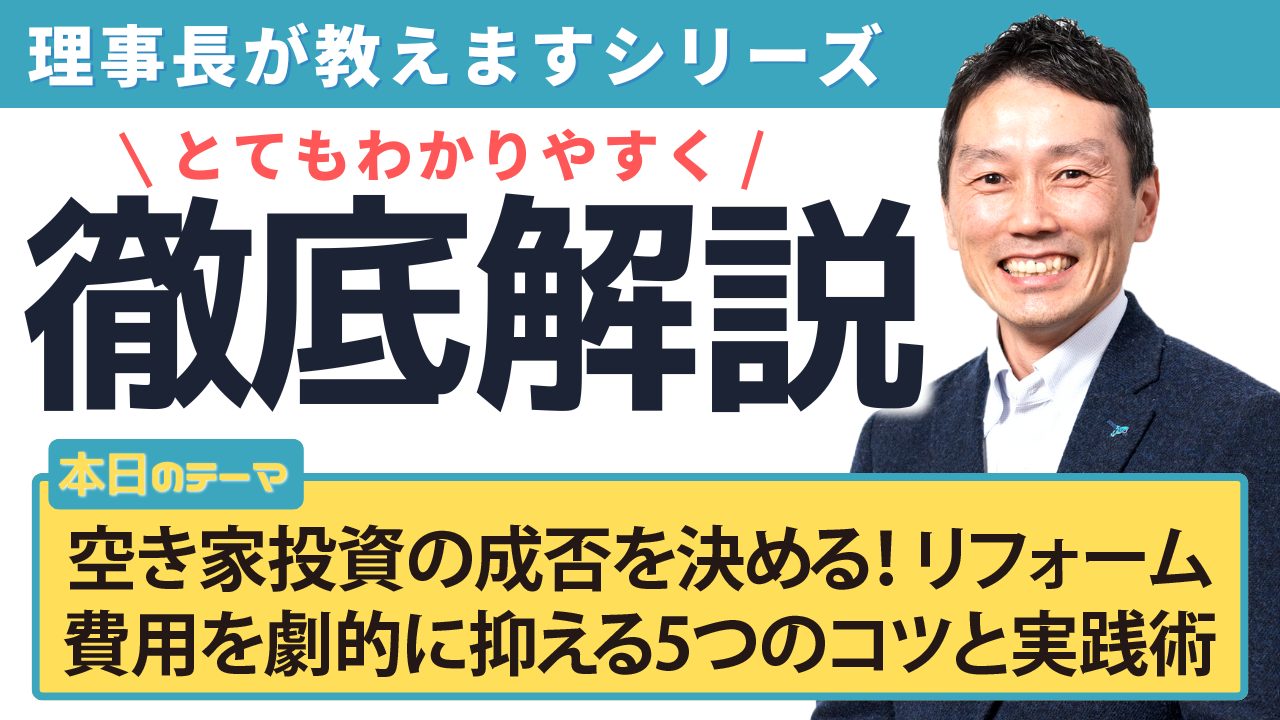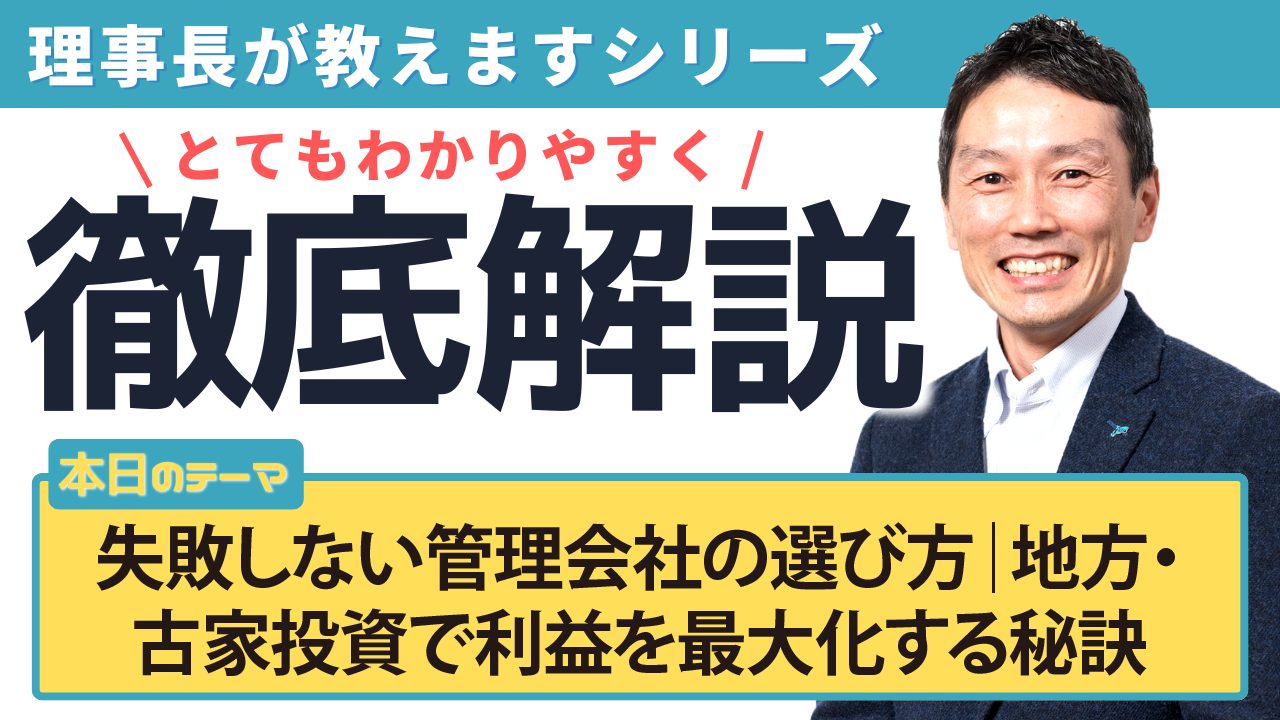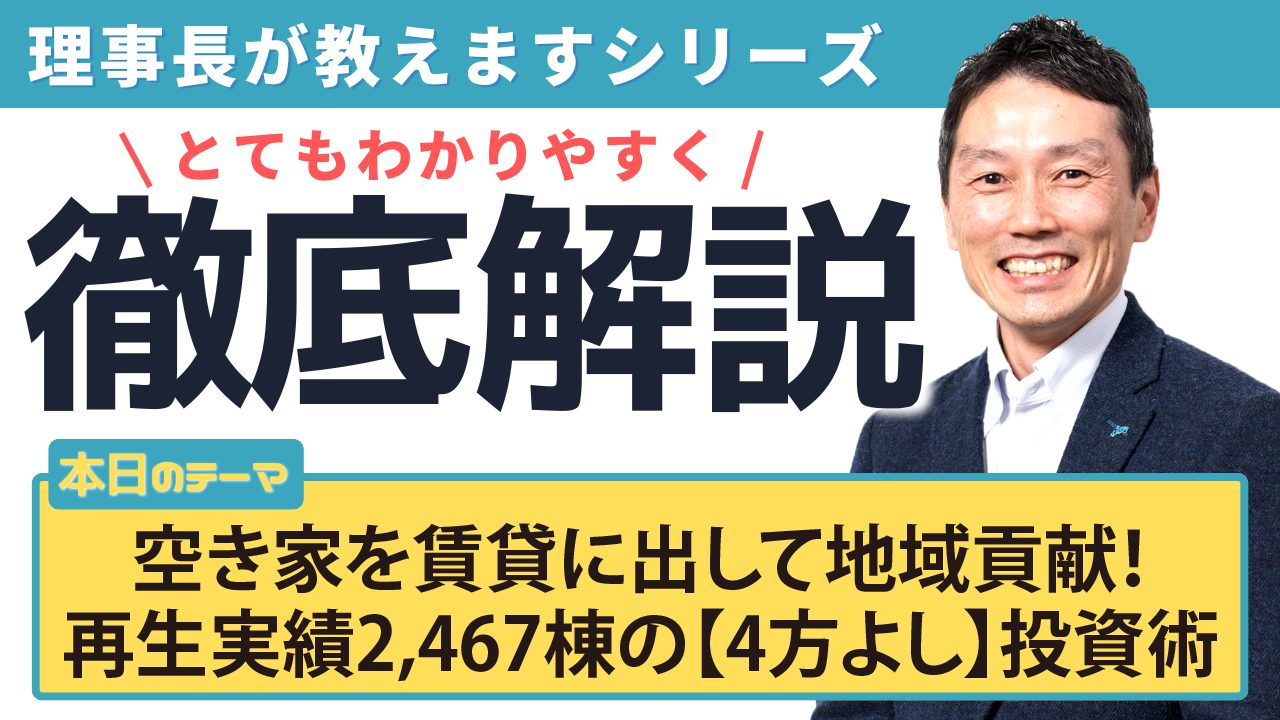
(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
日本が抱える空き家問題は、もはや他人事ではありません。全国で増え続ける空き家は、あなたが相続した実家を「負動産」に変えてしまうリスクを常に孕んでいます。特定空き家に指定されれば、固定資産税が最大6倍に跳ね上がり、維持管理のコストが重くのしかかります。その結果、ただでさえ価値の低い古家が、負の遺産と化してしまうのです 。
しかし、諦めるのはまだ早いです。私たち全国古家再生推進協議会は、空き家問題を「社会課題を解決しながら、投資家も地域も豊かになるビジネスチャンス」と捉えています。累計2,467棟の再生実績と20,280名の会員ネットワークから生まれた独自のノウハウこそが、その証です。
この記事を最後までお読みいただければ、空き家を放置するリスクから逃れ、「地域に喜ばれる『富動産』」に変える具体的な賃貸化戦略と、私たち協議会が提唱する「4方よし」の古家再生投資術が分かります。机上の空論ではない、実践に基づいた知識で、あなたの不安を希望に変えましょう。
目次
1. 放置は絶対にNG!空き家が「負動産」化する5大リスクと現状
1-1. 日本の空き家率の現状と将来予測
日本の空き家問題は、人口減少と高齢化という二重の要因で加速度的に進行しています 。2013年(平成25年)の時点で空き家は820万戸あり、2018年(平成30年)には1,000万戸に達するとも言われていました 。これは、全国で5〜6軒に1軒が空き家になる計算です 。
私たち協議会は、この問題をただの統計上の数字として見ていません。空き家は、放置されれば治安の悪化、行政サービスの維持困難、住環境の荒廃を招き、社会問題へと発展します 。この負の連鎖を断ち切ることが、私たちの社会的使命の一つです。
1-2. 負の連鎖を生む「空き家の防犯・衛生・景観」リスク
空き家を放置し続けることの具体的なリスクは、所有者自身を苦しめるだけでなく、地域社会全体に及びます。
| リスクの カテゴリー | 具体的な内容 | 所有者への影響 | 対策の必要性 |
| 税制リスク | 特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇が解除され、税額が最大6倍に跳ね上がる 。 | 年間の維持費が数十万円増加し、経済的負担となる 。 | 最優先で賃貸化または売却を検討し、「特定空き家」指定を避ける 。 |
| 物理的リスク | 建物の老朽化による倒壊、雨漏り、シロアリ被害の進行 。 | 修繕費用が青天井になり、資産価値がゼロになる 。1年間放置すると建物の傷みが思った以上にひどくなる 。 | 早急な賃貸化の判断で、資産の傷みを最小限に抑え、家賃収入を得る 。 |
| 近隣トラブル | 雑草の繁茂、害虫・害獣(ネズミなど)の発生、異臭、景観の悪化による近隣住民からのクレーム 。 | 精神的なストレス、賠償責任の可能性。近隣からの信頼を失う 。 | 定期的な管理または賃貸化による入居者による管理が必須 。 |
治安・ | 不法投棄、放火、不審者の侵入、犯罪への利用 。 | 地域の治安悪化に加担し、最悪の場合、人命に関わる事故に繋がる 。 | 賃貸化し、人が住む状態にすることが最良の防犯対策となる。 |
| 売却リスク | 傷みがひどくなると、市場価値が暴落し、購入希望者が現れなくなる 。 | 安値での買い叩き、または売却自体が困難となり「負動産」化 。売却の判断は早めにすべき 。 | 再生ノウハウを持つ専門家(古家再生士)に相談し、賃貸化を検討する 。 |
私が強調したいのは、空き家は「負動産」ではなく、賃貸化によって「富動産」に変えることができるということです 。
2. 地域と投資家が潤う「4方よし」の古家賃貸化モデルとは
2-1. 【4方よし】モデルの定義と仕組み(所有者・投資家・入居者・地域)
私たち全国古家再生推進協議会が提唱する「4方よし」のビジネスモデルは、単なる投資の成功に留まらず、社会的な意義を追求するものです 。これは、江戸時代の近江商人の精神に基づいた「三方よし(売り手・買い手・世間)」に、空き家問題の解決という現代の課題を加えたものです。
| 項目 | 価値(ベネフィット) | 社会的意義 |
| 所有者(売り手) | 負動産化リスクの回避、資産(古家)の売却または賃貸化による収益化、先祖の資産の継続 | 放置による地域への迷惑を解消し、空き家問題の解決に貢献 。 |
| 投資家(大家) | 少額投資(400万円〜)からの参入、高利回り(平均12〜15%)の実現、安定した家賃収入 。 | 空き家を再生・活用し、地域に新たな住まいと人の流れを提供 。 |
| 入居者(借り手) | 低家賃(相場より安価)で広い戸建に住める、ペット可など多様なニーズへの対応 。 | 住宅確保要配慮者(高齢者、低額所得者、子育て世帯)への良質な住居提供 。 |
| 地域(世間) | 空き家の減少、地域の治安・景観の向上、固定資産税の確保、地域経済の活性化 。 | 住居のストックを生かし、スクラップ&ビルドに頼らない持続可能な社会への貢献 。 |
私たちのゴールは、投資家だけが儲けることではありません。売主、買主、業者、入居者、そして地域社会のすべてがWIN-WINになる関係性こそが、この事業を長く継続させる秘訣です 。安く買って、安く貸すという哲学が、巡り巡って高い利回りと社会貢献を実現するのです 。
2-2. 累計2,467棟の再生実績が証明する「社会貢献と高利回りの両立」
全国古家再生推進協議会は、2014年7月の設立以来、空き家を活用するためのノウハウを体系化し、仕組み化してきました 。私たちの会員数は1,500名を超え(2017年9月時点)、2023年12月時点では1万4,000人以上となっており 、空き家再生数は2,000棟以上を達成しています 。
この圧倒的な実績は、私たちが提唱するビジネスモデルが、都市部から地方まで、全国どこでも通用することを証明しています。
実績の裏付け: 地方を含む全国平均でも、空き家・古家投資の平均利回りは12.9%、確定家賃ベースでは約14%という高水準を叩き出しています(2022年実績) 。
社会的な評価: この「4方よし」のビジネスモデルは、2016年に「関西IT百選」で優秀賞を受賞するなど、社会的な評価もいただいています 。
私たちは、空き家を単なる「ボロ家」としてではなく、「再生によって地域に光を灯す宝の山」として見ています。そして、このノウハウを広めることが、日本の空き家問題解決への最も具体的で、最も早く効果が出る道だと確信しています。
3. 「高利回り」を実現する空き家賃貸化の4ステップ
3-1. STEP1:物件の選定基準と「築古・広大」を狙う理由
空き家・古家投資で成功する鍵は、「家賃から逆算して購入価格を決める」という、一般の不動産売買とは真逆の思考法にあります 。
物件選定の基準
家賃相場の調査(最優先): まずは地域の戸建賃貸の相場を徹底的に調べます 。インターネット情報(HOME’Sの「見える!賃貸経営」など)と、地域の不動産業者(3軒以上)へのヒアリングを組み合わせ、適正家賃を算出します 。
- 築古(築40年以上)を狙う: 建物は築年数が経つほど価値が低くなるため、安価に購入できます 。また、木造物件の法定耐用年数(22年)を超えているため、融資の担保価値は低いですが、逆に現金での低額購入が可能となり、金融機関の意向に左右されにくくなります 。
- 土地の広さ(地方なら必須): 地方物件の最大の魅力は土地が広いことです 。駐車場を増設できるスペースや庭があれば、法人借り(社宅)やファミリー層への訴求力が高まり、家賃アップに直結します 。
- 路線価(資産価値の維持): 地方では、物件総額(購入費+リフォーム費)が路線価以下になる物件も多くあります 。これは、それ以上資産価値が落ちないという安定性を意味します。
購入価格の逆算式はシンプルです 。
例えば、想定家賃が5万円/月(年間60万円)、希望利回り15%、リフォーム費用200万円であれば、物件の購入上限額は200万円(総額400万円)となります 。この算定した買付額で売主と交渉し、合わなければ諦める冷静な判断が重要です 。
3-2. STEP2:リスクを極限まで抑える「無借金再生」戦略
空き家・古家投資の最大の特徴は、少額資金から始められることです 。私が推奨するのは、まず1軒目を現金で購入し、無借金で家賃収入を得ることで、次の投資へのリスクヘッジと経験を積むことです 。
1棟目は現金が原則: 最初の物件を現金で購入すれば、万が一空室が続いても、精神的なプレッシャーが少なく、次の物件の家賃で補うことができるため、ほとんどリスクがないと言えます 。
- リフォームローン活用(ハイブリッド): 物件価格が安く済む分、リフォーム費用は「空き家活用ローン」や日本政策金融公庫などの融資(2.0〜3.0%程度の低金利)を活用する手もあります 。これにより、手元の現金を温存し、複数の物件を所有する「無借金再生」と「融資活用」のハイブリッド戦略が可能になります 。
- 不動産の実績づくり: 現金購入後、確定申告で大家業の実績を積むことで、銀行に対する信用が生まれ、2棟目以降の融資が受けやすくなります 。
3-3. STEP3:入居者が殺到する「格安リフォーム」の極意
リフォームは、空き家再生のコストの大部分を占め、利回りに直結する最重要ポイントです 。ここで工務店に任せきりにすると、入居者のニーズを無視した高額な工事となり、投資の魅力を失います 。
コスト削減の鉄則
- 目的は「収益」: リフォームの目的は「きれいにすること」ではなく、**「高い利回りを得ながら、入居者をすぐに獲得できること」**です 。相場家賃(例:5万円)に見合った質のリフォームに抑えます 。
- 人件費を削減: リフォーム費用の大半は人件費です 。多機能工(さまざまな工事ができる職人)に依頼することで、複数の職人を呼ぶ手間とコストを削減します 。
- 和室を活かす「差別化」: 和室を無理に洋室化せず、塗装などでモダンな雰囲気に変えることで、安価に差別化を図ります 。土壁や砂壁への塗装は安価かつインパクト大です 。
- 水回りの優先順位: 毎日使う水回りは重要ですが、すべてを新品にする必要はありません。
必須: 電気容量のチェック、畳の表替え、ウォシュレット付きトイレ、室内洗濯機置き場の新設(入居動機に直結) 。
クリーニングで対応: 浴槽がステンレスであれば磨く、キッチンは使えるなら扉の色を変えるなど、手を加えずクリーニングや塗装で済ませる 。
リビングをLDK化: ファミリー層のニーズに合わせ、居間と台所を仕切る壁を取り払い、LDK化することで開放感を出し、部屋の魅力をアップさせます 。
古家再生士の役割: 私たち協議会が認定する古家再生士は、賃貸不動産の知識を持ち、家賃相場に基づいたリフォームを提案できる専門家です 。彼らは「ここは工事費がかかりすぎるのでやめましょう」「この利回りでは合わない」と、投資家が感情的になるのを防ぎ、冷静な判断を下します 。
3-4. STEP4:地域密着型の客付け戦略と家賃設定
リフォームが完了しても、入居者が決まらなければ収益はゼロです 。空き家・古家は物件数が少ないため、「マイソク(物件資料)」の質と「賃貸仲介業者への営業」が命運を分けます 。
- 家賃は「適正相場より少し安く」: 高い家賃設定で3カ月空室になるより、相場より少し安く設定してでも、早く入居してもらうほうが得です 。3,000円アップで3カ月空室が続けば、その差を取り戻すのに50カ月かかるという計算を忘れてはいけません 。
- マイソクでの差別化(インパクト): 賃貸仲介業者は毎日、大量の物件情報を見ています。再生士が手がけた差別化された内装写真(おしゃれな壁紙、和のモダンテイスト、キャットウォークなど)を載せることで、営業マンに強烈な印象を与え、優先的に紹介してもらいやすくします 。
- 戸建の強みを訴求:
ペット可: 戸建の強みは「独立性」です 。近隣住民とのトラブルが少ないため、マンションで断られることが多い猫・犬のペット可にすることで、大きな需要(猫OKは特に強い)を獲得できます 。ペット1匹につき3,000円〜5,000円の家賃アップも可能です 。
広い空間: 狭いアパート暮らしに不満を持つファミリー層に、広い戸建が低家賃で提供できることをアピールします 。 - 賃貸業者回り: 平日の午前中など、業者が比較的忙しくない時間帯に、自ら物件資料(マイソク)を持って訪問します 。周辺の競合物件の情報や、どのような客層がターゲットになるかなどの有益な情報を仕入れることができ、担当者との信頼関係も築けます 。
- 地域貢献の視点: 低家賃で広い住居を提供することは、生活保護世帯や子育て世帯など、住宅確保要配慮者の住環境を改善する社会貢献になります 。これは人口の多いゾーンをターゲットにすることになり、結果として大家業の繁栄にもつながるWIN-WINの戦略です 。
4. 【実例紹介】ボロ家が優良物件に変わった成功ストーリー
4-1. 失敗から学んだ再生事例:私の初期の苦い経験
私自身、空き家・古家投資を始める前は、大阪府東大阪市で小さな町工場を経営しており、常に「来月の仕事はあるのか」「従業員を守れるのか」という不安を抱えていました 。そんな私が、空き家投資に出会ったのは44歳の時です 。
初期の頃は、まだノウハウが確立されておらず、失敗も経験しました。
【山の上アパートの再生事例】 築50年の木造アパートを購入したことがあります 。場所は駅から遠く、山の上にある登山道の入り口で、普通の人なら絶対に買ってはいけない物件でした 。リフォーム後、賃貸業者に案内をお願いすると、「その物件はダメです。ただでも入居者を付けることができません。絶対無理です!」とハッキリ言われ、大変落ち込みました 。
しかし、私は諦めませんでした。
行動: 沿線にある100軒弱の賃貸業者を3カ月間で3〜4回訪問して回りました 。
- 差別化: 部屋にアクセントカラーを入れ、飾り付けをして写真映りを良くしました 。
- 家賃設定: 4DKで最安値になるように設定し、仲介会社向けのマイソクも分かりやすく作成しました 。
結果、3カ月で満室になりました 。中には、医者から「運動するように」言われ、山の上ならイヤでも歩くから、という理由で入居された方もいました 。この経験から、「入居者が付かない物件はない」と確信できるようになり、今の自信につながっています 。
また、私が経営する工場も、コロナ禍で売上が激減した時期がありましたが、空き家・古家投資による安定した家賃収入(複数戸所有で月20万円ほど)があったおかげで、会社を安定的に回し、不安なく事業を継続できました 。家賃収入は、いざという時の心の安定剤であり、冷静な経営判断の基盤になります 。
4-2. 会員事例:利回り25%を実現した投資家の挑戦
私たち協議会の会員の中には、私の初期の経験からノウハウを学び、素晴らしい実績を上げている方が多数います。
【中小零細企業経営者 Sさんの事例】
Sさんは、本業の売上安定化を目的として、空き家投資を始めました 。
| 物件情報 | 内容 | 特徴と教訓 |
| 物件1 (テラス) | 大阪大東市。家賃相場4万円のところ、4万7000円で入居決定。 | 高齢者が海外旅行のために売却。入居理由は「現在住んでいるマンションの家賃を減らすため」と、低家賃の需要を証明 。表面利回り15%。 |
| 物件3 (3階建5LDK) | 東大阪市。7人家族で自営業者。募集3カ月で入居。 | 大人数家族のニーズを捉えた。広さが強みとなり、表面利回り17%。 |
| 物件9 (アパート) | 兵庫県長田区。5戸の木造3階建。半分以上空室だったが、募集後3カ月で満室。 | 空室アパートの再生も可能。表面利回り27%。 |
Sさんは最終的に12棟を購入し、家賃収入の総額が年間約2,000万円に達しました 。彼が言うように、「購入すればするほどノウハウがたまり、大家業として成長しているのが実感できる。失敗したと思っても自分で何とかできる範囲が大きいのがいい」のです 。
【司法書士 中山泰道さんの事例】
司法書士として働く中山さんは、相続登記の依頼を受けた際、売却をためらっていた古家所有者に対し、再生士の査定と家賃相場の調査を行い、180万円のリフォームで家賃5万円で貸せることを提案しました 。
結果: 最初のリフォーム代はかかるものの、約3年で回収できる見込みが立ち、所有者は売却ではなく賃貸住宅にすることを選びました 。
- 教訓: 相続物件は、リフォーム費用だけで大家になれる、初期投資が少ない最高のチャンスです 。この事例のように、賃貸化は所有者に経済的なメリットをもたらすだけでなく、先祖から受け継いだ資産を生かすことにもつながります 。
5. 失敗を避け、確実に成功するための3つの鉄則
5-1. 鉄則1:物件に「惚れず」に「データ」で判断する
投資において、物件を感情的に「好きだから」「思い出があるから」という理由で購入するのは最も危険です 。不動産投資家は、冷静なデータ分析と逆算思考に基づいて判断しなければなりません 。
物件総額がすべて: 物件の売値(販売価格)に惑わされず、最終的な物件総額(購入価格+リフォーム費)が、年間想定家賃の何年分(利回り)になるのかを計算し、購入上限額を決定します 。
- 利回りの基準: 私たち協議会では、関西で13〜15%、関東で12〜14%を適正利回りの目安としています 。再建築不可や駅から遠いなどリスクが高い物件は、その分利回りを1〜2%高く設定し、収益でリスクを補います 。
- 家賃相場を調べる: 自分の物件の適正家賃を自分で算定できない人は、投資家として失格です 。インターネットで調べるだけでなく、現地に足を運び、複数の賃貸業者にヒアリングして、正確な相場感を身につけてください 。
5-2. 鉄則2:一人で抱え込まず専門家と「組織力」を活用する
空き家・古家投資は、物件の選定、リフォーム、客付け、管理、法律、税務など、多岐にわたる専門知識が必要です 。これらを初心者やサラリーマンが一人で完璧にこなすのは不可能です。
専門家の活用: 古家再生専門のノウハウを持たない一般の工務店にリフォームを依頼すると、工事費用が高額になり、採算が合わなくなります 。私たち協議会が認定する古家再生士のように、賃貸経営の知識を持ち、収益から逆算した工事ができる専門家との連携が不可欠です 。
仲間との情報交換: 物件見学ツアーや懇親会などに参加することで、同じ価値観を持つ仲間(先輩大家や専門家)と出会い、情報や経験を共有できます 。仲間の経験談は、あなたの不安を解消し、行動への勇気を与えてくれます 。
- 不動産業者との関係構築: 地元の不動産業者と良好な関係を築くことが、良質な物件情報や客付けの成功につながります 。彼らのビジネスを尊重し、あなたの再生事業が地域貢献につながることを具体的に伝えましょう 。
5-3. 鉄則3:出口戦略を先に決める「逆算思考」の重要性
不動産投資は長期戦です 。目先の利益だけでなく、「いつ、どのように、どれくらいの利益で売却(出口)するか」という出口戦略を念頭に置いておくことが、失敗しないための鍵です。
売却の柔軟性: 空き家・古家投資は、少額投資なので、賃貸経営で十分な収益を上げた後、売却して大きな資金を得るという次のステップへの土台にもできます 。
家賃収入の目標: 私が考える目標の一つは、「月100万円の賃料収入を借金のない状態で確保し、老後の経済的自由を達成すること」です 。この目標から逆算して、毎年の購入棟数や投資戦略を決めていくのが賢明です。
- メンテナンス費用の確保: 賃貸経営で得た家賃収入の30%ほどは、将来のメンテナンス費用として残しておく必要があります 。これを怠ると、いざ修繕が必要になった際に資金がなく、物件が空室になったまま次の入居者が決まらないという「ジリ貧」状態に陥り、資産が重荷になってしまいます 。
6. まとめ・結論
地域社会への貢献と未来の投資家へ
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
日本の空き家問題は深刻です。しかし、この社会課題の裏側には、少額の資金から始められ、高い利回り(平均12〜15%)を実現できる「空き家・古家再生投資」という大きなチャンスが眠っています 。
私たちが提唱する「4方よし」のビジネスモデルは、投資家であるあなた自身の資産を築くだけでなく、賃貸住宅に困っている人々に安くて広い住居を提供し、地域社会の活性化に貢献します 。
大切なのは、知識を得て、行動することです。「知って行わないのは、未だに知らないことと同じである」 という陽明学の言葉の通り、いくらノウハウを学んでも、一歩踏み出さなければ何も始まりません。
空き家・古家投資は、「誰でも再現可能」なビジネスモデルであり、あなたの不安を解消し、「経済的自由」への道筋をつけてくれる強力なツールです 。
まずは、あなた自身の目でボロ家が優良物件に変わる現場を体験し、ノウハウを体得することから始めてみましょう。
次はそんなに甘くない。本来の古家の問題はこんなものじゃない」と、覚悟を決めて取り組めば、あなたも必ずや、地域に愛され、社会に貢献できる「古家再生投資プランナー®️」として成功できるはずです。
POST: 2025.10.27