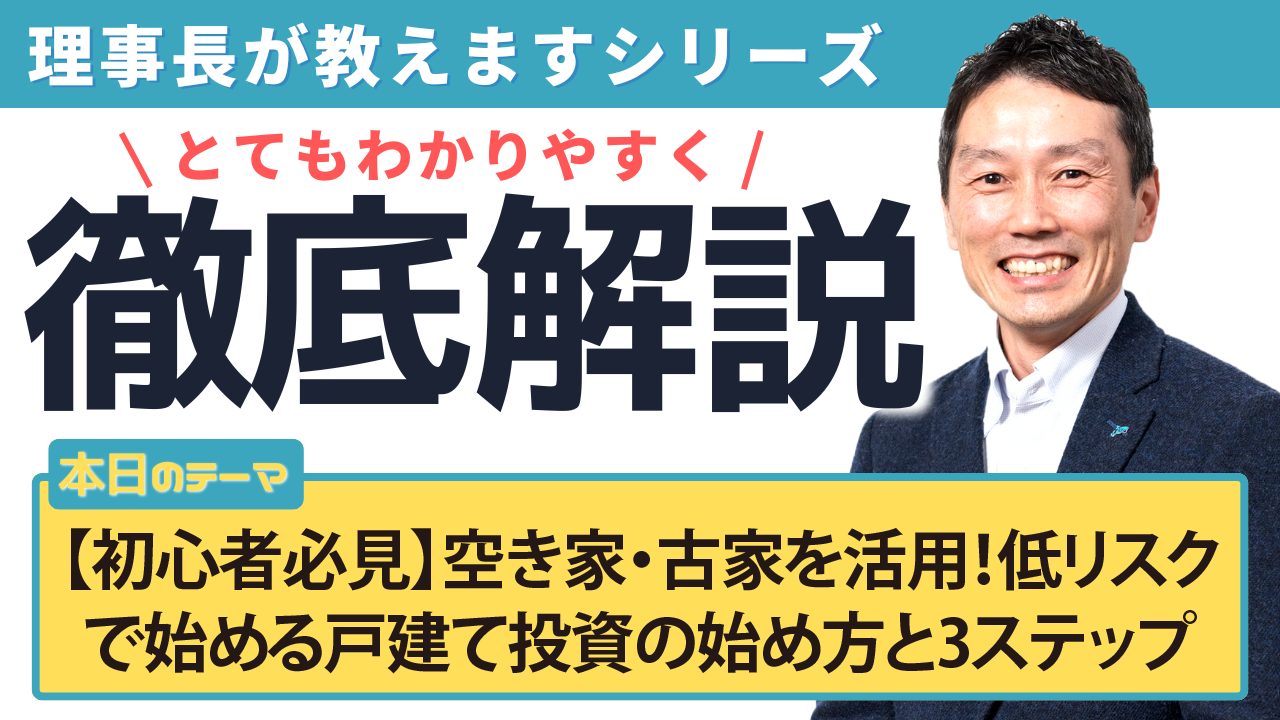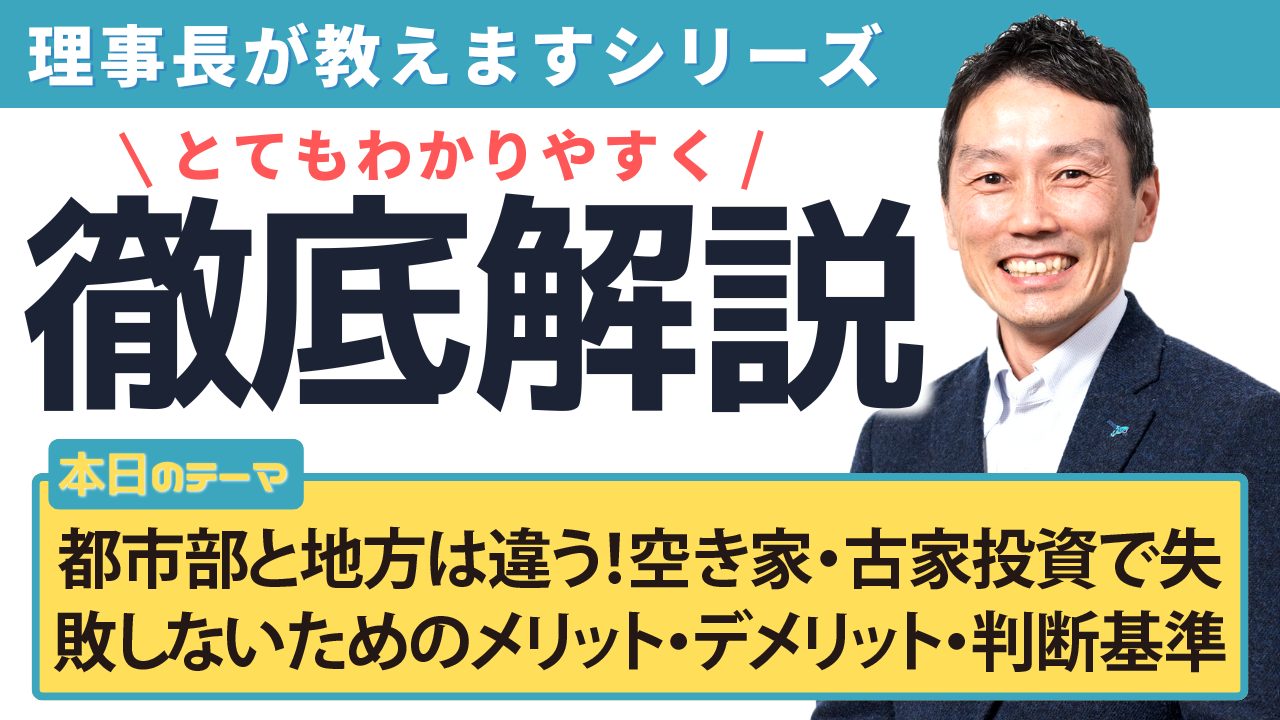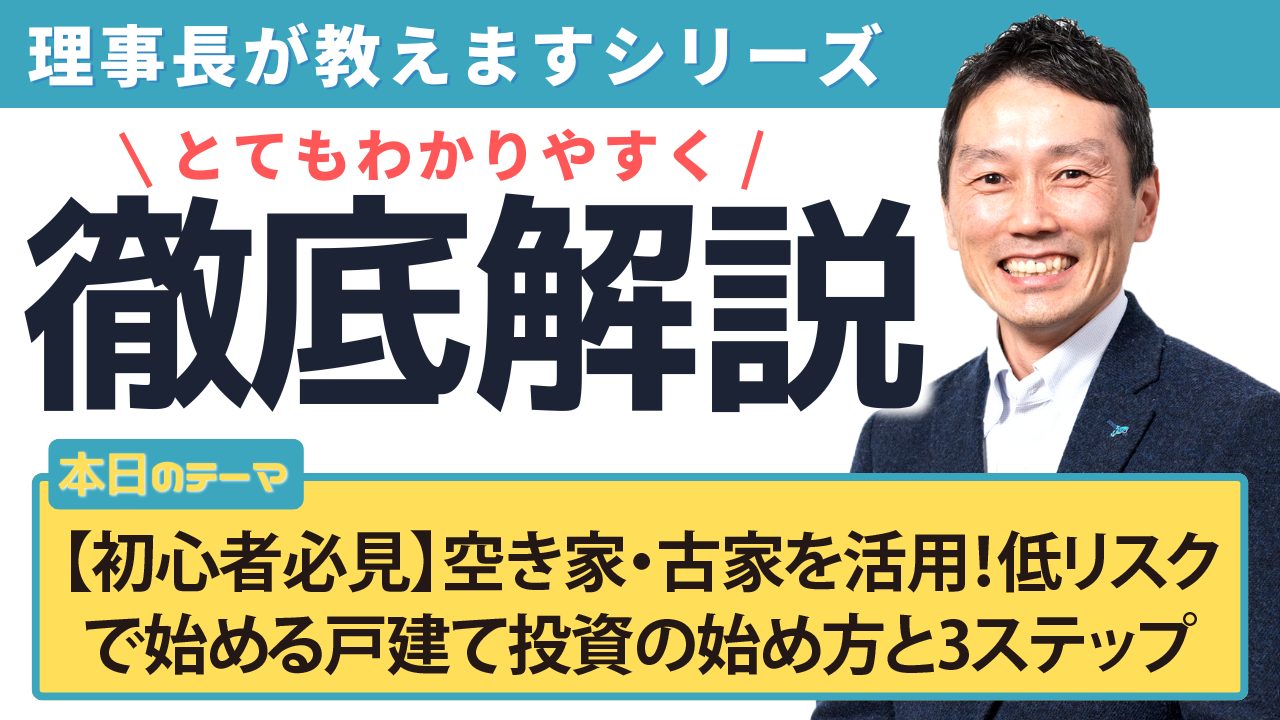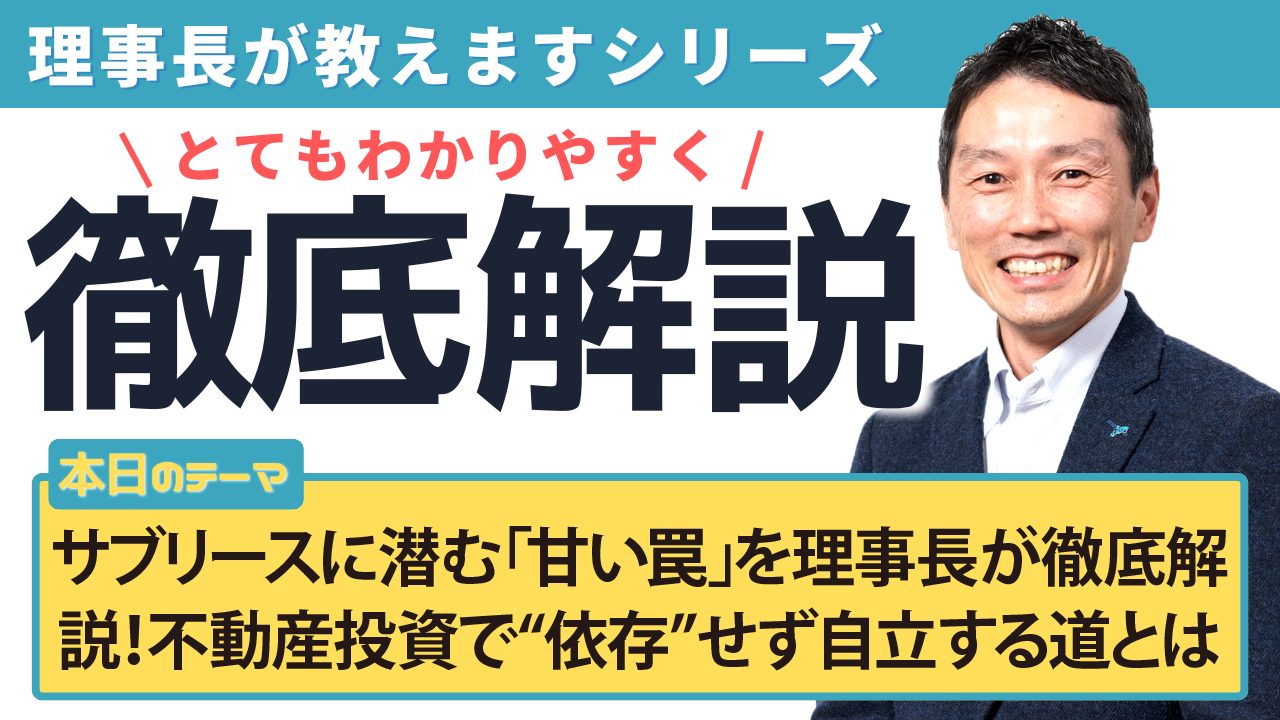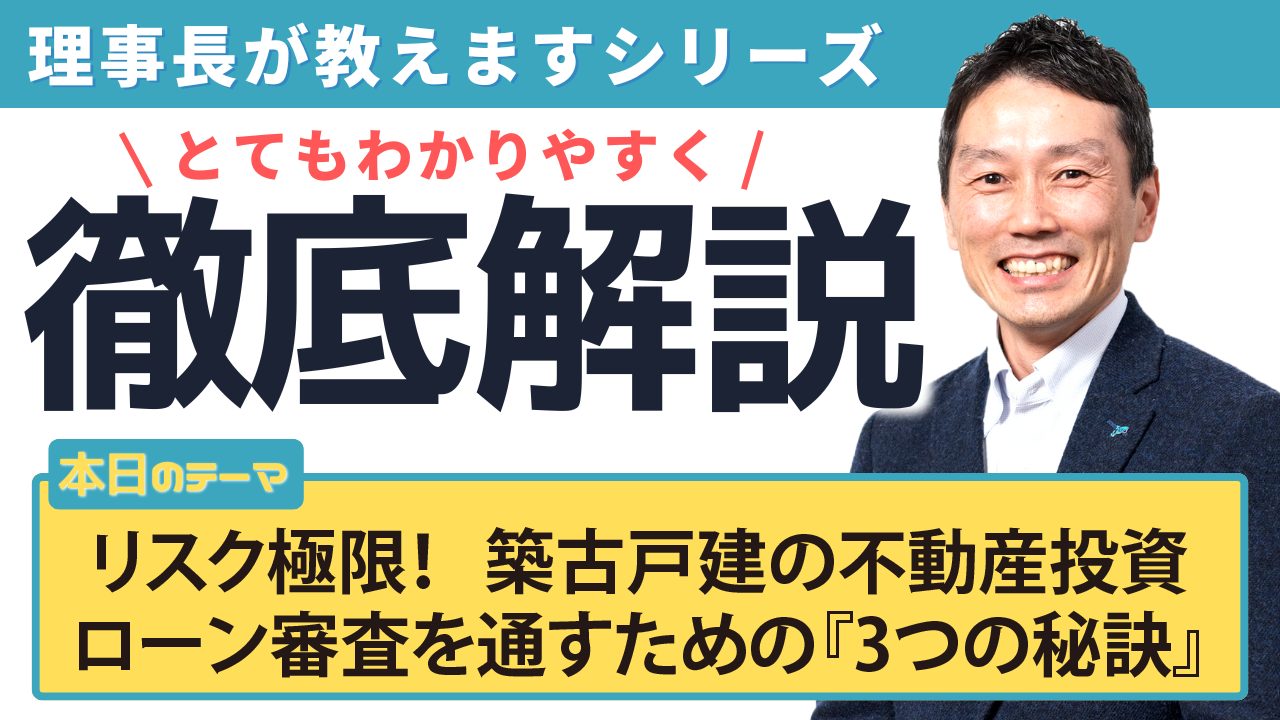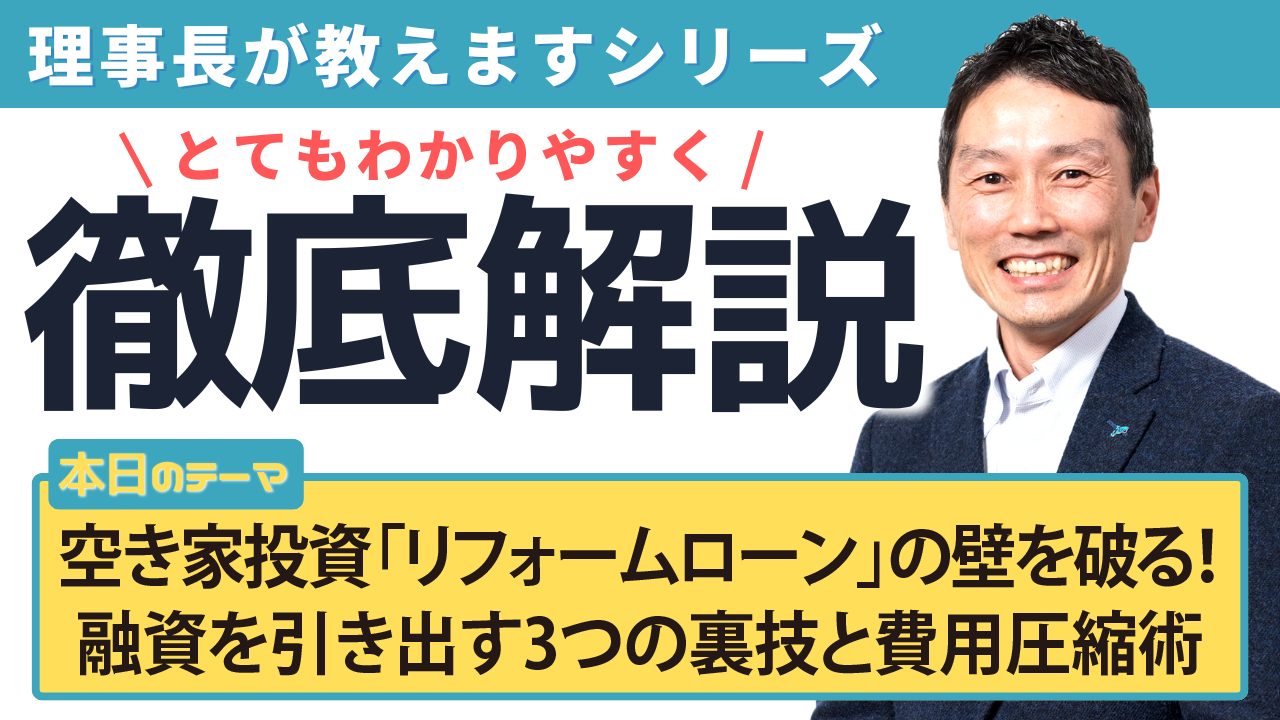
(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
もしあなたが「空き家投資を始めたいが、リフォームローンの壁が高すぎる」「築古物件なんて銀行は相手にしてくれないだろう」と不安を感じているなら、ご安心ください。それは、あなたが戦うべき土俵を間違えているだけかもしれません。
私たち協議会が累計2,467棟もの古家再生を実現し、20,280名の会員を抱えるコミュニティを築いてきたのは、決して裏口入学したわけではありません。誰もがぶつかる「融資」という最大の壁を、正しい知識と実践的なノウハウで乗り越えてきたからです。
特に築40年を超える古家の場合、通常の「不動産担保」に頼った融資は通用しません。必要なのは、**「融資を引き出す3つの裏技」と、ローンの負担自体を極限まで減らす「費用圧縮術」**という両輪の戦略です。
この記事では、机上の空論ではなく、私たち協議会の実践に基づいた具体的な資金調達ノウハウを、包み隠さずお伝えします。このノウハウを知れば、あなたの空き家投資の成功確率は劇的に高まるはずです。
目次
1. なぜ空き家投資で「リフォームローン」の壁にぶつかるのか?
1-1. 銀行が築古物件の融資に消極的な根本理由
銀行の融資の基本は、「貸したお金が返せなくなったとき、担保を売れば元が取れるか」という点にあります。このとき、築40年を超える木造の古家は、税務上の法定耐用年数(木造は22年)を大幅に超えていることがほとんどです。
物件価値がゼロ評価: 法定耐用年数を超えた物件は、銀行の評価基準では「建物価値がゼロ」として扱われます。
担保割れのリスク: 融資額が土地の担保価値と建物の残存価値を合わせた額を上回る場合、銀行は担保割れと判断し、リスクが高いと見なします 。
つまり、銀行はあなたの事業の収益性よりも、「モノ(建物)」の担保価値を見て判断しているのです。これが、古家再生投資家が最初にぶつかる大きな壁の正体です。
1-2. 一般的なリフォームローンの審査基準と古家再生投資のミスマッチ
多くの方がまず検討する「リフォームローン」は、一般的に住宅ローンの派生商品として扱われます。
金利は比較的低い: 目的が居住改善のため、金利は事業ローンに比べて低い傾向にあります。
審査が通りにくい: しかし、リフォームローンは「自己居住用」の側面が強く、賃貸事業(収益事業)を目的とした築古物件の改修には向いていません 。
担保物件の縛り: 融資の対象が「建物本体」であるため、物件自体の担保力が弱い築古物件では、そもそも高額な融資は困難です。
このミスマッチを解消するには、不動産担保という土俵から降り、事業性という土俵で勝負しなければなりません。
1-3. 融資の成功と失敗を分ける「不動産担保評価」のカラクリ
不動産投資における銀行の担保評価には、主に積算評価と収益還元評価の2つのカラクリがあります。
積算評価(主に融資で重視): 土地の路線価と建物の再調達価格(耐用年数で減価償却)で物件の価値を計算します。築古物件は耐用年数超過で建物価値がゼロになりやすく、積算評価は非常に低くなります 。
収益還元評価(古家投資で重視): 物件が生み出す将来の家賃収入から逆算して現在の価値を計算します。この評価こそが、古家再生投資で融資を引き出すための最重要ポイントとなります。
銀行は本来、積算評価を優先しますが、私たちが「この物件は事業として確実に利益を生む」という証拠(事業計画書)を提示し、収益還元評価へ審査の軸をずらすことができれば、融資の壁は一気に低くなります。
2. 【融資戦略】空き家投資で「融資を引き出す」3つの裏技
2-1. 裏技1: 不動産担保に頼らない!「事業性」で攻める融資戦略
築古物件への融資は、その建物を担保とする「不動産担保融資」では勝ち目がありません。そこで私たちが提唱するのは、あなた自身の事業(大家業)の信用で融資を引き出す戦略です。
大家業を「事業」として確立: 賃貸事業を個人的な副業ではなく、法人化することも視野に入れた「事業」として確立します。特に、賃料収入が1,000万円を達成したいなら、1軒目から法人にする方が賢明です 。
信用金庫・日本政策金融公庫を狙う: 都銀や地銀は築古物件に厳しいですが、信用金庫や日本政策金融公庫は、融資対象を事業性や個人の属性(属性とは、職業、年収、勤続年数など)に求めるため、築古物件でも融資が可能な場合があります 。
「紹介」が最強の武器: 金融機関は知らない人には基本的にお金を貸しません。誰かの紹介での訪問がベストです。私たち協議会では、政策公庫や信用金庫に会員を紹介し、実際に融資を引き出した実績が多数あります 。
実績例: 2017年6月、全古協が紹介したプランナー会員は、日本政策金融公庫で**「返済期間14年、固定金利1.9%、無担保」**の融資を得られました 。
2-2. 裏技2: 知られざる公的融資(自治体・公庫)の活用術
一般的なリフォームローンの対象から外れたとしても、古家再生事業に特化した融資制度は存在します。
日本政策金融公庫の「普通貸付」: 公庫では「不動産貸付業」で利用できる「普通貸付」の限度額が4,800万円という枠があり、これを活用して融資を受けることができます 。
地銀の「空き家活用ローン」: 地銀数行が扱う商品ですが、物件取得費は出ないものの、リフォームに対する融資は500万円まで可能です 。物件価格が安くリフォーム費用が多くかかる古家再生において、非常に有効な手段となります。
自治体の補助金・助成金: 耐震補強や景観改善など、行政が解決したい課題に関連するリフォームには、補助金や助成金が適用される場合があります。ただし、融資の壁を破るための耐震補強については、利回りが悪くなるケースも多いため、あくまでオプションとして提案しています 。
融資は「戦い方」を知れば、必ず道は開けます。重要なのは、融資担当者が上司に報告しやすい「根拠」を用意することです。
2-3. 裏技3: 銀行に物件の「未来の価値」を提示する事業計画書の作り方
融資担当者に「これは将来必ず儲かる物件だ」と確信させるための最強の武器が、「事業計画書」です。事業計画書は、単なる収支シミュレーションではなく、「築古物件がなぜ高利回り物件に生まれ変わるか」という未来の価値の証明書であるべきです。
事業計画書に必ず盛り込むべき3つの根拠:
市場調査の根拠: 「この辺りの家賃相場は5万円です。しかし、競合物件は築40年以上の未リフォーム長屋ばかり。リフォームすれば、競合優位性が生まれ、確実に5.5万円で貸せます」という明確な市場分析 。
再現性の根拠: 「リフォーム費用は古家再生士のノウハウで250万円に抑えます。このローコスト再生ノウハウは、既に2,467棟の実績があり、再現性が証明されています」という専門家による裏付け 。
出口戦略の根拠: 「このエリアは路線価が高く土地値が下がりにくい。賃貸収益で元本を回収した後、売却すればキャピタルゲインも狙えます」というリスクヘッジを含めた長期的な視点。
3. 【費用圧縮術】リフォーム費用を極限まで抑える4つの秘訣
3-1. 秘訣1: 古家再生投資プランナー®️が実践する「原状回復」の概念を変える
一般の工務店は「すべてを新品にすればきれいになる」と考え、結果的に1,000万円以上の見積もりを出します 。しかし、空き家再生の本質は「家賃に見合う質のリフォーム」であり、不必要な工事は徹底して排除します 。
優先順位の徹底: 入居者が最も気にする水回り(トイレ、洗面、室内洗濯機置き場)と、部屋の印象を決める壁・床に集中投資する 。
「使えるものは活かす」: 浴槽がステンレスなら磨いて塗装で仕上げる 、キッチンが使えるなら扉だけ色を変えるなど、交換せずに再利用することで大幅にコストを削減します 。
デザインで勝負: 和室を無理に洋室化せず、塗装でモダンな和のテイストを演出するなど、低コストで差別化を図ります。塗装はクロス(壁紙)よりも安価で差別化が図れる裏技です 。
3-2. 秘訣2: 業者任せにしない「分離発注・自主施工」でコストを半減
リフォーム費用の大半は「人件費」です 。これを削る最も効果的な方法は、「多能工」の職人を活用したり、自分でできる範囲を増やすことです。
多能工の活用: 1人で大工仕事、塗装、クロス貼りができる職人(多能工)に依頼すれば、専門職人を複数入れるより費用と日数が大幅に削減できます 。
分離発注の検討: すべてを一つの工務店に任せるのではなく、水回りはA社、内装はB社のように発注を分ける(分離発注)ことで、中間マージンを削減します。
DIYの限界を知る: 中途半端なDIYは、結局プロにやり直しを頼むことになり、費用と時間の大失敗につながります 。DIYは隙間テープを貼る程度の簡単なものに留め、品質が問われる部分はプロに任せる割り切りが重要です 。
3-3. 秘訣3: 入居者が決まる「絞り込みリフォーム」とは(優先順位付け)
あなたの目線で「きれいな部屋」を目指すのではなく、「その家賃帯の入居者が求める質」に絞り込みます 。
家賃相場が判断基準: 家賃相場が5万円なら、7万円の物件のようなリフォームはしません。5万円で探している入居者が「この物件は他の5万円の物件よりお得だ」と感じるレベルで十分です 。
内覧者へのヒアリング: 物件見学ツアー後の査定会で、参加者に「この物件ならいくらで借りるか」を質問するなど、常に入居者目線を養うことが、無駄な工事を避ける力になります 。
集客の武器を磨く: ペット可にする、駐車場を増設する 、キャットウォークを設置するなど、競合物件にない希少性を低コストで付加する差別化リフォームに予算を集中させます 。
3-4. 秘訣4: 投資家の自己資金を減らす「リフォーム費用の分割払い」交渉術
融資が難しい場合でも、リフォーム費用を工務店や再生士と交渉して、実質的な自己資金の負担を減らす方法があります。
契約金の分割: 工事費の一部を「入居が決まってから支払う」など、工務店との信頼関係に基づいた支払い時期の交渉。
古家再生士との連携: 私たち協議会では、古家再生士(認定工事業者)がオーナーの収益を第一に考え、融資や資金繰りに関する相談にも応じるパートナーシップを構築しています 。
コスト削減へのインセンティブ: コストを抑えることで、工務店(再生士)側にも「安定した受注」という利益があり、協力関係が成立します 。
4. 理事長が語る!融資成功に導いた協議会会員の具体事例
4-1. 築50年、担保評価ゼロから事業融資で成功したAさんのケース
経営者であるAさんは、当初テラス物件から投資を始めました。彼の課題は、物件が増えるにつれて融資をどう活用するかでした。
Aさんは、不動産市況が高騰する中で、一般の銀行で融資を受けるのは難しいと判断。そこで、事業性の証明に力を入れました。
融資戦略: 地方銀行と日本政策金融公庫に焦点を絞り、法人名義での融資を検討 。
事業計画の徹底: 既に所有する物件の確定申告書(実績)と、再生士が作成した高収益の事業計画書を提出し、「古家再生は安定した事業であり、担保に頼らずとも返済能力が高い」ことを証明しました。
結果: 銀行の担当者も納得し、無事に融資を引き出すことに成功。現在も戸建てを増やし続け、「空き家・古家不動産投資が一番リスクが少ない」という結論に至っています 。
この事例からわかるのは、「モノ(担保)」ではなく「事業の信頼性」を売る融資戦略の重要性です。
4-2. 失敗事例から学ぶ!担保評価を過信したために融資に失敗したBさんのケース
反対に、融資の仕組みを理解せず失敗した事例も紹介しなければなりません。
Bさんは、比較的新しい新耐震基準の物件(築30年程度)を見つけ、積算評価が高いだろうと過信し、融資に申し込みました。しかし、融資は断られてしまいました。
失敗の原因: Bさんは、物件の担保力に頼りきり、肝心な事業計画が疎かになっていました。銀行担当者から見ると、担保力は十分ではないのに、なぜこの物件で高利回りが実現できるのかという根拠が不足していたのです。
学び: 積算評価が高い物件でも、融資担当者は「なぜこの投資家がこの物件を選ぶのか」「事業としてどう収益を生むのか」というストーリーを求めています。担保物件ではなく、事業計画書こそが融資の成否を分けるのです 。
4-3. 私たち協議会が提供する「融資に強い事業計画サポート」の価値
私たちの協議会が最も注力しているのは、まさにこの**「融資の壁」を破るサポート**です。
再生士による精緻な試算: 古家再生士が現地調査の際に、家賃相場とリフォーム費用を即座に算出し、実現可能な利回りを提示します 。
融資に強い事業計画の指導: 銀行が納得する「事業計画書」の雛形提供、そして個別指導を通じて、あなたの事業の信用を高めるサポートを行います。
専門家ネットワークの活用: 税理士や司法書士など、不動産投資に必須の専門家と連携し、法人化や税務に関するアドバイスも提供することで、事業の信頼性を高めます 。
5. 古家再生投資で最も重要な「リスクを極限まで抑える」考え方
5-1. 融資を受ける前に確認すべき「キャッシュフロー」の安全ライン
融資を利用して物件を増やす場合でも、「借金のない賃貸経営を目指そう!」という私の哲学は変わりません 。融資を受ける前に、必ずキャッシュフローの安全ラインを確認してください。
1棟目は現金で、2棟目以降は融資: 理想を言えば、1棟目は現金で購入し、2棟目以降は融資を使うことです。なぜなら、1棟目の家賃で、2棟目以降の万一の空室リスクを補えるからです 。
メンテナンス費用の積立: 家賃収入の30%ほどは、不動産のメンテナンス用に残しておくことが必要です 。これを怠ると、修繕費用が出せずに物件がジリ貧になり、賃貸経営として成り立たない状況に陥ります 。
融資期間と返済額のバランス: 日本政策金融公庫の融資シミュレーションにあるように、仮に7棟を融資で購入した場合、月々の返済額と家賃収入のバランスをとり、空室や修繕に備えた余裕を確保することが重要です 。
5-2. 4方よしモデルを実現するための「持続可能な資金計画」(社会貢献の視点)
私たちが掲げる「4方よしモデル」は、融資戦略においても最も重要な羅針盤となります 。
買主よし: リスクを極限まで抑えた資金調達と高利回り。
借主よし: ローコスト再生で実現した家賃相場より安い良質な住環境。
工務店よし: 適正な利益で安定した仕事を受注し、多能工として成長できる 。
地域よし: 空き家が減り、住む人が増えることで地域が活性化する 。
融資で無理に利益を追求し、リフォームコストを削りすぎて入居者の満足度を下げては、このモデルは崩壊します。持続可能な資金計画とは、関わるすべての人を豊かにする計画なのです。
5-3. 次のステージへ:古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座への案内(導線)
この記事を読んで、「よし、行動しよう!」と決意したあなたへ。
融資の壁を破り、高利回りを実現するためのノウハウは、一朝一夕で身につくものではありません。大切なのは、体系的に知識を学び、実践的な経験を積むことです 。
私たち協議会が提供する「古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座」では、融資戦略、費用圧縮術、物件の見極め方、そして融資に強い事業計画書の作り方まで、空き家投資に必要なすべてのノウハウを凝縮して提供しています。
古家再生投資プランナー®️になることで、あなたは以下のものを手に入れられます。
融資戦略: 融資に強い事業計画書のノウハウ。
実践経験: 全国で開催される物件見学ツアーへの参加権。
専門家ネットワーク: 再生士や先輩大家、司法書士などの強力なチーム。
迷っている時間は、チャンスを逃している時間です。今日この瞬間に一歩を踏み出し、私たちと一緒に「4方よし」の豊かな大家業を始めませんか?
まとめ
空き家投資の「リフォームローン」の壁は、決して高すぎて超えられないものではありません。戦うべき土俵を「不動産担保」から「事業の信用力」へ変えることで、道は開けます。
最後に、融資成功と高利回り実現のための要点をまとめます。
融資戦略の転換: 築古物件は「モノ」ではなく「事業」として売る。信用金庫や公庫を狙い、事業計画書で将来の収益性を証明する 。
徹底的な費用圧縮: リフォームは家賃相場に見合う質に絞り込み、不必要な工事を徹底的に排除する 。多能工の活用や「使えるものは活かす」精神でコストを半減させる。
リスク管理の徹底: 融資を利用する場合でも、キャッシュフローの安全ラインを厳守し、家賃収入の一部をメンテナンス費用として積み立てる 。
あなたが一歩踏み出すことを、心よりお待ちしております。1年後のあなたは、まったく違う景色を見ているはずです。
POST: 2025.11.24