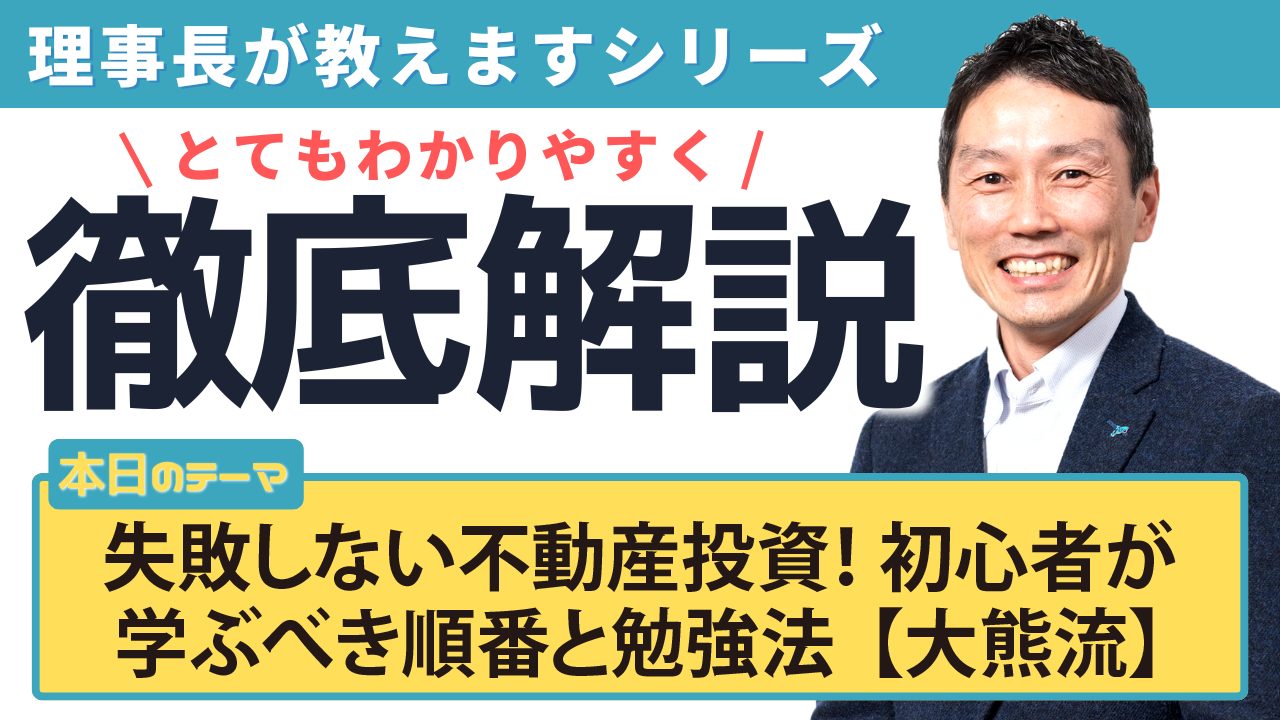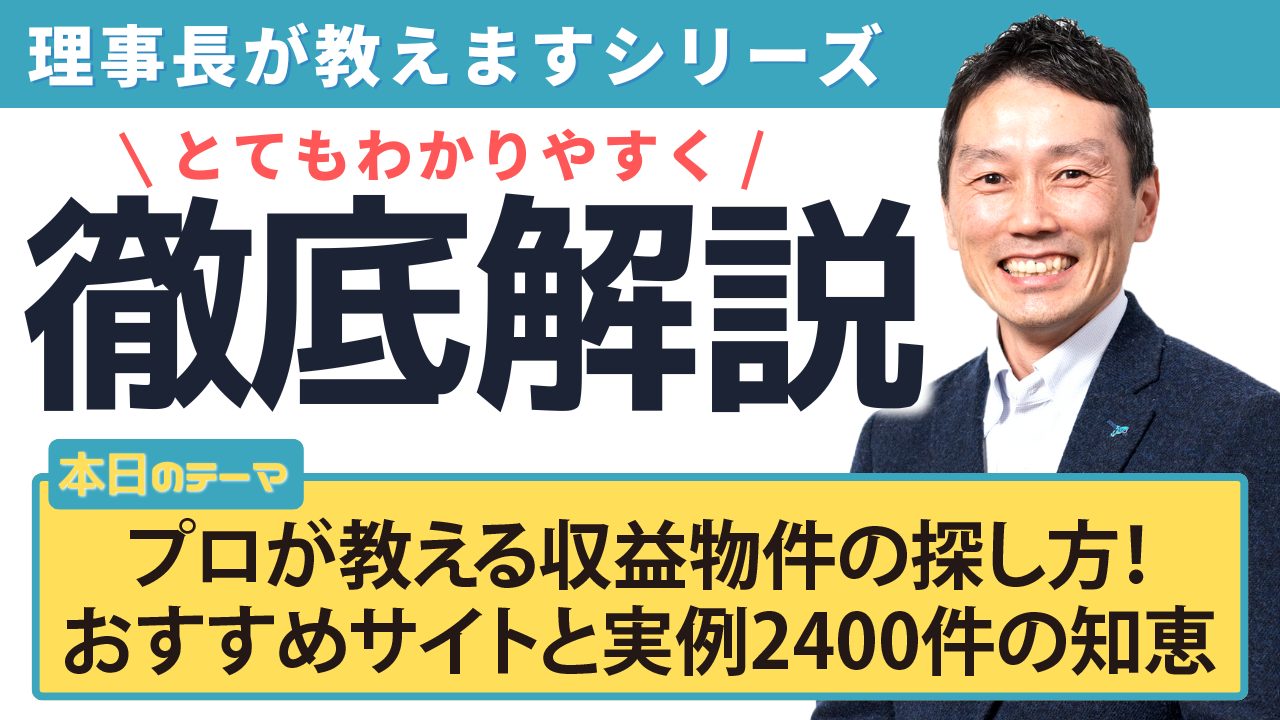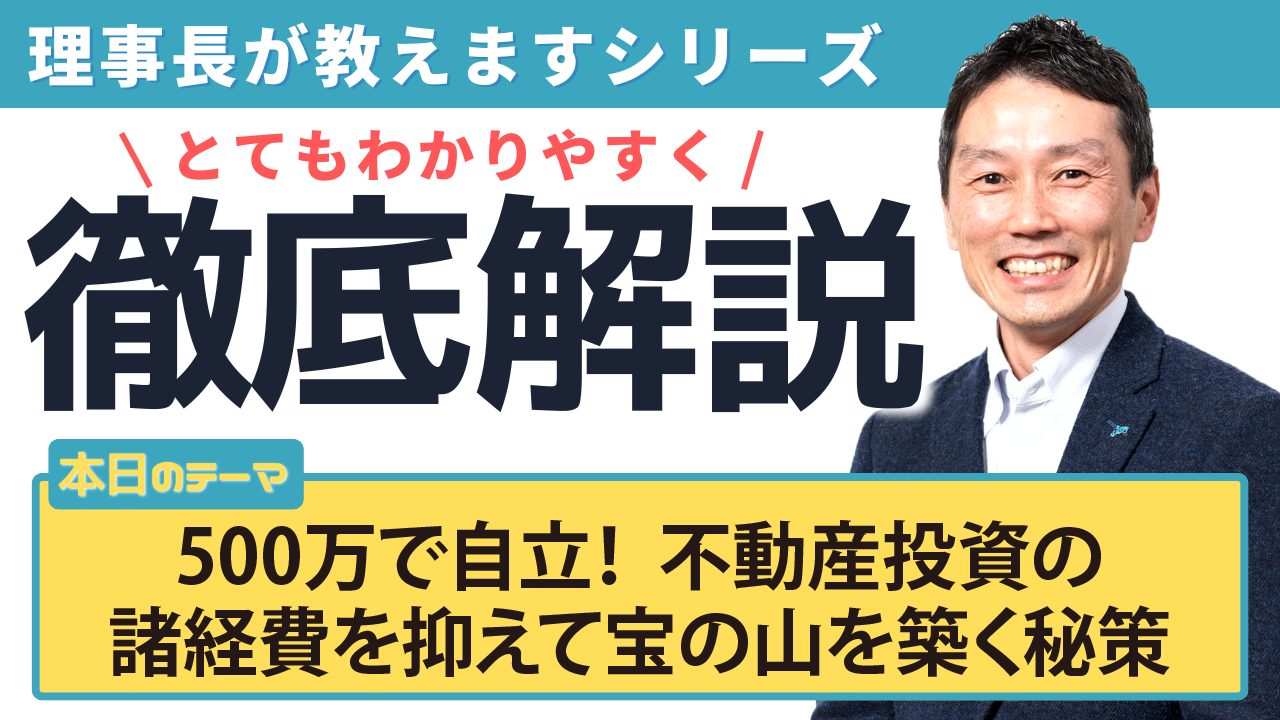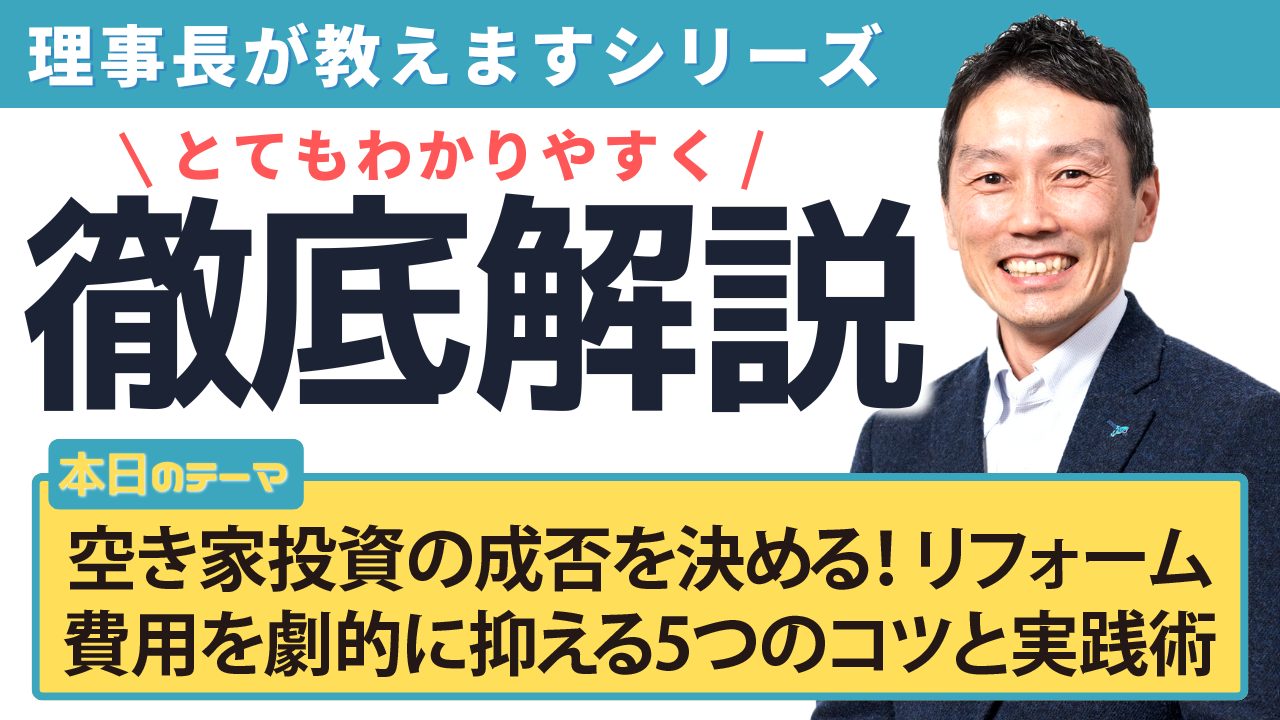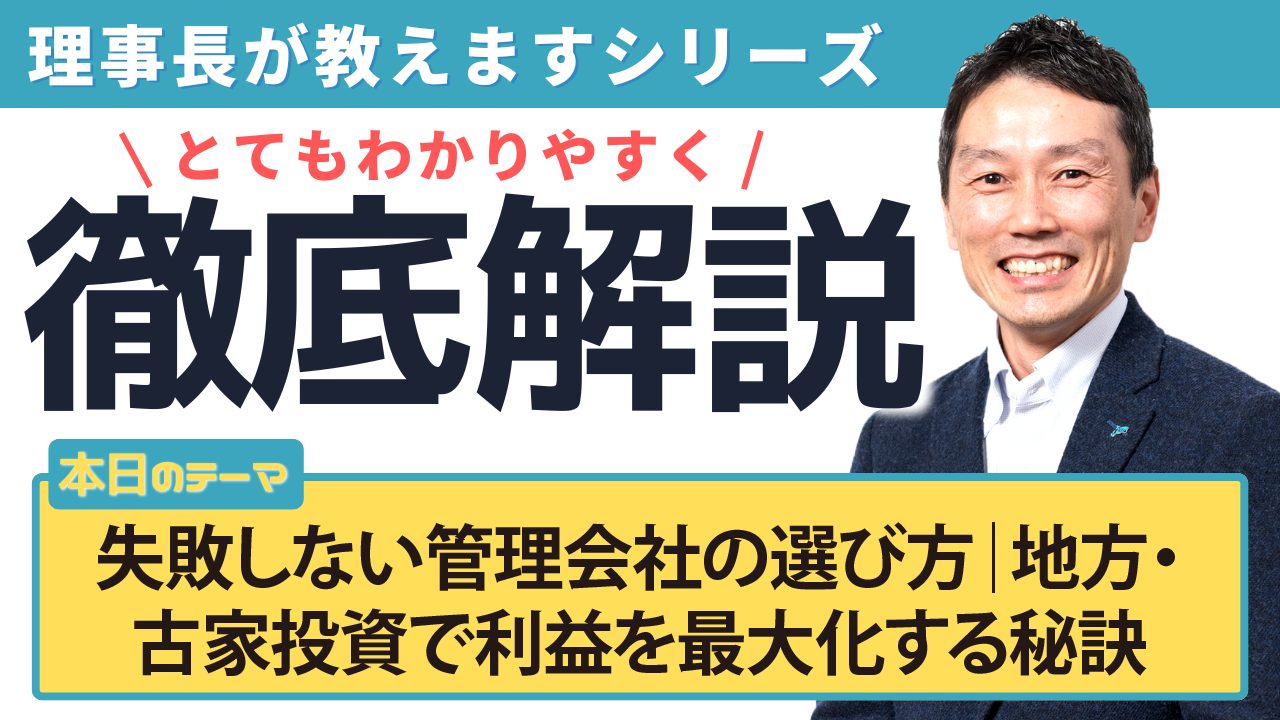こんにちは。(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
「親から相続した実家が空き家になってしまった」「誰も住む予定のない一戸建てをどうすれば良いか分からない」…そんなお悩みを抱えていませんか?
放置された空き家は、景観の悪化や倒壊の危険性だけでなく、税金の負担増という形で所有者に重くのしかかります。しかし、見方を変えれば、空き家は「負債」ではなく、新たな価値を生み出す「資産」となり得るのです。
この記事では、空き家問題に長年向き合ってきた専門家の視点から、具体的な空き家の活用方法を徹底的に解説します。賃貸や民泊、更地活用といった代表的な方法から、それぞれのメリット・デメリット、成功事例、注意すべき法律や規制、さらには資金調達の方法まで、あなたが知りたい情報を網羅しました。
この記事を最後まで読めば、あなたの空き家に最適な活用方法が見つかり、空き家という悩みの種を、収益と地域貢献につながる「宝物」に変えるための第一歩を踏み出せるはずです。さあ、一緒に空き家活用の可能性を探っていきましょう。
目次
空き家の活用方法とは?
そもそも空き家とは?法律上の定義と深刻な現状は?
「空き家」と一言で言っても、その定義や状況は一様ではありません。まずは、空き家が法的にどのように定義され、日本全体でどのような現状にあるのかを正しく理解することが、活用方法を考える上での第一歩となります。
●法律上の「空き家」の定義
2015年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空き家対策特別措置法)において、「空家等」は以下のように定義されています。
「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。」
(引用:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」第二条)
簡単に言えば、「年間を通して人の出入りがなく、居住やその他の目的で使われていない状態の建物とその敷地」が空き家である、というわけです。これには、一戸建ての住居だけでなく、アパートやマンションの一室、店舗なども含まれます。特に、適切な管理が行われていない空き家は「特定空家等」に指定される可能性があり、後述する税制上のペナルティを受けることになります。
●日本の空き家の現状と統計データ
日本の空き家は年々増加しており、深刻な社会問題となっています。総務省統計局が5年ごとに行う「住宅・土地統計調査」の最新(2023年)の結果によると、全国の空き家総数は過去最多の900万戸に達し、総住宅数に占める空き家率は13.8%となりました。
この増加の背景には、少子高齢化による人口減少や、核家族化の進行、都市部への人口集中など、複数の要因が絡み合っています。特に、親世代が住んでいた実家を相続したものの、子ども世代はすでに別の場所に住居を構えているため、居住する人がいなくなり空き家になってしまうケースが後を絶ちません。
また、地域による状況の違いも顕著です。地方や過疎地域では空き家の増加が著しく、コミュニティの維持さえ困難になっている場所も少なくありません。一方で、都市部であっても、利便性の悪い場所や再建築が難しい古い一戸建てなどが空き家として放置されるケースが見られます。ご自身の空き家がどのような場所にあり、周辺の状況がどうなっているかを把握することが、有効な活用方法を見つける上で非常に重要です.
なぜ今、空き家活用が重要視されるのか?その理由は?
増加し続ける空き家を放置することは、所有者個人にとってだけでなく、地域社会全体にとっても大きなリスクを伴います。そのため、国や市区町村も空き家の活用を強く推進しています。なぜ今、これほどまでに空き家活用が重要なのでしょうか。
●空き家が地域に与える負の影響
適切に管理されていない空き家は、様々な問題を引き起こします。
景観の悪化: 雑草が生い茂り、建物が老朽化していく様子は、周辺の景観を損ないます。
防災・防犯上のリスク: 老朽化した住宅は、地震や台風で倒壊する危険性があります。また、不法侵入や放火、不法投棄の温床となり、地域の治安を悪化させる原因にもなります。
衛生環境の悪化: ゴミの不法投棄や、害虫・害獣の発生源となることがあります。
これらの問題は、近隣住民とのトラブルに発展するだけでなく、地域全体の資産価値を低下させることにもつながります。兵庫県など、多くの自治体で空き家対策の条例が制定されているのも、こうした社会問題への対策が急務だからです。
●経済的な観点からの活用のメリット
空き家を放置すれば、固定資産税や維持管理費といったコストがかかるだけの「負の資産」です。しかし、これを活用することで、新たな収入源となる「プラスの資産」へと転換できます。
家賃収入: 賃貸住宅やシェアハウスとして貸し出せば、安定した収入を得ることが可能です。
事業収益: 民泊や店舗、コワーキングスペースなど、事業として運営すれば、家賃収入以上の高い収益性も期待できます。
資産価値の維持・向上: 適切なリフォームやリノベーションを行い、人が住むことで建物の老朽化を防ぎ、資産価値を維持・向上させることができます。
新築住宅の人気が高い日本ですが、近年では古い戸建てをリノベーションして住むことの魅力も再認識されています。空き家という既存のストックを有効活用することは、経済的にも非常に合理的な選択なのです。
●持続可能な社会に向けた役割
空き家の活用は、SDGs(持続可能な開発目標)の観点からも非常に重要です。
資源の有効活用: 新築の建築を減らし、既存の住宅を再利用することは、木材やエネルギーといった資源の消費を抑えることにつながります。
地域コミュニティの活性化: 空き家に新たな住民や事業者が入ることで、地域に活気が生まれます。子育て世代の移住を促進したり、高齢者の交流の場を提供したりと、多様な形で地域社会に貢献できます。
コンパクトシティの実現: 活用可能な空き家を増やすことで、無秩序な市街地の拡大を防ぎ、インフラを効率的に維持できるコンパクトなまちづくりに貢献します。
このように、空き家の活用は単なる個人の資産運用の問題ではなく、日本の未来にとって大切な社会貢献活動でもあるのです。
【初心者向け】代表的な空き家の活用方法3選とは?
それでは、具体的にどのような活用方法があるのでしょうか。ここでは、代表的な3つの方法をご紹介します。ご自身の空き家の状態や立地、そしてかけられる手間や費用を考えながら、最適な方法を検討してみてください。
最も手軽?空き家を賃貸物件として貸し出す方法
空き家活用の方法として、まず思い浮かぶのが賃貸として人に貸し出すことでしょう。これは比較的始めやすく、安定した収入が期待できる方法の一つです。
●地域の賃貸市場を調査する
まず最初に行うべきは、あなたの空き家がある地域の賃貸市場を徹底的に調査することです。周辺の物件はどのくらいの家賃で貸し出されているのか、どのような間取りや設備が人気なのかを調べましょう。不動産情報サイトで検索したり、地元の不動産会社に相談したりするのが有効です。借り手のニーズを把握しなければ、いくら安く貸し出したとしても入居者は見つかりません。
●適正な賃料を設定する
市場調査の結果を基に、適正な賃料を設定します。建物の築年数、広さ、間取り、駅からの距離、周辺環境などを考慮して、借り手にとって魅力的かつ、オーナーとしても納得のいく価格を見極めることが重要です。一度、専門家(不動産会社など)に査定を依頼してみるのも良いでしょう。
●契約内容を明確にする
借り手が見つかったら、賃貸借契約を結びます。この際、契約内容は書面で明確に残すことがトラブル防止の鍵です。家賃、共益費、敷金・礼金、契約期間、更新条件、修繕費の負担割合、禁止事項(ペット飼育、楽器演奏など)といった項目を漏れなく記載しましょう。いったん契約を結ぶと簡単に変更はできないため、慎重に進める必要があります。
空き家を放置するのではなく、資産として活かす第一歩として、賃貸での貸し出しは非常に有効な選択肢です。特に、国や自治体によっては、子育て世帯や高齢者向けに空き家を貸し出す場合に補助金が出る制度(借り上げ制度など)もあるため、調べてみると良いでしょう。
収益性が魅力?シェアハウスや民泊で活用する道
近年、新しいライフスタイルや観光の形として、シェアハウスや民泊の人気が高まっています。これらの活用方法は、通常の賃貸よりも高い収益性を期待できるのが魅力です。
ターゲット層を明確にする
シェアハウスや民泊を成功させるには、どのような人に利用してもらいたいか、ターゲット層を明確にすることが不可欠です。
シェアハウス: 学生、若手社会人、外国人、クリエイターなど、特定のコミュニティを形成することで、入居者同士のつながりが生まれ、満足度が高まります。
民泊: ファミリー層、グループ旅行客、ビジネス出張者など、ターゲットによって必要な設備やアピールポイントが変わってきます。例えば、ファミリー向けならキッチン設備を充実させたり、ビジネス向けなら高速Wi-Fiやワークスペースを設置したりといった工夫が考えられます。
●必要な設備を整える
ターゲット層が決まったら、そのニーズに合わせた設備を整えます。シェアハウスであれば、共用のリビングやキッチン、複数のシャワー・トイレが必要です。民泊であれば、旅館業法や住宅宿泊事業法(民泊新法)で定められた防災設備の設置が義務付けられています。建物ごと貸し出すのか、部屋ごとに貸すのかによっても必要な準備は異なります。快適に過ごしてもらうための家具や家電、アメニティの充実は、集客や高評価レビューにつながる重要な要素です。
●集客方法を工夫する
物件の準備が整ったら、集客です。現在は、SNSや専門のマッチングサイト(Airbnb、Booking.comなど)に物件情報を掲載するのが一般的です。魅力的な写真や分かりやすい説明文で、物件の特徴をアピールしましょう。地域のイベントと連携したり、独自の体験プランを提供したりすることで、他の物件との差別化を図ることもできます。複数の人が一つ屋根の下に住むシェアハウスや、不特定多数の人が宿泊する民泊は、コミュニティやつながりを生み出し、空き家に新たな命を吹き込む面白い活用方法です。
建物を解体!更地にして土地活用する選択肢とは?
建物の老朽化が著しく、リフォームに高額な費用がかかる場合や、維持管理が難しい場合には、建物を解体して更地にし、土地として活用する方法も有効な選択肢です。
●土地の利用目的を検討する
更地にした後の活用方法は様々です。
駐車場: 初期投資が比較的少なく、管理の手間も少ないため、手軽に始められる活用法です。月極駐車場やコインパーキングが考えられます。
トランクルーム: 都心部や住宅密集地で需要があります。コンテナを設置するだけで始められます。
太陽光発電: 日当たりの良い広い土地であれば、売電による長期安定収入が期待できます。
土地の売却: 管理の手間から解放されたい、まとまった資金が必要、という場合には売却も一つの手です。
建て替え: 自身の自宅や、新たな賃貸アパート・マンションを建築することも可能です。
どの活用方法が最適かは、その土地の立地や広さ、周辺の需要によって大きく異なります。まずは、どのような可能性があるかを広く検討することが重要です。
●法的規制を確認する
土地活用を行う際には、必ず法的規制を確認する必要があります。特に重要なのが「都市計画法」です。土地が「市街化区域」なのか「市街化調整区域」なのか、また「用途地域」は何に指定されているのかによって、建てられる建物の種類や規模が厳しく制限されます。計画を立てる前に、市区町村の都市計画担当部署や、国土交通省のウェブサイトで確認しましょう。
●コストと利益を算出する
更地活用で忘れてはならないのが、コスト計算です。まず、木造一戸建ての解体費用は、坪単価で4〜5万円程度、総額で100万円以上かかるのが一般的です。この解体・撤去費用に加え、選択した活用方法ごとの初期投資と、運営にかかるランニングコスト、そして固定資産税などを計算し、どのくらいの利益が見込めるのかをシミュレーションすることが不可欠です。空き地を放置すると、固定資産税の軽減措置が適用されなくなり税金が高くなる可能性があるため、解体後の計画はしっかりと行いましょう。
空き家を賃貸する際のメリット・デメリット
最も一般的な活用方法である「賃貸」。そのメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。ご自身の状況と照らし合わせ、本当に自分に合った方法なのかを判断する材料にしてください。
賃貸で貸し出すことで得られる3つのメリットとは?
空き家を賃貸に出すことには、金銭的なメリットだけでなく、資産管理や地域貢献といった多面的な魅力があります。
1. 安定した収入が得られる
最大のメリットは、何と言っても安定した家賃収入を得られることです。入居者が見つかれば、毎月一定の賃料が継続的に入ってくるため、将来の生活設計が立てやすくなります。これは、固定資産税の支払いや、将来必要になるであろう修繕費の積み立てにも充当できます。特に、年金の補完として不動産収入を考えている方にとっては、一番手軽で分かりやすい方法と言えるでしょう。アパート経営のように大規模なものではなく、まずは一戸建てから気軽に始められる点もポイントです。
2. 空き家の維持管理ができる
「家は人が住まなくなると傷む」とよく言われます。これは事実で、誰も住んでいない家は換気が行われず湿気がこもり、カビや腐食の原因となります。また、定期的な清掃やメンテナンスが行われないため、老朽化のスピードが格段に速まります。
賃貸に出して入居者が住むことで、日常的な換気や清掃が行われ、建物の状態が良好に保たれます。水道も定期的に使われるため、給排水管の錆びや劣化を防ぐ効果もあります。なぜこれが重要かというと、建物の資産価値を維持することに直結するからです。放置してボロボロになるのを防ぎ、大切な資産を守ることができるのです。
3. 地域貢献につながる
空き家に新たな住民を迎えることは、立派な地域貢献活動です。人が住むことで、地域の人口が維持され、コミュニティに活気が生まれます。特に、子育て世帯が入居すれば、地域に子どもの声が響き、学校や地域活動の担い手が増えることにもつながります。
例えば、滋賀県や兵庫県など、多くの自治体では移住・定住促進のために、空き家を活用した賃貸住宅の提供に力を入れています。あなたが空き家を貸し出すという一つのアクションが、地域の未来を支えることにもなるのです。この社会的な意義も、賃貸の大きな魅力の一つと言えるでしょう。
賃貸経営で注意すべき3つのデメリットとは?
魅力的なメリットがある一方で、賃貸経営には見過ごすことのできないデメリットやリスクも存在します。これらを事前に理解し、対策を考えておくことが成功の鍵です。
1. 入居者トラブルのリスク
残念ながら、全ての入居者が優良なわけではありません。賃貸経営で最も頭を悩ませるのが、入居者とのトラブルです。
家賃滞納: 最も多いトラブルです。督促しても支払われない場合、法的な手続きが必要になることもあり、精神的・時間的な負担が大きくなります。
近隣トラブル: 騒音やゴミ出しのルール違反など、入居者が近隣住民とトラブルを起こすケースです。オーナーとして対応を求められることがあります。
建物の損傷: 故意または過失によって建物を傷つけられたり、汚されたりするリスクです。退去時の原状回復を巡って揉めることも少なくありません。
こうしたトラブルは、オーナーにとって大きなストレスとなります。
2. 維持管理の手間と費用がかかる
入居者がいるからといって、管理が全く不要になるわけではありません。むしろ、貸主としての責任が発生します。
修繕対応: 給湯器の故障、雨漏り、エアコンの不具合など、設備の老朽化による修理は基本的にオーナーの負担と責任で行う必要があります。入居者からの連絡に迅速に対応しなければならず、手間がかかります。
定期的なメンテナンス: 長く安心して住んでもらうためには、外壁の塗り替えや屋根の補修など、ある程度の年数が経ったら大規模な修繕も計画的に行う必要があります。これらの費用は高額になることも少なくありません。
不動産経営は、思った以上に手間とコストがかかることを覚悟しておく必要があります。
3. 収入が不安定になる可能性
賃貸経営は、常に入居者がいることが前提です。しかし、常時満室を維持するのは、プロの不動産会社でも簡単ではありません。
空室リスク: 入居者が退去した後、次の借り手が見つかるまでの期間は家賃収入がゼロになります。この期間が長く続くと、収入計画が大きく狂ってしまいます。立地が悪かったり、建物が古かったりすると、空室リスクはさらに高まります。
家賃下落リスク: 建物は年々老朽化するため、それに伴い家賃も徐々に下がっていくのが一般的です。また、周辺に新しいマンションやアパートが建つと、競争のために家賃を下げざるを得ない場合もあります。
収入が思ったように得られない可能性があるというデメリットも、しっかりと認識しておくことが重要です。
シェアハウスや民泊の活用事例
賃貸よりも高い収益性が期待できるシェアハウスや民泊。しかし、運営には独自のノウハウが必要です。ここでは、成功事例と、始める前に必ず知っておくべき法律や規制について解説します。
空き家が生まれ変わる!シェアハウス・民泊の成功事例
全国各地で、空き家を魅力的なシェアハウスや民泊に再生し、成功を収めているケースが数多くあります。具体的な事例を見ることで、活用のヒントが得られるはずです。
事例1:地域コミュニティの拠点となった「古民家シェアハウス」(群馬県)
都心から移住してきた若者たちが、築80年の古民家をDIYでリノベーション。単なる住居としてだけでなく、地域住民も参加できるイベント(味噌づくりワークショップ、野菜の収穫祭など)を定期的に開催する「開かれたシェアハウス」として運営しています。SNSでの情報発信が功を奏し、移住希望者からの問い合わせが絶えない人気物件となりました。成功のポイントは、「住む」という機能に「交流」という付加価値を加えた点です。
事例2:インバウンド需要を取り込んだ「アート民泊」(大阪府)
大阪市内の古い長屋を、現代アートのギャラリーを兼ねた一棟貸しの民泊施設に改造。部屋ごとに異なるアーティストが内装を手掛け、宿泊しながらアート作品を鑑賞できるというユニークなコンセプトが、海外の旅行メディアで紹介され話題に。宿泊予約サイトでの評価も高く、高単価ながら高い稼働率を維持しています。このケースは、物件の持つ特徴とターゲット層のニーズを上手くマッチングさせた好事例と言えるでしょう。
●利用者の声の紹介
これらの成功事例では、利用者からのポジティブな声がさらなる集客につながっています。
「ただ泊まるだけでなく、地元の人と交流できたのが最高の思い出です」(シェアハウス利用者)
「まるで美術館に泊まっているような、非日常的な体験ができました。日本の伝統的な建物と現代アートの組み合わせが素晴らしい」(民泊利用者)
このように、物件のハード面だけでなく、そこで得られる体験というソフト面を充実させることが、成功の鍵となります。これらの事例を参考に、自分の空き家ならどんな特徴を活かせるか、どんな付加価値を提供できるかを考えてみるのがおすすめです。
トラブル回避!知っておくべき法律や規制とは?
シェアハウスや民泊を運営するには、関連する法律や規制を遵守することが絶対条件です。知らなかったでは済まされない注意点も多いため、事前にしっかりと確認しましょう。
●シェアハウスに関連する法律
シェアハウスは法的な定義が曖昧な部分もありますが、一般的には「建築基準法」や「消防法」の規制を受けます。特に、一つの建物を複数の人が区画して利用する場合、「寄宿舎」と見なされる可能性があります。寄宿舎に該当すると、廊下の幅や防火設備の設置基準などが一般の住宅よりも厳しくなります。また、入居者との契約は「賃貸借契約」となるため、借地借家法が適用されます。安易な立ち退き要求などはできないため、注意が必要です。
●民泊に関連する法律
民泊の運営は、主に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づいて行われます。
届出の義務: 都道府県知事等への届出が必須です。無許可での運営は罰則の対象となります。
年間営業日数の上限: 年間180日が上限と定められています。これを超えて営業する場合は、「旅館業法」に基づく許可が必要になります。
地域ごとの規制(条例): 自治体によっては、条例でさらに厳しい規制を設けている場合があります。例えば、特定のエリアでの営業を禁止したり、平日の営業を制限したりするケースです。これを「上乗せ条例」と呼びます。
これらの法律や規制は複雑で、違反すると高額な罰金や営業停止命令を受けるリスクがあります。計画を進める際には、必ず管轄の自治体(保健所や建築指導課など)に相談し、条件や必要な手続きを確認することが不可欠です。専門の行政書士などに相談するのも一つの方法です。比較的手軽に始められるイメージがあるかもしれませんが、法律面でのハードルは決して低くないという点を肝に銘じておきましょう。
更地にして土地活用する方法
建物の活用が難しい場合、解体して更地にするという選択肢があります。更地にした後の活用方法として代表的な「駐車場・トランクルーム運営」と「土地売却」について、それぞれのポイントを解説します。
初期投資を抑える!駐車場やトランクルームの運営
更地活用の中でも、比較的少ない初期投資で始められるのが駐車場やトランクルームの運営です。建物を建てる必要がないため、事業転換しやすいのもメリットです。
●需要を調査する
何よりも重要なのが、その土地で駐車場やトランクルームの需要があるかどうかを見極めることです。
駐車場の需要: 駅周辺、商業施設の近く、オフィス街、住宅密集地で月極駐車場やコインパーキングのニーズが高い傾向にあります。周辺の競合駐車場の料金や稼働状況を調査しましょう。
トランクルームの需要: 都心部やマンションが多いエリアでは、収納スペース不足に悩む家庭からの需要が見込めます。周辺に大手事業者のトランクルームがあるかどうかも、需要を測る一つの指標になります。
地元の不動産会社や、駐車場・トランクルーム運営を専門に行う事業者に相談し、需要調査を依頼するのも良いでしょう。
●適切な料金設定をする
需要調査と競合調査の結果を基に、料金を設定します。高すぎれば利用されず、安すぎれば収益が出ません。月極駐車場であれば周辺の相場に合わせ、コインパーキングであれば時間帯によって料金を変えるなどの工夫も有効です。初期投資の回収期間も考慮しながら、慎重に価格を決めましょう。
●運営管理をしっかり行う
駐車場やトランクルームは、運営開始後も管理が必要です。
自主管理: 自分で清掃や集金、トラブル対応を行います。コストは抑えられますが、手間と時間がかかります。
管理委託: 専門の運営会社に管理を委託します。管理料という負担は発生しますが、集金やクレーム対応など、面倒な業務を全て任せられるため、遠方に住んでいる場合でも安心です。大手事業者であれば、一括借り上げ(サブリース)方式で、稼働状況にかかわらず一定の賃料を受け取れるプランもあります。
介護施設や店舗などを建てるのに比べ、更地をそのまま活かせるこれらの方法は、土地活用の入り口として検討しやすい選択肢です。
手間から解放!土地を売却するという選択肢
「管理の手間や固定資産税の負担から解放されたい」「まとまった現金が必要」という場合には、土地を売却することが最もシンプルな解決策となります。
●市場価値を把握する
土地を売却する上で、まずやるべきことは、その土地がいくらで売れそうか、市場価値を把握することです。土地の価格は、立地、広さ、形状、前面道路の幅、法規制など、様々な要因で決まります。
複数の不動産会社に査定を依頼(一括査定サイトなどを利用すると便利)し、客観的な価格を知ることが重要です。一つの会社の査定額だけを鵜呑みにせず、なぜその価格になるのか、根拠をしっかり確認しましょう。
●信頼できる不動産業者を選ぶ
土地の売却は、パートナーとなる不動産会社の力量に大きく左右されます。単に査定額が高いだけでなく、販売実績が豊富で、地域情報に精通し、親身に相談に乗ってくれる会社を選びましょう。担当者との相性も大切です。売却活動の報告をこまめにしてくれるか、こちらの要望をしっかり聞いてくれるかなど、契約を結ぶ前に見極めることが重要です。
●適切なタイミングで売却する
不動産の価格は、景気や金利の動向、周辺の開発計画などによって変動します。売却を急ぐ必要がなければ、市場の動向を見極め、少しでも高く売れるタイミングを待つのも一つの戦略です。例えば、近隣に新しい駅や商業施設ができる計画があれば、土地の価値の高まりが期待できます。
売却によって得た資金で、より収益性の高い不動産を購入したり、別の投資に回したりと、新たな資産形成につなげることも可能です。空き家という問題を、現金という最も流動性の高い資産に変える、非常に有効な活用方法と言えます。
空き家活用のための資金調達方法
空き家を活用するには、リフォーム費用や解体費用など、初期投資が必要になるケースがほとんどです。自己資金だけでまかなうのが難しい場合、どのような資金調達の方法があるのでしょうか。
知らなきゃ損!補助金や助成金を賢く活用する方法
国や地方自治体は、空き家問題の解消に向けて様々な支援制度を設けています。これらを活用すれば、自己負担を大きく軽減できる可能性があります。使わない手はありません。
●地域の制度を調べる
補助金や助成金の制度は、お住まいの市区町村によって内容が大きく異なります。まずは、空き家のある自治体のウェブサイトで「空き家 補助金」「リフォーム 助成金」といったキーワードで検索してみましょう。自治体の担当窓口(建築指導課、都市計画課など)に直接問い合わせるのが最も確実です。
【補助金・助成金の例】
空き家改修(リフォーム)補助金: 空き家を住宅や店舗として活用するためにリフォームする際の費用の一部を補助。
耐震改修補助金: 旧耐震基準の建物を現行基準に適合させるための工事費用を補助。
解体撤去費用補助金: 危険な状態にある空き家を解体する際の費用の一部を補助。
移住者向け家賃補助: 空き家バンクなどを通じて移住者が賃貸する場合の家賃の一部を補助。
これらの制度は、予算の上限に達すると受付を終了してしまうことが多いので、早めに情報を集めて行動することが大切です。
●申請条件を確認する
各制度には、対象となる建物の条件(築年数、構造など)、所有者の条件(税金の滞納がないことなど)、活用方法の条件(一定期間の賃貸を義務付けるなど)といった、細かい申請条件が定められています。自分たちがその条件に合致するかどうかを、募集要項でしっかり確認しましょう。
●必要書類を整える
申請には、申請書、建物の登記簿謄本、工事の見積書、改修計画図、納税証明書など、多くの書類が必要になります。不備があると受け付けてもらえないため、事前にリストアップし、漏れなく準備することが重要です。手続きが複雑で分からない場合は、改修を依頼する工務店や専門家に相談するのも良いでしょう。有効活用できる制度は最大限に利用し、賢く資金計画を立てましょう。
自己資金が足りない…融資という選択肢をどう考える?
補助金だけでは足りない、まとまった資金が必要という場合には、金融機関からの融資(ローン)を検討することになります。
●金融機関の比較を行う
融資を受ける際は、一つの金融機関だけでなく、複数の選択肢を比較検討することが非常に重要です。
政府系金融機関: 日本政策金融公庫は、中小企業や個人事業主向けの融資に積極的で、民泊や店舗など事業目的の空き家活用に適しています。比較的金利が低く、審査期間が長い傾向があります。
民間金融機関(銀行、信用金庫など): 各金融機関が独自の不動産関連ローン(リフォームローン、アパートローンなど)を提供しています。取引実績のある金融機関や、地元の信用金庫などは、親身に相談に乗ってくれる可能性があります。
ノンバンク: 銀行に比べて金利は高めですが、審査のスピードが速く、柔軟な対応が期待できる場合があります。
それぞれの金融機関に、どのようなローン商品があり、どのような特徴があるのかを調べましょう。
●金利や返済条件を確認する
融資を比較する上で最も重要なのが、金利と返済条件です。金利には、借入期間中ずっと金利が変わらない「固定金利」と、市場金利の変動に合わせて金利が見直される「変動金利」があります。どちらにメリットがあるかは、将来の金利動向やご自身の資金計画によって異なります。
また、返済期間は何年に設定できるのか、繰り上げ返済は可能か、保証人や担保は必要か、といった条件もしっかり確認し、無理のない返済計画を立てることが不可欠です。
●専門家に相談する
融資の申し込みには、事業計画書や収支計画書の提出を求められることがほとんどです。特に、賃貸経営や民泊事業などの収益性をアピールする必要がある場合、素人が作成した計画書では説得力に欠け、審査で不利になる可能性があります。
このような時こそ、不動産投資や資金調達に詳しい専門家の知識が役立ちます。例えば、後述する「古家再生投資プランナー®︎」のような専門家は、収益性の高い事業計画の立て方や金融機関との交渉術に長けています。専門家と相談しながら、実現可能性の高い計画を練り上げることが、融資を成功させるための近道です。
空き家を活用する際の注意点
空き家活用は、夢のある話ばかりではありません。成功のためには、事前にリスクや注意点をしっかりと把握し、現実的な計画を立てることが何よりも重要です。
計画の前に必ずチェック!初期投資とランニングコスト
「儲かるらしいから」という安易な考えで始めると、想定外の出費で計画が頓挫しかねません。まずは、お金の計算を徹底的に行いましょう。
●初期投資を明確にする
空き家活用を始める時点(top)で、具体的にどのような費用がかかるのかをリストアップし、明確にすることが重要です。
物件取得費: 空き家をこれから購入する場合。
リフォーム・改修費用: 内装、外装、水回り、耐震補強など。
設備購入費: エアコン、給湯器、キッチン、家具、家電など。
解体費用: 更地にする場合。
諸経費: 不動産取得税、登記費用、仲介手数料など。
これらの費用は、活用方法や物件の古い状態によって大きく変動します。複数の業者から見積もりを取り、相場を把握した上で、余裕を持った予算を組むことが大切です。
●ランニングコストを計算する
見落としがちですが、運営を始めてから継続的にかかるランニングコストの計算も不可欠です。
税金: 固定資産税、都市計画税。賃貸収入などがあれば所得税、住民税。
保険料: 火災保険、地震保険。施設賠償責任保険(民泊などの場合)。
修繕積立金: 将来の大規模修繕に備えた積み立て。
管理委託費: 管理会社に委託する場合の費用。
光熱費・通信費: 空室期間中の費用や、共用部分の費用。
広告宣伝費: 入居者募集や集客のための費用。
これらのランニングコストを考慮して収支計画を立てないと、「家賃収入は入ってくるのに、手元にお金が残らない」という事態に陥ります。
●資金計画を立てる
初期投資とランニングコストの計算ができたら、自己資金、補助金、融資をどう組み合わせるか、具体的な資金計画を立てます。収入と支出をシミュレーションし、何年で初期投資を回収できるのか、安定した経営が可能かを判断しましょう。この資金計画が、空き家活用成功の基礎となります。
成功の鍵はココ!地域の需要を正しく見極める方法
どんなに立派なリフォームをしても、その地域に需要がなければ、借り手や利用者は現れません。思い込みや希望的観測ではなく、客観的なデータに基づいて需要を見極めることが成功の絶対条件です。
●地域の市場調査を行う
まずは、足で稼ぐ地道な調査が基本です。
街を歩く: 空き家のある地域を実際に歩き、どのような人が住んでいるか(高齢者、ファミリー層、学生など)、どのような施設があるか(学校、病院、スーパー、公園など)、街の雰囲気はどうかを肌で感じましょう。
地元の人に聞く: 地元の商店主や住民に話を聞いてみると、インターネットだけでは分からないリアルな情報(「この辺は子育て世帯が増えている」「最近、近くの工場に外国人の従業員が増えた」など)が得られることがあります。奈良県や和歌山県など、特定の地域に根差した情報は特に貴重です。
公的データの活用: 市区町村が公表している人口動態、年齢構成、将来人口推計などのデータは、長期的な需要を予測する上で非常に参考になります。
●競合物件の分析をする
あなたの空き家は、周辺にある他の物件と競争することになります。競合となる物件を徹底的に分析しましょう。
賃貸物件: 不動産情報サイトで、近隣の類似物件(間取り、築年数など)の家賃、設備、空室状況を調べます。なぜその物件が人気なのか、あるいはなぜ空室なのかを分析することで、自分の物件の強みや弱みが見えてきます。
民泊・シェアハウス: 専門サイトで、近隣施設の宿泊料金、稼働率、レビュー内容などをチェックします。どんな点が評価されているのか、どんな不満が出ているのかを分析し、自分の運営に活かしましょう。
●ターゲット層を明確にする
市場調査と競合分析の結果から、「誰に」「何を」提供するのか、ターゲット層を具体的に絞り込みます。
例えば、「大学が近いから、安価な家賃で住みたい学生」「テレワークが中心で、都心から少し離れた静かな環境を求める単身者」「古い日本の家に泊まってみたい外国人観光客」など、ターゲットが明確になれば、リフォームの方向性やアピールすべきポイントもおのずと決まってきます。
この需要を見極める作業を事前に行うかどうかが、空き家活用が成功するか失敗に終わるかの大きな分かれ道となるのです。
空き家の管理と維持の重要性
空き家を活用するということは、その建物を「資産」として長期的に維持・管理していく責任を負うということです。適切な管理を怠れば、せっかくの資産価値は下がり、大きなトラブルにつながることもあります。
資産価値を守るために不可欠な定期メンテナンスとは?
車に車検が必要なように、建物にも定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。これを怠ると、後で高額な修理費用が必要になることもあります。
●定期点検を行う
専門家でなくても、定期的に自分で行える点検はたくさんあります。最低でも半年に一度は、以下の項目をチェックする習慣をつけましょう。
屋外: 屋根の瓦やスレートにズレやひび割れはないか。外壁にひび割れや塗装の剥がれはないか。雨樋に詰まりや破損はないか。
屋内: 雨漏りのシミはないか。床や壁に傾きやきしみはないか。窓やドアの開閉はスムーズか。
設備: 水道から赤水は出ないか。蛇口や配管から水漏れはないか。換気扇は正常に作動するか。
チェックリストを作成し、毎回記録を残しておくと、変化に気づきやすくなります。
●必要な修繕を早めに実施する
点検で不具合が見つかった場合、「まだ大丈夫だろう」と放置せず、早めに修繕することが重要です。「小さなひび割れ」が雨漏りの原因となり、柱や土台の腐食につながるなど、小さな問題が時間とともに大きな損害を引き起こします。
最近では、DIYで簡単な修理を行う人も増えていますが、専門的な知識が必要な場合や、安全に関わる部分(電気、ガス、構造など)は、無理せずプロの業者に依頼しましょう。早めの対応が、結果的に修理費用を安く抑えることにもつながります。
●環境に配慮したメンテナンスを心がける
メンテナンスを行う際は、環境への配慮も大切です。例えば、断熱性能の高い窓に交換したり、節水型のトイレにリフォームしたりすることは、光熱費の削減(省エネ)につながり、入居者にとってもメリットがあります。また、耐久性の高い材料を選ぶことで、改修工事の頻度を減らし、廃棄物の削減にも貢献できます。長期的な視点で、資産価値と環境性能の両方を高めるメンテナンスを心がけましょう。
手間を減らして安心!プロの管理会社を利用するメリット
「遠方に住んでいて、自分で管理するのは難しい」「入居者からのクレーム対応が不安」という方には、管理会社の利用がおすすめです。コストはかかりますが、それに見合うだけのメリットがあります。
●専門知識を持つプロに任せる
不動産管理には、賃貸借契約に関する法律知識、建物の修繕に関する専門知識、税務に関する知識など、幅広い専門性が求められます。これらをすべて個人で対応するのは非常に大変です。
管理会社は、これらの専門知識を持つプロの集団です。入居者募集から家賃の集金、滞納時の督促、退去時の立ち会い・精算、クレーム対応、定期的な建物点検・清掃まで、煩雑な管理業務をすべて代行してくれます。これにより、オーナーはお客様対応の手間から解放され、安心して経営に専念できます。
●トラブル時の迅速な対応が可能
夜中に「給湯器が壊れた」、休日に「水漏れがする」といった緊急のトラブルが発生した場合、個人で対応するのは困難です。管理会社は、24時間対応のコールセンターを設けていたり、提携している修理業者をすぐに手配してくれたりするため、迅速な対応が可能です。スピーディーな対応は入居者の満足度を高め、長期入居にもつながります。これが、管理を委託する大きな理由の一つです。
●コストの見積もりを事前に確認する
管理会社を利用する際は、事前にサービス内容とコストをしっかり確認しましょう。管理委託料は、一般的に家賃収入の5%前後が相場ですが、会社やプランによって異なります。基本の管理料に含まれるサービスは何か、追加で費用が発生するのはどのようなケースか(例:退去時のリフォーム費用、広告料など)を、契約前に詳しく確認することが重要です。
複数の管理会社から見積もりや提案を受け、保有物件のカテゴリーや自身の運営方針に合った、信頼できるパートナーを見つけることが、長期的に安定した空き家活用を実現するための鍵となります。
空き家活用の成功事例
理論だけでなく、実際に空き家を活用して成功を収めた事例を知ることは、具体的なイメージを掴む上で非常に役立ちます。ここでは、「地域活性化」と「収益化」という2つの側面から成功事例をご紹介します。
街が元気になる!地域活性化に貢献した事例
空き家活用は、単なるビジネスに留まらず、地域全体を元気にする力を持っています。
事例1:多世代交流の拠点「まちの縁側」(大阪府)
以前は商店だった空き家をリノベーションし、誰でも気軽に立ち寄れるコミュニティスペースとして再生した事例です。日中は高齢者向けのサロンや子育て中の親子の交流の場、週末には地域の若者が企画するイベントやマルシェが開催されるなど、多世代が集う地域の「縁側」のような存在になっています。運営は地域のNPO法人が行っており、自治体からの補助金も活用しています。この活動により、地域のつながりが深まり、防犯面の向上にも貢献しています。
事例2:アートプロジェクトで観光資源化(群馬県)
過疎化が進む山村地域の複数の空き家を舞台に、国内外のアーティストが滞在制作を行う「アーティスト・イン・レジデンス」事業を展開。空き家そのものがアート作品となり、それらを巡るツアーが新たな観光資源となっています。この取り組みをきっかけに移住してくるアーティストも増え、地域に新たな文化と活気をもたらしました。これは、空き家という「点」の活用から、エリア全体の価値を高める「面」の活用へと発展させた具体例です。
これらの事例に共通するのは、空き家を「箱」として捉えるのではなく、そこに「人」が集い、「活動」が生まれる「場」として活用している点です。アイデア次第で、空き家は地域活性化の起爆剤となり得るのです。
資産が増える!収益化に成功した具体的な事例
もちろん、しっかりと収益を上げることも空き家活用の大きな目的です。ここでは、賢く収益化に成功した事例を見ていきましょう。
事例1:徹底したターゲット設定で高利回りを実現した賃貸物件(千葉県)
駅から遠く、一般的な賃貸には不向きとされていた郊外の一戸建て。しかし、所有者は「車通勤のファミリー層」にターゲットを絞り、広い駐車スペースを確保し、ペット飼育可(ドッグラン付き)という条件でリフォームを行いました。ニッチな需要を的確に捉えた結果、相場より高い家賃設定にもかかわらず、すぐに借り手が見つかりました。事前の市場調査と、ターゲットのニーズに合わせた付加価値の提供が収益化成功の鍵となった事例です。
事例2:「古家再生投資」で安定収入を確保(全国各地)
私たち(一社)全国古家再生推進協議会が推進しているのが、この「古家再生投資」です。これは、市場価格が低い古い空き家(古家)を安く購入し、必要最低限のリフォームを施して賃貸に出すという事業モデルです。
例えば、物件購入費200万円、リフォーム費用200万円の合計400万円を投資し、月6万円の家賃で貸し出したとします。年間の家賃収入は72万円となり、表面利回りは18%という高い収益性を実現できます。実際に、私たちの会員である「古家再生投資プランナー®︎」たちは、この手法で全国の空き家を再生し、安定した収益を上げています。このモデルのポイントは、初期投資を抑えることで、投資回収期間を短縮し、リスクを低減できる点にあります。
これらの収益化事例からわかるのは、ただ漠然と活用するのではなく、明確な事業計画と戦略(ターゲット、コンセプト、収支計画)を持つことが、実際に利益を生み出すためには不可欠であるということです。
空き家問題を解決するための制度
個人での活用努力だけでなく、国や自治体が設けている制度を上手く利用することも、空き家問題を解決する上で非常に重要です。ここでは、代表的な制度である「空き家バンク」と、その他の支援制度について解説します。
マッチングの鍵!空き家バンクを上手に活用するには?
「空き家を売りたい・貸したい人」と「空き家を買いたい・借りたい人」を、自治体が仲介役となってつなぐ仕組み、それが「空き家バンク」です。
●空き家バンクの概要
多くの市区町村が、公式ウェブサイトなどで空き家バンクのページを運営しています。所有者が物件情報を登録すると、その情報がサイト上に公開され、利用希望者が閲覧・問い合わせできるという仕組みです。自治体が運営しているため、安心して利用できるのが大きなメリットです。相続した実家など、どう扱ってよいか分からない物件の最初の相談先として非常に有効です。
●具体的な利用方法
【空き家を登録したい(売りたい・貸したい)場合】
1. 空き家のある市区町村の担当窓口(企画課、まちづくり課など)に相談します。
2. 申込書や物件の概要書などの必要書類を提出します。
3. 自治体の担当者や提携している宅建業者が、物件の現地調査を行います。
4. 調査後、問題がなければ空き家バンクのサイトに物件情報が掲載されます。
5. 利用希望者から問い合わせがあれば、自治体を通じて連絡が来ます。
【空き家を利用したい(買いたい・借りたい)場合】
1. 興味のある地域の空き家バンクのサイトを検索し、物件を探します。
2. 気になる物件があれば、サイトの案内に従って問い合わせをします。
3. 自治体の担当者から連絡があり、物件見学の日程などを調整します。
空き家バンクは、特に移住希望者にとって地域の物件を探す重要なツールとなっており、都市部から地方への人の流れを活かし、空き家を再生させる大きな期待が寄せられています。
●成功事例の紹介
千葉県のある町では、空き家バンクに登録された古民家を、都市部から移住してきた若い夫婦が購入。DIYでカフェにリノベーションし、今では地域の人気スポットになっています。これは、空き家バンクがきっかけで、所有者の「手放したい」という悩みと、移住者の「田舎で暮らしたい」という夢が見事にマッチングし、新たな価値が生まれた好事例です。
自治体も応援!地域の取り組みと支援制度を知ろう
空き家バンク以外にも、各地域では空き家対策のために独自のユニークな取り組みや手厚い支援制度が用意されています。
●地域の具体的な取り組みを紹介
お試し移住制度(和歌山県など): 空き家を活用した短期滞在施設を整備し、本格的な移住の前に、その地域での暮らしを体験できる制度です。
専門家派遣制度(東京都など): 空き家の活用方法に悩む所有者の元へ、建築士や宅建士などの専門家を無料で派遣し、相談に乗ってくれる制度。
空き家パトロール: 地域のシルバー人材センターなどと連携し、定期的に空き家を見回り、状況を所有者に報告してくれるサービス。
これらの取り組みは、所有者の負担を軽減し、活用の第一歩を後押ししてくれます。
●支援制度の種類を列挙する
前述の補助金・助成金に加えて、以下のような支援制度もあります。
税制優遇措置: 特定の条件を満たすリフォーム(耐震、バリアフリー、省エネなど)を行った場合、所得税や固定資産税の控除が受けられる制度。
低利融資制度: 自治体が金融機関と提携し、空き家活用を目的としたリフォームローンなどを通常よりも低い金利で提供する制度。
空き家活用モデル事業プランの募集: 地域活性化につながるユニークな空き家活用プランを公募し、優れた提案には事業化のための支援金が交付される制度。
全国の自治体が、子育て支援や景観保全といった地域の課題と結びつけながら、様々な角度から空き家対策のサポートを行っています。自分の空き家がある地域の環境や制度を詳しく調べ、最適なプランを立てることが重要です。
まとめ:空き家の活用方法を考える
これまで、空き家の現状から具体的な活用方法、注意点、支援制度まで、多岐にわたる情報をお伝えしてきました。最後に、これらの情報を踏まえ、あなた自身がどう行動していくべきかを考えていきましょう。
あなたに最適な活用方法は?自分に合った方法の見つけ方
空き家の活用方法に、唯一の正解はありません。大切なのは、物件の状況、地域のニーズ、そしてあなた自身の状況を総合的に考慮し、最も自分に合った、無理なく続けられる方法を見つけることです。
●地域のニーズを調査する
繰り返しになりますが、これがスタート地点です。あなたの空き家は、学生街にありますか?観光地にありますか?それとも静かな住宅街ですか?地域の人々が何を求めているかを理解することが、活用の方向性を決める最大のヒントになります。
●自身の資金や時間を考慮する
どれくらいの初期投資ができますか?管理にどれくらいの時間を割けますか?DIYは得意ですか?副業として手堅く収入を得たいのか、それとも本格的な事業として取り組みたいのか。自分自身のライフプランやスキル、かけられるリソースを正直に見つめ直し、身の丈に合った計画を立てることが、成功への近道です。
●アイデアをリストアップして優先順位をつける
この記事で紹介した方法以外にも、アトリエ、書斎、未来型農園ハウス、VR体験センター、テーマ型エスケープルームなど、アイデアは無限にあります。まずは思いつく活用方法をすべてリストアップしてみましょう。そして、「収益性」「実現可能性」「社会貢献度」「自分がワクワクするか」といった基準で、それぞれに点数をつけ、優先順位を決めてみてください。この作業を通じて、自分が本当にやりたいこと、やるべきことが明確になってくるはずです。
悩みや不安は一人で抱えない!専門家への相談を検討する
ここまで読んでも、「何から手をつけていいか分からない」「自分一人で判断するのは不安」と感じる方も多いでしょう。そんな時は、決して一人で悩まず、専門家の力を借りることを強くお勧めします。
●信頼できる専門家を探す
空き家活用に関する専門家には、不動産会社、建築士、工務店、行政書士など、様々な立場の人がいます。それぞれの専門分野が異なるため、自分の悩みに合わせて相談相手を選ぶことが重要です。
そして、その中でも特におすすめしたいのが、私たち(一社)全国古家再生推進協議会が認定する「古家再生投資プランナー®︎」です。
●古家再生投資プランナー®︎とは?
「古家再生投資プランナー」は、空き家や古家を活用した不動産投資、いわゆる「古家再生投資」のプロフェッショナルです。古家再生投資プランナー認定オンライン講座を通じて、物件の選定方法、適切なリフォームの見積もり、賃貸経営のノウハウ、資金調達の方法まで、空き家活用に必要な知識を体系的に学んだ専門家です。
この資格を取得すると、私たちが主催する物件見学ツアーへの優先参加権や、紹介された優良物件への買付け権限など、実践的なメリットも得られます。
●相談後のアクションプランを考える
専門家に相談する際は、事前に自分の空き家の情報(場所、広さ、築年数など)や、どのような活用をしたいかの希望、予算などを整理しておくと、話がスムーズに進みます。
専門家からのアドバイスを受けたら、それを基に具体的なアクションプラン(行動計画)を立てましょう。「まずは自治体の補助金制度を調べる」「次は3社のリフォーム会社から見積もりを取る」といったように、やるべきことを具体化し、一つずつ実行していくことが、空き家という悩みを解決する着実な一歩となります。
●最後に…
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
空き家問題は、もはや日本が避けては通れない大きな課題です。しかし、この記事を通して、空き家が決して厄介なだけの「負債」ではなく、アイデアと行動次第で、収益を生み、地域を豊かにする無限の可能性を秘めた「資産」になり得ることを感じていただけたのではないでしょうか。
大切なのは、現状を嘆くのではなく、「自分ならこの空き家をどう活かせるだろう?」と、前向きな視点で考えることです。そして、小さな一歩で構いません、今日から行動を始めてみてください。
もしあなたが、空き家問題の解決に主体的に関わりたい、専門的な知識を身につけて、自らの手で資産形成と社会貢献を両立させたいと本気で考えるなら、ぜひ「古家再生投資プランナー®︎」の道を検討してみてください。
全国で1万人を超える仲間たちが、あなたと同じ志を持って、日本の空き家を次々と価値ある資産へと再生させています。あなたもその一員となり、私たちと一緒に、日本の未来を明るく変えていきませんか。
あなたの挑戦を、心から応援しています。
POST: 2025.07.27