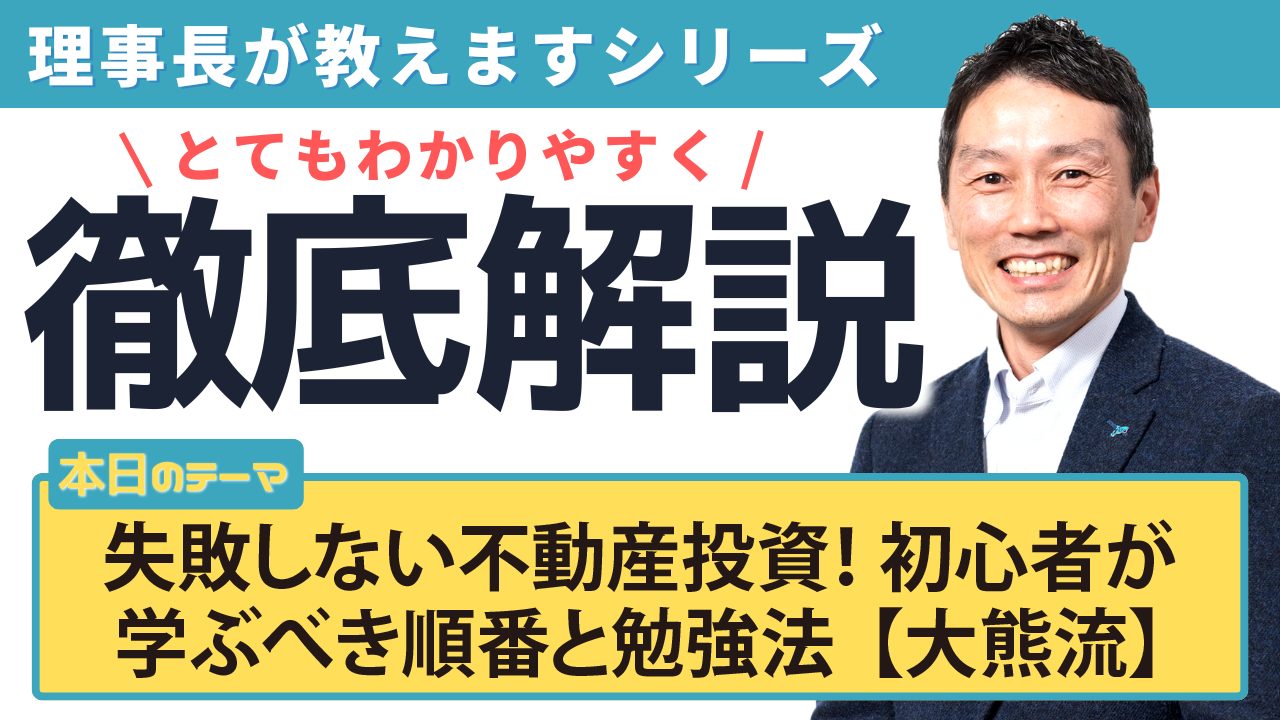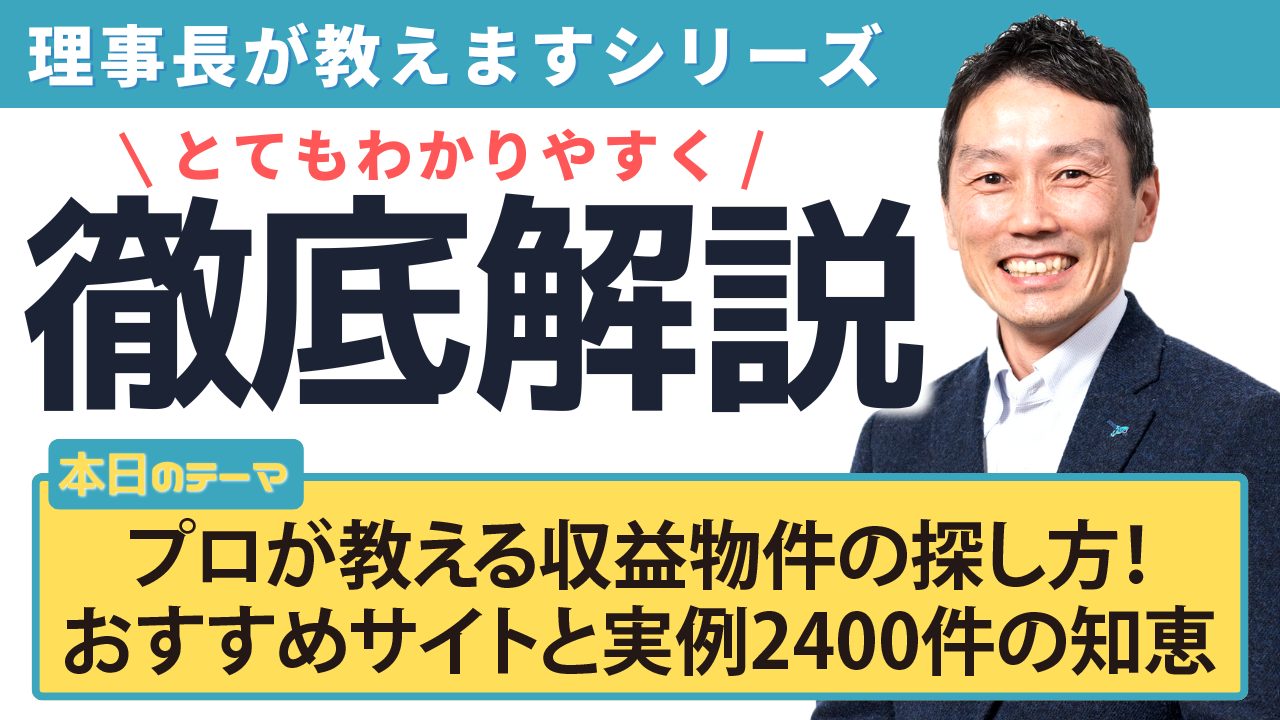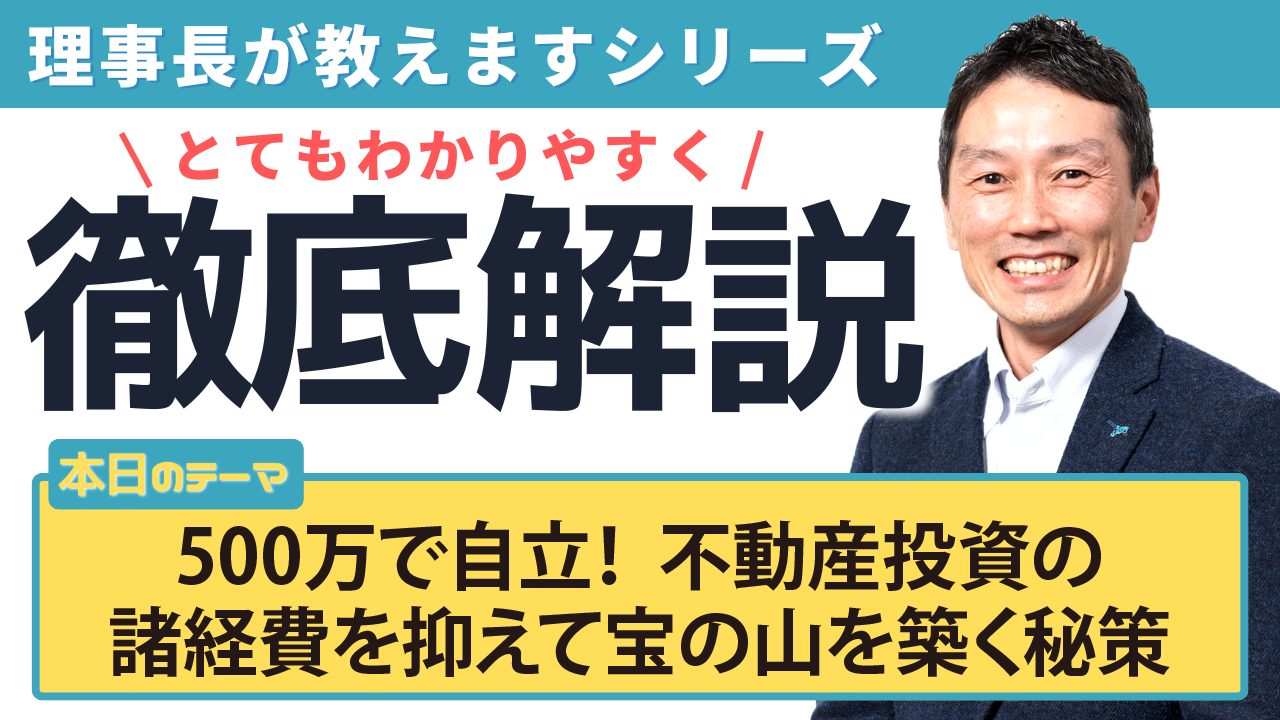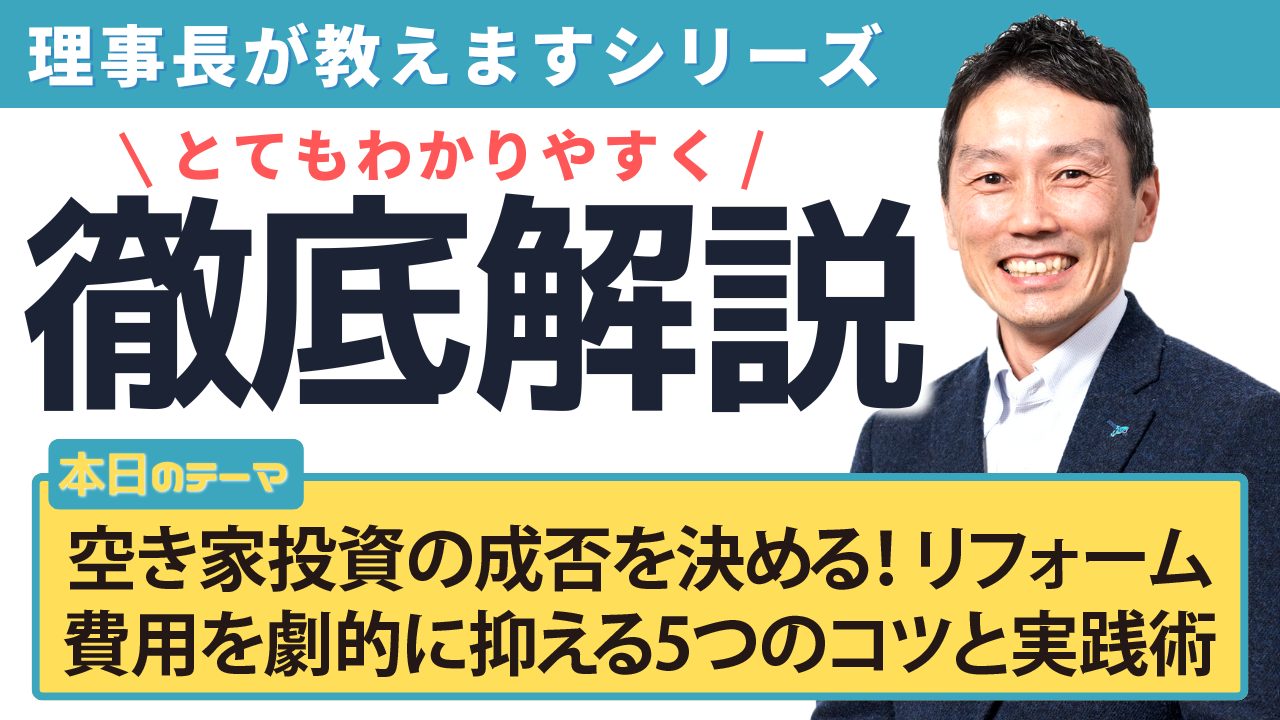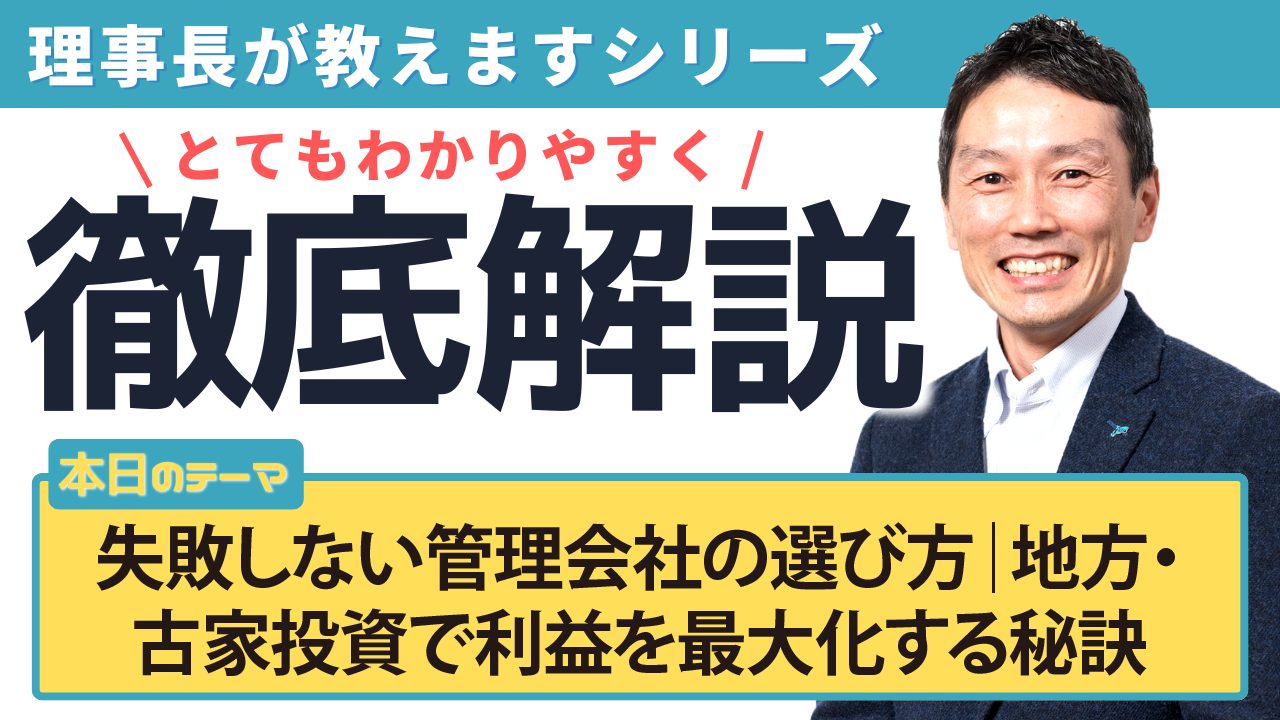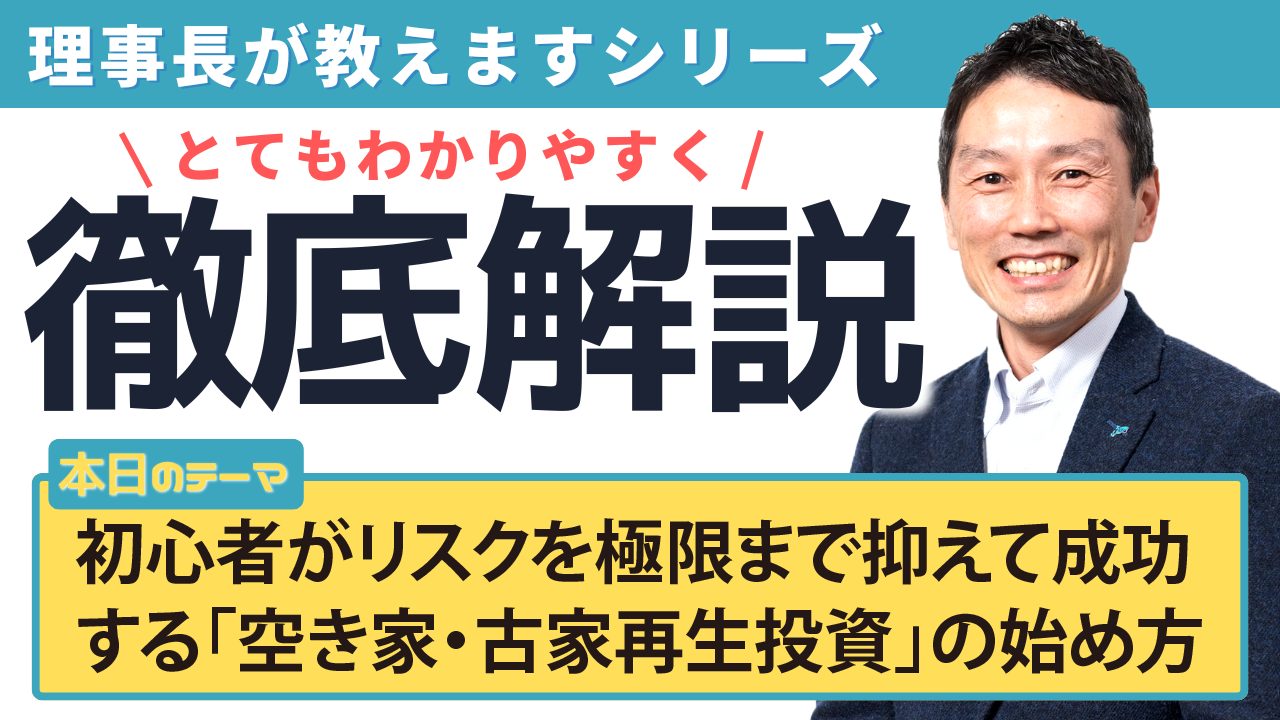
(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
不動産投資に興味はあるけれど、心の中では「大金が必要なのでは?」「失敗して借金を抱えたらどうしよう」と、一歩踏み出すことをためらっていませんか?その不安、よく分かります。なぜなら、私自身が小さな町工場の経営者として、かつては不動産投資に対して「怖いもの」「自分には縁がないもの」という固定概念を持っていたからです 。
しかし、私たち全国古家再生推進協議会は、累計2,467棟の再生実績と会員20,280名のコミュニティ(2025年10月20日時点)で培った、机上の空論ではない、誰でも再現できる低リスクの投資法を確立しました。それが「空き家・古家再生投資」です。
この記事を最後までお読みいただければ、あなたが抱える不動産投資への根拠なき恐怖は解消され、少額資金で始める古家再生投資の具体的な5つの実践ステップが分かります。理事長としての責任と、実践者としての経験に基づいた、最も堅実で社会貢献性の高い投資術を、包み隠さずお伝えします。さあ、一緒に「怖い」を「ワクワク」に変える旅を始めましょう。
目次
なぜ初心者が「不動産投資は怖い」と感じるのか?その正体と古家再生投資が持つ優位性
不動産投資の初心者が抱える「怖い」という感情は、高額な取引と情報の非対称性から生まれています。その不安の正体を明らかにし、なぜ「空き家・古家再生投資」がその恐怖を打ち消す最適解となるのかを、私の経験を交えてお話ししましょう。
初心者が抱く3大恐怖心(高額な借金・空室リスク・売却難)の正体
一般的な不動産投資(新築アパートや区分マンション)を検討する際、初心者は主に以下の3つの恐怖に直面します。
高額な借金(ローン): 数千万円、時には億単位のローンを組む必要があるため、「もし返済できなくなったら」という重圧がのしかかります。特に日本の不動産は新築依存の体質が強いため、高額な新築物件に手を出すことへのリスクは無視できません 。
空室リスク: せっかく高いローンを組んでも、入居者が決まらなければ家賃収入がなく、自分の給料からローンを補填し続けなければなりません 。特に人口減少社会においては、都市部であっても競合の多いエリアでは空室が増えるリスクがあります 。
売却難(流動性の低さ): 「いつでも売れる」と思いがちですが、不動産は株のようにすぐに換金できません 。特に地方の物件や、収益性の低い物件は、いざ売ろうと思っても買い手がつかず、「負動産」と化してしまう可能性があります。
新築・中古ワンルームとの決定的な違い—古家再生投資が「リスクを極限まで抑えられる」理由
これらの恐怖を、古家再生投資は根本から解消します。その秘密は、一般的な不動産投資とは真逆のロジックにあるからです。
| 特徴 | 一般的な投資(アパマン/新築) | 古家再生投資(戸建賃貸) |
| 購入価格 | 数千万円〜数億円 | 数十万〜数百万円(低額) |
| ローン | 必須。多額の借金 | 現金購入が可能。借金なしも可能 |
| 物件価値 | 新築時は高いが、時間と共に急落 | 築古のため既に低い。これ以上下がりにくい |
| 利回り | 4%前後が多い | 12%〜20%以上も可能 |
| 競合 | 多い。新築との競争に晒される | 少ない(戸建賃貸自体が希少) |
古家再生投資は、物件価格が安いため、まず多額の借金をする必要がないという点で、初心者が抱く最大の恐怖を回避できます 。そして、建物の価値はすでに低い(築40年で価値はほとんどない )ため、これ以上価値が大きく下がるリスクが極めて低いのです。
さらに、投資効率を測る利回りが12%〜15%程度が適切とされており 、新築アパートの3〜4%とは比べ物にならないほど高い収益性を持っています。
著書から学ぶ:私が古家投資にたどり着くまでの失敗と学び
実は、私自身も最初から順風満帆だったわけではありません。東大阪の小さな町工場を経営していた私は、下請けからの脱却と会社の安定を求めて、最初にマンションの不動産投資を試みました 。
しかし、結果は失敗です。マンション投資は、物件調査、長期の収支シミュレーション、資金調達、入室対策など、専門的なノウハウを吸収するのに資金以上に時間がかかり、本業と並行して行うにはあまりにも甘くありませんでした 。
この失敗から、私は「誰でもできる」「少額で始められる」「本業と両立できる」投資法を模索し、たどり着いたのが空き家・古家再生投資でした。この経験から学んだのは、「知識だけで投資しようとするから不安になる」ということ 。そして、不動産投資の成功者は「知識30%、経験70%」だということです 。机上の空論ではなく、実際に現場で経験を積み、自信を持つことが、恐怖を克服する唯一の方法なのです。
古家再生投資の「4方よしモデル」こそが究極の低リスク戦略である
古家再生投資が低リスクである最大の根拠は、私たちの活動の核である「4方よしモデル」にあります。これは、投資家だけが儲かる「一方向」のビジネスではなく、関わるすべての人々が恩恵を受ける持続可能なビジネスモデルです。
古家再生投資の核となる「4方よしモデル」の徹底解説
私たちが提唱する「4方よしモデル」は、以下の4つの要素がすべてWIN-WINとなることを目指しています 。
買主よし(投資家): 低額で物件を取得し、高利回り(12%〜15%)で運用することで、安定した家賃収入を得ることができます 。多額の借金がないため、心理的なリスクが低く、無理なく資産形成が可能です。
借主よし(入居者): 古家を再生し、地域の平均より安い家賃で、広くて快適な戸建の住環境を提供できます 。特に、アパート・マンションでは難しいペット可の物件も提供しやすく、ファミリー層やペットオーナーのニーズに応えられます 。
地域よし(地域社会): 放置され、治安や景観を悪化させる空き家を減らし、新しい住民を呼び込むことで、地域の活性化に貢献します 。
売主よし(物件所有者): 「売りたくても売れない」と処分に困っていた空き家や相続物件を、再生して活用することで、売主の悩みや負担を解消します 。
このモデルでは、投資家が無理に利回りや利益を貪(むさぼ)ることが善だとは考えていません 。すべての人が喜び、継続できる関係こそが、長期的な成功の秘訣なのです 。
このモデルが空室リスクと賃料下落リスクを回避するメカニズム
「4方よしモデル」は、前述の初心者の恐怖心を克服する、具体的なメカニズムとして機能します。
空室リスクの回避: 再生された戸建賃貸は、アパートやマンションに比べて数が少なく希少価値が高いため、需要に対して供給が追いついていないのが現状です 。特に「広さ」「庭付き」「ペット可」といった戸建ならではの強みは、ファミリー層や住宅確保要配慮者(高齢者、低額所得者、子育て世帯など )に強く求められており、競合が少ない分、入居が決まりやすいのです 。私たちの実績でも、100%の確率で入居者が付いていると断言できます 。
賃料下落リスクの回避: 古家をリフォームして相場より少し安めの家賃で提供することで、入居者に長く住んでもらえる可能性が高まります 。さらに、生活保護受給者向けの住宅扶助(家賃補助)の制度が、家賃の極端な下げ止まりを防ぐ要因にもなっています 。
協議会の実績(2,467棟)から見る、「満室経営」を実現している会員の共通点
私たち協議会の会員が満室経営を実現している共通点は、まさに「4方よし」を実践していることにあります。
入居者目線でのリフォーム: 自分の感覚で過剰なリフォームをするのではなく、「その家賃帯で探している入居者が本当に求めるもの」を見極めています 。例えば、和室をあえて残し、古家の良さを生かしたモダンなデザインにしたり 、ペット用のキャットウォークを設置したりするなど、差別化を図っています 。
物件への愛着と地域への貢献意識: ただの「投資商品」ではなく、再生した物件を「自分の家」のように大切にし 、「空き家をなくす」という社会貢献の意識を持っています 。ご近所への挨拶や配慮を欠かさないため、地域からの信頼も得て、結果的に良い入居者を紹介してもらえることも少なくありません 。
【実践編】知識ゼロ・資金不安な初心者が古家再生投資を始める5つのステップ
知識ゼロ、資金不安な初心者でも、正しいステップを踏めば必ず成功できます。ここでは、私たちが実践指導している具体的な5つのステップを解説します。
STEP 1:まずは知識武装より「行動」—物件見学ツアーの重要性
「不動産投資の成功者は知識30%、経験70%」とお話ししました 。まずは机上の知識を詰め込むより、物件をリアルに体験することが重要です 。
私たち協議会が開催している「空き家・古家物件見学ツアー」は、まさにこの「経験」を積むための仕組みです。初めて参加する方は不安を抱えていますが、先輩大家さんの話を聞いたり、ボロボロのビフォー物件と再生されたアフター物件を目の当たりにすることで、「誰にでもできる」と実感し、90%以上の不安が解消されます 。
物件見学ツアーの価値:
恐怖の解消: 実際のボロ家を見て「本当に直るのか?」という不安が、完成物件を見て「これなら住みたい」という確信に変わります 。
目利き力の養成: 再生士(リフォーム専門家)の解説を聞きながら、リフォームのポイントや概算工事費を現場で学ぶことができます 。
仲間づくり: 経験者や同じ初心者の仲間と出会い、情報交換や励まし合うことで、孤独な戦いにならず、購入への勇気が湧きます 。
STEP 2:物件探しの鉄則—「高値掴み」を避けるための家賃からの逆算思考
物件を探す際は、売主がつけた「販売価格」に惑わされてはいけません。大切なのは、「その物件でどれくらいの儲けが出るのか」です 。
私たちが実践している鉄則は、家賃から逆算して「買付額」を算出することです 。
具体的な手順:
家賃相場の調査: インターネットや地元の不動産業者にヒアリングし、「リフォーム後の相場家賃」を正確に把握します 。この際、入居者の目線で「確実な家賃設定」を試算することが重要です 。
リフォーム費用(概算)の算出: 再生士などの専門家と一緒に現地へ行き、10〜15分程度で概算の工事額を算出します 。
希望利回りの設定: 関西では13〜15%、関東・名古屋では12〜14%が目安です 。再建築不可や駅から遠い物件など、リスクが高い場合は1〜2%高く設定し、収益でリスクを補います 。
買付額の決定: 上記の計算式で、販売価格ではなく、自分が買うべき「買付額」を決めます 。
STEP 3:最も重要!「再生コスト」を極限まで抑えるための業者選定とDIYの考え方
古家再生投資で利益を出す上で最も重要なのが、リフォーム費用、すなわち「再生コスト」のコントロールです 。
費用削減の鍵は「人件費」: リフォーム費用の大半は材料費ではなく人件費です 。通常の工務店は分業制で多くの職人が関わるため、人件費がかさみます 。費用を抑えるには、1人で複数の作業ができる多能工の職人に依頼するのがコツです 。
工事業者の選定基準: 通常の工務店は賃貸物件のリフォーム経験が少ないため、大家さんに収益を提供することを目的とした専門家が必要です 。私たちが認定する古家再生士は、「家賃相場」「客付けの仕方」「差別化リフォーム」の3つのスキルを持ち 、相場家賃に合った予算内で、競合物件より良いリフォームをしてくれます 。工事業者に「この辺りの家賃相場を知っていますか?」と聞いて、答えられるかどうかで信頼性を判断できます 。
DIYの罠: DIYはコストを抑える手法として流行していますが、初心者が手を出すと、仕上がりの質の低さや作業の遅れにより、トータルで見たときにコストが高くつく、という失敗例を多く見てきました 。賃貸住宅は「家賃を払ってくれる入居者が納得できるクオリティー」が必要であり 、質を維持できないなら、プロに任せて入居付けを急いだほうが賢明です 。
STEP 4:出口戦略を意識したリフォーム設計—「誰に貸すか」を明確にするペルソナ設定
リフォームは、あなたの趣味や自己満足で行うものではありません 。その地域の「誰に住んでもらいたいか」という明確なペルソナ設定に基づいて、費用対効果を最大化するデザインを施します 。
LDK化の検討: 戸建賃貸の主なターゲットはファミリー層です 。古い古家は台所と居間が分かれていることが多いため、壁を取り除いて広々としたLDKにすることで、物件の魅力を高めます 。
差別化のポイント: 競合が少ない戸建賃貸であっても、入居者に選ばれるためには**「インパクト」**が必要です 。
和室の活用: あえて和室を残し、塗装や照明でモダンな和のテイストを演出します 。
水回り: 毎日使うトイレ、洗面台、風呂は入居者が特に気にする部分です 。ここには予算をかけても、シャンプードレッサーやウォシュレット付きトイレを導入するなど、現代のニーズに合わせることで入居動機につながります 。
ペット可: 駐車場と並び、戸建の大きな強みとなるのがペット可です 。猫用のキャットウォークを設置するなど、ペットオーナーのニーズに応えることで、家賃アップにもつながる差別化になります 。
STEP 5:賃貸付けの極意—古家でも入居者に選ばれるための仕掛け
リフォームが完了しても、入居者が決まらなければ収益はゼロです。最後の仕上げは、賃貸付けの極意を知ることです。
マイソク(物件資料)へのこだわり: 賃貸仲介業者への販促チラシであるマイソクは、あなたの物件の顔です 。古家再生士は、再生によって一線を画した内装デザインの「印象に残る写真」をマイソクに載せることで、営業マンに「この物件ならお客さんに勧めたい」と思わせる強烈なインパクトを与えます 。
業者回りで情報を仕入れる: 管理会社や客付け業者に任せきりにせず、自ら業者回りをすることで、「周辺地域の相場」「競合の状況」「ターゲット層のニーズ」といった有益な生きた情報を仕入れることができます 。これにより、戦略的に家賃設定や設備条件を見直すことが可能になります。
入居者への柔軟な対応と「4方よし」の精神: 私たちの会員には、猫12匹を飼いたいという家族に対し、家賃を1万円増額することで入居を決定した事例があります 。これは、「お困りの方に応える」という商売の原点と、「退去時の修繕費」を家賃増額分でカバーするというリスクヘッジを両立させた「4方よし」の精神の現れです 。入居者満足こそが、長期的な大家業の成功の鍵となります 。
古家再生投資のよくある失敗事例とそれを回避するための「大熊式チェックリスト」
正直に言います。古家再生投資は低リスクですが、失敗がないわけではありません。しかし、失敗から学ぶことこそが、最も価値のある経験です 。私や会員の事例から、初心者が陥りがちな失敗を共有し、その回避策をお伝えします。
失敗事例1:エリア選定の誤り—賃貸需要のない地域に手を出したケース
失敗の教訓: 「安すぎる物件」に飛びつき、賃貸需要が全くない過疎地域に手を出してしまうケースです。物件価格が100万円以下でも、入居者がいなければ収益はゼロで、管理コストだけがかかる負動産になります 。
回避策: 物件価格ではなく、「家賃相場」と「賃貸需要の有無」を最優先に考えます 。地元の不動産業者にヒアリングしたり、協議会のネットワークで実績を確認したりして、「その地域に賃貸を求めている層がいるか」を必ず確認してください。たとえ地方でも、工業団地、大学、病院の周辺など、人が動く場所には必ず需要があります 。
失敗事例2:リフォームの過剰投資—家賃設定を無視した「自己満足リフォーム」の罠
失敗の教訓: 「入居者のため」と思い込み、家賃相場に見合わない豪華な設備やリフォームに予算をかけすぎてしまうケースです 。例えば、5万円の家賃帯で探している入居者に、10万円の物件に見合うクオリティーを求めても、採算が合わず、利回りの低いボランティア物件になってしまいます 。
回避策: リフォーム前に、必ず家賃からの逆算シミュレーションを行い 、工事業者にも「この家賃相場(例:5万円)で、競合に勝てるリフォームを、予算200万円で実現する」という明確な指示を出します 。工事業者は工事額を上げようとしがちなので、大家自身がしっかりと予算管理を行う必要があります 。
失敗事例3:融資の勘違い—古家投資における融資の適切な活用法と注意点
失敗の教訓: 築古の古家は、税務上の法定耐用年数(木造22年)を超えていることが多いため、民間金融機関の融資対象から外れることが多いという事実を知らずに、融資を前提として購入を進めてしまうケースです 。
回避策: 私の経験から、「できれば1軒目は現金で購入し、2軒目以降は融資を検討する」ことを推奨します 。1軒目を現金で買えば、2軒目以降で万一空室になっても、1軒目の家賃で補填できるため、リスクを極限まで抑えられます 。融資を利用する場合も、日本政策金融公庫や信用金庫など、築古物件に比較的柔軟な金融機関を検討します 。
失敗を未然に防ぐ!私が協議会で徹底している「物件調査7つのチェックリスト」
これらの失敗を回避するため、私たちが物件購入の際に現場でチェックする項目を共有します 。
電気容量: 古家は容量が足りない場合が多く、入居後すぐにヒューズが飛ぶクレームを防ぐため、リフォーム時に電気のリフォームも検討します 。
水回り(特に給排水): 1階部分の床をめくるリフォームをする際、給排水管の老朽化をチェックし、必要に応じて補修を行います 。
シロアリ被害: 床が緩んでいる物件は、腐食やシロアリが原因の可能性が高く、床をめくって土台・柱の状態を確認し、シロアリ駆除剤の散布を行います 。
雨漏りの形跡(ベランダ・屋根): 戸建はベランダからの雨漏りが多いので、防水塗装が必要です。雨漏りの形跡をチェックします 。
基礎の傾き: 建物が大きく傾いている場合、多額の費用がかかるため、床を造作でレベル調整できる範囲内かどうかを判断します 。
周辺家賃相場と競合: 賃貸業者へのヒアリングやネット調査で、周辺の家賃相場と競合物件の状況を把握します 。
賃貸市場の慣習: 地元の不動産業者と話をし、その地域の慣習(ペット可の需要、駐車場の重要性など)を把握します 。
【組織の力】初心者が一人で悩まないために—古家再生投資プランナーという選択肢
空き家・古家再生投資は、孤独な戦いではありません。むしろ、知識・経験・人脈というチームの力が、成功を大きく左右します。
古家再生投資は孤独な戦いではない—協議会という「全国最大級のコミュニティ」の存在意義
私たち全国古家再生推進協議会(全古協)は、投資家が一人で悩むことなく、不動産投資の知識と経験を積める環境を提供しています 。
仲間と情報交換: 物件見学ツアーの懇親会では、税金や融資、過去のトラブル事例など、リアルな話が飛び交います 。同じ価値観を持った仲間と交流することで、不安が解消され、勇気が湧いてきます 。
情報の集約と共有: 全国各地の古家再生士が、日々物件情報や再生ノウハウ、地域の慣習などの生きた情報を集め、協議会全体で共有しています 。これは、個人が独力で集められる情報量をはるかに超える「組織の力」です。
誰でも再現できるノウハウを体系化—古家再生投資プランナー認定講座の価値
不動産投資の成功に必要な知識と経験を、誰でも効率的に身につけられるよう、私たちは「古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座」を提供しています 。
体系的な知識: 不動産業界の基礎から、物件の見方、家賃設定、リフォーム、客付け、税務、融資まで、大家業に必要なすべての知識を体系的に学べます 。
現場で使えるノウハウ: 理論だけでなく、「家賃からの逆算思考」「再生士との連携」「マイソクの作り方」など、現場で即座に使える実践的なノウハウに重点を置いています 。
認定資格: 講座を受講し、試験に合格することで「古家再生投資プランナー®️」として認定されます 。これは、あなたの知識と経験の証明となり、不動産業者や金融機関、そして何よりあなた自身の自信につながります 。
会員の声から学ぶ:初心者から卒業し、プロの大家に成長した会員の成功ストーリー
知識ゼロから始めた会員が、私たちのコミュニティとノウハウを活用し、着実に資産を増やしている事例は枚挙に暇がありません。
サラリーマン大家の成功: Tさん(30代半ば)は、最初は不安を抱えながらも物件見学ツアーに4回参加し、合計30軒の事例を見ることで自信をつけ、5回目で物件を購入 。資金500万円で2棟を取得し、月額約12万円の家賃収入を得ています 。
経営者から大家へ: Sさん(中小零細企業の経営者)は、会社の売上安定化のため古家投資を開始。「これはいける!」と確信し、12棟を購入。家賃収入は年間約2,000万円となり、本業の安定化にもつながっています 。
古家再生投資プランナーになることで得られる3つのメリット(資格、人脈、実践ノウハウ)
古家再生投資プランナー®️になることは、単なる資格取得に留まりません。
資格(知識の証明): 体系的な知識を身につけ、不動産投資における「知識30%」の部分を最短でクリアできます。
人脈(組織の力): 全国20,280名の会員と、専門知識を持つ古家再生士という最強のチームを得られます 。物件の情報、リフォームの相談、入居者付けの悩みなど、一人で抱える必要はありません。
実践ノウハウ(経験の蓄積): 物件見学ツアーやオンライン講座を通じて、成功と失敗の事例を学び、他人の経験を自分のノウハウとして蓄積できます 。
まとめ・結論
不動産投資への「怖い」という感情は、高額な取引や情報不足から生まれる当然の不安です。しかし、空き家・古家再生投資は、物件価格を極限まで抑え、利回りの高い戸建賃貸という希少性の高い市場を狙うことで、このリスクと恐怖を最小限に抑えることができます。
【記事の要点】
恐怖の正体は「高額な借金」:古家再生投資は低額購入が基本のため、借金リスクが極めて低く、初心者でも始めやすい投資です。
成功の鍵は「4方よしモデル」:投資家、入居者、地域、売主すべてが喜ぶこのモデルこそが、空室や賃料下落といったリスクを回避し、長期的な安定経営を実現します。
実践の鉄則は「家賃からの逆算」:売値ではなく、リフォーム後の相場家賃から逆算して購入額を決定することで、「高値掴み」を回避できます。
コスト削減の極意は「専門家との連携」:家賃相場を理解した古家再生士と連携し、自己満足ではない費用対効果の高いリフォームを行うことが、高利回りを維持する鍵です。
成功の秘訣は「行動力と仲間」:「知識30%:経験70%」の法則に基づき、まずは一歩踏み出し、古家再生投資プランナーというコミュニティで知識と経験(人脈)を積むことが、成功への最短距離です。
机上の空論で終わらせないでください。
もしあなたが将来の不安を解消し、社会に貢献しながら資産を築きたいと本気で考えているなら、この瞬間に一歩を踏み出す勇気が必要です。私たちの協議会は、あなたの最初の一歩から、その後の資産形成まで、組織の力と実績を持って全力でサポートします。
「いつかやろう」は、いつまで経っても来ません。
まずは、私たちの古家再生投資プランナー®️認定講座で、その「知識30%」の部分を固めましょう。そして、全国で開催している物件見学ツアーで、「経験70%」への最初の一歩を踏み出してください。
あなたの人生を変える転機は、もう目の前にあります。勇気を持って、一歩前へ。
(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之
POST: 2025.10.27