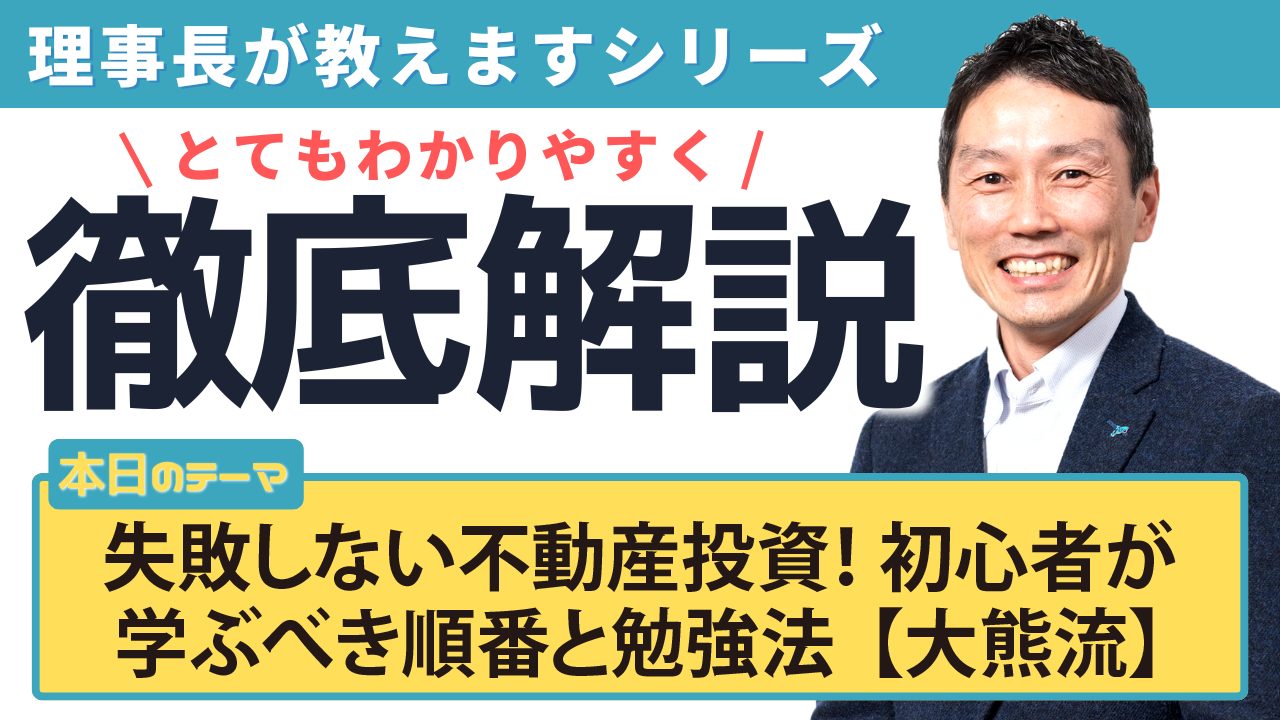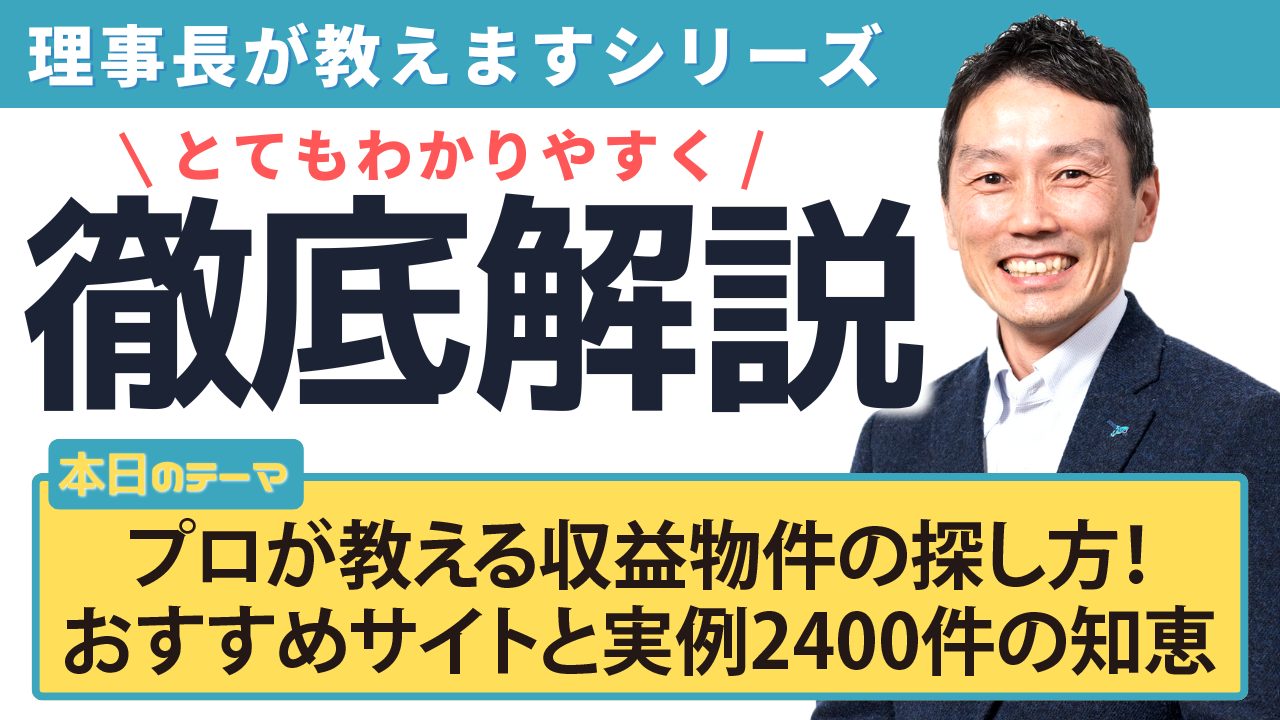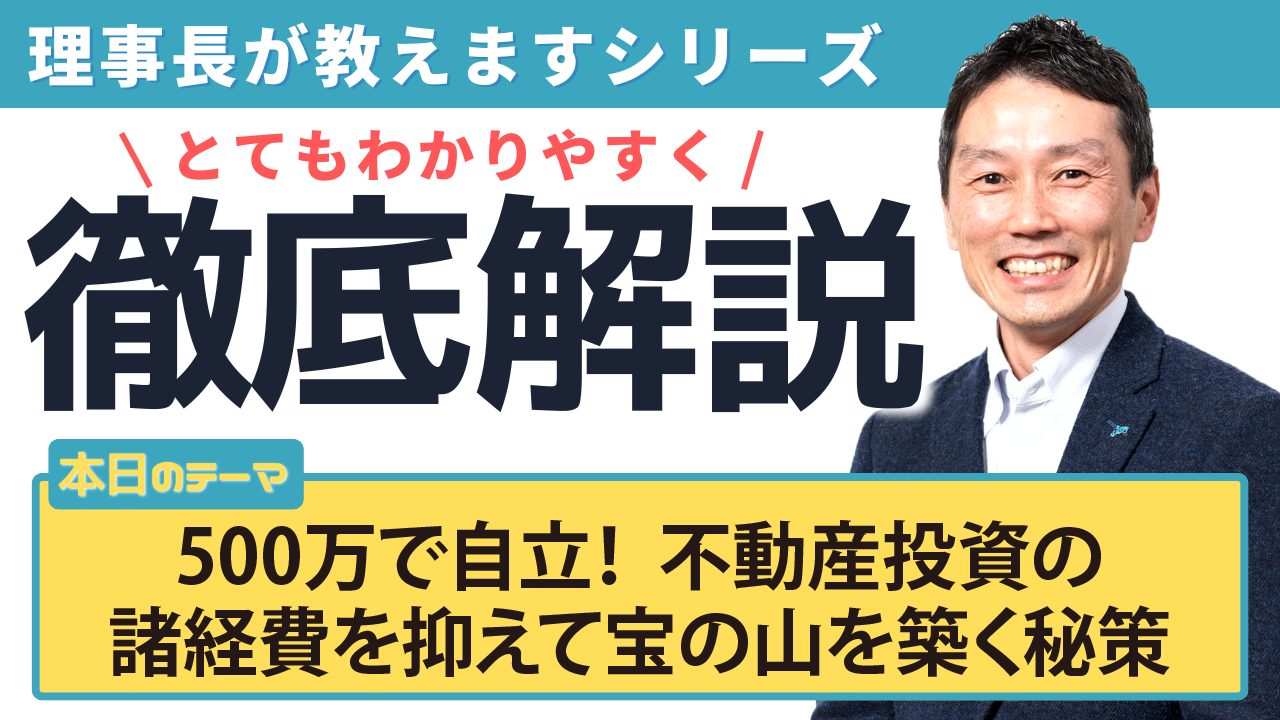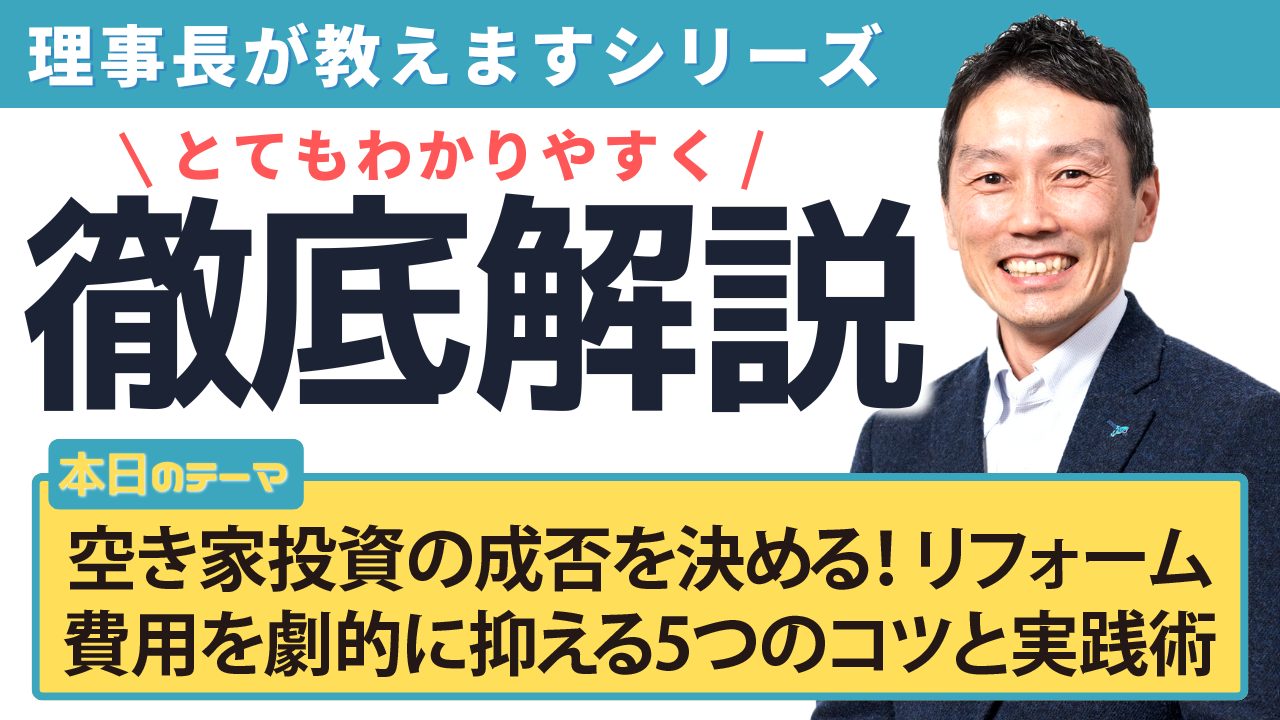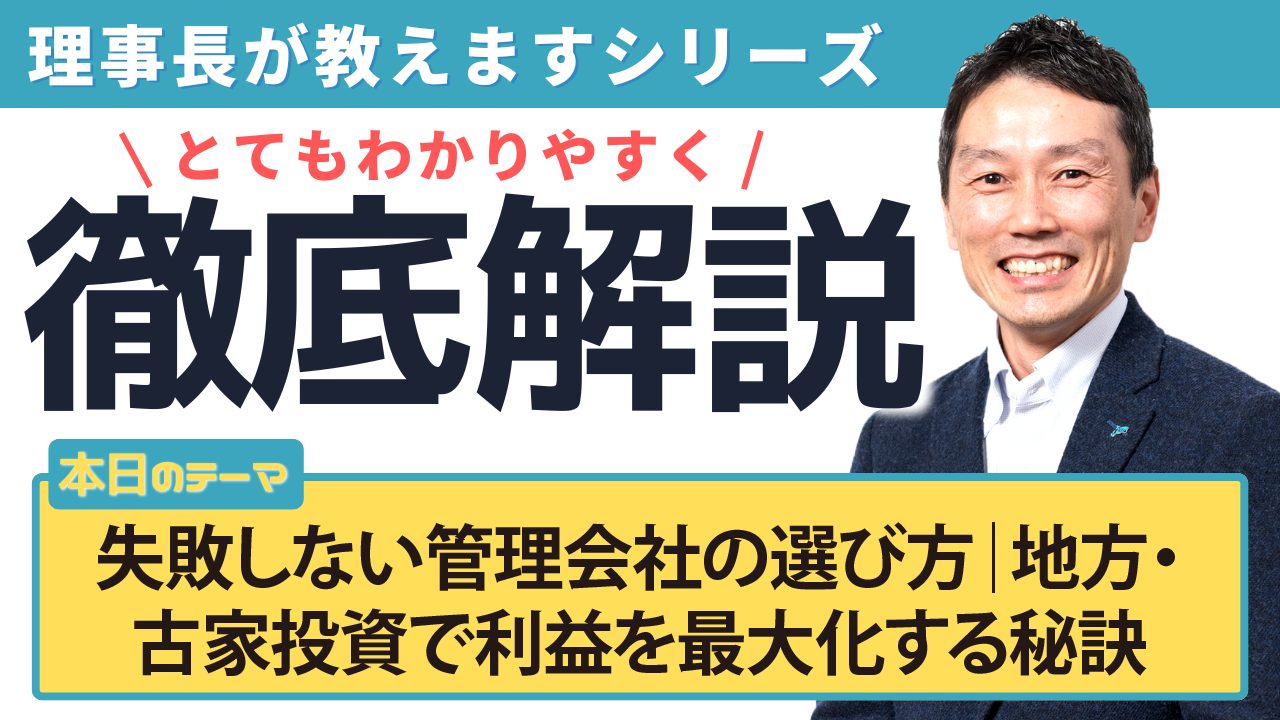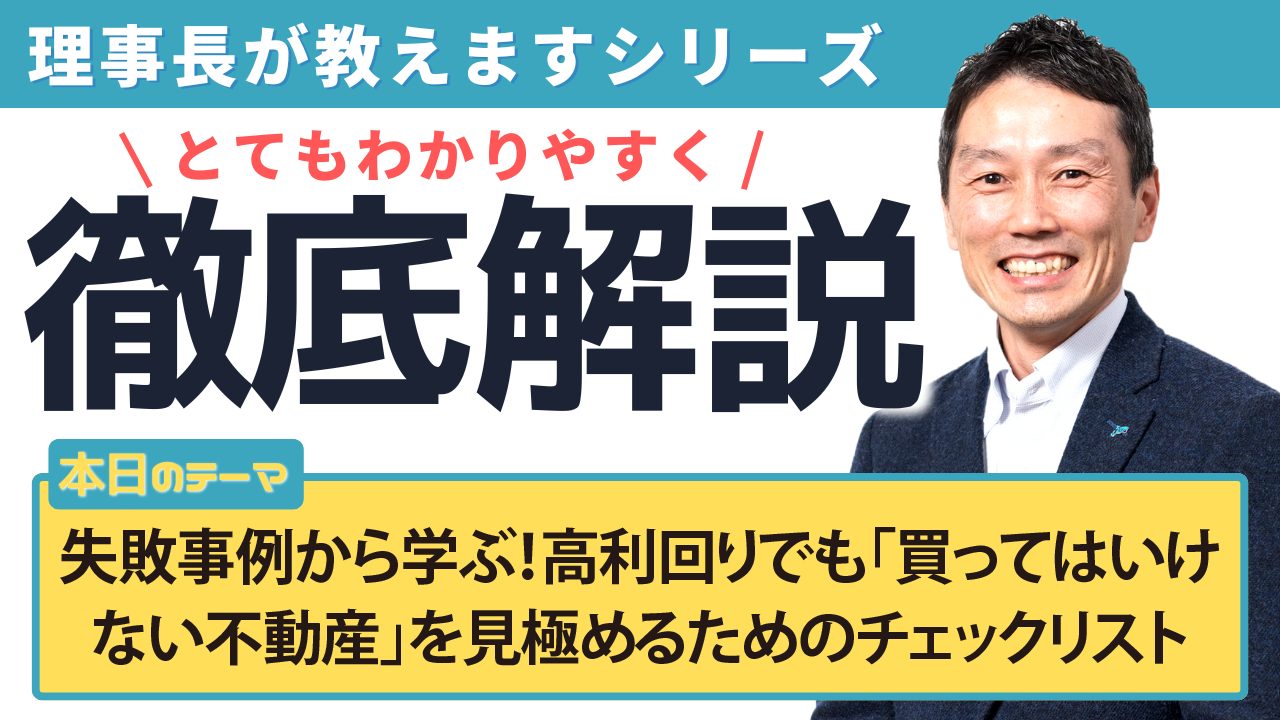
(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
不動産投資で失敗する人の共通点は、「高利回り」という甘い言葉に騙され、目先の数字しか見ていないことです。
特に古家再生投資は、物件価格が安い分、一見すると利回りが高く見えますが、その裏には「再生しても貸せない」「修繕コストで利益が吹っ飛ぶ」といった致命的なリスクが潜んでいます。投資で成功するために最も重要なことは、大きなリターンを追求することではなく、リスクを極限まで抑えることです。
私たち協議会では、これまで累計2,467棟以上の再生実績と、全国20,280名の会員ネットワークから、多くの成功事例だけでなく、失敗事例も分析してきました。机上の空論ではなく、実際の泥臭い現場で学び得た教訓こそが、あなたの成功への確かな道筋となります。
この記事を最後まで読めば、あなたが不動産投資で絶対につかまされてはいけない「買ってはいけない不動産」の具体的な特徴を理解し、そのリスクを未然に防ぐための古家再生士のチェックリストを手に入れることができます。
目次
なぜ高利回り物件ほど危険なのか?初心者が陥る「買ってはいけない不動産」の罠
あなたが物件を探すとき、何を最優先しますか?
「利回り20%!」、「現金で購入可能!」といったキャッチフレーズに心を惹かれるかもしれません。しかし、私の経験上、表面的な高利回りほど、裏に隠されたリスクが大きいのが不動産投資の世界の鉄則です。特に、物件価格が極端に安い古家の場合、この傾向は顕著です。
表面利回りだけでは見えない「古家の真のコスト」
不動産の利回りは、年間家賃収入を物件価格で割った「表面利回り」で語られることが多いですが、古家再生投資においてはこの数字はほとんど意味を成しません。なぜなら、古家は必ずと言っていいほど、購入後に想像以上の「真のコスト」がかかるからです。
この真のコストとは、修繕費、維持管理費、空室期間中の損失(空室リスク)、そして取得時・保有時にかかる税金や諸経費などが含まれます。
【古家再生投資で初心者が過小評価しがちなコスト】
目先の高利回りに釣られて、これらの「真のコスト」を軽視すると、数年後にはキャッシュフローが回らなくなり、最悪の場合は投資ではなく負の資産へと変わってしまいます。
失敗事例1:フルローン・高額融資に飛びつき、キャッシュフローが回らなくなったAさんのケース
私の著書『儲かる!空き家・古家不動産投資入門』の中でも警鐘を鳴らしていることですが、特に初心者は「融資がつくなら」と背伸びをしてしまいがちです。
ここで、実際に協議会メンバーの初期の失敗事例(仮名Aさんのケース)を紹介しましょう。
【Aさんの失敗物件データ】
物件所在地: 地方都市の郊外
購入価格: 50万円(極端に安い)
表面利回り: 25%を想定
融資: フルローンに近い高額融資を実行
実際の修繕費: 当初見積もり100万円 → 実際350万円(原因:床下の深刻なシロアリ被害と配管総入れ替えが必要だった)
結果: 実際の利回りは8%に低下。高額融資と相まって毎月の返済額がキャッシュフローを圧迫し、別の物件を買う余力が完全に失われました。
Aさんは、物件価格の安さから「利回り」と「レバレッジ」に目が眩み、現地調査の重要性を軽視しました。「50万円だから失敗してもいい」という考えが、結果的に自己資金を大きく超える損失に繋がってしまったのです。
私が常に会員に伝えているのは、「古家再生投資の成功は『利回り』ではなく『再現性』で決まる」ということです。再現性とは、誰がやっても同じ結果が出せる確かなノウハウのことです。この再現性を担保するのが、リスクを極限まで排除するための体系的な知識とチェック体制なのです。
古家再生投資の成功は「利回り」ではなく「再現性」で決まる
私たちが推奨する古家再生投資は、価格の安い古家を買い取り、費用対効果の高いリフォームで再生し、賃貸に出すというシンプルなモデルです。しかし、その成功は「利回り」ではなく、いかにリスクを排除し、健全なキャッシュフローを生み出し続けるかにかかっています。
この「再現性」を実現するために不可欠なのが、「4方よしモデル」の視点です。
高利回りだけを追求し、「借り手よし」「世間よし」を無視した物件は、結局は入居者がつかず、最終的に「貸し手(あなた)」が損をする、という形で跳ね返ってきます。投資の哲学として、この4方よしの視点を持つこと自体が、最大の「買ってはいけない不動産」を見極めるフィルターとなるのです。
古家再生士が警告!絶対に見送るべき「買ってはいけない不動産」の4大特徴
ここからは、古家再生推進協議会の理事長として、私が会員に断固として見送るように指導している「買ってはいけない不動産」の具体的な4つの特徴を解説します。これらの特徴を持つ物件は、再生ノウハウをもってしてもリスクが高すぎてカバーできないと判断するべきです。
特徴①:再建築不可物件・接道義務を満たさない物件の致命的なリスク
不動産投資において、「再建築不可」という言葉は、最も恐ろしいリスクの一つです。
再建築不可とは?
建築基準法上の道路(幅4m以上の道路など)に、敷地が2m以上接していない物件のことです。
『地方は宝の山! リスクを極限まで抑えて儲ける「空き家・古家」不動産投資』でも詳しく解説していますが、火災や地震などで建物が倒壊しても、そこに新しい建物を建てることができません。
これが致命的である理由は、金融機関の評価がゼロに等しくなるためです。古家を再生して賃貸経営をしている間は問題ありませんが、将来的に売却しようとしたとき、一般の買い手がつきにくく、価格交渉で非常に不利になります。最悪の場合、売却できず、負の資産として抱え続けることになります。
協議会の事例でも、再生ノウハウはあったものの、再建築不可の物件を「安いから」という理由で仕入れてしまい、数年後に売却する際に大幅な損失を出したケースがありました。
初心者は、「安くて再生すれば儲かる」という目先の利益に惑わされがちですが、将来の出口戦略が閉ざされている物件は、たとえ価格が安くても避けるべきです。
特徴②:特定エリア・地域の需要がゼロの「負の資産」予備軍
私は「地方は宝の山」だと常々発信していますが、これは「地方の物件なら何でも買っていい」という意味ではありません。地方の中でも、特定のエリアを選定する基準が極めて重要になります。
【買ってはいけない「需要ゼロ地域」のサイン】
インフラが極端に脆弱な地域: 上水道、下水道、ガスなどのインフラ整備がされておらず、再生に大きなコストがかかる、または入居者が生活に不便を感じる地域。
周辺に生活利便施設が全くない地域: スーパー、コンビニ、病院、学校などが極端に遠く、車がないと生活できない上に、周辺の人口減少が激しい地域。
特定の嫌悪施設(墓地、工場など)が至近距離にある地域: 入居者募集で不利になり、家賃を下げる必要が出てくるため、収益性が確保できません。
古家再生投資は、地域で「必要とされている家」を再生して提供することで成立します。需要がゼロの地域では、どんなに綺麗にリフォームしても入居者はつきません。これが、「古家再生は地域選定が命」と言い切る理由です。
特徴③:シロアリ被害や雨漏りなど「構造上の欠陥」が重篤な物件
古家は必ず劣化していますが、許容できる劣化と、手を出すべきではない重篤な欠陥があります。特に危険なのが、構造体の深刻なダメージです。
深刻なシロアリ被害: 柱、梁、土台などの構造材が食い荒らされている場合、交換費用が莫大になります。また、シロアリ駆除と防蟻工事も必須となり、コストが雪だるま式に増えます。
大規模な雨漏りによる躯体の腐食: 長期間放置された雨漏りは、屋根だけでなく、壁の内側や柱を腐食させています。これは建物の寿命を大幅に縮め、修繕費用が物件価格の数倍になることもあります。
これらの構造欠陥は、素人目には見分けにくいものですが、リフォームの見積もりを出した途端に判明し、再生予算を大きく上回る原因となります。私の経験から、修繕費用が物件購入価格の3倍以上になるような物件は、原則として手を出してはいけないラインだと判断しています。
特徴④:違法建築・未登記増築など「コンプライアンス」に問題がある物件
これもまた、将来の売却や融資の際に大きな障害となるリスクです。
違法建築:建築確認を取っていない増築部分がある、用途変更が違法に行われているなど。
未登記増築:増築した部分が登記簿に記載されていない。
これらの物件は、売却時に金融機関が融資を出し渋る原因になったり、行政指導の対象になったりする可能性があります。特に、増築部分を賃貸として使用しようとした際に、法的に問題があることが判明すると、その部分を取り壊す必要が出てくるなど、大きな損失に繋がります。
不動産投資は、長期にわたる事業です。目先の利益のために、法的なリスクを負う物件には絶対に手を出してはいけません。
買ってはいけない物件をチャンスに変える!古家再生士の「リスク徹底排除チェックリスト」
では、これらの「買ってはいけない不動産」をどうやって見極め、リスクを排除すればいいのでしょうか?私たち古家再生士は、感覚ではなく、徹底した事前調査と現場での確認を通じて、このリスクを排除します。
このチェックリストは、全国の会員20,280名が実践し、2,467棟以上の再生実績を支える、「失敗を未然に防ぐ」ための実用的なノウハウです。
【購入前編】事前調査で「買ってはいけない」を排除する3つの質問
物件の内見に行く前に、まずは以下の3点について、仲介業者や役所に確認し、書類上の致命的なリスクを排除します。
●チェックリスト項目A: 役所に確認すべき「都市計画・建築制限」
特に接道状況の確認は最優先です。「43条但し書き道路」など、例外的に再建築が可能なケースもありますが、初心者は原則として避けるのが賢明です。
⚫︎チェックリスト項目B: 不動産仲介業者に確認すべき「告知事項・過去の修繕履歴」
仲介業者は知っている情報を伝える義務(告知義務)があります。必ず書面での回答を求め、口頭での説明に満足してはいけません。
チェックリスト項目C: 現地調査で確認すべき「周辺環境の需給バランス」
周辺の賃貸物件の入居率と家賃相場: ライバル物件の情報を調べ、あなたの物件の想定家賃が現実的かを判断します。
近隣の空き家率: 地域全体の空き家が多すぎる場合、需要の低さを示唆しています。
生活利便施設(スーパー、駅、バス停)へのアクセス: ターゲット層(単身者、ファミリー)にとって致命的な不便さがないか確認します。
【現地確認編】物件見学時に確認すべき「致命的な欠陥」チェックポイント10選
現地に足を運んだら、いよいよ古家再生士の視点で「買ってはいけないサイン」を探します。
特に、水回り、給排水管、床下の3点は、リフォームの際に最もコストがかさむ箇所です。これらの劣化が激しい物件は、価格が安くても手を出さないのが鉄則です。
【再生コスト編】「このラインを超えたら見送り」の修繕費用判断基準
古家再生投資のキモは、修繕費用をコントロールできるかどうかにあります。
私の著書『地方は宝の山! リスクを極限まで抑えて儲ける「空き家・古家」不動産投資』でもお話ししていますが、私たちが目指すのは「投資効率の最大化」です。
古家再生推進協議会では、以下の基準を投資効率を判断する一つの目安としています。
リフォームの見積もりは、必ず複数(最低3社)取得し、相場感を養ってください。そして、「予備費」として、見積もり額の20%〜30%を必ず予算に組み込んでおくことが、予期せぬコスト増大による失敗を防ぐための古家再生士の常識です。
机上の空論でなく、必ず「最悪の事態」を想定したキャッシュフロー計算をしてください。
失敗を恐れず確信を持って進むために:古家再生投資プランナー®️という選択肢
「買ってはいけない不動産」を見極めるためのチェックリストをお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。
知識があれば、リスクは「怖いもの」から「コントロールできるもの」に変わります。
私たちが20年以上の経験と2,467棟以上の実績を通じて体系化し、誰でも再現できるようにしたのが、古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座です。
机上の空論から脱却し「成功の再現性」を高めるノウハウ
古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座では、まさにこの記事で解説した「買ってはいけない不動産」を徹底的に排除するための現地調査技術、修繕コストの見極め方、そして地域需要の分析手法を体系的に学ぶことができます。
リスクヘッジ: 構造欠陥を見抜くスキル、法的なリスクを回避する知識。
コスト管理: 適正な修繕費用を導き出すための見積もりチェック能力。
出口戦略: 地域に合わせた再生プラン(デザイン、間取り)の設計能力。
これらのスキルを身につけることで、「この物件を買っていいのか?」という判断に確信を持つことができるようになります。
仲間と専門家がいる環境こそが最大のリスクヘッジ
不動産投資は孤独な戦いではありません。
私たち(一社)全国古家再生推進協議会が提供する最大の価値は、知識だけでなく、「仲間と専門家がいる環境」そのものです。
全国20,280名の会員ネットワークや、地域で活動するマスター古家再生士との連携は、あなたの投資活動における最大のリスクヘッジになります。物件を見つけたとき、「これは買ってはいけない物件か?」と迷ったとき、すぐに相談できるプロがいる。これが、失敗を未然に防ぎ、成功への再現性を高める最も確実な方法なのです。
社会貢献と収益の両立を実現する「4方よしモデル」の追求
古家再生投資は、単なる金儲けではありません。
空き家問題が深刻化する日本において、私たちは「負動産」を「優良な賃貸住宅」に再生することで、地域社会に貢献しています。この「4方よしモデル」を追求し、社会的に意義のある事業として取り組むことが、私たちが業界をリードする存在であり続ける理由です。
あなたも、この「リスクを極限まで抑えながら、社会貢献もできる」投資の仕組みを、古家再生投資プランナー®️として一緒に追求しませんか。
まとめ・結論
高利回りという甘い言葉に惑わされず、真のリスク(再建築不可、構造欠陥、需要ゼロ)を見極めることが成功の第一歩です。
高利回りの罠: 表面利回りではなく、「真のコスト」(修繕費、空室リスク)を織り込んだ総投資額とキャッシュフローで判断すること。
4大買ってはいけない物件: 再建築不可、需要ゼロ地域、重篤な構造欠陥、コンプライアンス問題の4つを徹底的に排除すること。
古家再生士のチェックリスト: 事前調査と現地確認を体系的に行い、リスクを極限まで抑えるための再現性のあるノウハウを実践すること。
古家再生投資は、知識とスキルを身につければ、誰でも再現性の高い資産形成が可能です。失敗を恐れるのではなく、正しい知識を持って「買ってはいけない物件」を回避し、確信を持って行動してください。
もしあなたが、この古家再生投資のノウハウを体系的に学び、確信を持ってリスクを排除できる投資家になりたいのであれば、古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座がその道を開きます。
行動なくして、未来は変わりません。
リスクを避け、健全な資産形成を目指すあなたの一歩を、私たち全国古家再生推進協議会は全力で応援します。
POST: 2025.10.27