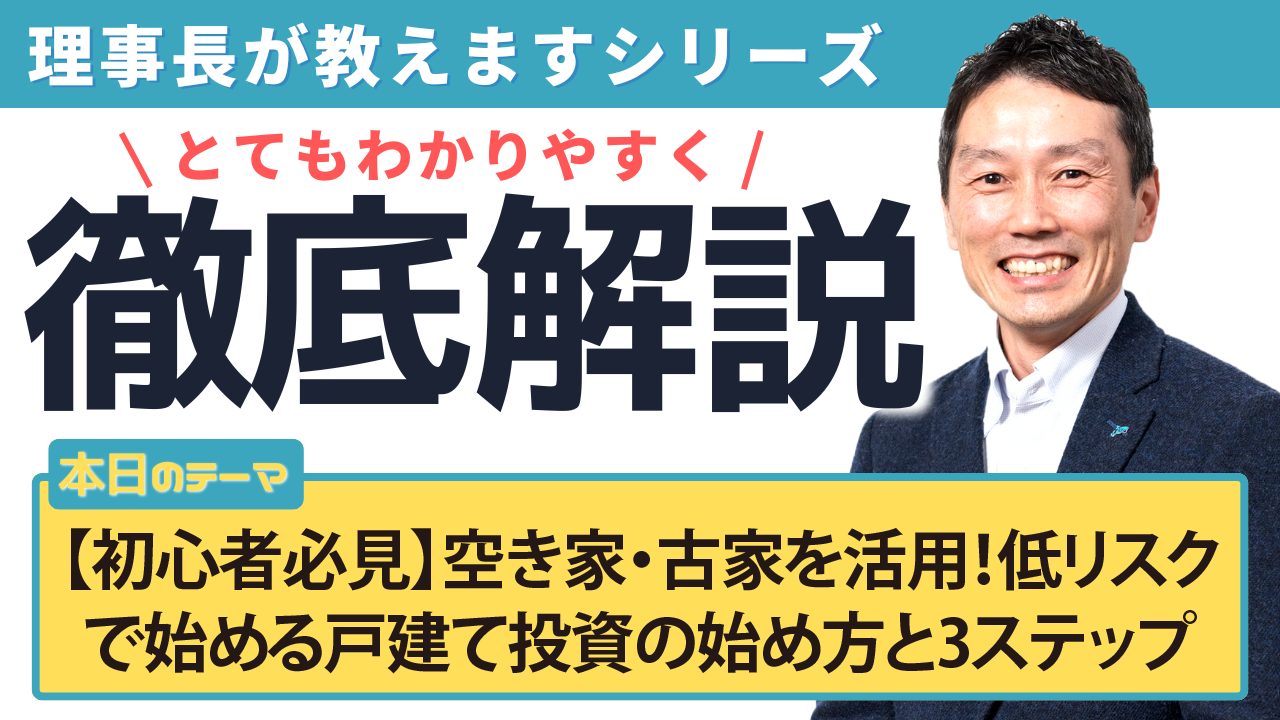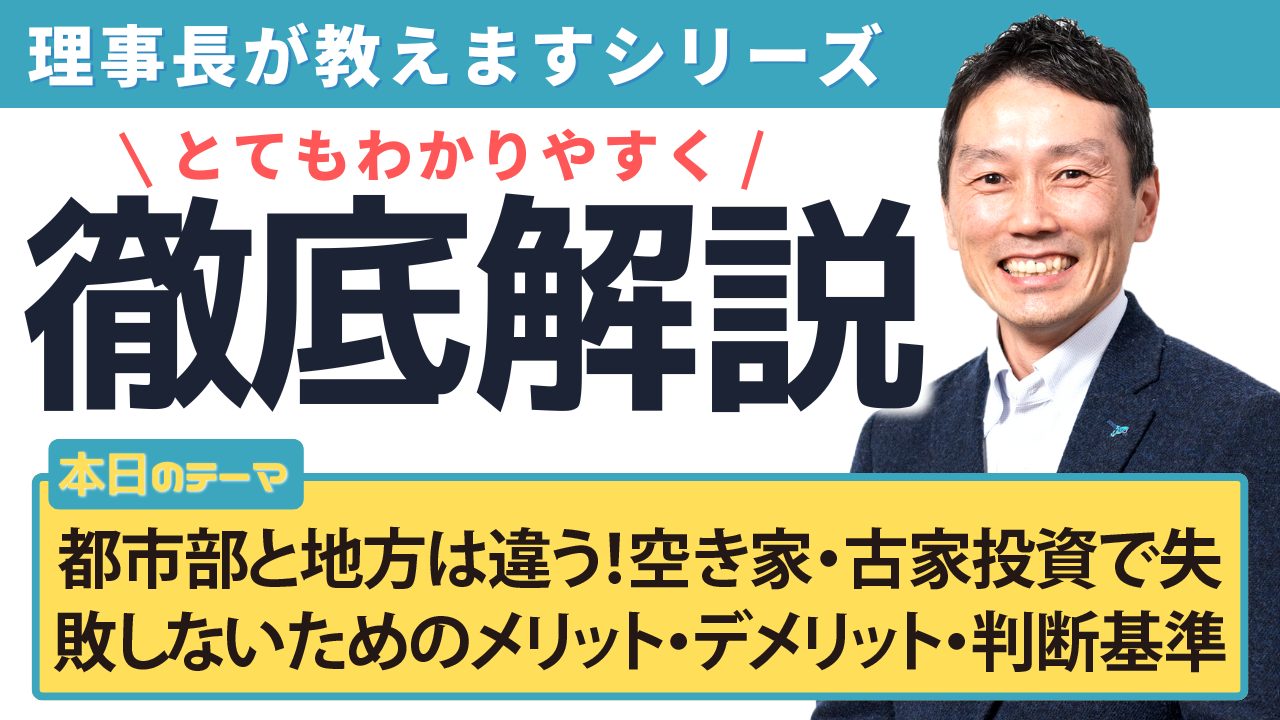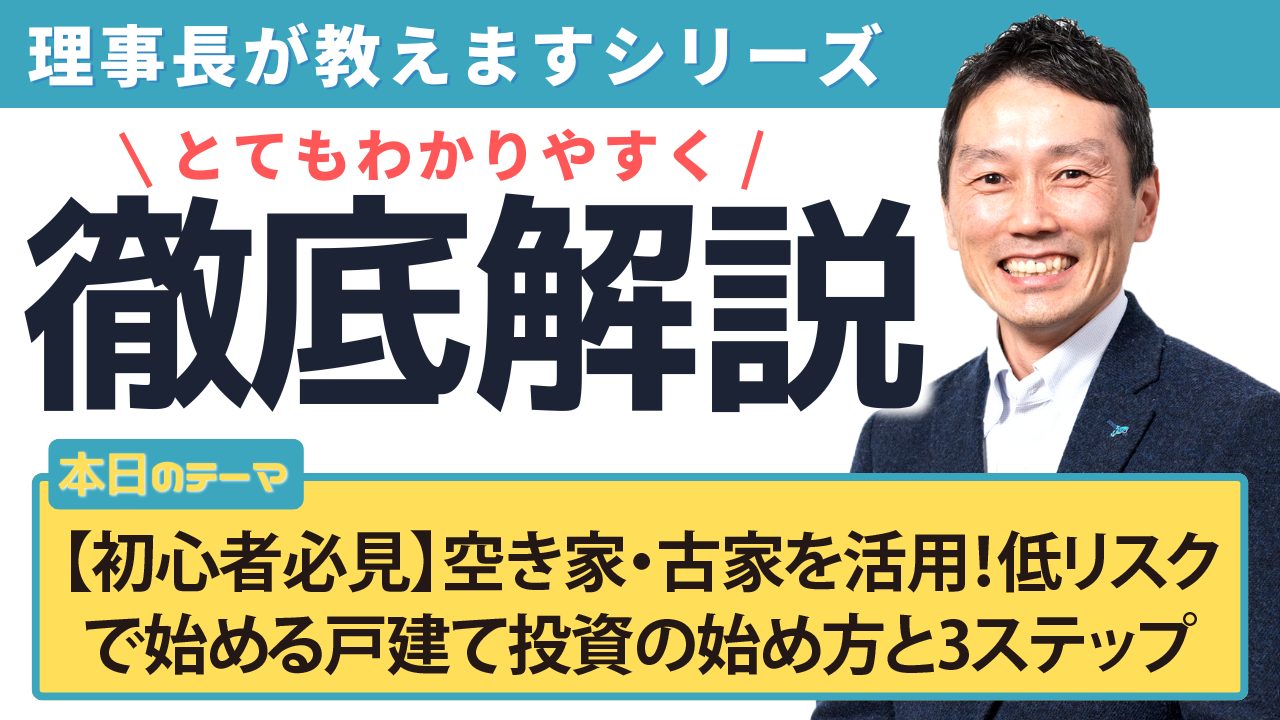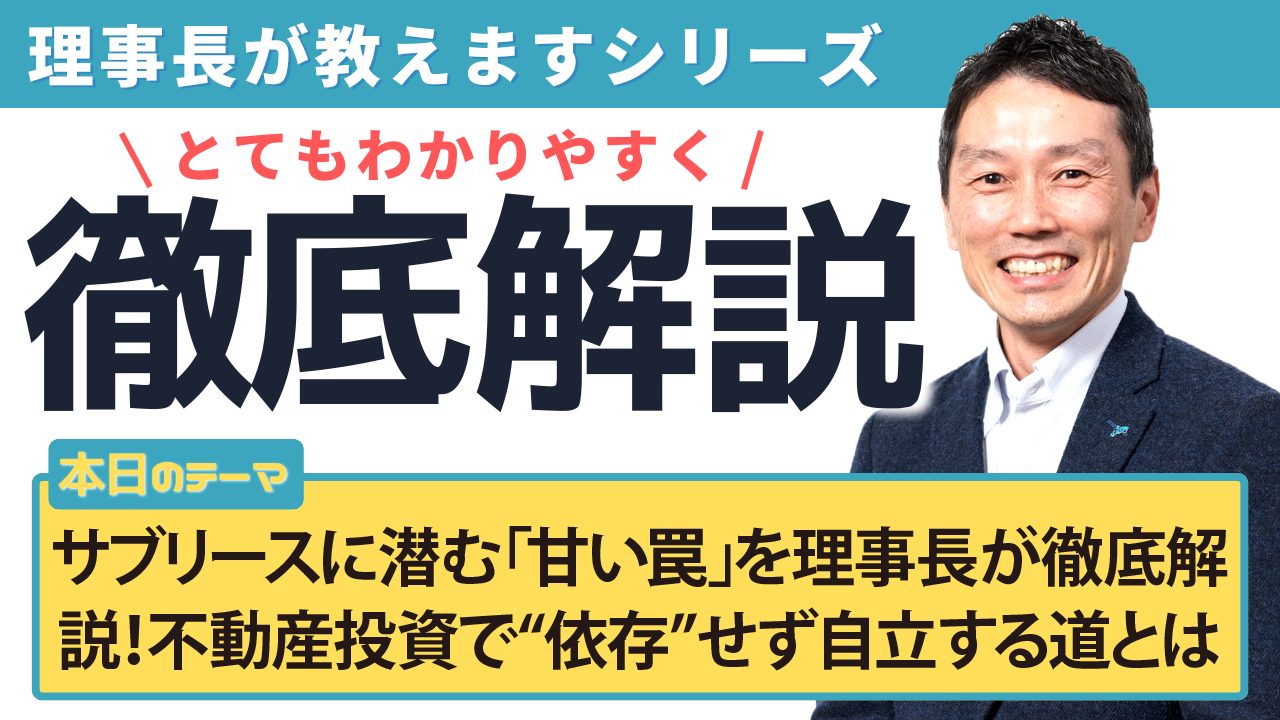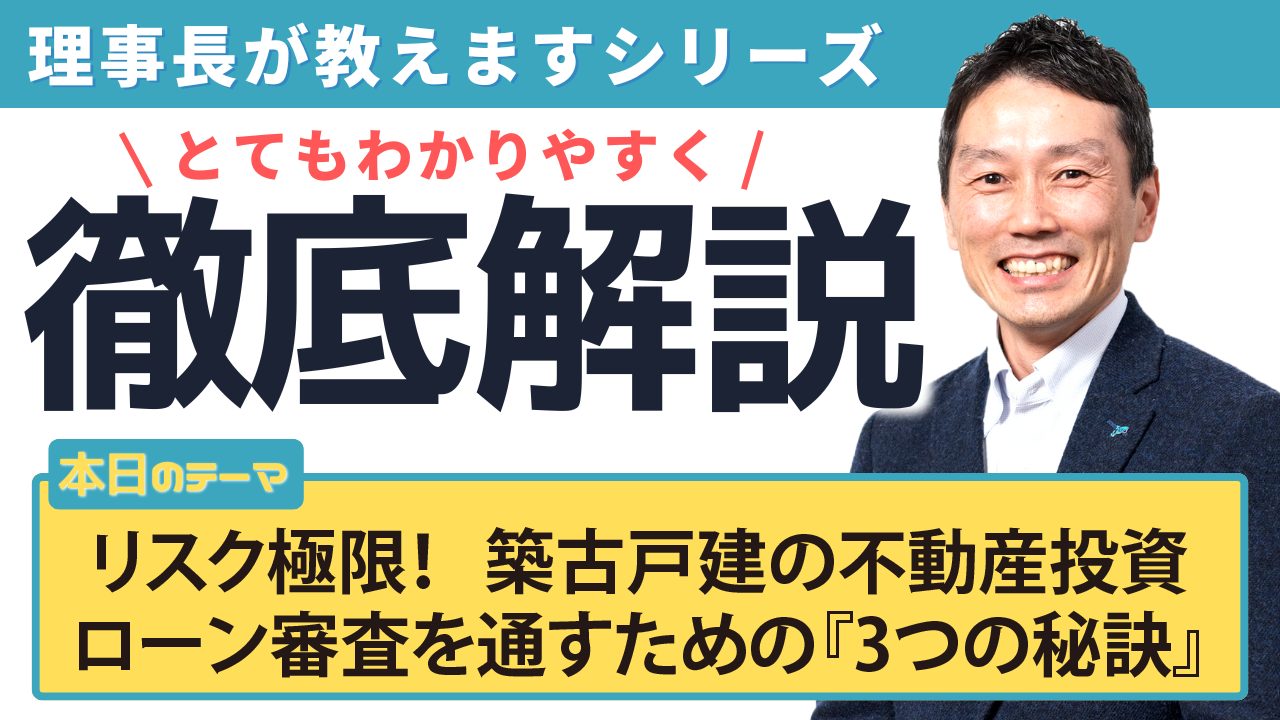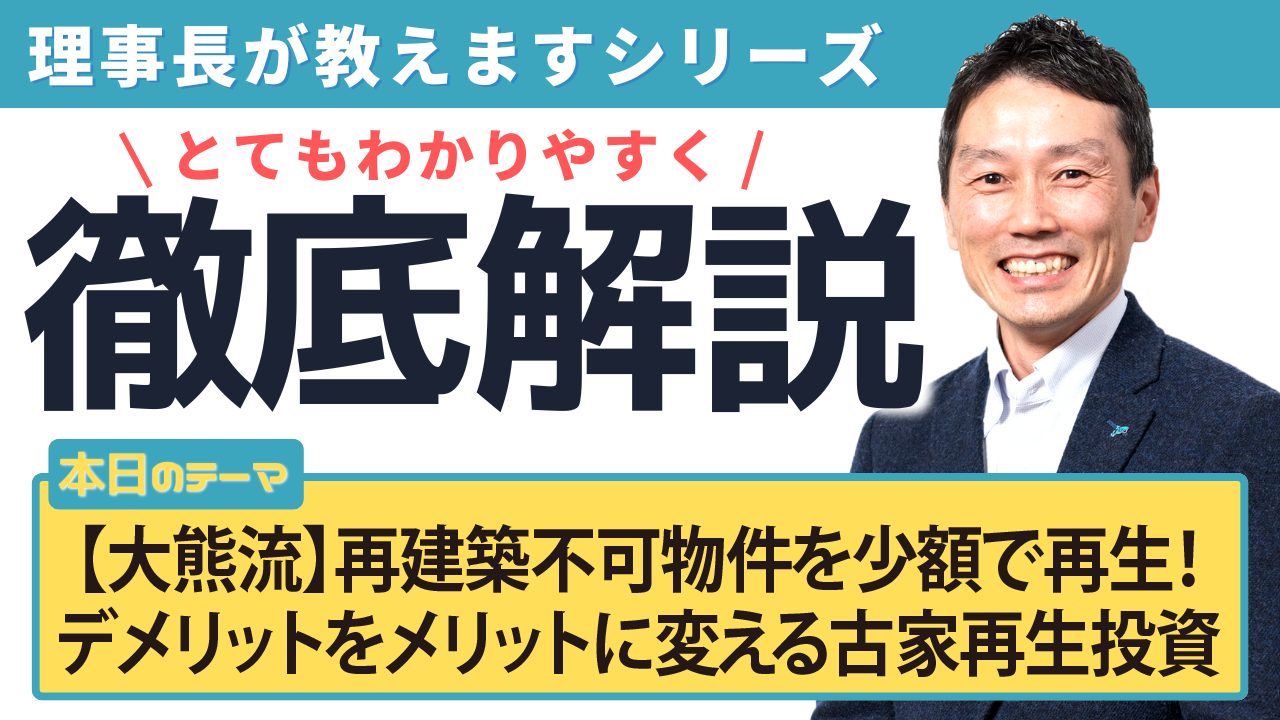
(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
もしあなたが不動産投資に一歩踏み出したいけれど、「大金を用意できない」「リスクが怖くて手が出せない」と感じているなら、今日お話しするテーマは、あなたの人生を変えるターニングポイントになるかもしれません。
そのテーマとは、不動産のプロさえ敬遠する「再建築不可物件」です 。
「再建築不可」と聞くと、誰もが「危険な物件」「買ってはいけないババ物件」というイメージを持つでしょう 。しかし、私たち全国古家再生推進協議会(全古協)の2,467棟を超える再生実績が証明しているのは、その真逆です 。再建築不可物件こそ、少額の資金で仕込め、利回り20%超えを叩き出す「宝の山」になり得るのです 。
なぜ、リスクが高そうな物件が、少額で高収益を生むのか?
それは、不動産投資の常識を逆手に取り、「デメリットをメリットに変える」私たち大熊流の古家再生投資術があるからです。本記事では、この物件に潜むリスクを極限まで抑えながら、高利回り物件を仕込むための裏技と、成功大家が実践する物件選定基準を、包み隠さず公開します。
この記事を最後まで読めば、あなたの不動産投資に対する固定概念は一変し、この物件が持つ圧倒的なチャンスが見えてくるはずです。
目次
再建築不可物件が「宝の山」になる大熊流の投資哲学
再建築不可物件とは、その名の通り、現在の建築基準法では建物を取り壊して新たに建て直すことができない土地上の建物です 。特に「接道義務」(建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に間口が2m以上接していなければならない)を満たしていない物件がこれに該当します 。
しかし、この大きな「制約」こそが、私たち少額投資家にとっては最大の「武器」になるのです。
なぜ不動産のプロは再建築不可を敬遠するのか?
不動産業者や一般的な投資家が再建築不可物件を敬遠する理由は、主に以下の3点に集約されます。
資産価値が低い: 銀行が担保価値を認めないため、高額な融資がつきません 。また、土地の活用方法が限定されるため、市場価格が低く抑えられます。
売却が難しい: 資産価値が低く、買い手が限定されるため、流動性が非常に低くなります 。特に一般の買い手にとって、建て替えができないことは大きなデメリットです。
手間とリスクが大きい: 築年数が古い古家が多く、シロアリ、雨漏り、傾きなどのリスクが高い上、売買の手間が大きく、不動産業者にとって「儲けにくい仕事」だからです 。
通常の不動産投資は、担保価値と流動性を重視するため、プロほどこの物件を「危険な不良在庫」として扱います。しかし、ここがチャンスです。プロが避けるからこそ、価格が安くなり、競争相手が極めて少なくなるのです 。
「リスク」を「収益」で上回る!高利回り投資の逆転の発想
私たち大熊流の投資哲学は極めてシンプルです。それは、「リスクに見合うリターンを確保すること」 。
再建築不可物件は、たしかに「再建築できない」という最大のリスクを抱えています。しかし、そのリスクを織り込んだ上で、市場価格より圧倒的に安く仕入れ、賃貸収入で短期的に回収してしまえばいいのです 。
通常の不動産投資では、利回り10%でも優良と言われますが、私たちは再建築不可物件や借地物件など、リスクのある物件を狙うことで利回り20%以上を目標に掲げます 。
例えば、再建築不可の物件を100万円で仕入れ、リフォームに300万円かけたとして、年間家賃収入が80万円だとすれば、表面利回りは です 。この高いリターンがあれば、数年で投資額を回収でき、その後はすべてキャッシュフローとなり、再建築ができないというリスクを凌駕できるのです。
「利回りが高いということは、それだけリスクも高いということです。ですから、今示した以上の利回りを求めすぎると思わぬ落とし穴にはまる可能性が高くなります。投資はバランスが大切です 。」
このバランスを追求することで、リスクを極限まで抑えた少額投資が実現します。
再建築不可物件は都市部から地方までどこにでもある「希少な投資商品」
再建築不可物件は、都心部の古くから栄えた住宅密集地や、地方の旧市街地など、日本全国どこにでも存在します。
都市部: 開発前の狭い路地や私道に面したテラスハウス 。土地の価値が高いため、再建築不可でも物件価格が比較的高くなりますが、賃貸需要は極めて旺盛です。
地方: 土地が広くても接道が公道ではなく農道や私道になっているケース 。物件価格が安く、土地が広いため、駐車場を増設するなど活用幅が広くなります。
再建築不可物件は、不動産サイトでも特集が組まれることは少なく、プロが敬遠するため、情報自体が希少です。まさに、「知識と行動力のある者だけが入手できるお宝物件」なのです 。
少額仕入れを可能にする!再建築不可物件の「価格破壊」の仕組み
再建築不可物件の最大の魅力は、その「価格」です。通常の物件価格の相場とはまったく違うロジックで価格が決定されるため、少額の現金で仕込むことが可能になります。
「再建築不可」が物件価格を安くする明確な理由
再建築不可物件の価格が安いのは、シンプルに「担保価値がない」見なされるからです 。
金融機関の評価: 銀行は、万が一債務不履行になった場合に備えて土地を担保に取りますが、再建築不可では土地を売却する際に大幅な値引きが必要となり、担保として非常に弱くなります。そのため、ほとんど融資がつきません 。
売主の「出口がない」心理: 相続などで物件を所有した売主は、売れないまま固定資産税や管理費だけがかかる状況に陥ります 。特に「空き家対策特別措置法」により、空き家を放置すると固定資産税が3〜6倍に跳ね上がるリスクがあるため、「タダでもいいから手放したい」という心理が働き、物件価格は驚くほど安くなります 。
この「売主の焦り」と「市場の評価の低さ」が組み合わさることで、物件が100万円台という価格帯で流通することになるのです 。
現金購入が基本!融資に頼らないリスクの極限抑制
再建築不可物件は融資がつきにくいため、購入は「現金」が基本となります 。
「現金で数百万は大変だ」と思うかもしれませんが、これは実は最大のメリットなのです。
競争力の確保: 買い付け時に「現金一括」を提示できることで、他の融資を使う買い手よりも交渉力が圧倒的に強くなります 。売主は現金をすぐに得られることを優先するため、価格交渉も有利に進められます 。
金利リスクの回避: 金利支払いがないため、賃貸経営が傾いた際のリスクが極限まで抑えられます 。
早期回収: 利回り20%で数年で回収できるため、投資期間が短縮されます 。
少額の現金投資をすることで、多額の借入による「不動産投資の失敗」という最大のリスクを回避できる。これこそが、初心者にとって最も安全な投資法なのです 。
借地権物件という「裏技」を使い利回り25%を実現した事例
再建築不可物件の応用編として、私たち全古協の会員が実践する「借地権物件」という裏技があります 。
借地権物件とは、土地は他人が所有し、建物のみを購入する物件です 。この物件も再建築不可と同様に資産価値が低く、銀行の担保価値もないため、普通は買いません 。
しかし、考え方を転換すれば、リスクを安く買うことになります 。
【借地権物件・利回り25%の事例 】
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 物件購入価格 | 50万円 | 安価に購入 |
| リフォーム費 | 60万円 | |
| 総投資額 | 110万円 | |
| 年間家賃収入 | 69.6万円(月5.8万円) | |
| 表面利回り | 63.2% | *借地代、名義変更料を除く |
借地物件の場合、購入価格以外に名義変更料(30~60万円程度)や地代支払いが発生しますが 、それを加味したとしても、利回り20%以上を狙うのが目安となります 。借地物件を仕込む際は、地主の了承、地代の確認、契約書の詳細確認が必須です 。
デメリットを魅力に変える「古家再生」格安リフォーム術
再建築不可物件の最大のデメリットは、「建物の老朽化」です。これを、高額なリフォーム費用をかけずに、入居者が「ここに住みたい!」と思える魅力的な物件に変えるノウハウが、古家再生投資術の核心です 。
賃貸住宅を専門とする「古家再生士」が不要な工事を見抜く
一般的な工務店に再建築不可の古家のリフォームを依頼すると、「あれもこれもダメ」「すべて新築レベルに直さないと」と高額な見積もりが出てきます 。なぜなら、彼らは賃貸経営の視点を知らないからです 。
私たち全古協が認定する「古家再生士」は、以下の3つのスキルを持つ、賃貸戸建てリフォームの専門家です 。
賃貸不動産の知識: エリアの家賃相場、入居者のニーズを理解している 。
差別化リフォーム: 家賃相場に合った「余分な工事をしない」再生ができる 。
協議会のルール遵守: 投資家の利益を守り、社会貢献を両立させる 。
古家再生士は、「7万円の物件のようなリフォームはしません。5万円の物件を探している入居者が満足する工事」に絞り込み、徹底的にコストを削減します 。これが、平均200万円台という格安リフォームを実現する秘訣です 。
躯体・基礎・配管…必ずリフォームすべき最優先箇所
再建築不可物件は、建物の老朽化が激しいため、安全性と入居後のクレームを避けるために、リフォームを「しない」判断以上に、「必ずしなければならない」箇所を見極めることが重要です 。
| 箇所 | 必須リフォームの理由 | 古家再生士の対応例 |
| 電気 | 容量不足によるヒューズ飛びはクレームの元。生活インフラは最優先。 | アンペア数をチェックし、必要に応じて容量を増やす 。 |
| 床 | 床の緩みや腐食はシロアリ被害の可能性、入居者の安全に関わる。 | 緩んでいる部分は張り替え 。問題がなければクッションフロアか畳の表替え 。 |
| 畳/壁 | 汚れや臭いは入居付けの大きな障壁。清潔感は必須。 | 畳は表替え、壁は80%を塗装で対応。塗装は安価に差別化が可能 。 |
| 浴槽 | ホーローは交換 。グラスファイバー、ステンレスは磨きや塗装で対応。 | ユニットバスに入れ替える場合もあるが、予算と相談 。 |
| 配管/配線 | 給排水の老朽化は漏水事故に直結。床下工事時に確認・補修。 | 古い配線の取り換えを推奨 。 |
| シロアリ | 瑕疵担保免責(売主の責任免除)の場合、買主が処置必須。 | 床をめくり、土台や柱に問題があれば補強。可能性があれば薬を散布 。 |
再建築不可物件でこそ効果を発揮する「デザインの差別化」
高額なリフォームができないからこそ、安価でインパクトのある「デザインの差別化」が決定的な武器になります 。
特に再建築不可物件が多い築古戸建ては、和室が多く残されています。これを無理に洋室化せず、和のテイストを残したまま、モダンな雰囲気に演出することが重要です 。
塗装の活用: 綿壁や砂壁はクロス張りよりも塗装のほうが安価で、色やデザインの自由度も高く、差別化に最適です 。
キャットウォーク/ガレージ: 土地の広さや構造を利用し、猫好きにはたまらないキャットウォークや、車庫のない物件にインナーガレージを新設することで、家賃アップを狙います 。
ステージング: 家具や小物を配置し、「ここに住みたい」と思わせる演出をすることで、内見時の印象を強烈に引き上げます 。
家賃を1万円アップさせた「猫可(キャットウォーク)」の成功事例
再建築不可物件は土地が広いことが多く、「ペット可」にすることで競合物件との差別化が図れます 。
【猫12匹家族を入居させ家賃アップした事例 】
12匹の猫を飼う大家族が、他の物件で断られ困っていました 。オーナーのYさんは「お困りの方に応える」という理念のもと、入居を検討。
リフォーム: 物件にキャットウォークを設置 。
条件設定: 退去時の修繕費用のリスクヘッジとして、家賃を1万円増額(7万円) 。
結果: 入居希望者から「むしろそうしていただいた方がありがたい」と快諾され、無事入居が決定 。
一般のマンションでは猫不可が多い中で、戸建の強みを活かし、社会貢献(お困りの家族を助ける)と収益(家賃アップ)を両立させた「4方よし」の成功事例です 。
再建築不可でも入居者に困らない「客付け」の秘訣
「再建築不可でも本当に借り手がつくのか?」という不安は、誰もが抱くでしょう 。しかし、私たちの実績では、収益に見合わない無理な物件は最初から購入しないため、入居率は100%です 。再建築不可物件でも、客付けには明確なロジックが存在します。
競合物件が少ないからこそ成り立つ「戸建賃貸」の希少価値
戸建賃貸は、アパートやマンションと比べて圧倒的に数が少ない「希少性の高い賃貸物件」です 。特に再建築不可物件は、土地の活用が難しいため、「戸建のまま朽ち果てる」か、「古家再生」で「賃貸戸建として再生される」かの二択になることが多くなります 。
ファミリー層のニーズ: 小さいお子さんがいる家族は、上下左右の音を気にせず生活できる戸建を好みます 。
ペットオーナーのニーズ: ペット可の戸建はさらに希少価値が高く、高い需要があります 。
外国人入居者: 共有部分でのトラブルが少なく、まとまった人数で住める戸建は、外国人労働者の社宅としても需要が高まっています 。
競合が少ないため、入居者獲得競争に巻き込まれにくく、安定した客付けが可能になるのです 。
駅から遠くても「この家賃なら住みたい」と思わせる家賃設定の極意
家賃設定は、投資の成功を左右する最重要ポイントです 。特に再建築不可物件の場合、立地条件が悪いことも多いため、「入居者の気持ち」になって設定することが重要です 。
大熊流の家賃設定の原則:
相場より少し安く設定する: 例えば、相場5万円のところを4.8万円に設定することで、早期に入居を決めます 。家賃を5.3万円に上げて3カ月空室になるよりも、4.8万円で即決する方が、トータルでの収益は高くなります 。
確実な家賃相場を算出: インターネットや複数の不動産業者へのヒアリングを通じて、客観的な適正家賃を割り出します 。大家の希望で高く設定してはいけません 。
付加価値で家賃を上乗せ: 駐車場確保、ペット可、デザインリフォームなどで、入居者満足度を高め、適正家賃にプラスαの上乗せ交渉をします 。
「賃貸不動産業者とのやり取りやリフォーム工事での問題…経験したことがその後に役立ちます 。」この経験と知識の蓄積が、適正家賃を見極める「目利き力」を養います 。
再建築不可物件を民泊転用し、利回り25%を実現した大阪の事例
再建築不可物件は、賃貸住宅としてだけでなく、民泊施設として転用することで、さらなる高収益を狙えるケースもあります 。
【再建築不可物件を民泊転用した事例 】
大阪環状線近くの再建築不可物件(築45年、状態悪)。
| 項目 | 費用・収益 | 備考 |
| 物件購入費 | 350万円 | 当初の買付額230万円は通らず、350万円で交渉 |
| 民泊工事費 | 400万円 | 旅館仕様への改修 |
| 総投資額 | 750万円 | |
| 年間宿泊料 | 192万円(月16万円) | 運営業者手数料20%控除後 |
| 表面利回り | 25% | 驚異的な高利回り |
この物件は、再建築不可というデメリットから当初の利回りが低すぎましたが、**「民泊」**という新しい使い道を考えたことで、一気に高収益物件へと変貌しました 。さらに2年後に1,200万円で売却という「出口戦略」も成功させています 。
ただし、民泊は旅館業法の許可が必要であり、法規制に左右される側面が大きいため、ギャンブル性が高い投資であることを認識しておくべきです 。
業者回り・マイソク作成…入居付けで勝つための実践テクニック
入居付けを成功させるには、管理会社に丸投げするのではなく、大家自身が「経営者」として動く必要があります 。
業者回り: リフォーム完了後、地域の賃貸仲介業者100軒弱に直接訪問し、物件の魅力を売り込みます 。手土産のドリンク剤を持って行き、顔を覚えてもらうことも重要です 。
差別化マイソク: 仲介業者がお客様に紹介する物件資料(マイソク)は、差別化された内装デザインのカラー写真を使い、強烈なインパクトを与えるように工夫します 。
条件の柔軟性: 敷金・礼金ゼロ 、ペットの条件緩和など、柔軟に対応することで、仲介業者のモチベーションを上げ、優先的に紹介してもらいやすくします 。
リスクを極限まで抑える再建築不可物件の「出口戦略」
再建築不可物件は、少額の資金で高利回りという大きなメリットがありますが、やはり「売却のしにくさ」というデメリットが残ります。だからこそ、出口戦略までを見据えた計画が必要です。
キャッシュフローを貯めて売却する、短期での回収を目指す戦略
再建築不可物件の出口戦略の基本は、「売却で儲ける(キャピタルゲイン)こと」を目的とせず、「賃貸収入で短期回収する(インカムゲイン)こと」を最優先にすることです。
回収年数の目標: 利回り20%を確保すれば、5年で投資額を回収できます。
資金の再投資: 5年で回収した資金は、次の物件への投資資金(種銭)として活用します 。
売却の判断: 回収後、物件を維持してキャッシュフローを増やし続けてもいいですし、もし相場以上の価格で買い手(現金購入可能な投資家など)が現れれば、ためらわずに売却します。売却益がなくても、投下資金が戻っていれば成功なのです。
「売却、賃貸の判断は早めにすることが大切です 。」迷ったら、空き家にしておくことによる**「賃貸収入の損失」と、建物の劣化による「資産価値の低下」**という二重のリスクを回避するため、早めに賃貸化を決断することが重要です 。
再建築不可物件の「売却の難しさ」は承知の上でどう対処すべきか
再建築不可物件は、その名の通り、売却のハードルが高いのは事実です 。しかし、そのデメリットを解消する手立てもあります。
再生専門家間の取引: 私たち全古協のコミュニティ内では、「オーナーチェンジ」(入居者が入ったままの状態で売却)という形で、古家再生投資のノウハウを理解している投資家同士が取引を行います 。これにより、一般市場で売れない物件も、適正な収益物件として売買が成立します。
再建築可能になる可能性: 再建築不可の理由が「私道」による接道義務違反である場合、近隣の協力が得られれば、私道を買収したり、公道として指定を受けたりすることで、将来的に再建築可能になる可能性はゼロではありません 。
資産の分散(リスクヘッジ): 再建築不可物件を多数所有することで、個別の物件の売却リスクを分散します。全体でキャッシュフローが安定していれば、数棟売れなくても問題ありません 。
「不動産は現金化しにくいというデメリットも軽減でき、リスクの減少になると思います 。」
再建築可能となる可能性を見越して保有する戦略
再建築不可物件は、建て替えができないことが前提の投資ですが、もし将来的に「再建築可能」になれば、土地の資産価値が跳ね上がり、大きな売却益(キャピタルゲイン)を得られます。
私たちが再建築不可物件を仕込む際には、賃貸経営の視点(インカムゲイン)だけでなく、こうした可能性も念頭に置きます。
周辺の再開発情報: 行政の道路拡張計画、区画整理計画などの情報を確認します。
隣地との関係構築: 隣地所有者と良好な関係を築き、将来的に私道問題の解決に協力してもらう準備をしておきます 。
「投資は知識30%、経験70%」です 。こうした知恵と経験の蓄積が、再建築不可物件のデメリットをメリットに変え、圧倒的な成功を収める鍵となります。
まとめ
私たち大熊流の古家再生投資術は、不動産のプロが敬遠する再建築不可物件を、少額の資金で仕込み、高利回り(20%超)を実現する「宝の山」に変える逆転の投資法です。
この投資術の核心は、再建築ができないという「リスク」を、徹底したコスト削減とデザインの差別化による「高収益」で上回り、短期間で投資額を回収してしまうことにあります。
【再建築不可物件を成功に変える3つのステップ】
少額仕入れの裏技:担保価値の低さというデメリットを逆手に取り、現金購入で安く仕込む。借地権物件も検討し、利回り20%超を目標にする。
格安リフォーム術:賃貸経営の視点を持つ「古家再生士」に依頼し、安全に関わる箇所(躯体、配管、電気)以外は徹底的にコストを削減する。
高収益客付けの秘訣:戸建賃貸の希少性を武器に、入居者目線の適正家賃で早期に客付けする。駐車場確保やペット可などで家賃アップを狙う。
そして何より、この投資は「4方よし」のビジネスモデルです 。
あなた(投資家): 少額投資で高利回り、安定収益を実現。
入居者: 手頃な家賃で、広くて快適な戸建の住環境を提供。
地域社会: 放置されていた空き家問題の解決に貢献。
売主: 処分に困っていた物件が生まれ変わり、手放せる。
単なるお金儲けではなく、地域社会に貢献しながら資産を築く、持続可能なビジネスなのです。
このノウハウをより体系的に学び、再建築不可物件の目利き力と高収益リフォームの知識を身につけたい方は、私たち(一社)全国古家再生推進協議会が提供する「古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座」で学ぶことをお勧めします。
私たち協議会は、机上の空論ではなく、累計2,467棟の再生実績から得られた「現場の知恵とノウハウ」を体系化し、あなたに提供しています 。
「いつかやろう」と迷っている間に、再建築不可物件のような「宝の山」は誰かの手に渡ってしまいます 。
まずは一歩、踏み出してください。あなたの人生を変える「行動」が、未来の資産を築きます。
あなたの挑戦を、心よりお待ちしております。
POST: 2025.11.20