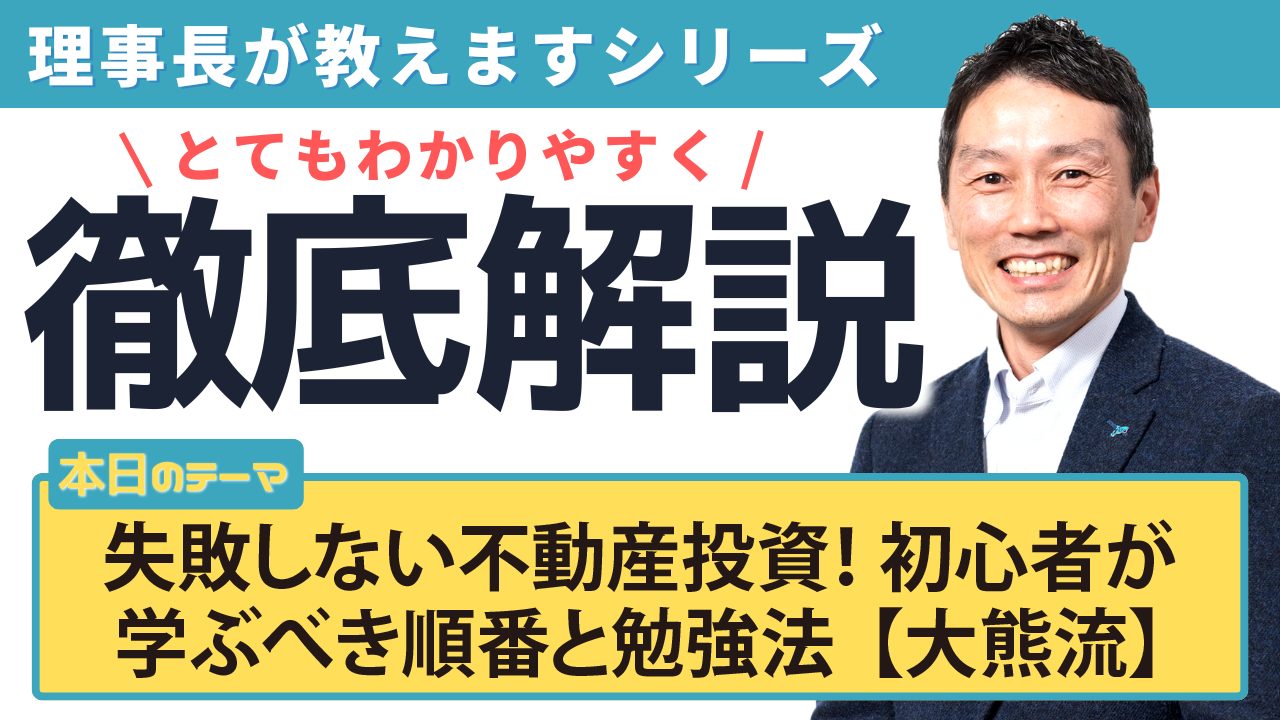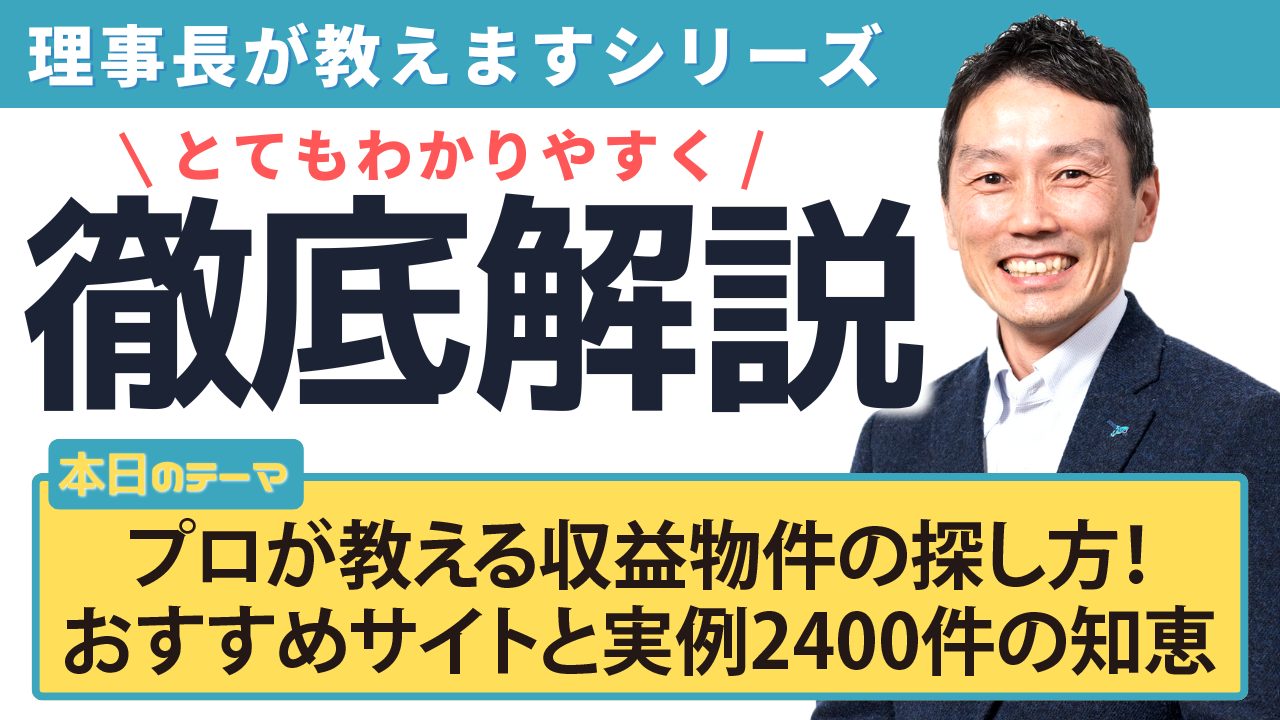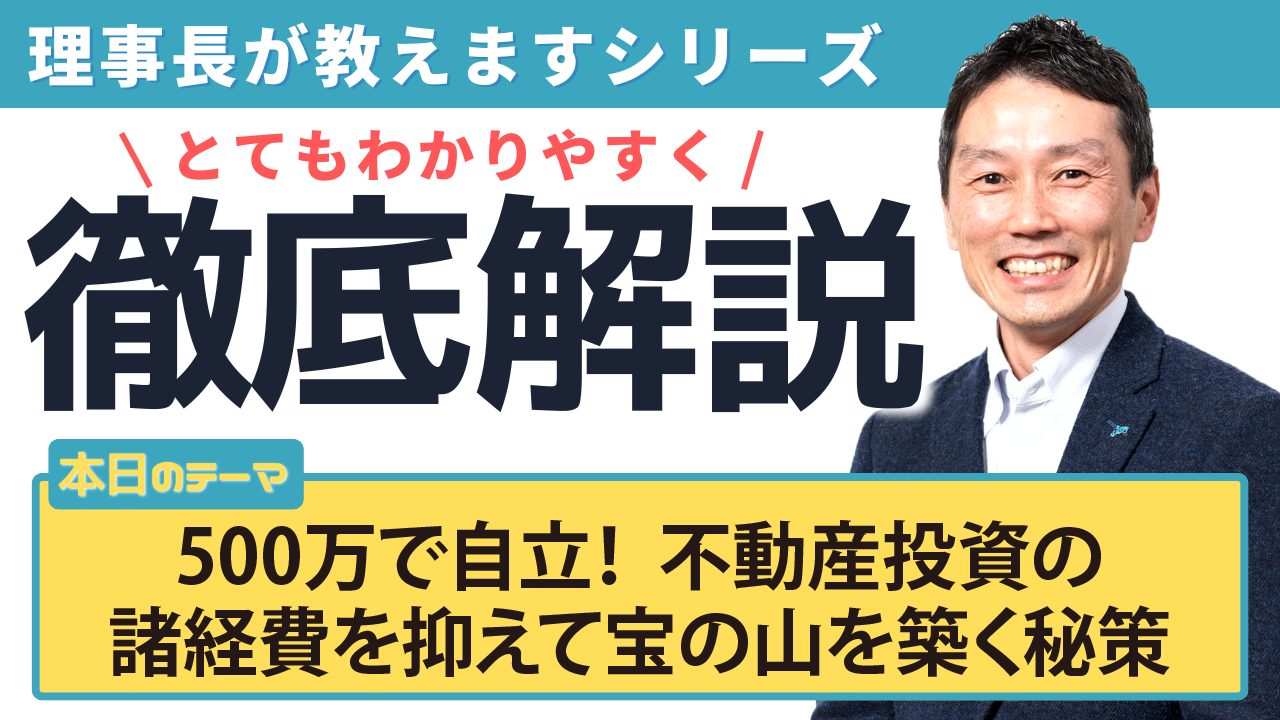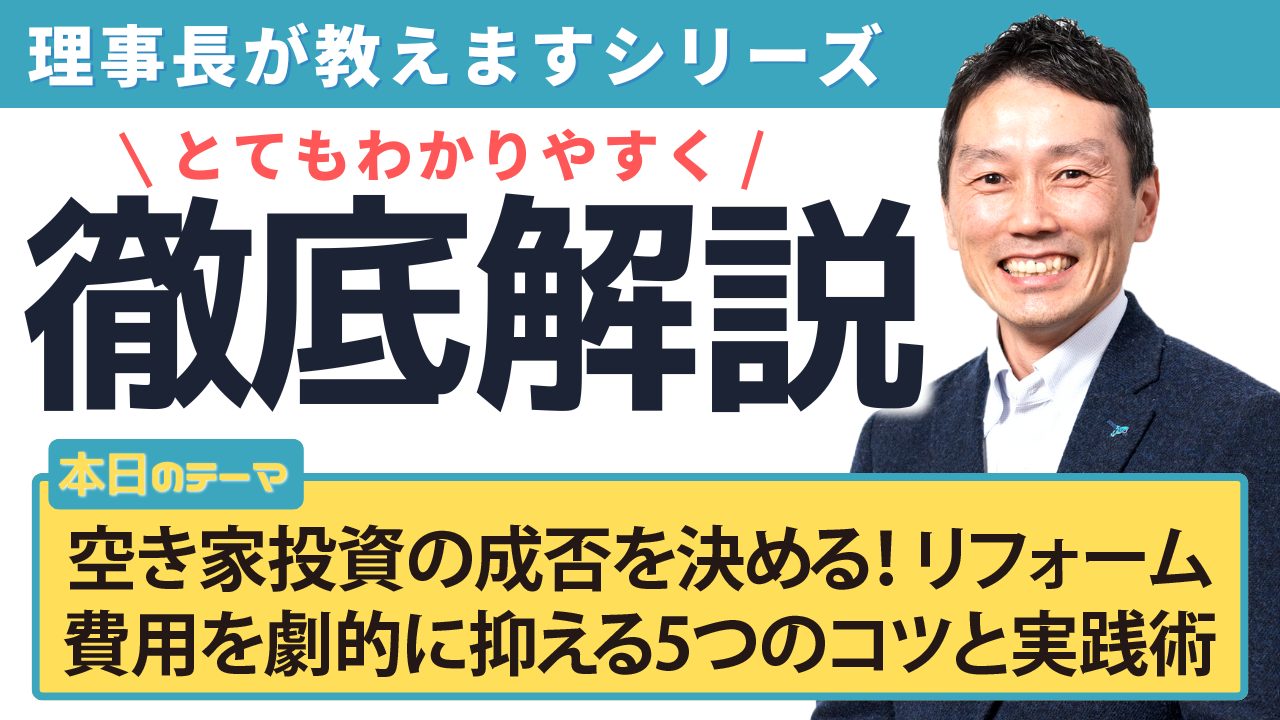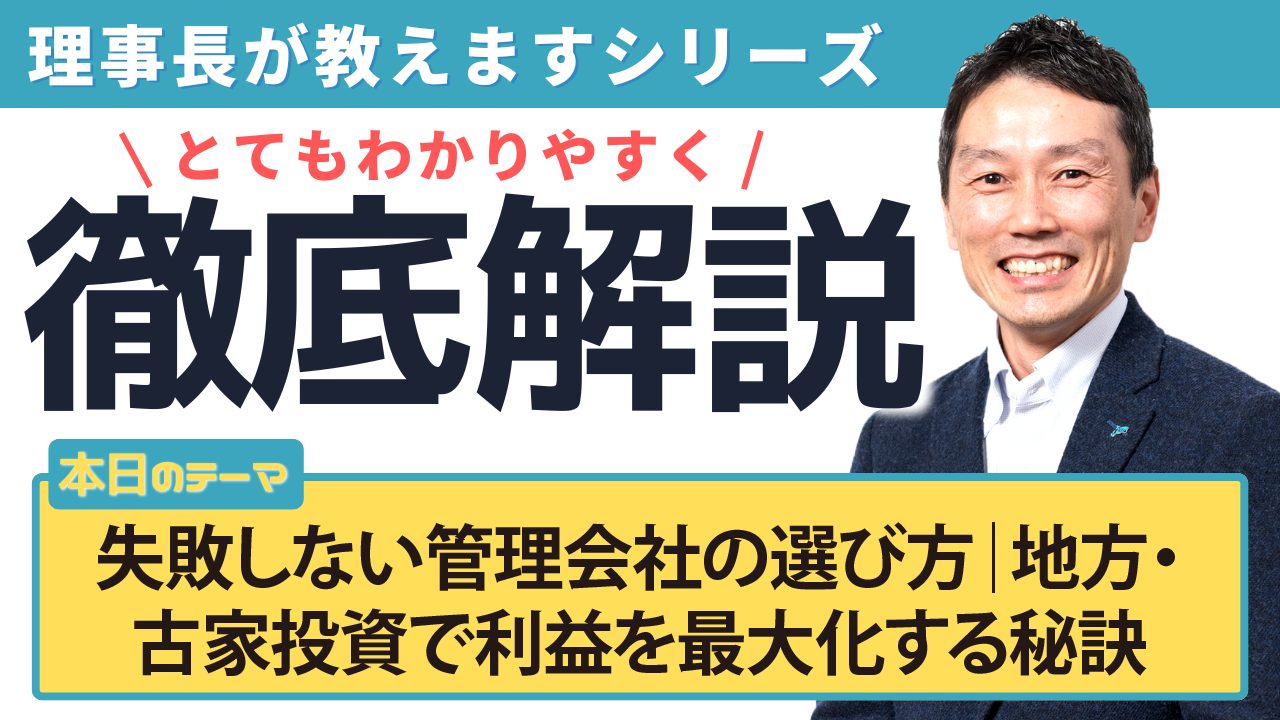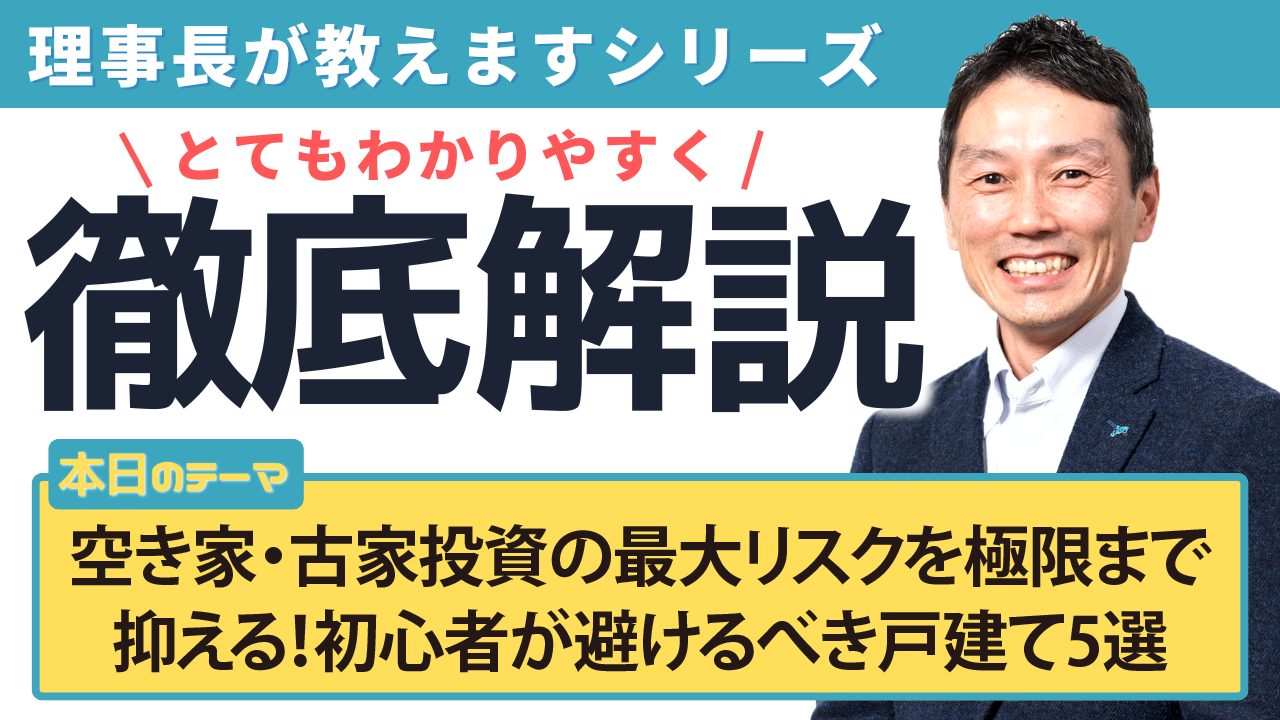
(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
空き家・古家不動産投資は、「無借金で億単位の資産を築ける」「地方の社会課題解決に貢献できる」という点で、最も再現性が高く、そして意義深い投資手法だと私は確信しています。事実、私自身がゼロからこの投資を始め、今では全国20,280名の会員、そして累計2,467棟の再生実績を持つ組織の理事長を務めるまでになりました。
しかし、どんな投資にもリスクはつきものです。特に、古家投資に興味を持ったばかりの初心者の皆さんが最も恐れるのは、「買ってはいけない戸建て」、いわゆる「ババ物件」を掴んでしまい、想定外の高額な出費に苦しむことではないでしょうか。
机上の空論で「不動産は買ってはいけない」と論じる人もいますが、それは的外れです。大切なのは、「買ってはいけない物件の明確な基準」を知り、それらをプロの視点で見抜くスキルを身につけることです。
この記事を最後まで読めば、あなたは以下のことが明確にわかります。
古家投資における「最大のリスク」とは何か、その正体。
初心者が絶対に避けるべき戸建て5つの具体的な特徴とそのチェックポイント。
リスクの高い物件を「お宝物件」に変える大熊流リスクヘッジ戦略。
私たちの協議会が2,467棟の再生を通じて得てきた生きたノウハウと失敗事例を惜しみなく公開します。この知識を武器に、あなたの古家投資の最大リスクを極限まで抑え、安心感を持って高利回りの未来を掴みましょう。
目次
1. そもそも古家再生投資における「最大のリスク」とは何か?
1-1. 初心者が最も恐れる「想定外の出費」の正体
不動産投資の成功は、結局のところ「知識30%、経験70%」です。いくら本で知識を蓄えても、現場で何が起こるか予測不可能なのが不動産投資のリアル。そして、初心者が最も失敗し、最も恐れる「最大のリスク」とは、「想定外の出費」に他なりません。
これは単なるリフォーム費用が予算を少し超えるという話ではありません。私の著書『地方は宝の山!』でも再三強調していますが、「根拠なく安さだけで物件を購入してしまい、後から構造的な欠陥が発覚し、リフォーム費用が購入価格の何倍にも膨れ上がる」ケースです。
例えば、「リフォームは200万円で済むだろう」と楽観視していたら、実はシロアリ被害が柱の奥深くまで進行しており、躯体の補強を含めて400万円、500万円と青天井に費用が膨らむ。結果、高利回りの見込みが消え、利回りがたった数%の物件に成り下がる。これが古家投資における最も避けるべきリスク、すなわち「最大のリスク」なのです。
私自身も、過去には物件を見誤り、想定よりも大幅にコストがかかってしまった苦い経験があります。だからこそ、私たち協議会は、物件の目利き力と適正価格の算出を最重要視しています。
1-2. 失敗を避けるための大原則:「家賃からの逆算」思考
最大のリスクを極限まで抑えるためには、私たちが提唱する「家賃からの逆算」という大原則を絶対に守ってください。
多くの投資家は、まず物件価格を見て「安いから買おう」と考えます。これは完全に思考が逆です。
正しい思考プロセスは以下の通りです。
想定家賃の決定: その物件が再生後、いくらで貸せるかを徹底的にリサーチし、想定家賃(例えば7万円)を決定する。
目標利回りの設定: 私たちの協議会では利回り20%以上を目標としています。
適正な総投資額の算出: 「想定家賃 × 12ヶ月 ÷ 目標利回り(0.2)」で、物件価格とリフォーム費用を合わせた**「総投資額」**の限界値を算出します。(例:7万円 × 12ヶ月 ÷ 0.2 = 420万円)
リフォーム予算の決定: この総投資額(420万円)から、物件の購入価格を差し引いた金額が、その物件にかけるべきリフォーム費用の最大予算となります。
この「家賃からの逆算」をせずに、ただ安いという理由だけで飛びつくと、リフォーム費用が青天井になり、最終的に利回りの悪い物件を掴むことになります。買ってはいけない物件とは、この逆算が成り立たない物件のことなのです。
2. 【本題】初心者が絶対に避けるべき「買ってはいけない戸建て」5選
ここからは、私たちの協議会の2,467棟の再生実績と、全国の会員からの報告に基づき、古家再生投資の初心者が見送り、または高度な専門知識なしには手を出してはいけない「ババ物件」の特徴を5つに絞って解説します。
2-1. リフォーム費用が青天井になる「構造的欠陥」がある戸建て
これは、戸建て投資における最も危険な地雷」です。表面的な汚れや傷みはリフォームで解決できますが、家の骨格(躯体)に関わる問題は、費用が天井知らずになる可能性があります。
避けるべき具体的な欠陥:
躯体の著しい傾き・歪み:
ビー玉が転がる、ドアや窓の開閉が異常に硬い、というレベルの傾きは危険です。基礎からのやり直しが必要になる可能性があり、費用は数百万〜1,000万円を超えかねません。
基礎の致命的な損傷:
幅が1cmを超えるような大きなヒビ(大割れ)や、基礎が沈下している形跡がある場合、大規模な基礎補修・補強工事が必要です。特に、古い布基礎(コンクリートの底面がない基礎)で状態が悪いものは要注意です。
柱や土台の腐食・シロアリ被害の広範囲な進行:
床下や壁の内部まで広範囲にわたってシロアリの食害や雨漏りによる腐食がある場合、柱や梁といった構造材の交換が必要になります。部分的な修繕では済まず、家全体を支える構造体の入れ替えは非常に高額です。
大熊流チェックポイント: 安易な判断はせず、必ず床下と屋根裏を徹底的にチェックしてください。特に床下に潜り、土台や柱に指先で力を加えてみる。少しでもグラつきやボロボロと崩れる感触があれば、それは「買ってはいけない」サインの最たるものです。
2-2. 借地権・再建築不可など「権利・法的な制限」が重すぎる戸建て
物件そのものが安くても、法的な制約が厳しすぎると、「売却したいのに売れない」「担保価値がない」という最大のリスクを抱えることになります。
避けるべき法的な制限:
借地権物件(旧法):
土地の所有権がないため、地代の支払いが必要で、増改築や売却時に地主の許可と承諾料が必要です。特に旧法借地権は、半永久的に地主の権利が強く、投資の自由度が極めて低い。
再建築不可物件:
現行の建築基準法を満たしていないため、今の建物を壊すと、新しい建物を建てることができない物件です。多くの場合、「接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接していること)」を満たしていません。
ただし、これは例外があります。私たち協議会では、再建築不可物件でも、徹底的なリフォームで建物を長寿命化させ、賃貸として高利回りを出す戦略は取ることがあります。しかし、売却時の難易度や融資のハードルが格段に上がるため、初心者が最初に手を出してはいけない物件です。
著しい違法建築:
極端な容積率オーバー、違法な増築部分が大きく、行政から是正指導が入るリスクがある物件です。是正には多額の費用がかかるか、または取り壊しが必要になります。
大熊流チェックポイント: 不動産投資で失敗しないためには、*「出口戦略(売却)」を常に意識する必要があります。再建築不可や借地権付きの物件は、売却の選択肢を大きく狭めます。初心者はまず、所有権付きで再建築可能な戸建てから始めるべきです。
2-3. 「市場性」が極端に低い戸建て(入居者がつかない立地)
どれだけ物件を安く買い、綺麗に再生したとしても、入居者がつかなければ収益はゼロです。
避けるべき市場性の低い立地:
賃貸ニーズが皆無の超僻地:
「地方は宝の山」と私は主張しますが、それは賃貸ニーズがある地方の話です。車で数十分走ってもコンビニ一つない、近隣に会社や工場、学校もない場所では、再生しても入居者は現れません。
競合物件との差別化が不可能:
新築や築浅の物件が多数立ち並ぶエリアで、古家を再生しても価格勝負にしかならない場合。古家の強みは「家賃の安さ」と「広さ」ですが、競合が多すぎるとその強みも薄れます。
災害リスクが極端に高いエリア:
ハザードマップ上、頻繁な浸水や土砂崩れの危険性がある「レッドゾーン」に指定されているような物件は、入居者付けが難しく、保険料も高くなります。
大熊流チェックポイント: 私の著書にもありますが、「空室リスク」は絶対に避けて通らなければなりません。購入前に「周辺の空室状況」「同程度の物件の家賃相場」「ターゲット(ファミリー層、単身者など)の多さ」を徹底的に調べ、最低でも3ヶ月以内に入居者がつく確信が持てる物件を選んでください。
2-4. 「特殊な設備や間取り」で改修コストが高い戸建て
一見、問題なさそうに見えても、特殊な仕様になっているために、一般的なリフォーム業者では対応できず、専門業者に依頼することで費用が高騰するケースがあります。
避けるべき特殊な仕様:
特殊な規格の給湯器・設備:
非常に古い規格で、交換する際に配管や電源の引き直しが必要になる給湯器、または海外製の特殊なシステムキッチンなど。交換部品の入手が困難な場合、全てを総入れ替えするしかなくなり、費用が跳ね上がります。
あまりに複雑で非効率的な間取り:
増改築を繰り返した結果、細切れの部屋が異常に多い、廊下が極端に長いなど、現代の賃貸ニーズに合わない間取り。壁を抜いて広々としたLDKに変更しようにも、構造上抜けない壁が多い場合、改修コストがかさみます。
未確認の浄化槽や汲み取り式トイレ:
下水道が通っているエリアでも、物件が浄化槽や汲み取り式の場合、売却時や賃貸時に公共下水道への接続工事が必須になることがあります。この工事はエリアによって数百万円かかる場合があり、この費用が「想定外の出費」に直結します。
大熊流チェックポイント: 現地調査の際、設備類(特に水回り)の製造年とメーカーを必ず確認してください。特殊な間取りは、「どれだけ壁を抜けるか」をプロ(古家再生投資プランナー®️)の視点で判断してもらうことが、リスクヘッジに繋がります。
2-5. 「心理的瑕疵」が隠されている戸建て
最後に、目に見えないリスクとして心理的瑕疵が挙げられます。
避けるべき心理的瑕疵のある物件:
告知義務のある重大な心理的瑕疵:
過去に事件や事故があった物件は、買主だけでなく、賃借人にも告知義務が発生します。
家賃の大幅な下落リスク:
心理的瑕疵物件は、その事実を告知すると家賃を相場より2割〜5割下げなければ入居者がつかないことがあります。高利回りを目指す古家投資において、家賃の大幅な下落は致命的です。
大熊流チェックポイント: 仲介業者に必ず書面で過去の経緯を尋ねてください。また、近隣住民への聞き込み(「事故物件ではないですか?」とストレートに聞くのではなく、「この家、昔から空き家なんですか?」「前の住人の方はどんな方でしたか?」と丁寧に聞く)も、周辺環境や過去の情報を得るための重要な情報収集手段です。
3. 「ババ物件」を「お宝物件」に変える大熊流リスクヘッジ戦略
最大のリスクである「買ってはいけない戸建て」を回避するための具体的な行動戦略を解説します。私たちの協議会が最も得意とする、リスクを極限まで抑えるためのノウハウです。
3-1. 専門家による「リフォーム概算診断」の絶大なる効果
初心者が失敗する最大の原因は、リフォーム費用を自分で見積もることです。仲介業者が提示する「リフォーム概算」も、あくまで営業トークであり、鵜呑みにしてはいけません。
私の著書でも触れていますが、不動産投資で最も大切なのは「キャッシュフロー」、つまり手元に残るお金です。リフォーム費用を甘く見積もると、このキャッシュフローが崩壊します。
リスクヘッジの鉄則:
必ず購入前に「古家再生士」などの専門家を同行させる。
構造的な欠陥がないか、専門家の目でチェックしてもらう。
「修繕必須箇所」と「付加価値のためのリフォーム」を切り分ける。
その場で「最大値」と「最低値」の概算を出してもらう。
この「リフォーム概算診断」は、古家投資の成否を分ける最も重要なステップです。例えば、素人目には汚いだけに見える和室でも、プロが見れば「畳と襖の交換だけで済む」と判断でき、コストを大幅に抑えることができます。
3-2. 「無駄なリフォーム」を徹底的に排除する技術
高利回りを実現するためには、「投資家エゴ」を捨て、「入居者視点」に立つ必要があります。
買ってはいけないのは、「リフォームしないと住めない物件」ですが、「過剰なリフォームを必要とする物件」もまた、利回りを下げる悪い物件に変わりありません。
費用対効果を最大化するリフォームノウハウ:
私の著書で紹介している古家投資の基本は、「綺麗さ」を追求するのではなく、「清潔感」と「機能性」を確保することです。ターゲットとする入居者(例:低家賃を求めるファミリー層)が「快適に住める」レベルまで引き上げれば十分です。過剰なリフォームは、あなたの利回りを確実に蝕みます。
3-3. 4方よしモデルで築く「出口戦略」の安心感
私たちが推進する「古家再生」投資が、最大のリスクヘッジとなるのは、「4方よしモデル」という確固たる哲学に基づいているからです。
このモデルで経営を続ければ、物件の市場価値が高まり、**売却時にも「地域に貢献した物件」**として高く評価される可能性が高まります。単なる「儲け」だけを追求する投資が最もリスクが高いのです。社会に価値を提供し、感謝される投資こそが、最も安全で成功率が高いと断言します。
4. 現場こそが最大の教科書!協議会会員の失敗と成功事例
机上の空論ではなく、実際の現場で起こった**「買ってはいけない戸建て」**にまつわる事例を、私たちの協議会の会員実績からいくつかご紹介しましょう。
4-1. 【失敗事例】安さにつられて購入した後の「隠れた雨漏り」地獄
これは特に初心者が陥りやすいケースです。
事例: あるサラリーマンの会員Aさんは、地方の築40年の戸建てを50万円という破格の安さで購入しました。現地調査では、雨漏りの跡は天井に一部あったものの、「これくらいならコーキングで直せるだろう」と楽観視し、リフォーム予算を200万円に設定しました。
結果: リフォーム業者に依頼し、屋根の修理に入ったところ、屋根裏の梁の一部が長期的な雨漏りにより腐食しており、構造材の補強が必要な状態でした。さらに、天井裏の断熱材も雨水でカビだらけ。結果的に、屋根の総葺き替え、梁の交換、断熱材の入れ替えで、リフォーム費用は450万円に膨れ上がりました。
教訓: 物件価格50万円に対し、総投資額が500万円を超え、想定利回りは10%台に急落しました。「安物買いの銭失い」とはまさにこのことです。雨漏りは、放置すると構造材を蝕む最大のリスクです。屋根裏のチェックを怠ったことが、この失敗の最大の原因です。
4-2. 【成功事例】法的な問題をクリアし、高利回りを実現したケース
一方で、一見するとリスクが高く「買ってはいけない」と判断されがちな物件を、私たちのノウハウとネットワークで「お宝物件」に変えた事例もあります。
事例: ある会員Bさんが購入を検討したのは、再建築不可、かつ傾斜地に建つ築50年の物件でした。多くの投資家は避ける物件です。しかし、この物件は主要駅から徒歩圏内にあり、賃貸ニーズは非常に高い立地でした。
戦略: 会員Bさんは、古家再生投資プランナー®️の資格を持ち、「出口戦略は賃貸」に絞ることを決断。
地盤調査を徹底し、傾斜地であっても構造上の問題がないことを確認。
再建築不可のデメリットを理解した上で、徹底的に耐久性を高めるリフォームを実施し、建物を長寿命化。
リフォーム費用を徹底的に抑え、購入価格と合わせても総投資額を400万円に収めることに成功。
結果: 想定家賃7万円で募集したところ、即座に入居者が決定。利回り21%という高利回りを実現しました。再建築不可というリスクを上回る立地と、リフォーム費用を抑える技術が勝利の要因です。
教訓: 「買ってはいけない物件」の中には、「初心者が手を出すべきではない物件」と「プロの知恵と技術があれば再生できる物件」が混在しています。その見極めには、体系的な知識とネットワークが不可欠なのです。
5. 古家再生投資プランナー®️がリスク回避の「鍵」となる理由
5-1. なぜ初心者は「知識」と「ネットワーク」が必要なのか
私は、皆さんに「買ってはいけない戸建て」を掴んでほしくありません。そのための最も確実な方法は、自己流の投資を捨てることです。
初心者が失敗するパターンは決まっています。
知識不足: 物件の構造的な欠陥を見抜けない。
ネットワーク不足: 信頼できるリフォーム業者や古家再生士を見つけられない。
戦略不足: 買いたい気持ちが先行し、「家賃からの逆算」を忘れる。
古家再生投資プランナー®️は、これらのリスクをまとめて解消するために私たちが開発・提供している資格認定講座です。
5-2. 体系的な知識を学び、安心感を持って投資を始める
私たちが提供する古家再生投資プランナー丸®️認定オンライン講座は、単なる知識を詰め込むだけでなく、現場での実践的な目利き力と高利回り実現のためのリフォームノウハウを体系的に学ぶことができます。
プランナーになることの価値:
「買ってはいけない戸建て」を瞬時に見抜くプロの目線が身につく。
全国の古家再生士、リフォーム業者のネットワークを使えるようになる。
最新の成功事例・失敗事例を学び、自己投資のリスクを極限まで抑えられる。
私たちのコミュニティには、かつての私と同じように、不動産の知識ゼロからスタートし、今では毎月安定した家賃収入を得ているサラリーマンや主婦が大勢います。彼らは皆、「まず正しい知識と専門家のネットワークを手に入れた」ことで、最大のリスクを回避できたのです。
机上の空論で投資を諦めるのではなく、体系的な知識を身につけることで、空き家問題の解決に貢献しながら、自己の資産形成を確実なものにしてください。
まとめ:最大のリスクを避け、古家投資の可能性を掴むために
この記事を通じて、皆さんが「買ってはいけない戸建て」を明確に理解し、古家再生投資における最大のリスクである「想定外の出費」を回避する具体的な方法を学んでいただけたなら幸いです。
私たち(一社)全国古家再生推進協議会が最も伝えたいことは、リスクを恐れるのではなく、リスクの正体を見極めることです。
最後に、古家投資成功のための3つの要点をおさらいします。
判断基準の明確化: 「構造的欠陥」「法的な制限」「市場性の低さ」など、避けるべき戸建て5選をチェックリストとして活用する。
逆算思考の徹底: 必ず想定家賃から総投資額の限界値を逆算し、予算内で収まる物件のみを検討する。
専門家の活用: 購入前に必ず古家再生士などのプロを同行させ、リフォーム概算診断を受け、自己流の判断をしない。
日本全国で増え続ける空き家は、単なる社会問題ではありません。それは、私たちが手を加えることで再生し、地域社会に新たな価値をもたらす「宝の山」なのです。
一歩踏み出す行動こそが、あなたの未来を創ります。
この知識を、ぜひあなたの投資の「鍵」として活用してください。そして、より体系的に、そして安心感を持って古家投資に取り組みたいと考える方は、ぜひ一度、私たちが提供する古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座を検討してみてください。あなたを全力でサポートするためのネットワークが、ここにあります。
POST: 2025.10.27