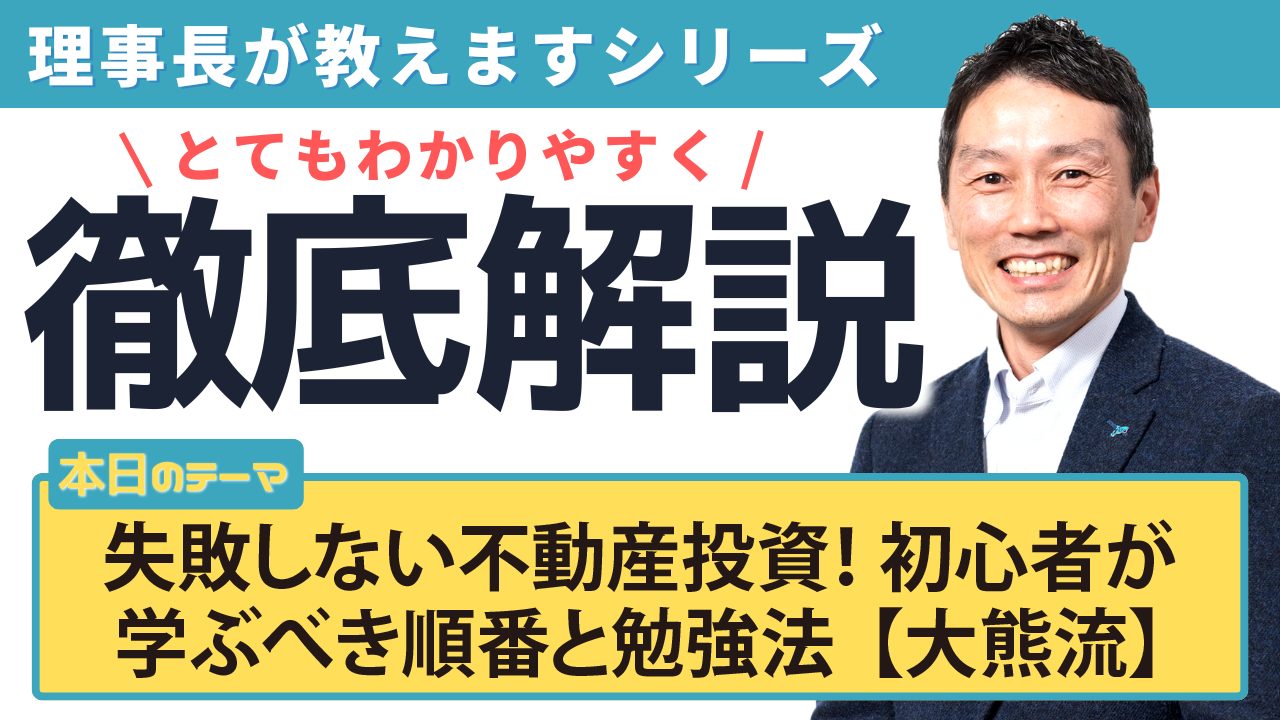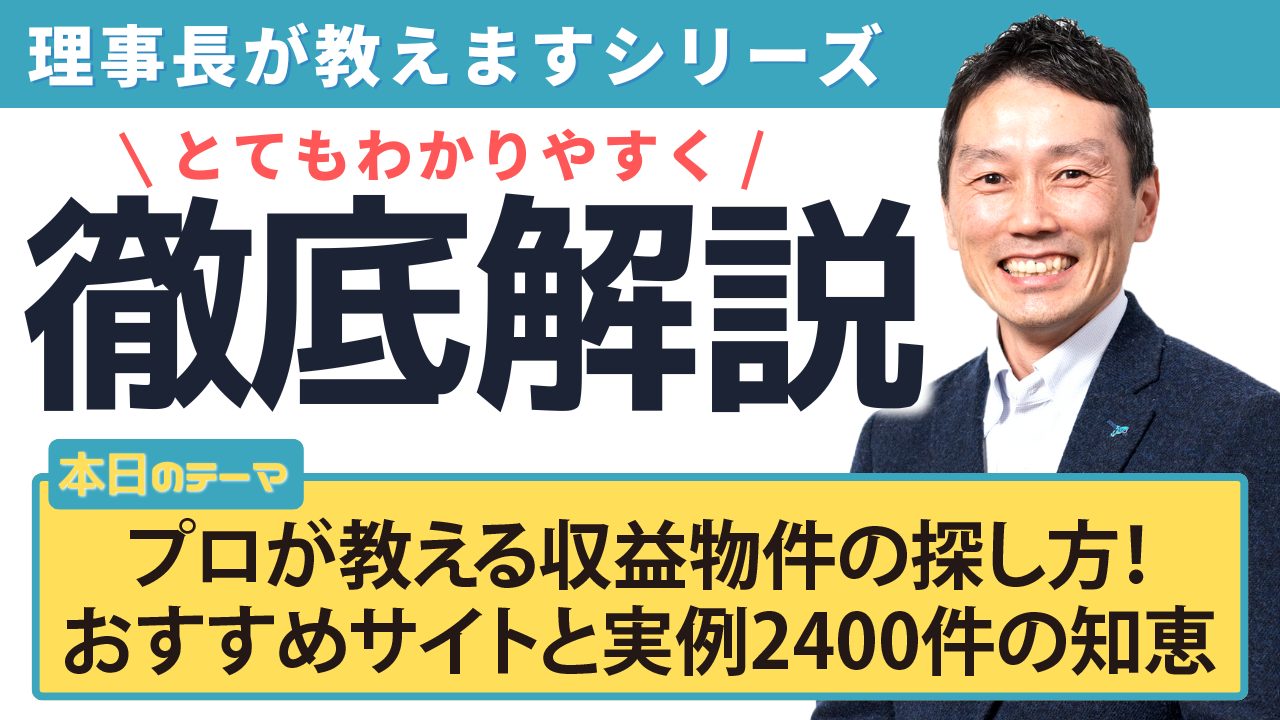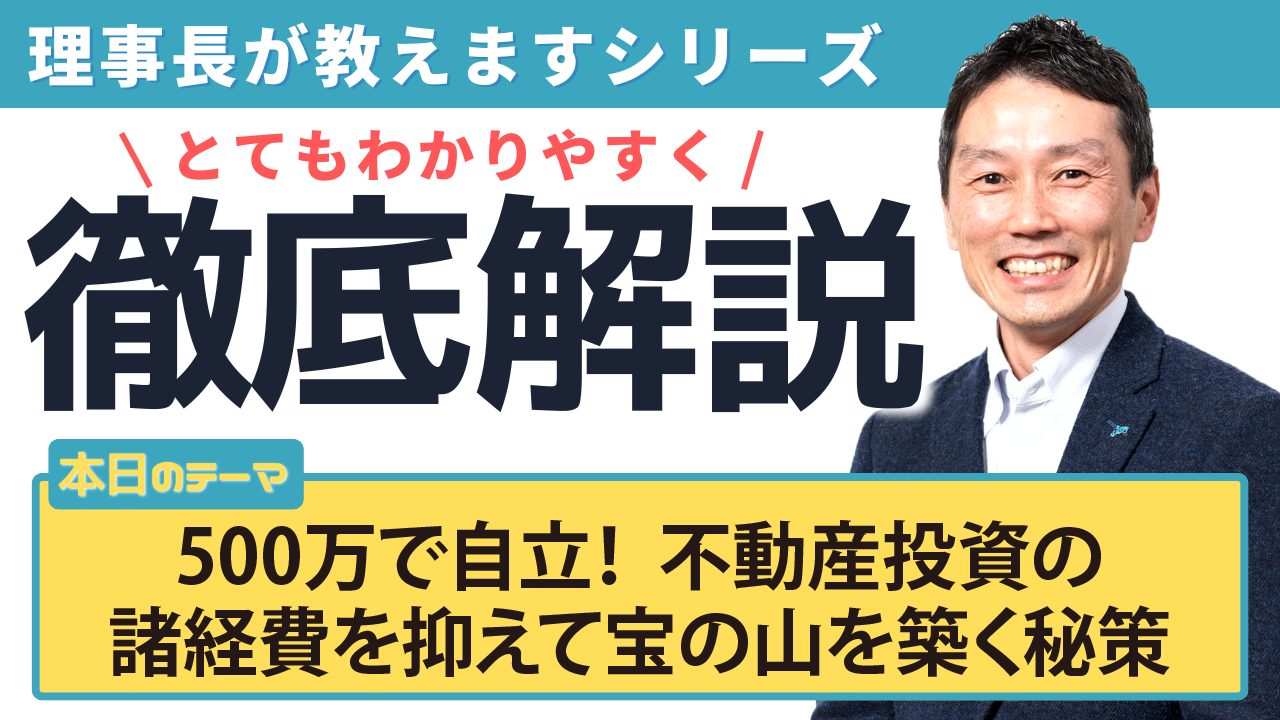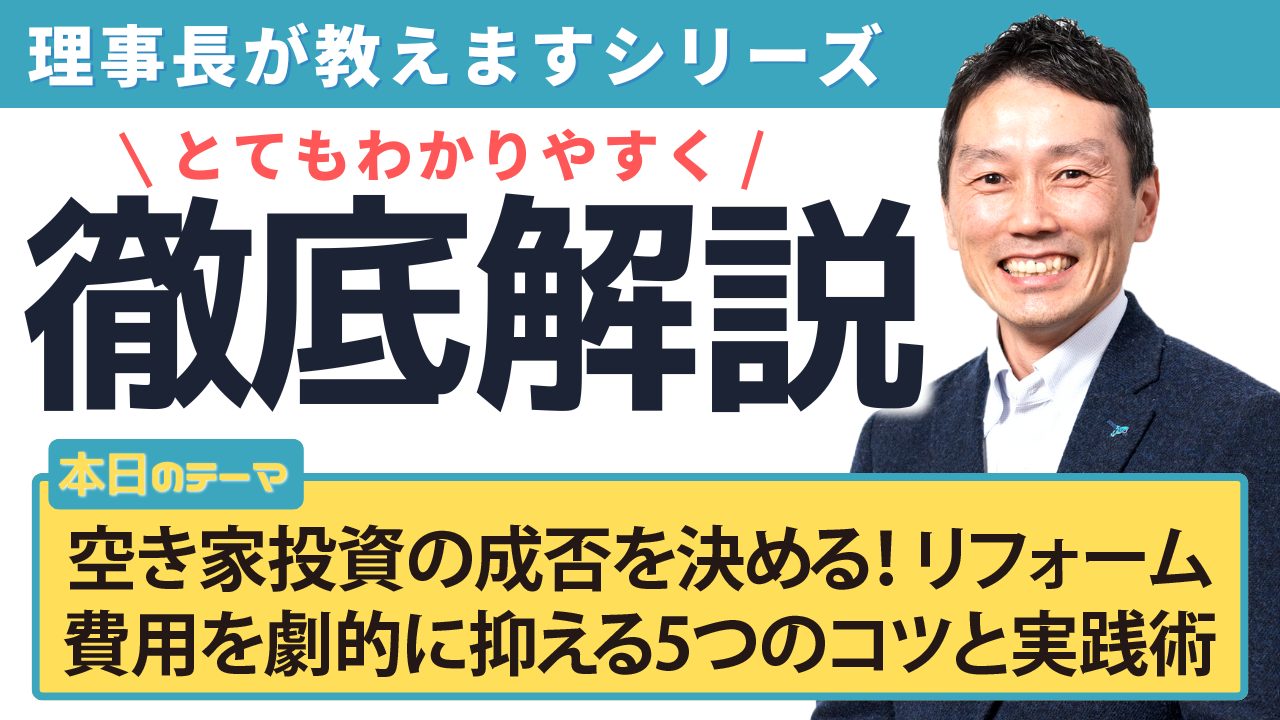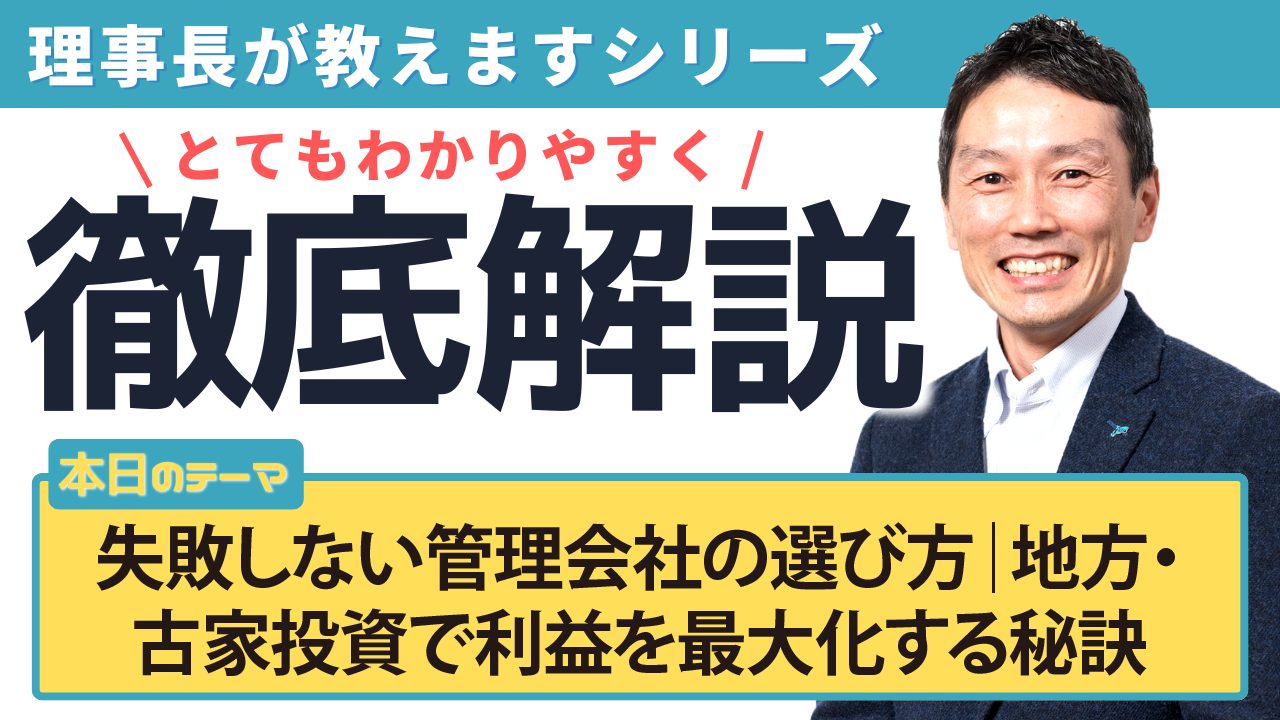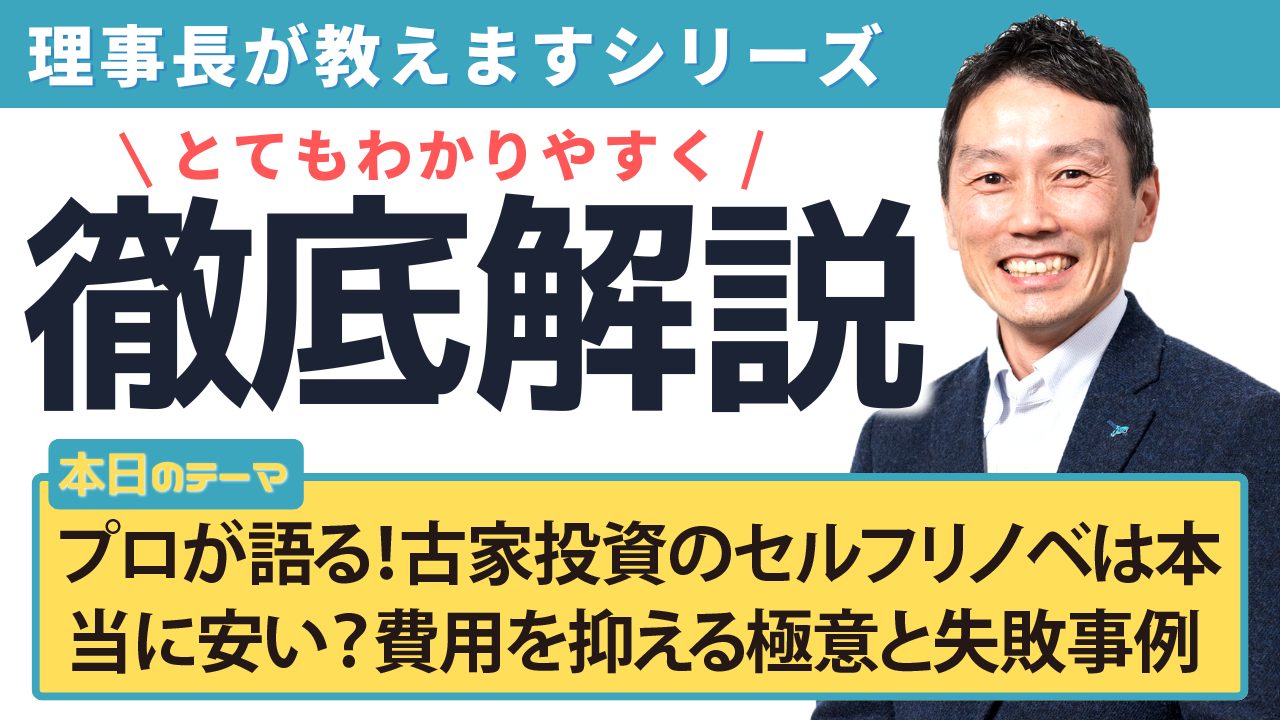
(一社)全国古家再生推進協議会 理事長 大熊重之です。
古家再生投資を始めたばかり、あるいはこれから始めようと考えている方が、まずぶつかる壁。それは「リフォーム費用」ではないでしょうか。
「物件価格は安いけれど、リフォームに何百万円もかかったら、結局は新築と変わらない…」
この悩みに対する多くの古家投資初心者の答えが、「セルフリノベーション(DIY)」です。「自分でやれば費用が浮く。その分、利回りが上がる」と、誰もが考えます。
しかし、私の20年以上にわたる事業経験と、会員数20,280名、累計2,467棟の再生実績を持つ私たち協議会の知見から、敢えて断言します。
多くの古家投資におけるセルフリノベーションは、投資効率を悪化させる「罠」になり得る、と。
この記事は、あなたの「費用を抑えたい」という切実な気持ちに寄り添いながらも、感情論を排し、プロの投資家としての冷静な視点と具体的な数字で、DIYの本当の費用対効果を徹底的に解説します。
最後まで読んでいただければ、単に「セルフリノベーション 費用」の相場が分かるだけでなく、あなたの古家投資を成功に導くための「費用対効果の黄金ルール」と、リスクを極限まで抑えて儲けるための道筋が見えてくるはずです。
目次
1: なぜ「セルフリノベーション(DIY)」は古家投資の罠になるのか?
1-1: DIYの最大の魅力「圧倒的な安さ」の裏にある本当のコスト
「セルフリノベーション 費用」を考える時、多くの人が計算するのは「資材費」だけです。ホームセンターでペンキや壁紙、フローリング材を購入し、「この材料費だけで済んだ!」と喜びます。確かに、この瞬間、プロに依頼した場合の「人件費」が浮いたように見えます。
しかし、これは投資家としての判断が完全に欠落している証拠です。
私の著書『地方は宝の山! リスクを極限まで抑えて儲ける「空き家・古家」不動産投資』でも詳しく述べていますが、投資において最も大切なコストは「時間」、そして「機会損失」です。
想像してみてください。あなたは古家投資を副業として始めました。 週末ごとに物件に通い、慣れない作業に四苦八苦します。1日8時間作業したとして、壁紙張りに3週間、床の張り替えに5週間かかりました。合計8週間、つまり約2ヶ月です。この間、物件は家賃を生み出していません。
プロに依頼すれば2週間で完了する作業に2ヶ月かけるということは、その6週間分の家賃収入を自ら捨てていることになります。家賃が月5万円なら、6週間で約7.5万円の損失です。
さらに、プロレベルの仕上がりが保証されないため、入居後に手直しが必要になったり、入居付けが遅れたりするリスクも加わります。
DIYの真のコスト(見えない費用)
時間のコスト: 本業の時間を削り、家族との時間や投資活動に充てるべき時間を消費する。
機会損失: 物件が空室である期間が長くなり、得るはずだった家賃収入を失う。
品質のコスト: 素人仕事による品質低下は、家賃設定の下落や退去後の再リフォーム費用増につながる。
つまり、表面的な「セルフリノベーション 費用」が安く見えても、総合的な投資効率で見ると、DIYが最も高コストな選択肢になる場合が多いのです。
1-2: 素人が手を出すべきではない「賃貸物件」の品質基準
古家投資は「自分の家」を作るのではありません。「入居者さんに安心して生活してもらうための商品」を作っているのです。
賃貸物件として提供する以上、求められるのは「最低限の安全基準」と「長期安定稼働のための耐久性」です。
素人によるDIYでよく失敗するのが、水回り、電気、構造に関わる部分です。
水回りの配管接続ミスは、下の階への水漏れという大惨事を招き、数百万円単位の賠償問題に発展する可能性があります。
電気配線の不備は、火災という人命に関わるリスクを伴います。
賃貸経営におけるリスク管理の鉄則は、「リスクは専門家へ任せる」ことです。私たちが推奨する古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座では、DIYを完全に否定しませんが、「プロに任せるべきリスク極限箇所」を徹底的に指導します。
たとえば、ガス給湯器の交換、電気配線の増設、構造に関わる壁の撤去などは、絶対に有資格者であるプロの領域です。
DIYで費用を削ることに夢中になり、入居者さんの安全と、あなたの投資家としての信用を失っては本末転倒です。これが、私が「DIYは古家投資の罠になり得る」と警鐘を鳴らす最大の理由です。
2: 【実践者の告白】DIYで大失敗!プロが語る3つの残念な失敗事例
私の元には、DIYで痛い目を見た多くの古家投資家からの相談が寄せられます。ここでは、私の著書『儲かる!空き家・古家不動産投資入門』などで紹介している、典型的な失敗事例を3つご紹介しましょう。
2-1: 失敗事例1:時間と資材をムダにした「中途半端なDIY」の末路
最も多い失敗がこれです。Aさんは「費用を徹底的に削る」ことを目標に、床の張り替えや壁紙張りに挑戦しました。
最初の見積もり: プロに依頼すると総額200万円。
Aさんの判断: DIYで100万円に抑える。
しかし、いざ始めてみると、週末だけの作業では進まず、半年が経過。素人仕事のため仕上がりも悪く、物件内覧者からは「なんだか薄暗くて雑な仕上がりですね」と敬遠されました。
結局、入居付けが難しくなり、Aさんは残りの作業と手直しをプロの業者に依頼せざるを得なくなりました。
プロによる手直し費用: 150万円(素人の中途半端なDIYの撤去費用が上乗せ)。
損失: 資材費(DIY分)+プロ費用+半年分の家賃収入(約30万円)。
結果的に、最初からプロに200万円で依頼していれば、半年早く満室経営がスタートできていたのです。費用対効果どころか、DIYが原因で50万円以上の損失を出し、時間をムダにしました。DIYは「安さ」ではなく、「完成度」と「スピード」を犠牲にするということを肝に銘じてください。
2-2: 失敗事例2:入居者トラブルを招いた「水道管の自己修理」
Bさんは、洗面所の古い排水管からの水漏れを、インターネットで調べた情報と市販の補修キットで自己修理しました。
「セルフリノベーション 費用」を抑えることに成功した!と喜んでいましたが、悲劇は入居から3ヶ月後に起こりました。
入居者から「下の階の天井から水が漏れている」との緊急連絡が入ったのです。
原因は、Bさんが修理した排水管の接続部分の緩みでした。賃貸物件は、毎日、複数の入居者が水を使うため、素人の修理では水圧や振動に耐えられなかったのです。
Bさんの自己負担: 漏水の原因調査費用、階下住民の天井・壁の補修費用、Bさんの物件の再修理費用、そして入居者への迷惑料。
この一連のトラブルでBさんが支払った金額は、100万円を超え、何よりも入居者からの信頼を失い、最終的にその入居者は退去してしまいました。
私の著書『不動産投資入門』でも常に強調していますが、投資においてリスク管理こそが最重要課題です。水回り、電気、ガスなどのインフラは、「リスク極限箇所」であり、DIYで費用を削る対象ではありません。素人判断が、一瞬にしてあなたの資産と信用を吹き飛ばすことを忘れないでください。
2-3: 失敗事例3:業者も匙を投げた「ボロボロDIY物件」のその後の費用
Cさんは、築40年の古家をフルDIYしました。しかし、途中で限界を感じて、一部の作業を近所の工務店に依頼しようとしました。
工務店の職人さんが物件を見た時の言葉は、「素人さんの上からペンキ塗っただけじゃ、この壁は持たないよ。この床も傾いたままだし、ゼロからやり直した方が安上がりだ」というものでした。
Cさんの行ったDIYは、「リフォーム」ではなく「リフォームの邪魔」になってしまっていたのです。素人による中途半端な作業は、プロの作業効率を著しく下げ、結果的に「ゴミ処理費用」や「解体費用」という形で、本来不要だった費用を上乗せしてしまうのです。
最終的にCさんは、私たち協議会の古家再生士に相談しました。古家再生士®️は、その物件の残存価値と必要な最低限の工事を冷静に判断し、何とか収益化できる道筋を提案できましたが、Cさんが当初DIYで使った資材費や時間の損失は計り知れません。
DIYの真の恐ろしさは、あなたの物件を「商品価値のない産業廃棄物」に変えてしまうリスクがあることなのです。
3: 「机上の空論」ではない!費用対効果で考えるリフォームの鉄則
では、「セルフリノベーション 費用」を抑えるという目的は諦めるべきなのでしょうか?
答えは「ノー」です。費用を抑えることは投資の鉄則ですが、「抑えるべき費用」と「投資すべき費用」を見極めることがプロの仕事です。
ここからは、私の古家投資哲学に基づいた、費用対効果で考えるリフォームの鉄則を解説します。
3-1: 賃貸物件のリフォーム費用は「家賃から逆算」で決めるべし
「リフォーム費用はいくらまで出せますか?」と聞かれた時、あなたが答えるべきなのは「50万円です」という固定額ではありません。
プロの投資家は、まず「この物件で得たい家賃(利回り目標)」を設定し、そこから「物件購入費」と「リフォーム費用」を逆算します。これが私の提唱する「家賃から逆算」の法則です。
目標利回り: 15%
想定家賃: 月5万円(年60万円)
利回り15%を達成するための総投資額は、年収益(60万円)÷利回り(0.15)で、400万円です。
もし物件購入費が150万円であれば、リフォーム費用に使えるのは、残りの250万円(総投資額400万円 − 購入費150万円)までとなります。
つまり、リフォーム費用の予算は、物件の残存価値と目標利回りによって自動的に決まるのです。この枠内で、最大限の入居者満足度を実現するために、プロの知恵とノウハウを使うことが重要です。費用を抑えるためにDIYを始めるのではなく、決まった予算内でプロの業者と交渉し、どこまで工事ができるかを見極めるのが、賢明な古家投資家のあるべき姿です。
3-2: コストを抑えるための「手をかけるべき4つの重要箇所」
「セルフリノベーション 費用」をプロに頼んで削るのではなく、「プロが手をかけなくて済む、効果的な箇所」を見極めることが、費用対効果を最大化します。これはDIYでやってもリスクが少なく、物件の印象を劇的に改善できる部分です。
私の経験上、費用対効果が高いリフォーム箇所は以下の4点です。
これらは、「集客力」に直結し、「安全性」に関わらない箇所です。特に、清掃(クリーニング)は費用対効果が最強です。プロに頼む水回りの本格清掃以外は、入念な自己清掃でプロの作業範囲を狭めることが、DIYによる費用削減の最も賢い方法です。
3-3: DIYでなくプロに任せるべき「リスク極限箇所」の見極め方
前述の通り、以下の箇所は、安易にDIYで費用を削ろうとすると、後で膨大な追加費用やトラブルを招く「リスク極限箇所」です。必ず専門のプロに依頼してください。
プロに任せることは「費用を浪費する」ことではありません。それは「投資のリスクを極限まで抑えるための保険料」であり、「投資の再現性を高めるためのノウハウの購入費」なのです。プロの仕事は、費用を抑えるどころか、長期的に見てあなたの利益を守るための費用です。
4: 古家投資で「安さ」と「再現性」を両立する「古家再生士」の仕組み
「リフォーム費用の逆算は分かった。でも、結局プロに頼むと予算オーバーしてしまう…」
このような悩みに応えるために、私たち(一社)全国古家再生推進協議会は存在しています。私たちが提供するのは、DIYの安さに匹敵し、かつプロの品質とスピードを持つ、「古家再生士®️」という仕組みです。
4-1: なぜ一般の工務店は古家再生で高額見積もりを出すのか
一般的な工務店やリフォーム業者は、新築や築浅物件のリフォームを主戦場としています。彼らのビジネスモデルは、以下の構造になりがちです。
分業制: 大工、水道屋、電気屋、左官屋など、職種ごとに業者を手配するため、中間マージンと移動コストが発生する。
新築基準の品質: 築古物件であっても、新築に近い品質や工法を提案しがちで、オーバースペックなリフォーム費用になりやすい。
賃貸経営の知識不足: 投資家が求める「利回り」や「費用対効果」の概念がないため、入居付けに不要な工事まで盛り込まれる。
結果として、古家特有の「安く買って、安く直して、高く貸す」というビジネスモデルの邪魔になるような、高額な見積もりになってしまうのです。
4-2: 賃貸経営を知るプロ集団「古家再生士」が費用を抑えるカラクリ
私たちが全国で育成し、活動している「古家再生投資プランナー®️」のネットワークには、古家再生士®️という専門家がいます。彼らは、一般の工務店とは一線を画した費用削減のカラクリを持っています。
古家再生士は、単なる職人ではありません。彼らは、私の著書『地方は宝の山!』で提唱しているように、「賃貸経営、建築、客付け」の3つ全てを熟知しています。
費用対効果の理解: リフォーム費用はすべて「家賃から逆算」で考え、利回り目標から外れる工事は一切行いません。
最小限の工事: 「古家は古いままが魅力」という考え方を持ち、本当に必要な最小限の工事に留めます。例えば、壁のすべてを張り替えず、汚れがひどい部分のみを補修するなど、知恵とノウハウで費用を抑えます。
仕入れのノウハウ: 古家に特化しているため、質の高い中古品や、古家向けに特化した安価な資材の仕入れルートを持っています。
これにより、一般の工務店と比較して、リフォーム費用を30%〜50%削減できるケースも珍しくありません。DIYの安さにプロの品質とスピードを加える。これが古家再生投資の成功の秘訣です。
4-3: 「多能工」による人件費の削減とスピード化の秘訣
私の著書『不動産投資入門』でも解説していますが、リフォーム費用の大部分を占めるのは人件費です。
一般工務店の分業制では、大工さんが来て、水道屋さんが来て、電気屋さんが来て、と、作業のたびに業者が入れ替わり、移動費や待ち時間が発生します。
しかし、古家再生士は®️、多能工(たのうこう)というスキルを持っています。
多能工: 1人で大工仕事から、簡易な水道・電気工事、内装工事まで、複数の職種をこなせる職人。
多能工なら、複数の作業を効率的に、かつ一連の流れで完了させることができます。これにより、中間マージン、業者の移動費、待ち時間をすべてカットできます。
古家再生士®️のネットワークに依頼することで、あなたはDIYで失うはずだった「時間」と「家賃収入(機会損失)」を確保し、さらにプロの技術で「リスク」を排除しながら、費用も削減できるのです。
5: リスクを避け、収益を最大化する「プロに頼む」という勇気ある一歩
DIYで費用を削るというのは、一見、賢明な判断に見えます。しかし、古家投資の本質は、「どれだけ早く、リスクなく、安定したキャッシュフローを生み出せるか」です。
DIYを選ぶことは、「時間」と「リスク」という2つの投資家にとって最も大切な資源を、自分で抱え込むことを意味します。
5-1: 「空き家・古家は宝の山」を証明する平均利回り12%超えの実績
私たち全国古家再生推進協議会の会員が再生した物件は、累計2,467棟を超え、平均利回りは12%以上を誇ります。
なぜ、これほどの高利回りが実現できるのか?
それは、DIYで時間をムダにするのではなく、「古家再生士®️」というプロのチームを活用し、「安く、早く、適切に」リフォームを完了させているからです。
購入費: 地方の空き家を低価格(100万円〜300万円)で仕入れる。
リフォーム費: 古家再生士のノウハウで、費用対効果の高いリフォームに抑える(例: 200万円〜300万円)。
高利回り: 質の高い再生物件は入居者に喜ばれ、長期間安定して家賃を生み出す。
この「4方よしモデル」を確立しているからこそ、古家・空き家投資は「地方は宝の山」になるのです。机上の空論ではなく、この確かな実績が、プロのノウハウに投資する価値を証明しています。
5-2: 地方投資でこそ「プロのチーム」が必要な理由
古家投資の多くは、地方物件が対象になります。あなたが都市部に住みながら地方の古家にDIYで通うのは、交通費、宿泊費、そして何より「移動時間」という巨大なコストを伴います。
地方物件でこそ、地元の古家再生士®️というプロのチームの存在が不可欠になります。
遠隔地でのスピード対応: 物件取得後のリフォーム開始が早い。
緊急時の対応: 入居後のトラブル発生時、地元のプロが即座に対応し、DIYの失敗事例2のような大惨事を防ぐ。
地域の特性: その地域特有の気候や建物の知識、地域の客付け業者との連携を持っている。
古家投資を再現性の高いビジネスとして成功させるには、個人事業主から、プロのチームを率いる経営者へと、あなたの意識を変える必要があります。DIYは孤独な個人プレイヤーの作業ですが、古家再生投資は、専門家と連携するチーム戦なのです。
「プロに頼む」という勇気ある一歩を踏み出すことこそが、あなたの投資のスピードを上げ、収益を最大化するための最も賢明な費用対効果の判断となります。
まとめ
この記事では、「セルフリノベーション 費用」を削るという行為が、古家投資においていかにリスクが高く、結果的に高コストになる可能性があるかを、私の経験と協議会の実績からお話ししました。
重要なポイントを再度整理します。
DIYの罠: セルフリノベーションの最大のコストは、失われた「時間」と「家賃収入(機会損失)」です。中途半端なDIYは、プロによる手直し費用を上乗せし、結果的に最も高額なリフォームになります。
費用対効果の鉄則: リフォーム費用は、感情や固定額で決めず、「得たい家賃から逆算」して予算を決める。水回り、電気、構造などのリスク極限箇所は、費用を削らずプロに任せるべきです。
古家再生士の活用: 費用削減の鍵は、DIYではなく、「多能工」のノウハウを持つ古家再生士®️にあります。彼らは賃貸経営の視点から最小限の工事を見極め、安価で質の高い再生を実現し、DIY以上の費用対効果を提供します。
あなたが古家投資で成功するために、今すべきことは、「目の前の作業」に追われるDIYプレイヤーになることではありません。「リスクを極限まで抑え、収益を最大化する経営者」になることです。
私たち(一社)全国古家再生推進協議会が提供する「古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座」は、この「経営者視点」を徹底的に学んでいただくためのものです。
失敗しない物件選定のノウハウ
家賃から逆算するリフォーム費用の計算方法
全国の古家再生士ネットワークの活用方法
プロの業者との交渉術
これらの知識とノウハウを体系的に学ぶことが、DIYで自己流の失敗を繰り返すよりも、何倍も賢明な「先行投資」となります。
「リスクを極限まで抑えたい」「誰でも再現できる成功ノウハウが欲しい」と本気で考えているなら、まずはその一歩を踏み出してみませんか。
私たちは、あなたの行動を全力でサポートし、空き家問題という社会課題解決に貢献する仲間が増えることを心より願っています。
「いつかやろう」ではなく、「今すぐ行動する」。これが成功者とそうでない人を分ける唯一の差です。
古家再生投資プランナー®️認定オンライン講座に関する詳細は、ぜひ以下のリンクからご確認ください。あなたとお会いできる日を楽しみにしています。
POST: 2025.11.10